「場」:力、相互作用、場、エネルギを包括した概念
InterLab (オプトロニクス社), 2007年 5月号 (No. 103), pp. 37-40
| 連載: 技術革新のための創造的問題解決技法!! TRIZ | |
| 第17回 TRIZの基本概念(3) 「場」:力、相互作用、場、エネルギを包括した概念 |
|
| 中川 徹 (大阪学院大学) InterLab (オプトロニクス社), 2007年 5月号 (No. 103), pp. 37-40 |
|
| 許可を得て掲載。無断転載禁止。 [掲載:2007. 5. 6] |
English translation of this page is not ready yet. Press the button for going back to the English top page.
編集ノート (中川徹、2007年 5月 5日)
本件は、研究・技術開発者のための情報誌『InterLab』誌に掲載している長期連載の第17回です。同誌のご好意によりここに掲載しています。連載の親ページ
。同誌の発行は前月15日で、本ホームページには当月1日以降の掲載を標準にしています。
同誌で発行された形のものは PDFファイルにしています。ここをクリック下さい
(PDF 302 KB) 。
また、ここにHTML形式のページを作り、いろいろなところへのリンクを張りましたので、ご活用下さい。
なお、このページはTRIZについて初心者の方のための、TRIZ紹介のページとしても位置づけております。TRIZ紹介の親ページ
その他の記事へも多数リンクしておりますので、ご活用下さい。
目次:
1.1 物理学の「場」の概念
1.2 TRIZにおける「場」の用語
1.3 TRIZにおける「場」のさまざま
1.4 TRIZでの「場の階層」の概念3.1 アルトシュラーの「物質-場モデル」
3.2 機能による解釈
3.3 「物質-場モデル」のねらい
3.4 機能の概念とTRIZ参考文献
第17回
TRIZの基本概念(3)
「場」:力、相互作用、場、エネルギを包括した概念
大阪学院大学 中川 徹
InterLab誌, 2007年 5月号 (No. 103), pp. 37-40
この連載
は、創造的な問題解決の技法TRIZについて、その考え方をできるだけ分かりやすく、いろいろな例を使いながら解説することを目指しています。
いままでに、TRIZの概要説明FAQ
、発展の歴史、やさしい適用事例、科学技術の情報を整理し直したTRIZ知識ベース、マネジャのための導入・適用の勘どころ、などを説明してから、TRIZの基本概念の説明を始めました。
第15回(前々回)
で述べましたのは、膨大な体系を持つTRIZも、そのエッセンスを捉えると、(英文で)50語で説明できることです。そして前回から、このエッセンスに表されている主要な基本概念の説明を始めたところです。この一連のものは、つぎのような予定でおります。
TRIZの基本概念
(1) TRIZのエッセンス: 50語表現
(2) システム: 問題の体系と技術システムの概念
(3) 「場」: 力、相互作用、場、エネルギを包括した概念
(4) 理想性とその向上
(5) リソースとその活用
(6) 矛盾とその解決
(7) 問題解決の基本モデルもちろんこれらの基本概念は、やさしい事例を使いながらいままでにも説明してきていますし、TRIZの知識ベース
を説明したときにも、いろいろと関連して説明しています。それでも、それぞれの基本概念をもう少しきちんと説明して、その後の問題解決の技法を理解するための土台をしっかりしておこうというのが、いまの意図です。
さて、前回に「システム」という概念について説明しました。これには二つの意味があり、その一つは「体系」と訳すのが適切です。もう一つは、「技術システム」というときの基礎になっている概念で、広く「関連する部分たちの一群で、一つの全体を形成して一緒に働くもの」といった意味です。
そして、システムの階層性、技術システムが備えるべき要素(「技術システムの完全性の法則」)などを説明しました。
今回は、システムの要素間の関係を考えるための概念を説明しましょう。TRIZで特に注目するのは、配置や構造などの関係よりももっと抽象化した、働き(あるいは、作用、機能) の関係です。
この働きを説明するのに、TRIZの創始者であるアルトシュラーは、独自の概念と表現を使いました。それが「場」という概念と、「物質-場モデル」という表現です。
TRIZでいう「場」は、標題のように、自然科学における力、相互作用、場、エネルギをすべて包括した概念です。
この「場」という概念は、非常に包括的・抽象的なものですが、同時に非常に具体的・実際的であり、TRIZのユニークな性格を示しています。通常の科学技術の用語で置き換えることができないので、英語の文献では大文字でFieldと記述され、私は日本語の表現ではいつも「 」をつけて「場」と記述しています。
このような(古典的な)TRIZの独自の考え方を理解し、そしてその考え方を科学技術の通常の言葉遣いによっても説明していけるようになれば、TRIZの理解と定着が本物になっていくでしょう。この意図から、最近の研究者の説明をも後半に記述します。
1. TRIZの「場」の概念
さていまから、「ものとものとの間の働き」を説明することを考えよう。金槌で釘を打つ、鉄釘を磁石でつり上げる、鉄釘が錆びる、などいろんな現象を説明したいからである。
1.1 物理学の「場」の概念
現在の科学技術の理解の中核を成すのは物理学である。そこでは、いろいろな現象を説明するための根本原理を探求していった。そして、ものとものとの間に働く力(相互作用)が、究極的に 4種類であることを解明した。
(1)重力相互作用 (万有引力)
(2)電磁相互作用
(3)強い相互作用
(4)弱い相互作用このうち、(3)は原子核の中の陽子と中性子の結合などに関与し、(4)はニュートリノなどの素粒子間に働く極めて小さな距離での相互作用であるから、通常のマクロの世界には関係しない。
(1)は、天体間の力であるとともに、日常的に重力としてよく実感される。それは物の重さ、大気圧、静水圧、などとして顕れる。
(2)の電磁相互作用は、もちろん電気器具や磁石などでマクロに顕れているものであるが、実は、物質を構成している原子核と電子の間に働き、電磁場として長距離に及ぶものだから、ミクロの世界のほぼすべて、そしてマクロの世界の大部分の現象に関わっている。化学的な性質のすべて、そして生体関係のすべての性質が、結局はこの電磁相互作用から生れて来る。(例えば、臭いの感覚は物質を直接的に検知しているのだから、化学的な性質に依存するのであり、それは分子レベルでの電子的な性質に帰着するといえる。)
物理学では(素粒子論に関わらないでいうと)、「場(field)」という用語を、「電場」「磁場」「重力の場」などの形で使い、上記のような力(相互作用)が及んでいる空間を意味している。「電場に置かれた電荷が、電場から力を受ける」というように考える。
1.2 TRIZにおける「場」の用語
TRIZの考え方はもっと泥臭く、直感的、経験的である。要するに、自然現象のすべてを、「もの」と「その間に働く相互作用 (力)」として説明したい。そのときに、「もの」を「Substance(物質)」と呼び、ものとものとの間に働く一切の種類の相互作用(力)をまとめて「Field(場)」と呼ぶのである。
このように、多様なものを包み込んでそれに名前をつけることは、概念を創ることであり、抽象化することである。その上で、TRIZでは、包み込んだ多様なものをできる限り具体的に列挙し、それらを実際的に分類して、特徴を整理して何らかの経験法則を見つけ出していこうとする。
だから、TRIZにおける「場」は、(電場、磁場などの)物理学の「場」よりもずっと広く、各種の力、相互作用を意味し、「エネルギの任意の形の源」を意味すると考えるのがよい。
1.3 TRIZにおける「場」のさまざま
どのような「場」があるかは、例えば、Darrell Mann のTRIZ教科書[1] が参考になる。その一部を記す。
力学的 (重力、摩擦力、遠心力、張力、弾性、振動など)、
水圧/油圧/空気圧
熱的(熱伝導、対流、輻射、熱膨張)
圧力(静圧力、浮力、真空など)
電気的(電気力学、電磁気的、交流など)
化学的(酸化還元、燃焼、溶解、化学反応、など)
生物学的(酵素、光合成、発酵など)
磁気的(強磁性、電磁気的、など)
光学的(反射、屈折、赤外線、など)
音響的(音、超音波)
臭いまた、これらの一つ一つがさまざまな形態を取る。例えば、重力でも、それが力として顕れるだけでなく、重力の場、重力加速度、重力のポテンシャルエネルギなどとして考えるとよいこともある。
1.4 TRIZでの「場の階層」の概念
上記のように多様な「場」を考え、その特徴をTRIZは考察する。その中で、技術の歴史の当初に使われていた「場」から、次第に高度な、より制御しやすい「場」に移行していくことが分かってきた。
その大まかな順序をTRIZでは、「力学的(Me)→熱的(T)→化学的(Ch) →電気的(E)→電磁気的(M)」と捉えて、「MeTChEM(メッチェム)」と略称している。
これをさらに詳しくして、段階的な発展として捉えた一覧表は、例えばLarry Ball [2] のものを参照されたい。
2 TRIZの「場」の概念の活用
TRIZが創った「場」という概念を、最大限に活用させる優れた図が、Invention Machine社のソフトツール TechOptimizer 3.5J にある。これを図1に引用する。
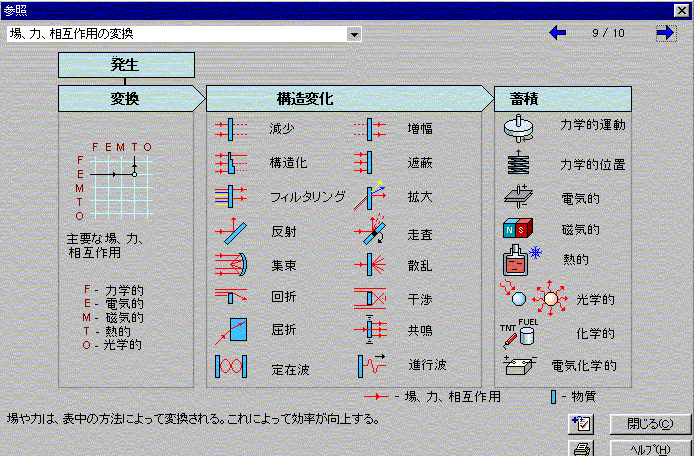
図1. 「場」の発生、変換、構造変化、蓄積 (Invention Machine社 TechOptimizer 3.5J より)
この図は、TRIZでいうさまざまな「場」(すなわち、力、相互作用、場、エネルギなど)を、生成し、変換し、構造を変化させ、(エネルギとして) 蓄積するための技術を概観している。
図1の左下には、「場」の主要な5形態を示し、それぞれを変換する技術/デバイスを考察することを促している。図の例は、電気的な「場」から熱的な「場」への変換を指し示しており、例えば、電気を使った加熱/冷却の方法を意味する。膨大な科学技術の中で、このようなエネルギ形態の変換に関わっている技術が極めて多くある。
図1の中央は、「場」の構造をさまざまに変える方法を図示している。この図は光に対して操作していると考えると分かりやすい。光を減衰させるのは、吸収板を使えばよい。光を増幅させることは、レーザ技術を使って初めて実現した(注:もちろん、光→電気→光のような形での増幅はもっと以前からあったが)。
光をフィルターすることは、例えば光の波長によって通したり通さなかったりすることであるが、それは [もちろん、いろいろな自然の素材を使ったり、色ガラスなどを組み合わせて使う方法があるが、望んでいる波長領域を適切に選択しようとすると、] 随分高度な材料設計、薄膜設計によって初めてできている。狭い幅の波長だけ透過させたり、その波長域を変化させたりとなると、さらに高度な問題になるに違いない。
これらの操作を、他の形式の「場」で考えると、さらに難しい問題だと分かる。例えば、力学的な力について「収束させる(焦点を結ばせる)」ことは、空間的に広がっている大きな力を、一点(極めて小さな空間)に集中させることである。それは人工ダイヤの製造技術などで工夫されてきていることである。
このように、ここに示された一つ一つの図式を、さまざまな「場」の構造を変化させるという技術的要請であると解釈して、現在の科学技術を整理してみることは非常に重要で、興味深いことであろう。
図1の右下には、これらの「場」を蓄積する技術を整理している。力学的な力を蓄積することは、力学的な形でエネルギを蓄積することである。弾み車のような動的なやり方、弾性応力のような静的なやり方、そして重力ポテンシャルなどがある。
電気の蓄積(コンデンサ)、磁力の蓄積(永久磁石)、熱の蓄積、光エネルギーの蓄積(燐光)などの例が上がっている中で、電気化学的(電池)、化学的(火薬、燃料)などを見ると、化学的な方法のエネルギ蓄積の大きさがよく分かる。そして、原子核のエネルギ蓄積(すなわち、原子力)はさらに大きなエネルギ蓄積の方法である。
ともかく、TechOptimizer のこの図は、TRIZが創った「場」という概念をベースとして、包括的に技術を理解する深く広い可能性を指し示しており、大変含蓄のある優れた図である。
3 TRIZの「物質-場モデル」とその理解
3.1 アルトシュラーの「物質-場モデル」
1節の最初に述べたように、アルトシュラーが「場」という概念を創った目的は、ものとものの間の働き(作用) を統一的に表現することであった。その働きを表す最も基本的な図式は図2のようであり、これをアルトシュラーの「物質-場モデル」と呼ぶ [3]。
図2. 「物質-場モデル」の基本図式
この図は、「物質S2が、「場」Fによって、物質S1に作用を及ぼしている」と読む。このような三角形の配置がアルトシュラーの典型的な表現形式である。
3.2 機能による解釈
上記図2の基本図式は、現在の通常の機能モデルでは、図3のように理解され、表現される。
図3. 機能分析の基本図式
これは、「物質S2が物質S1に作用 (あるいは機能)f を及ぼしている」と読む。ここで、「場」Fと、作用/機能f とは、基本的に対応するものであるが、表す内容が少し異なっているので文字を違えた。
例えば、金槌S2 が釘 S1を「打つ/叩く/衝撃を与える」というのが機能の言葉である。このとき、アルトシュラーは、「場」Fとして、「力学的な場/衝撃力」という表現をするであろう。打つとか叩くとかで及ぼしている力の本質的な形態が何かをはっきり記述しようとするのである。
なお、図3で S1とS2の配置は図2に合わせたものであり、配置にはこだわらないのが普通である。それでも、いろいろな意図のもとに、この矢印の向きが、右向き配置を標準にしたり、上向き配置を標準、あるいは下向き配置を標準にしたりするやり方がある。
3.3 「物質-場モデル」のねらい
アルトシュラーが「物質-場モデル」を記述することを薦めるねらいは、おおまかにいうと二つある。
第一は、あるシステムのメカニズムを考察するのに、そのエッセンスを図2の基本図式にあてはめて、各要素を明確にし、メカニズムの本質を明示させることにある。もしこれを明示できないなら、そのシステムは本質のところで不完全で、うまく働かない。
物質S1に対して望んでいる作用を及ぼすには、物質S2として何を選べばよいか、そして作用をさせるエネルギの形態Fとして何がよいかを、考えさせることが、この「物質-場モデル」を描かせる第一のねらいである。
なお、Larry Ball [2] は、このようなシステムを組み上げるための考察の順序として、S1(対象物)→ F(「場」、あるいは物理現象)→ f(機能)→ S2(作用物質)という順に選択、決定していくことを薦めている。
第二のねらいは、物質S2から物質S1への作用(働き)が、有効・適切な状況でなく、不十分、過剰、有害などの問題がある状況になっていることを明示し、それらのいろいろな場合に、採用するとよい解決策の方針を図式的に示すことにある。
これらの状況を区別するために、アルトシュラーは図2の矢印を図4のように区別して表現した。
図4. 作用の有益/有害などの区別
このような「物質-場モデル」の表現を基礎にして問題を分類し、アルトシュラーはそれぞれの場合に解決策の指針を図式的に明示した。この方法を「物質-場分析」と呼び、その解決策の指針を「発明標準解」という。
「物質-場モデル」が不完全な場合、作用が不十分な場合、過剰の場合、有害な場合、そして検出と測定の問題の場合について、全部で76種の発明標準解をアルトシュラーは示した (例えばSalamatov [3] またはMann [1] を参照されたい)。
3.4 機能の概念とTRIZ
上述のようにアルトシュラー自身は「機能」という言葉をあまり使わず、1980年頃にSimon Litvin他の弟子たちが機能分析の考え方をTRIZに導入したのだという。そのような歴史にも関わらず、「機能」の概念はやはりTRIZの中核にあるといってよい。
機能についての考え方で、参考になるのは、Ed SickafusのUSITにおけるOAF記述、Larry BallのTRIZ教材 [2] である。これらは、具体的な「機能」について、その機能が作用する「もの」(対象のオブジェクト)のどのような性質(「属性」)を変えようとしているのかを、明確に考察・記述しようとする。
機能の表現に、通常、「〜を〜する」という他動詞を使うが、Larry Ball はもっと明確に「〜(というもの)の〜(という性質)を変化させる/制御する」という表現法を推奨している。例えば、「(金槌で)釘を打つ」のだとすれば、「(金槌で衝撃を与えて)釘の位置(打込み深さ)を変化させる」と記述する。この後者(「長形式」)の記述をしてみることによって、前者(「短形式」)の意味が明確になるのだという。
このように機能と属性を結びつけて考える、「機能属性分析」については、後日、TRIZによる問題解決の諸技法を説明するときに、きちんと説明しよう。
参考文献
[1] Darrell Mann 著、中川徹監訳: 『TRIZ 実践と効用(1)体系的技術革新』、創造開発イニシアチブ、2004年
。
[2] Larry Ball 著、高原利生・中川徹訳:「階層化TRIZアルゴリズム」、『TRIZホームページ』連載、URL: http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/、2006-2007年
。
[3] Yuri Salamatov著、中川徹監訳: 超発明術TRIZ シリーズ5 思想編「創造的問題解決の極意」、日経BP、2000年
。
| 本ページの先頭 | 記事の最初 | 1. TRIZの「場」の概念 | 2. 「場」の概念の活用 | 3. 「物質-場モデル」 |
| 連載の親ページ | 第13回 事例(3) ホッチキス |
第14回 導入・適用・推進法 (マネジャのために) |
第15回 TRIZの基本概念(1) TRIZのエッセンス |
第16回 基本概念(2) 技術システム |
第17回(今回)のPDF |
| 連載の親ページ | 第1回FAQ | 第2回歴史(1) 旧ソ連 | 第3回 歴史(2) 米殴 | 第4回 歴史(3) 日韓 | 第5回 事例(1) 裁縫 | 第6回 事例(2) 万引き防止 | 第7回 知識ベースとソフトツール |
| 第8回 Effects DB | 第9回 技術進化のトレンド | 第10回 機能から手段を知る | 第11回 40の発明原理 | 第12回 矛盾マトリックス | InterLabサイト | TRIZ紹介のページ |
| 総合目次 |
新着情報 | TRIZ紹介 | 参考文献・関連文献 | ニュース・活動 | ソフトツール | 論文・技術報告集 | 教材・講義ノート | フォーラム | General Index |
|
| ホームページ |
新着情報 | TRIZ紹介 | 参考文献・関連文献 | リンク集 | ニュース・活動 | ソフトツール | 論文・技術報告集 | 教材・講義ノート | フォーラム | Home Page |
最終更新日 : 2007. 5. 6 連絡先: 中川 徹 nakagawa@utc.osaka-gu.ac.jp