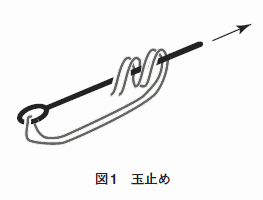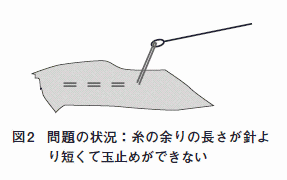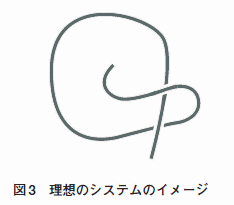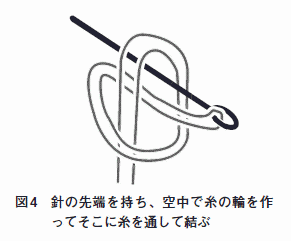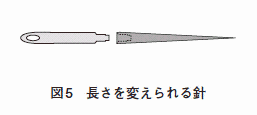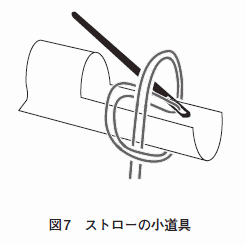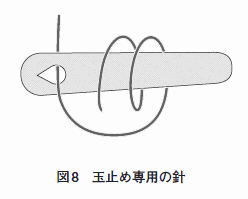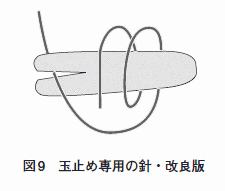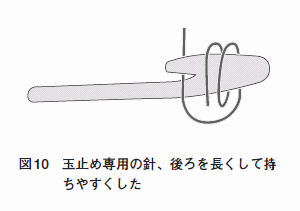TRIZ/USIT ����E�Љ� TRIZ/USIT ����E�Љ� |
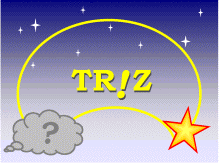 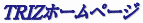 
|
�A��: �Z�p�v�V�̂��߂̑n���I�������Z�@!! �s�q�h�y
|
��5�� TRIZ/USIT�̂₳�����K�p����i1�j
�ٖD�ŒZ���Ȃ��������~�߂���@
|
����@�O�@�i���w�@��w�j
InterLab�@(�I�v�g���j�N�X�Ёj, 2006 �N 5���� (No. 91), pp. 49-54
|
| ���Čf�ځB���f�]�ڋ֎~�B [�f�ځF2006. 5. 9]
|
English translation of this page is not ready yet. Press the  button for going back to the English top page.
button for going back to the English top page.
�ҏW�m�[�g (����O�A2006�N 5�� 7��)
�{���́A�Y�w���A�g�x���}�K�W���wInterLab�x���Ɍf�ڊJ�n���������A�ڂ̑�5��ł��B�����̂��D�ӂɂ�肱���Ɍf�ڂ��Ă��܂��B�A�ڂ̐e�y�[�W �B�Ȃ��A�����̕ҏW�ƃ��C�A�E�g�����̂��э��V����܂����B
�B�Ȃ��A�����̕ҏW�ƃ��C�A�E�g�����̂��э��V����܂����B
�����Ŕ��s���ꂽ�`�̂��̂� PDF�t�@�C���ɂ��Ă��܂��B�������N���b�N������ (PDF 365 KB)  �B
�B
�܂��A������HTML�`���̃y�[�W�����A���낢��ȂƂ���ւ̃����N��܂����̂ŁA�����p�������B
�Ȃ��A���̃y�[�W��TRIZ�ɂ��ď��S�҂̕��̂��߂́ATRIZ�Љ�̃y�[�W�Ƃ��Ă��ʒu�Â��Ă���܂��BTRIZ�Љ�̐e�y�[�W  ���̑��̋L���ւ����������N���Ă���܂��̂ŁA�����p�������B
���̑��̋L���ւ����������N���Ă���܂��̂ŁA�����p�������B
�ڎ�:
�͂��߂�
(1) TRIZ�̎���̊w�ѕ�
(2) ���̓K�p��������グ���|
(3) ���̐ݒ�
(4) ���̕���: ��ԓI�E���ԓI����
(5) �I�u�W�F�N�g�|�����|�@�\�ɂ�镪��
(6) ���z���C���[�W����
(7) ��X�̉����� (1)
(8) ��X�̉����� (2) �]���̂��̂̓���
(9) ��X�̉����� (3) ������j�⎅
(10) ��X�̉����� (4) �V����������
(11) ������̓������Ƃ�������
(12) �K�p���Ⴉ��w�Ԃ���
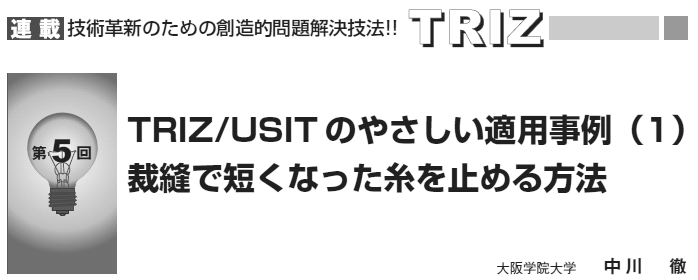
�Z�p�v�V�̂��߂̑n���I�������̋Z�@!! TRIZ
��5�� TRIZ/USIT�̂₳�����K�p����i1�j
�ٖD�ŒZ���Ȃ��������~�߂���@
���w�@��w ���� �O
InterLab��, 2006�N 5���� (No. 91), pp. 49-54
�@���̘A�ڂł́A�Z�p�v�V�̂��߂ɑn���I�ɖ�������������@�_�Ƃ��āATRIZ�����グ�Đ������Ă��Ă���B��1���Q&A �̌�A��2�`4��ɁATRIZ�̗��j���q�ׁA���\�A�Ŏ�������
�̌�A��2�`4��ɁATRIZ�̗��j���q�ׁA���\�A�Ŏ������� �A�āE���ɓ`����Ĕ��W��
�A�āE���ɓ`����Ĕ��W�� �A��������E�Ŏ�e����ĕ��y���Ă��Ă���
�A��������E�Ŏ�e����ĕ��y���Ă��Ă��� ���Ƃ��q�ׂ��B
���Ƃ��q�ׂ��B
�@�����̎��M�v��ł́A������TRIZ�̑S�e���܂Ƃ߂āA���ꂩ�珇���ATRIZ�̒m���x�[�X��\�t�g�E�F�A�c�[����������A�������̋Z�@��������悤�ƍl���Ă����B�������A���̐�������͂�c��ɂȂ��Ă��܂����ꂪ���邽�߁A����܂��ATRIZ �i�����TRIZ���₳��������USIT�j��K�p�����₳���������������悤�Ǝv���B
�@�ŏ��ɁA�ǂ�Ȏ�����A�ǂ��w�ԂƂ悢�̂��ɂ��āA���ӂ𑣂��Ă��������B���̏�ŁA�\��̂悤�Ȑg�߂Ȏ�����������B
(1) TRIZ�̎���̊w�ѕ�
TRIZ���w�ڂ��Ƃ���Ƃ��ɁA�T�O�I�i���_�I�j�Ȑ�����A�Z�@�̈ꕔ�n�I�̐�����ǂ蕷�����肷�邾���ł͂悭������Ȃ��āA���ۂɓK�p��������w�т����Ƃ����̂́A����ł����v�����Ƃł���B�S�_�̋t�オ��ł��A��荂�x�ȑ�ԗւł��A���_�����K���Ăł����l�͂��Ȃ��ɂ������Ȃ��B
�@�������A�ǂ�Ȏ�ނ̎��Ⴊ�~�����̂��A������̂��A�]�ނׂ��Ȃ̂��A�w�ԉ��l������̂��A�����āA������ǂ̂悤�Ɋw�ԂƂ悢�̂��A�Ȃǂɂ��āA���X�ɂ��ċc�_����������̂ŁA���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�uTRIZ���g���ăr�W�l�X�I�ɐ�����������͂���̂��H�v
�u���������̋Z�p����ł̍Ő�[�̐V�����K�p����͂Ȃ��̂��H�v
�u�Â��Z�p�ł̎���ł́A�܂�Ȃ��B�v
�u�т����肷��悤�ȉ������A�K�p�͈͂������ł͂Ȃ����B�v
�u����ȑ�K�͂ȉ��ς́A�R�X�g���œK�p�ł��Ȃ�������ɗ����Ȃ��B�v
�u���̂悤�ȓ����́A���łɒN�����l���Ă���̂���Ȃ��̂��H�v
�u��������������Ă��A�ǂ̂悤�ɍl���Ă�����̂���������Ȃ��B�v
�u������q���g�ɂ��ĂЂ�߂����̂��A�����ł͕�����Ȃ��B�v
�u�N������������Ƃ���t���Ő������Ă��A���H�Ŗ{���ɂł��邩�ǂ����킩��Ȃ��B�v
�u����ȁAToy Problem�ł͂��������Ȃ��B�v
�c
�@�����̗v���A�ᔻ�A�^��A���Ȃǂɂ́A�����Ă���l�̗���E��]����͂����Ƃ��ȓ_�����邪�A�K�p����̊w�ѕ�����l����ƊԈႢ����t����B�����A��������������c�_���悤�Ƃ���ƁA����S�����g���Ă�����Ȃ����낤����A��߂�B
�@�����A�����_���̑I��̑�ԗւ̋Z�ɂ�����A�̂̂��݂��݂̗͂̓������^�C�~���O�̎����Ȃǂ��A�����̔]�Ƀ��A���^�C���ɓ`����ĕ��������Ƃ��Ă��A�����̑̂̒b�����Ɣ\�͂ł͋��炭�����ł��Ȃ����낤�B
(2) ���̓K�p��������グ���|
�@������グ��K�p����́A���w�@��w���w���̎��̃[�~�ŁA���c���N���s�Ȃ������ƌ����̐��ʁi2006�N1���j�ł���B
�@���̃[�~�̗l�q�́A���̂��ї����グ���w�w���ɂ��w���̂��߂�TRIZ�z�[���y�[�W�x �����Ă��������ƕ����邾�낤 �i�����wTRIZ�z�[���y�[�W�xhttp://www.osaka-gu.ac.jp/ php/nakagawa/ TRIZ/
�����Ă��������ƕ����邾�낤 �i�����wTRIZ�z�[���y�[�W�xhttp://www.osaka-gu.ac.jp/ php/nakagawa/ TRIZ/ ����A�N�Z�X�ł���B[����ɂ��Љ
����A�N�Z�X�ł���B[����ɂ��Љ (2006. 3.17)]�j�B
(2006. 3.17)]�j�B
�@���́A2�N������Ɂu�n���I�������v�Ƃ����e�[�}�iTRIZ/USIT���܂ށj�ŁA90��13��̍u�`�����Ă��� [2001�N�x�̍u�`����  ]�B3�N������̏T1��90���̃[�~�ł́A�Z�p�I�f�{���܂��Ȃ��w�������ɑ��āATRIZ/USIT�̕�����ǂ܂�����A���_�I�ɋ����悤�Ƃ��邱�Ƃɂ͍���������B�����ŁA���낢��Ȏ���ʼn��K������TRIZ/USIT�̍l�������w�����B�܂��A���ƌ����i�����I�ɂ� 4�N���̏H�ȍ~�j�ł́A�g�߂Ȗ���TRIZ��USIT��K�p���Ď����ʼn�������悤�Ɏw�������B
]�B3�N������̏T1��90���̃[�~�ł́A�Z�p�I�f�{���܂��Ȃ��w�������ɑ��āATRIZ/USIT�̕�����ǂ܂�����A���_�I�ɋ����悤�Ƃ��邱�Ƃɂ͍���������B�����ŁA���낢��Ȏ���ʼn��K������TRIZ/USIT�̍l�������w�����B�܂��A���ƌ����i�����I�ɂ� 4�N���̏H�ȍ~�j�ł́A�g�߂Ȗ���TRIZ��USIT��K�p���Ď����ʼn�������悤�Ɏw�������B
�@�u�ٖD�ŒZ���Ȃ��������~�߂���@�v�Ƃ����e�[�}�́A������Ă����������̒�����A���c�N���I���̂ł���B�ނ�͏��w�Z�̉ƒ�ȂŏK���čٖD���o�����Ă���B
�@���̎���ł́ATRIZ�Ƃ�����₳��������USIT���g���Ă��邪�A�u���ȏ��I�v�u�}�j���A���I�v�ȓK�p�@�ł͂Ȃ��B�搶��TRIZ/USIT���n�m������ŁA�iUSIT����̂ɂ��āj���R�Ɏg���ă��[�h���Ă���A����̊w���́ATRIZ/USIT�ɂ��ė������\���łȂ��܂܂ł�͂莩�R�ɔ��z���Ă���B�����Ŏg���Ă���l�����͂��낢��Ȗ��ɓK�p�ł�����̂ł���B
�@���̎���̂悢�_�́A���̐ݒ�A���́A������̐����Ƃ����A�ꕔ�n�I�������Ă��邱�Ƃł���B���������ۂ̎v�l�ߒ��͉��s�����藈���肵�Ă��邪�A����������`�Ŏ������B����ł��v�l�̉ߒ��̓g���[�X�ł��Ă��邩��A�{�e�̖����ɕ⑫��������B
(3) ���̐ݒ�
�@���̏͂��̂悤�ł���B�u�ٖD�ŁA�D���I���ɂ͎�������Ŏ~�߂�B�ʏ�́u�ʎ~�߁v�i�}1�j�Ŏ~�߂�B���āA���܁A�D���I����Ď~�߂悤�Ƃ�����A�]���Ă��鎅�̒������j�̒��������Z���āA�ʎ~�߂��ł��Ȃ����Ƃ����������B�Z���Ȃ��������w��Ō��Ԃ̂͑�ςł���B�����~�߂�悢���@���l����B�v
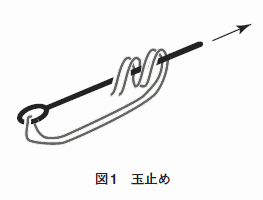
USIT�̂����ɏ]���āA�܂����������Ɩ��m�ɂ��悤�B
�ia�j�u�����Ă��邱�Ɓv�́A�]��̎����Z���āA�֗��Ȓʏ�̎��̎~�ߕ����ł��Ȃ����ƁB
�ib�j����āA�u�����������ۑ�v�́A�D���I���ŁA�]���������j�̒������Z���Ȃ����Ƃ��ɁA�����~�߂�悢���@�����o�����Ƃł���B
�ic�j���̏��u�Ȍ��Ȑ}�v�Ɏ����ƁA�}2�̂悤�ł���B
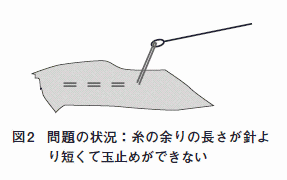
�id�j�u�l�����鍪�{�����v�́A���̗]�����j�̒������Z�����Ƃł���B
�ie�j�u���̖��Ɋւ���Ă�����́i�I�u�W�F�N�g�j�v�́A�i�D�����Ƃ��Ă���j�z�A�j�A�i�]��́j���A�����āA�i���łɖD�����j���ł���B
�@�����A�ia�j�`�ie�j�́u �v���̍��ڂm�ɂ��邱�Ƃ��AUSIT�ł́u����K�ɒ�`����v�Ƃ����B�k�ʏ�͍ŏ��̒i�K�Ŗ�肪�����ƞB�����t�s���Ă��邩��A���̖���`�̒i�K���d�v�ł���B�l
(4) ���̕��́F��ԓI�E���ԓI����
�@���͂���ɓ������āA��ԓI�ȓ����A���ԓI�ȓ������ᖡ���邱�Ƃ́A�命���̖��Ŕ��ɗL�v�ł���B
�@�D���I���ɂ͕��ʁA�k����I�ɂ����l�u�������ԁv�B����͉��̂��߂��낤���H�@�v����ɁA�k��ԓI�����ł����l�u���̒[�ɒc�q������Ă���v�̂ł���A�u���̒[�����Ă���v�̂ł���B����́A�k�@�\�I�ɂ����l�u�����߂������Ɏ�����������ꂽ�Ƃ��ɁA�����z�ɐ��荞��ōs���Ȃ��悤�ɂ���v���߂ł���B
�@��ԓI�ȓ����Ƃ����_�ł܂��A�u���ԁv�Ƃ��A�u�j�̌��v�Ɓu���v�Ƃ��́A�g�|���W�ɊW������̂ŁA�����Ɣ����Ȃ��Ƃ�����B������ł��A���ׂĂ��Ȃ����Ƃ�����B�܂��A��q�̂悤�ɁA�j�́u���v�����S�ȁu�ցv�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ă��悢�̂��ƕ�����B
�@���ԓI�ȓ������l���邱�Ƃ́A���̏ꍇ�ɂ͍ٖD�̃v���Z�X�i�H���j���l���邱�Ƃł���B�ʏ�A���̂悤�ȍH�������ǂ�B
�@ �D���ׂ��z�ƁA�j�Ǝ���p�ӂ���B
�A �j�̌��Ɏ���ʂ��A�����A�[�����ԁB�i��d�D���Ɠ�d�D���̏ꍇ������j
�B �z��D���n�߂�B
�C �D������r���B�^�j�A������������B
�D �D���I���A������������B
�E �ʎ~�߂����A������āA�I���B
�@�{���̖��ł́A�D���I�����A�E�����悤�Ƃ��āA����ɑ������Ă���B
�@�����ʼn����̕����Ƃ��āA���̇E�̉ߒ������ōH�v���Ă��悢���A�D�A����ɇC�̍H���܂ŋt����Ă�蒼�����@������A����ɂ́i�{���́j�@�`�D�̍H���̂��ꂼ��ʼn��炩�̑��\�ߍu���Ă������@������̂��A�ƕ�����B�k����ɍH���̏��Ԃ�ς���ꍇ������B���̂悤�Ȋϓ_�̓v���Z�X�������ꍇ�̏퓹���ƁATRIZ/USIT���w�Ԃƕ������Ă����悤�ɂȂ�B�l
(5) �I�u�W�F�N�g�|�����|�@�\�ɂ�镪��
�@����ɖ����悭�������邽�߂ɁAUSIT�ł́u���݂̃V�X�e�����u�I�u�W�F�N�g�|�����|�@�\�v�̊T�O�ŕ��͂���v�Ƃ����B�ȒP�ɂ����ƁA
�u�I�u�W�F�N�g�v�͍\���v�f�̂��Ƃł���A�u�����v�Ƃ͐����̃J�e�S���̂��ƂŁA�u�@�\�v�Ƃ͈�̃I�u�W�F�N�g��������̃I�u�W�F�N�g�ɋy�ڂ��ω����̍�p�̂��Ƃł���B
�@�{���ɂ�����V�X�e���̃I�u�W�F�N�g�́A����`�́ie�j�ŗ��� 4�� �i�z�A�j�A�]��̎��A�D�������j�ł���B����4�ɏœ_���i���čl����ƁATRIZ/USIT�ł͑E�߂�B
�@���̉����̂��߂Ɏg���f�� �iTRIZ�ł́u���\�[�X�i�����j�v�Ƃ����j�Ƃ��ẮA����4�K�w������ƁATRIZ�͋�����B
�i1�j���ɒ��ڊւ��4�̃I�u�W�F�N�g�A
�i2�j�����̃I�u�W�F�N�g���C���܂��͒lj��������́i�`��ς����j�A2�{�ڂ̐j�Ȃǁj�A
�i3�j���ɂ����Ēʏ킷������ɂ������ �iTRIZ�ł́u�����ɂ�����́v�Ƃ����j�i�Ⴆ�A�͂��݁A�{�^���A�A�C�����Ȃǁj�A
�i4�j���̑��̂��́B
�@�ł��邾���]���Ȃ��̂������ɁA�ŏ����̕ύX�Łi���Ȃ킿��L�� �i1�j�ɋ߂��K�w�Łj�A��������Ɩ�����������悤��TRIZ/USIT�ł͑E�߂�̂ł���B
�@���ɁA����4�̃I�u�W�F�N�g�́u�����v���������悤�B�u�����v�Ƃ����̂́A�����̃J�e�S���i��ށA���e�j�̂��Ƃł���A�e�I�u�W�F�N�g�͑��l�ȑ��������B�Ⴆ�A�j�́A�����A�����A�f�ʌ`��A�ގ��A��[�̉s���A���a�A�\�ʂ̊��炩���A�Ȃǂ̑���̑��������B�e�������A�����Ɋւ�����́u�����v�𐬂���USIT�ł͕\������B���̊e�����̒l�̍ו��i�Ⴆ�A�j�̒����� 5 cm�� 6 cm���j����ɂ���̂łȂ��A�����Ƒ�݂͂Ɂi�萫�I�Ɂj�������Z������������ɂ���̂�USIT�̗���ł���B
�@���āA�{���̖��Ɋւ���X�̑����������Ă����ƁA���ʂ̈Ӗ��ł͂��̒l���i�萫�I�Ɂj�Œ�E�s�ςł���A�͂��߂�����́u����v�ƍl��������̂��������ƂɋC�����B�����Ă���炪�A�u���i���邱�Ɓj�v���\�����Ă���̂ł���B�Ⴆ�A
�E ���̒����i�]���j�͕ς��Ȃ��^�L�тȂ��B
�E �j�̌`���������ς��Ȃ��B
�E �j�̑����͖D�����߂ɍׂ����Ƃ��K�v�B
�E �j�̌��̌a�͏������B�i������A����j�̌��ɒʂ��̂͑�ρB�j
�E ��d�D���̎��͐�Ȃ��Ɛj�̌����甲���Ȃ��B
�E �j�̌��͍Ō㕔�ɂ���B
�E �������Ȃ��Ǝ~�߂��Ȃ��B
�@�����́u������O�v�����āA���́u���{�����v�ɂ��������Ă��Ȃ������B�������A���͂����͂����́u�v�����݁v�ł���A�����́u����v�����O���Ă݂邱�Ƃ��u�n���I������v�����Ȃ̂ł���B�k���c�N�������̐�����u���{�����v�Ƃ��ċL�q�����̂����āA���͂��̂��Ƃ̏d�v���ɋC�Â����B�l
�@���Ɂu�@�\�v�ɂ��čl���悤�B�j���u�D���@�\�v�������Ă���͓̂��R�ł��邪�A���܂͂����D���I����Ă���̂����炻�̋@�\�͖��ɗ����Ȃ��B�u�ʎ~�߁v�ł̐j�̋@�\�́A�u���������t����y��ɂȂ�A���̊������ւ̒��Ɏ��̖��[��ʂ��A���̌��ʌ��іڂ����v���Ƃ��Ƃ�����B���̂悤�ȋL�q�͂悭�悭�ώ@���Ȃ��ƂȂ��Ȃ�������Ȃ��B
�@�Ȃ��ATRIZ�ł�USIT�ł��A�I�u�W�F�N�g�Ԃ́u�@�\�I�ȊW�v�̐}�����̂��W���̕��@�ł���B�����A���̗�ł͍������X�L�b�v���悤�B
(6) ���z���C���[�W����
�@�����USIT�ł́A�u���z�̃V�X�e���̃C���[�W�v�����Ƃ����B�����āA�u���z�̌��ʂ��C���[�W���Đ}�ɕ`���A���������̎�i�́i�܂��������Ă��Ȃ��̂�����j�`���Ă͂����Ȃ��v�Ǝw������B�Ȃ��Ȃ���������ł���B�����ł͐}3�̂悤�ɁA�]��̎����u�ЂƂ�łɁv�ւ����A���̗ւ����̒[���ʂ蔲���Ă������Ƃ��C���[�W�����i�u�j�v�͖{���łȂ�����`���Ă��Ȃ��j�BUSIT�ł́A�u���@�̗��q �iParticles�j�v��������\�ɂ��Ă���ƃC���[�W���āA�ނ�̐U�镑�����l�@����̂ł��邪�A�����Ȃ�̂ŏȗ�����B
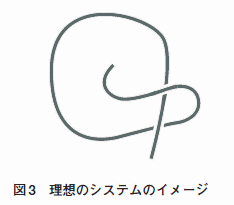
(7) ��X�̉�����i1�j
�@�ȏ�̕��͂܂��āA���m�̕��@���܂߂čl������Ă����낢�돑���o���A�V�����i�Ǝv���j�A�C�f�A������Ă������B
�@�܂��A���ʂȕ��⓹����g��Ȃ����@�ɂ͈ȉ��̂��̂��l������B�k �l ���͍l�����B
�ia�j�z�ɖD���������̎�����������o���āA�ꎞ�I�ɗ]��̎������āA�ʎ~�߂�����B�k���\�[�X�̊��p�l
�ib�j�����i���āj�j����O���A�������̖D���ڂ������āA�]�T�̂���]���̈ʒu�Ŏ������ԁB�k�H����߂�l
�ic�j�j�̐�[�������A�]�����̎��ŗւ����A�i���іڂ��ł���悤�Ɂj���̗ւɐj�̌�������ʂ��A�r���Ŏ~�߁A������Ă���j���߂��A���̌��іڂ����� �i�}4�j�B�k�u���𑀍삷�铹��v�Ƃ��Đj���g���A�Ő}3�����s���悤�Ƃ���B�l��ʓI�Ɏg������@�����A���ŗւ�����ɍ��̂�����A���K��v����B
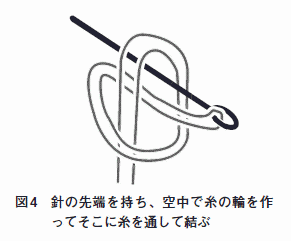
(8) ��X�̉�����i2�j�]���̂��̂̓���
�@���ɁA�]���̕���������������悤�B
�id�j�ނ�̉��̏d��̂悤�Ȃ��̂�t����B
�ie�j�z�b�N�̂悤�Ȍ`�̕R�~�߂����^�ɂ������́B
�if�j�����ׂ̍��X���b�g�������^�̃{�^����̂��̂Ɏ�������܂���B
�ig�j�]���̎����ۂ߂Đڒ��܂Ōł߂�B
�@�����̑������ގ��̏ꍇ�̉�������q���g�ɂ��Ă���B�������A�u�]���̕��v��������@�ł́A�d�オ���Ɂu�]���̕��v���c��A�]�܂����Ȃ����Ƃ�������B
(9) ��X�̉�����i3�j������j�⎅
�ih�j���ɗ؏�̕\�ʍ\�����������āA�D�������ɂ͐i�ނ��A�t�s���Ȃ������݂ɂ���B�i�������A�g�p���ɖ����鋰�ꂪ����B�j
�ii�j�u������ς�����j�v�F�j�𒆉��ł˂�����2�i���ɂ��āA�ʎ~�߂̕K�v���������Ƃ��Ɏ��O���āA�u�Z���j�v�Ƃ��Ďg�� �i�}5�j�B�k����́A�u������ς���v���߂̋���̍�ł���A�r�����m�ȃA�C�f�A�ł���B���̈Ă����c�N���o�����Ƃ��A���́u����Ȃ̐�������ς���v�Ƃ������B�������A��q�̏�������̌��`�ƂȂ����B�l
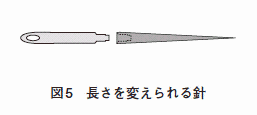
�ij�j�u���ɐ،���������j�v�F�j�̓����}6�̂悤�ɂȂ��Ă��āA�������S�ɕ��Ă��Ȃ��B���̂悤�Ȏs�̕i���������B���̐�����ɒʂ��Ȃ��Ă��A���̓r�������̐،����ɉ������ނƌ��Ɏ�������B�ēx���̓r����،����ɉ������ނƁA�i��d�D���̎����ւɂȂ����܂܁j�����j����O���B������g���Ǝ���������O������^�ʂ����肷��̂��y������A��U����������O���A�}6�̂悤�Ɏ���j�Ɋ����t���Ă���A�ēx�������ɒʂ��A�ʏ�̂悤�ɐj��O�Ɉ��������ƁA�ʎ~�߂��ł���B�k���c�N�����̐j���������狳���Ė���Ď����Ă����Ƃ��́A��͂�Ռ��I�ł������B�����A����ȃA�C�f�A������̂��A��x�ʂ��Ƃ����Ɣ�����̂��A�Ƃт����肵���B�l

(10) ��X�̉�����i4�j�V����������
�@���āA��������̉����{�����̃I���W�i���ł���B�����������������̓��ōl���o�����̂�����u�n���I�v�ł���B�������A���l�ȈĂ��u���łɂǂ����ł��ꂩ���l���Ă����v�\���͍����B������A��������p�V�ĂɂȂ�Ȃ���������Ȃ��B�u�V�K���v�A�u�������v�A�u�n���I�v�́A�߂�����ǂ��݂��Ɉ�����T�O�ł���B
�@��L�̂��낢��ȉ�������l������ŁA�������x�[�X�ɂ��āA�u�ȒP�ȏ�������g���V�����āv�����̂悤�ɐ������邱�Ƃ��ł����B
�ik�j�u�X�g���[�̏�����v�F�X�g���[�̐�[����1�`2 cm �茇�����}7�̂悤�ȏ�����B���m�̕��@ �ic�j�̗v�̂ŁA���̐�[�Ɏ��������A��O����X�g���[�̍a�ɉ��킹�Đj�̌㕔������B���̏�ԂŎ����A������������Ȃ���X�g���[����O�ɔ������B����́ic�j�Łu�Ɂv����Ă������̗ւ�����ɍ��A���A���̗ւ̒��Ɏ���ʂ��悤�ɐj�̓������K�C�h������̂ł���B
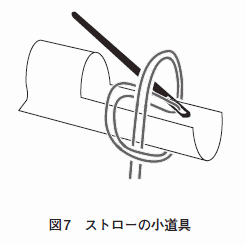
�il�j�u�ʎ~�ߐ�p�̐j�v�Ƃ����������F�D���I�������ŁA���܂܂ł̐j�ł͋ʎ~�߂��ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ��ɁA�Z�������u�ʎ~�ߐ�p�̐j�v�ɐ芷����B���́u�j�v�͂��͂�D���K�v���Ȃ��̂ŁA��[������Ă���K�v���Ȃ��A�ׂ��K�v���Ȃ��A�]���Č��������傫�����āA�����ȒP�ɒʂ���T�C�Y�ɂ���悢�B�}8�̂悤�Ȃ��̂ŁA�S�̂�2 cm���x�ƒZ������B�㕔�̌��́A�~�`�ł��悢���A�}�̂悤�ɃX���b�g��̕��������Ƃ�����Ɣ�����̂�h���邩��悢���낤�i���邢�́A�ij�j�̌`���ł��悢�j�B�v���X�`�b�N���Ȃ����ł��邪�A���i�ɂ���Ȃ���������悢�B
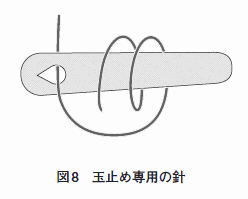
�im�j��L �il�j�̉��ǔłŁA�㕔�Ɍ��͂Ȃ��A�X���b�g�ɂ��Ď����͂��ݍ��ށB����̕������̂��̂����ȕւɑ���ł���B�}9�B
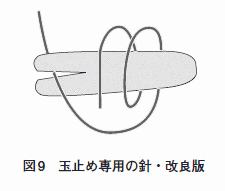
�in�j��L �im�j������ɉ��ǁB�����₷�����邽�߂ɁA�u�ʎ~�ߐ�p�̐j�v�̌㕔������B�im�j�̌㕔�̕Б����������āA��Ώ̂ɂ���B�����͂��ރX���b�g�́A��[����1 cm���x�̏��ɂ���i���ꂪ���̍ŏ��ɍl���Ă����u�j�̒����v�ɑΉ�����j�B���ۂɎg���Ƃ��ɂ́A�����i���܂܂ł́j�j����͂������ɁA�j�̐�[�������Ď������̏�����Ɋ����t���A�X���b�g�Ɏ����͂��݂���ł���A�j���玅��藣���A������̐�[�������đO���ɔ����A�������������Ĕ���B�O���ɔ����Ă��܂��̂ŁA������S�̂̒�����6 cm���x�ƒ����Ă��悢�̂ł���B�i�j�́u���v�������ƑO���ɂ���Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���B�j
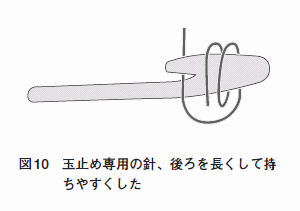
(11) ������̓������Ƃ�������
�@��L�̂悤�ȉ��������l���o���Ă����w�i�ɂ́A���낢���TRIZ�̍l���� �i�u40�̔����̌����v�Ȃǁj��USIT�̉����������@�i5��32�T�u��@�j�Ȃǂ̒��Ŏg���Ă���B���̒��ł͂����̑����̕��@���ӎ��I�^���ӎ��I�Ɏg���A�����ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ��ƍl���Ă���B������Ƃ��Đ����ɋL�q���Ă���̂́A�����̒��Łu�L�]�����ȓ����v�ɓ��B�������̂����ł���B
�@�u�X�g���[�̏�����v�́A���m�� �ic�j�̕��@�̉��ǂƂ��čl���������̂ł��邪�A����́A�u���z�̃C���[�W�v����U������Ă���B�i�������A�u���z�̃C���[�W�v�͒����ԁA���̒��ɂ����������ŁA�}�ɕ`�����̂͂����ƌ�ł������B�����Ƒ����ɕ`���Ă���悩�����ƍ��ɂȂ��Ďv���j�B���̗ւ������@�Ƃ��čŏ��́u���v��̂��́A�u���b�p�v��̂��̂��l���A�������O���i���݂Ƃ͋t�j�ɍl���Ă����B�i�o�߂��悭�v���o���Ȃ����A�����u�،����̂��錊�v�̉����h������j�u���v��ł͂Ȃ��āA�����J�����u�a�v��ł悢�̂��A�u�a�v��̕����悢�̂��Ǝv�������B����Ǝ�������t�ɂł���B�����C�����āA�X�g���[�Ŏ��삵�A���ۂɂ��܂��s�����Ƃ��m���߂��B
�@�u�ʎ~�ߐ�p�̐j�v�̏�����́A2�i���́u�Z���ł���j�v�����`�Ƃ��āA�������̏����ȉ��ǂ̌��ʓ���ꂽ���̂ł���A���̉ߒ��͏�L�ɐ��������B�u����v���O�����߂̋���̍A����ɔ��W�������̂ł���B�K�v�ȁu�@�\�v������I�m�ɉʂ����悤�ɁA���܂��܂ȁu�����v�����Ă����Ă���B
(12) �K�p���Ⴉ��w�Ԃ���
�@�ȏオ�u�ٖD�ŒZ���Ȃ��������~�߂���@�v�Ƃ����K�p����ł���B�����Ȏ���ł��邪�A�g�߂Ȗ��ŁA�n���I�������̈ꕔ�n�I�������Ă���_�ňӋ`������B
�@���̎���Ŏg���Ă���A�u���̒�`�v�A����сA�u��ԁE���Ԃ̓����̕��́v�A�u�I�u�W�F�N�g�|�����|�@�\�ɂ�镪�́v�A�u���z�̃C���[�W�ɂ�镪�́v�Ƃ������@�́A�ǂ�Ȗ��ɂ����ʓI�Ɏg����B�����̕��͂���̉����������ɂ��낢��Ȍ`�Ŋ��p����Ă��邱�Ƃ𗝉��������������B�����āA�����̕��@�� �i�₳��������TRIZ�ł���jUSIT�̕W���菇�Ȃ̂ł���B
�@������̐����i�K�́A�\�ɂ͌���Ă��Ȃ����̒��́i�����č���^����́j�v�l�̃v���Z�X����R����B���̎v�l�̓����́A�]���@�̂悤�Ɂu�q���g��͍����A�ޔ�v�l�ōl����v�̂ł͂Ȃ��B���͌��ʂ�TRIZ�̔������� �i���邢��USIT�̉����������@�j�Ȃǂ��g���āA�l���������n��o���A�u�����Â����������v�l�̓w�́v�����Ă���B���͂��ꂪTRIZ/USIT�ɂ��u�n���I�������v�̖{���ł���Ǝv���B
�@����ɂ�������̐g�߂ȓK�p������������\��ł���B
�ŏI�X�V�� : 2006. 5. 9 �A����F�@���� �O nakagawa@utc.osaka-gu.ac.jp