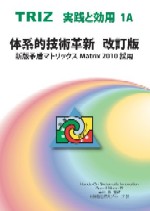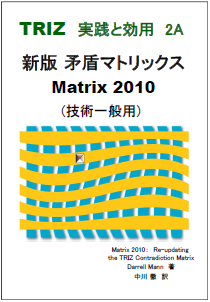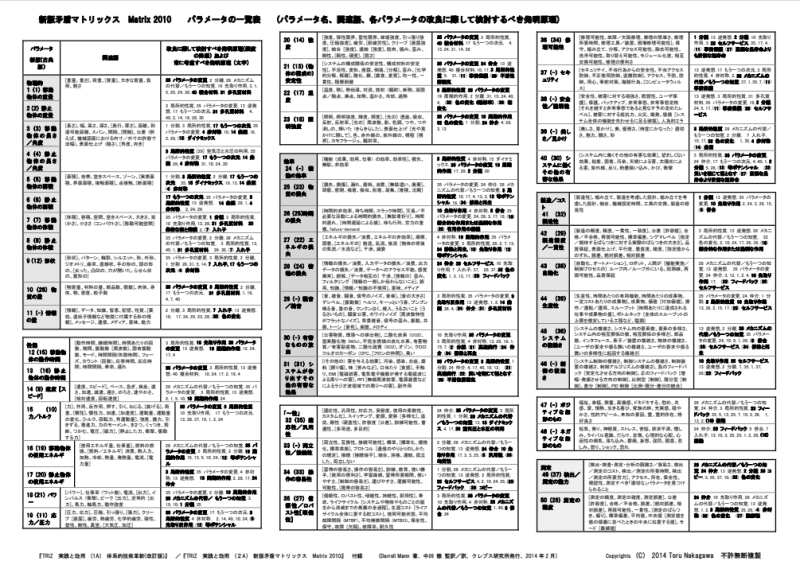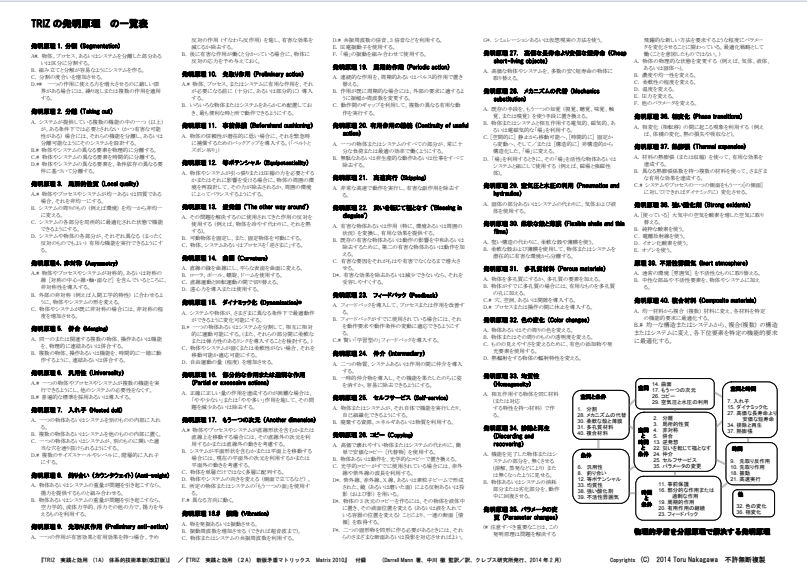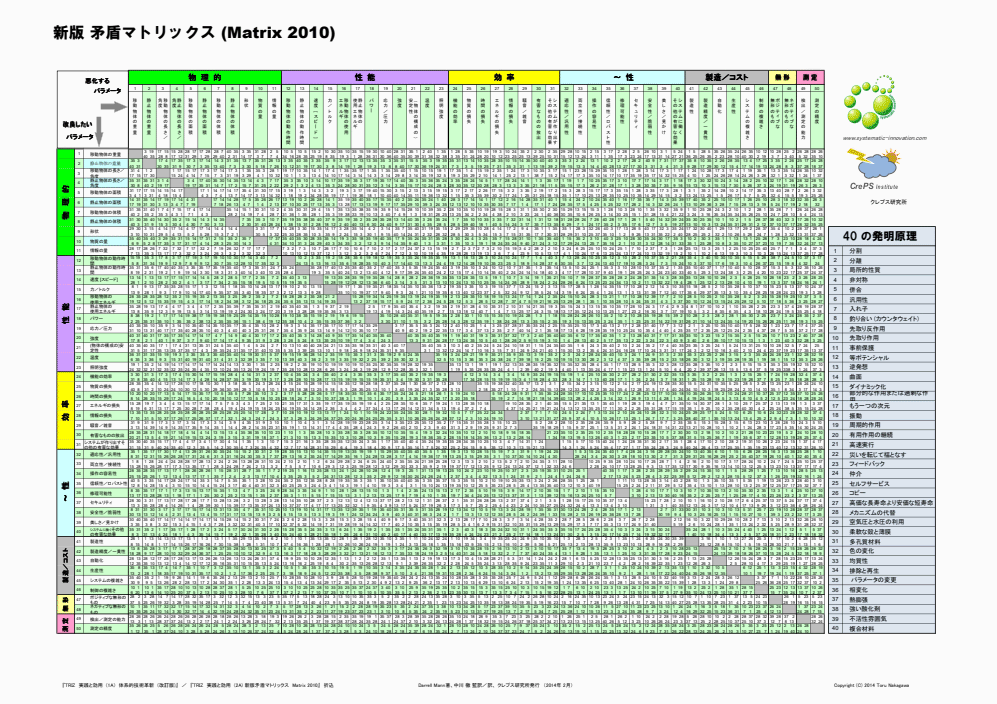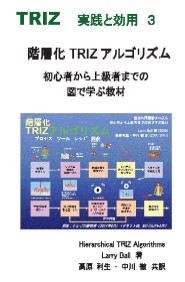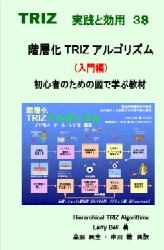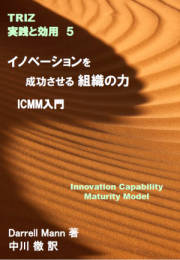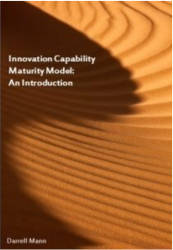本書のテーマについて
いま世界中で、「イノベーション」が注目され、求められています。成功すれば、製品が売れ、ビジネスが急拡大し、産業構造が変わり、社会が変わり、人々の生活が大きく変わり、世界情勢さえ左右するものになるからです。各国の政府も、数多の大企業や中小の企業も、そして何億人かの科学者・技術者・事業家・ビジネスマン・農業者さまざまな人々が、あらゆる分野でそれを夢みて、また真剣に取り組んでいます。しかし、イノベーションを目指したプロジェクトのほとんどが失敗・不成功で、成功するのは2%程度だと(著者は)言います。「どうすれば、イノベーションを成功させる能力を作り上げることができるのだろうか?」というのが本書のテーマです。
イノベーションは、「品質管理」、「生産性向上」、「継続的改善」、「最適化」などの目標設定とは、本質的に違う、と著者は言います。いままでのものを改良していく延長線上にあるのではなく、いままで想定していたこと(常識の前提)を破って、新しい観点・発想・概念・技術などが必要なのです。
では、「発明」とか、「創造的問題解決」とは違うのかと、疑問になります。これらにはいろいろなレベルのものがありますから一概には言えませんが、「矛盾を解決したアイデア」であるなら、イノベーションの種にはなるでしょう。しかし、それが、実地に実現され、社会に受け入れられないと、イノベーションにはなりません。
著者の「イノベーション」の定義は簡潔であり、「成功したステップチェンジ(階段状の変化)」です。この定義の後半は、該当のもの(製品、サービス、技術など)の価値の変化をグラフにしたときに、非連続にジャンプしていることを意味し、上記の「矛盾の解決」による飛躍に対応しています。定義の前半は、その成果が社会(国民一般、市場)に受け入れられたこと、最も端的には、得られた利益が投入した全コストを上回ったこと、を意味します。成功したかどうかは、アイデアの段階や製品の市場投入の段階ではなく、投入後すくなくとも数年しないとわからないことです。
この定義のポイントの一つは、イノベーションのための方法や手段については何も限定していない(「発明」などの言葉がない)ことです。また、対象の分野・領域も限定していません。2000年頃には、技術分野に焦点がありましたから、私はイノベーションという外来語を避けて「技術革新」と訳したことがあります。いまは領域を限定しないで、イノベーションというのが一般的です。
上記の「成功した」という実績は、発明とか創造的問題解決による「アイデア」「解決策」の良さだけでは得られません。全体状況の分析とニーズ(需要)の把握、問題分析の矛盾の解決によるアイデア獲得、詳細な設計と改良、製造・物流、市場投入と販売・アフターサービス、などすべての過程を確実に実施していかなければできません。それは全社的な組織活動が、すべての段階で的確・迅速・果敢に行われて初めてできることです。技術・人材・設備・販売網・経営などの状況が整っており、経済環境・社会環境にも恵まれる必要があるでしょう。「アイデア・解決策」の段階では「常識の前提を破る」個人の創造性が求められ、その他のすべての段階でそれを実現する全社活動が求められるところに、イノベーションの成功の難しさがあります。(主として)「アイデア」から出発するイノベーションプロジェクトの2%程度しか成功しないのは、「常識破りのもの」を実現させねばならない全社活動のウエイトが大きいからでしょう。この意味で、「イノベーションを成功させるのは、組織の力だ」と本書は言うのです。では、「そのためには組織はどのような考え方で、どのように運営されるべきか?」というのが、その次の、本書の中心テーマです。
本書を訳出した背景と経過
さて、ここで、本書訳出の経過を記しておきます。私は1997年に、TRIZ(発明問題解決の理論)を知り、以後、「創造的問題解決の方法」の研究・教育・普及に努力してきました。その中で、TRIZを現代化して、研究・著作・実践・指導している Darrell Mann の仕事に傾倒しました。彼の発表「TRIZ の現代化: 1985-2002年米国特許分析からの知見」(2003)を私の『TRIZホームページ』に掲載し、彼の著書2編を和訳出版しました(『体系的技術革新』(2004, 2014)、『矛盾マトリックス』(2004, 2014))。さらに、第1回TRIZシンポジウム (2005)でも基調講演をしてもらっています。その後Darrell Mannは、「Systematic Innovation」を標語にして、ソフト開発分野、ビジネス・マネジメント分野、イノベーション方法論一般、などに矢継ぎ早に論文・著作を出して行きました。私はそれらを到底追いきれませんでした。
昨年(2020年)秋に、コロナ禍でのオンライン開催の国際会議で、久しぶりにDarrell Mann の講演を聞き、その研究の進展の凄さと重要さを改めて認識しました。自分の学習不足を反省し、彼の助言を受けつつ取り掛かったのが(ビジネス関連は一旦横に置いて)、本書『Innovaton Capability Maturity Model』(2012) の和訳です。著者の了解のもとに、和訳原稿全文を4回に分けて『TRIZホームページ』に掲載しました。その掲載後、著者から改めて、日本語版への前書き(「ICMMの10年」)と、後書き(「ICMMの未来」)を書いて貰いましたので、本書の現在の進展状況と意義が非常によくわかるようになりました。
本書の構成と概要
本書の概要を、章ごとに書くと、以下のようです。
第1章: イノベーションの定義、イノベーションが失敗する主な理由
第2章: 「イノベーション能力成熟度モデル(ICMM)」の作成の意図と経過、考え方
第3章: イノベーションの中核プロセス: 6ステップサイクル(感知・解釈・設計・決定・調整・応答)
第4章: 進化のS-カーブ、現行S-カーブから次のS-カーブへの飛躍、飛躍のための「英雄の「旅」」
第5章: 矛盾、「A or B」でなく「A and B」を探求する、矛盾の定義のテンプレートと解決策の考察法
第6章: ハイプサイクル: 技術のトリガー、ハイプ(誇大広告、過大評価)、幻滅、啓蒙、定着
第7章: (組織の)イノベーション能力の自己評価、25の質問表(5選択回答)、スコアリングの方法
第8章: ICMMの5つの能力レベル(種を蒔く、チャンピオンを作る、管理する、戦略化する、挑戦する)、
イノベーションの成果の5タイプ、能力→成果の関連、各レベルの特徴(一覧表)(組織の特徴、
次のレベルへの試練、該当する教科書や方法など)
第9章: FAQ; 第10章: これからするべきこと; 第11章: 参考文献; 第12章: 連絡先
この構成で、7章までが準備、8章が本体で、(組織の)イノベーション能力の向上の段階に明確な区切りがあること、その各段階の特徴、次の段階に進むために克服するべき矛盾などを述べています。そのうちのレベル3までは、日本の大企業などで技術開発の体制として積み上げて行っているのに近いのですが、レベル4になると組織運営がずっと柔軟になり、課題と目標に応じて戦略的な再編が繰り返されていきます。詳しくは、本文を参照ください。
原書出版(2012年)以後の状況と発展
日本語版への前書きでは、2012年の出版以後の動きを述べています。特に2014〜2018年頃に、イノベーションの領域に進出してきたビッグファイブを中心としたコンサルタントたちが、継続的改善・生産性向上などをかかげ、矛盾の解決によるステップチェンジの重要性を理解しなかったので、イノベーションの世界は混乱し地に落ちたと論じます。ICMMモデルこそ、実地に使われ、その機能が実証されてきていると言います。
一方後書きでは、ICMMのレベル判定は、7章の記述から格段に進んで、どんな企業のICMMレベルも、外から客観的に測定できるようになったと言います。その方法は、公開の特許情報から、その「質」を自動的に解析できること、またその企業自身のあるいは周囲の各種の発話データを大量に集めて分析すると、組織内の士気・信頼関係・価値観などの質的情報を測定できると言います。そして、年間2000冊のビジネス教科書の内容を系統的に調査して、ICMMの各レベルと関連づける整理を行っています。これにより、ICMMのレベル間の飛躍の「旅」のための資料の蓄積が進んでおり、『英雄の旅』の本を2021‐2022年に2冊ほどを出版する予定と言います。
またすでに、昨年6月には『Hero's Start-Up Journey (英雄の起業の旅)』の本を出版しました。コロナ禍で沢山の人たちが解雇され、独自の起業を余儀なくされている。それをICMMのレベル0だと捉え、その人たちの起業が成功してビジネスとして成立する(すなわち、レベル1になる)ように、リードする本だと言います。[出版直後から、大変好評とのこと。私は日本語版の作成・出版を引き続き計画しております。]
日本語版の訳出と出版について
このような中で、著者は今回の日本語版の出版を、喜び、期待してくれています。ありがたいことです。
今回の翻訳は私が単独で行いました。構文が複雑なこと、口語的慣用表現があることなどで、翻訳には苦労しました。(硬い)直訳でないように、(ごまかしの)意訳でないように、できるだけ著者の論述・論理に忠実に、そして読みやすく分かりやすいように、心掛けております。本文中の( )は著者の注釈的表現、[ ]は訳者の注です。章内の、節や見出しはすべて訳者が独自判断で付けたものです。強調のための太字も訳者がつけました。段落の区切りも少し増やしています。これらの編集作業を原著者が許容してくれていることは、ありがたいことです。もし、お気づきの改良点がありましたら、ご連絡ください。
表紙のアートワークは、著者自身の作成です(12章末尾を参照ください)。本件は、『TRIZ 実践と効用』シリーズの第5巻として、クレプス研究所から刊行します。書名は趣旨が分かりやすいように、『イノベーションを成功させる組織の力: ICMM入門』を選びました。 原書はA6 A5 サイズですが、訳書はB5サイズにしました。Amazonのサイトで販売(クレジットカード支払い)の予定です。『TRIZホームページ』で和訳の全文を先行掲載しましたが、製本出版の後もホームページ上では無料公開を続ける計画です。
コロナ禍の危機の時代、大きな変動の時代の最中にあって、著者Darrell Mann教授のこの素晴らしい著作が、日本の皆さんに読まれ、日本発の多くのイノベーションが成功し、新しい時代・新しい世界の構築に寄与することを願います。特にその新しい時代が、平和で、格差が狭まり、豊かで、民主的で、明るく、創造的な活気のあるものであるようにと、祈ります。
2021年4月9日 千葉・柏の自宅で 中川 徹
jSW-TN-C1-CrePSInst-BookPublication-1408 『中川 徹 著作選集』 C1