�w�@�B�v�x�@(�����H�ƐV���Д��s�j, 2007�N 8����
���Čf�ځB���f�]�ڋ֎~�B(1)(2)(3)(4)(5) [�A�ڊ���]
[�f�ڊJ�n�F2007. 7.22; �ŏI�X�V��: 2007.12. 9]
Press the button for going back to the English top page.
�ҏW�m�[�g (����O�A2007�N 7��21��)
�{���́A�����H�ƐV���Д��s�̌������w�@�B�v�x(Machine Design) �ɏ�����Ďn�߂܂����uUSIT����v�̘A�ڋL���ł��B2007�N8���� (7��10�����s) ����A�ڊJ�n���A12�����܂ł̑S5��̗\��ł��B���Ђ̂����F�����������܂����̂ŁA�{�wTRIZ�z�[���y�[�W�x�ɂ́A���A�ڂ�HTML�łŌf�ڂ��܂� (������PDF�ł��f�ڂ��邱�Ƃ͂ł��܂���)�B�����̎Q�Ƃ̃����N��lj����܂����̂ŁA���Ђ����p�������B
�ǎ҂̊F���������̂悤�ɁA���͍�N��1������A�u�A��: �Z�p�v�V�̂��߂̑n���I�������Z�@!! �s�q�h�y�v�Ƃ����L�����A�wInterLab�x�� (�I�v�g���j�N�X�Д��s) �Ɍf�ڂ��Ă���A���ݑ� 20��܂Ōf�ڂ���A�܂������ƘA�ڂ𑱂������ł���܂��B����TRIZ�A�ڂł́A�ł��邾�����E��TRIZ�̂��낢��ȗ���荞��ŁA���̖ڂ��琮�����Ȃ����ď����Ă������Ƃ��Ă���܂��B���̒��ł�������g�����i���Ă��܂��uUSIT�v�ɂ��Ă��L�q���Ă��܂����A�ǂ����Ă��b�̈ꕔ���Ƃ��Ă̋L�q�ɂȂ�܂��B
�{���̘A�ځuUSIT����v�́A5��Ƃ������肵���ł����AUSIT�ɏW�����Ă�����Ƃ܂Ƃ߂�����ɂ���\��ł��B���̂悤�ȍ��q�̍\���ɂ���\��ł���܂��B
��1�� USIT�Ƃ͉����HFAQ 2007�N 8����
��2�� USIT�̂₳�����K�p���� 2007�N 9����
��3�� USIT�ɂ����̒�`�ƕ��͂̕��@ 2007�N10����
��4�� USIT�ɂ��n���I�ȉ�����̐����@ 2007�N11����
��5�� USIT�̎��H�@ 2007�N12�������̑�1��́AUSIT�̏Љ�����ꓚ�̌`���ŋL�q�������̂ł��B���̂悤�ȍ\���ɂ��Ă��܂��B
�Ȃ��A�ȉ��ɁA�e��̓��e�ڎ����A�����A�ꗗ�\�ɂ��Čf�ڂ��܂��B
| �� | �f�ڍ��A�y�[�W | �@�e�[�} | �ז� ���o�� | �g�o�f�� |
| ��1�� | 2007�N 8���� pp. 56-63 |
USIT�Ƃ͉����H FAQ | (1) �͂��߂ɁA(2) USIT�Ƃ�: ���̐����ߒ��A(3) USIT�̏�Ƌ��ȏ��A (4) USIT�̃��`�[�t�Ɠ����A (5) USIT�ɂ������̃v���Z�X�A (6) USIT�̎��H�@�A (7) USIT�̕��y�ƈӋ` |
|
| ��2�� | 2007�N 9���� pp. 92-98 |
USIT�̂₳�����K�p���� | (1) USIT�̖������v���Z�X�̑S�̑��A(2) �z�b�`�L�X�̐j���Ԃ�Ȃ�������@ [���̐ݒ�A���̕��́A���̐V���������A�V�����V�X�e���̂��߂̃A�C�f�A�A������̃R���Z�v�g���|���@�̏��l�̕��@�A������̎���]�A(3) �ٖD�Őj���Z���Ȃ��������~�߂���@ [���̒�`�A���ԓ����̕��͂Ƌ�ԓ����̕��́A�@�\�̕��́A���� (�\���v�f�̐���)�̕��́A���m�̂��낢��ȉ����@�A���z�̃C���[�W�����A������̃A�C�f�A���l����A�X�g���[�̏�����A�ʎ~�ߐ�p�̐j�̏�����A�{����ł̉����������i�K�̂܂Ƃ�] | 2007. 8.17 |
| ��3�� | 2007�N10���� pp. 90-96 |
(1) ���̒�`�ƕ��͂̕��@�̊T�v [���̒�`�Ɩ��̕��́A�u�I�u�W�F�N�g-����-�@�\�v�̊T�O]�A(2) �����`������@ [USIT�ɂ�����u�K�ɒ�`���ꂽ���v�A����`�i�K�̒��ӎ���]�A(3) ��蕪��(1)���݂̃V�X�e���̗��� [��ԓ����̕��́A���ԓ����̕��́A���݂̃V�X�e���̋@�\�I�W�̗����A ���݂̃V�X�e���̖��ɊW���鑮���̗���] �A(4) ���̕���(2)���z�̃V�X�e���̗��� [���͒i�K�ŗ��z�̃V�X�e�����l����Ӗ��A���z�̌��ʂ��C���[�W����A���@��Particles (�������l����)�AParticles �@�̓K�p��] | 2007.10.15 |
|
| ��4�� | 2007�N11���� pp. 100-107 |
(1) �uUSIT��6�������v�ɂ���������������i�K�̊T�v [�f�[�^�t���[�}�Ƃ����\���`���Ƃ��̈Ӗ��A�u�V�V�X�e���̂��߂̃A�C�f�A�v�Ƃ́AUSIT�ɂ�����u�A�C�f�A�����v�̒i�K�AUSIT�ɂ�����u������̍\�z�v�̒i�K�A�u������̎����v�̒i�K]�A(2) USIT�I�y���[�^ [USIT�I�y���[�^�̐����AUSIT�I�y���[�^�̑S�̑��AUSIT�I�y���[�^�̗�Ǝg�����A�v�l�̉ے���USIT�I�y���[�^�̎w�j]�A(3) �����������i�K�̕����Â� [���z�̃C���[�W����̎v�l�̉ߒ��A�����̉����Ɖ������g�����@�A������̊K�w�I�ȑ̌n��] | 2007.11. 1 |
|
��5�� (��) |
2007�N12���� pp. 89-97 |
(1) USIT�����̂��߂Ɏg���̂�?�A (2) �ǂ̂悤�ɂ��Ċw�Ԃ�?�A (3) USIT�̃g���[�j���O [�����̎������݂ƌ��吧�ł̖������AUSIT 2���ԃg���[�j���O�̃v���O����]�A(4) USIT�̏K���̃{�C���g [���𑨂���/��`����i�K�A���͂���i�K�A�A�C�f�A�̐����Ɖ�����̍\�z�̒i�K�A���������������i�K�AUSIT���ł�TRIZ�̖���]�A(5) USIT�̎��H�Ɛ��i [�g�D�̒��ł̕��y�E���H�E�蒅�����̐i�ߕ��AUSIT�̎��H�����A�Z���W���̖������̎��H�@]�A(6) TRIZ/USIT�̐��i����A(7) �܂Ƃ� | 2007.12. 9 |
[�NjL (���� �O�A2007.12. 9): ��L�̂悤�ɁA�����̌v��ǂ���A�S5��ł��̘A�ڂ������������܂����B�R���p�N�g�ɑS�̂�m�邱�Ƃ��ł�����̂ɂȂ������̂Ǝv���Ă���܂��B]
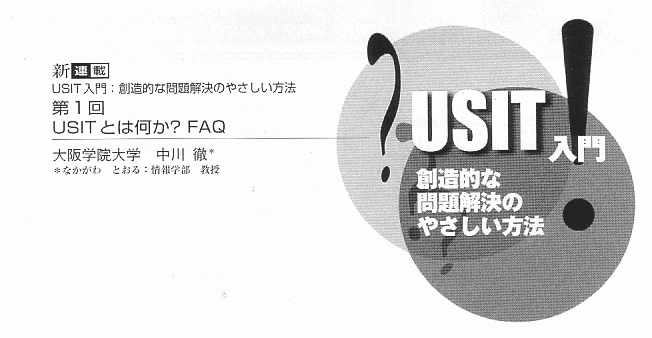
�A��: USIT����: �n���I�Ȗ������̂₳�������@
��1��?USIT�Ƃ͉����H�@FAQ
����@�O�@�i���w�@��w�j
�w�@�B�v�x�@(�����H�ƐV���Д��s�j�A2007�N 8�����App. 56-63
1. �͂��߂�
���̂��сC�w�@�B�v�x���ɏ�����āC�uUSIT����v�Ƃ����A�ڂ��T��̗\��Ŏ��M���邱�ƂɂȂ�܂����B���ꂵ�����Ƃł��BUSIT�́C�n���I�Ȗ������̂��߂̋Z�@�ŁC���ɂ��̈ꕔ�n�I�̍l��������̓I�Ɏ����C�₳�����w�сC���H�ł���悤�ɂ������̂ł��B
�����镪��ŋZ�p�v�V���i�݁C�Љ�̕ϓ����������C���܂��܂Ȋ�Ƃ������c��������ċ����ɂ��̂�������Ă��܂��B�w�@�B�v�x�̓ǎ҂̊F����͂������̂��ƁC������Z�p����̋Z�p�ҁE�����҂��Ǘ��҂��C�܂�������Y�Ƃɏ]�����Ă���l�������C��ɉ����V�������Ƃ��l���o���C�H�v���C���H���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ��C�g�ɟ��݂Ēm�炳��Ă��܂��B���퐶���ł��������C�V�����H�v���K�v�ɂȂ邱�Ƃ͂��낢�날��܂��B
����ł��C�V�������Ƃ��l���o���C������������Ă������Ƃ́C�ʏ�����ł͂���܂���B�u�n���I�ɍl����v�Ƃ����C�u�����_�炩���v�C�u���z���_��Ɂv�Ƃ����Ă��C�����Ă��낢��ȗ��������Ă��C���̂悤�ȗ͂��K�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��Ƃł��B
�����̂悤�ȐV�����A�C�f�A���v�����ɂ́C�u�Ђ�߂��v�邱�Ƃ��K�v�ŁC����͒����w�͂ƔE�ςƎ��s����̖��ɁC�ӂ��Ƃ������q�ɓ�������̂��Ƃ����̂��C�Ȋw�҂̎��т̌�����S���w�̌������瓾���Ă���ʐ��ł��B
�������C���̒����w�͂̊Ԃɂǂ̂悤�ɍl����悢�̂��C�������@�͂Ȃ��̂��Ǝv���͓̂��R�̂��Ƃł��B�����č��܂ł́C���R�z���ɍl����Ƃ����u���C���X�g�[�~���O�����̂��߂̎�v�ȕ��@�ł����B�������C����͋Z�p�I�ȉۑ�ɑ��Đςݏグ�������@�ł͂���܂���B�����ƉȊw�I�Ȋ�Ղ����������@���������͂ق����̂ł��B
���̂悤�ȗv���ɓ�������̂Ƃ��āC���\�A�̖��Ԃ�60�N�ɓn���đn���Ă������@�ɁCTRIZ�i�u�����������̗��_�v�j������܂��B���E�̓�������e�I�ɕ��͂��āC�Z�p�̊Ⴉ��Ȋw�Z�p��̌n�����Ȃ������c��Ȓm���x�[�X�����C�������̂��߂̑����̋Z�@��n��܂����B���I����C���������ɒm���C�Z�p�J���̂��߂̈�ʓI�ȋZ�@�Ƃ��āCQFD�i�i���@�\�W�J�j��^�O�`���\�b�h�i�i���H�w�j�ƕ���ł��̕K�v���^�L�������m����悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
���̘A�ڂŎ��グ�܂�USIT�i�u�����I�\���������v�l�@�v�j�́C����TRIZ�̉e�����āC�č���Ed Sickafus��1995�N�ɊJ���������̂ł��B�Z�p�I�Ȗ������̃v���Z�X���킩��₷���������܂����B���̌�USIT�͓��{�ʼn��ǂ���C���{�̂������̊�Ƃɒ蒅������܂��B
���݂̓��{��USIT�́C�c��ȑ̌n�����̂ɕ��G�ł�����TRIZ����������ĕҐ����āC�������₷���C���H���₷�������C�u�₳����TRIZ�v�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��C���ꂾ���łȂ��C�u�n���I�Ȗ������̐V�����p���_�C���v���w�������Ă���̂ł��B
���܂��܂ȋZ�p�ۑ�ɂ��āC�]���̋Z�p�J���̕��@�ōs���l�܂����Ƃ��ɁC���̕ǂ�ŊJ���đn���I�ɉ������邽�߂̍l����v���Z�X��USIT�͒��Ă��܂��B�u�Ђ�߂��v�ɂ��傫�ȃW�����v�łȂ��C�ؓ����Ăčl���Ă��钆�ŁC�������̐V���������ƐV�������z��n��o���āC�����ȃW�����v���J��Ԃ��āC��w�������ɓ��B���悤�Ƃ��Ă���̂ł��B
���̂悤�Ȃ��Ƃ𗝉����Ă���������悤�ɁC���̘A�ڂ͂��̂T��\���Ő������Ă����܂��B
��P��@USIT�Ƃ͉����HFAQ
��Q��@USIT�̂₳�����K�p����
��R��@USIT�ɂ����̒�`�ƕ��͂̕��@
��S��@USIT�ɂ��n���I�ȉ�����̐����@
��T��@USIT�̎��H�@
2. USIT�Ƃ́F���̐����ߒ�
Q. USIT�̐������̂́H
A. �p�����́CUnified Structured Inventive Thinking�B���{�ꖼ�́C�����I�\���������v�l�@�B�i���[�W�b�g�ł͂Ȃ��j���[�V�b�g�Ɣ������܂��B
Q. �N����������̂Ȃ̂ł����H
A. �č���Ed Sickafus�i�G�h�E�V�J�t�X�j���m���C1995�N�ɍ��܂����B�����t�H�[�h�����Ԃ̌������̕����w���咷�ŁC���������w�̑f�{�������C����ȑO�ɑ�w�������߂����Ƃ̂���l�ł��B
Ed Sickafus���m (2007�N)
Q. �����y��ɂȂ������̂�����̂ł����H
A. ���������́C1993�N��UC Berkeley�ł��܂��܃C�X���G���̐l������SIT�@�̃Z�~�i�[�������Ƃ��Ə����Ă��܂��B�������̕��@�Ƃ��Ĕ��ɖʔ����Ǝv���C�ނ���t�H�[�h�ɏ����ĂP�T�Ԃ̃Z�~�i�[�����Ƃ����܂�
�B
Q. SIT�@�Ƃ����͉̂��ł����H
A. ���\�A��Genrich Altshuller���n����TRIZ���C�����Ɗȗ��������̂�SIT�@�ł��BTRIZ���m�����ꂽ�̂�1970�N�㏉�߂ł����C1980�N��̏��߂ɒ�q�����̈ꕔ���C�X���G���ɈڏZ���C�����ŕč��n�̌��n�q��Ђ̋Z�p�҂�����TRIZ�y������ɂ������āC�啝�Ȋȗ����̕K�v�������āC�n�������̂ł��BSIT�@�iSystematic Inventive Thinking�j�ł́C���Ƃ��CTRIZ��40�̔����������C�S��̉�@�����Ɉ��k���Ă��܂�
�B
Q. ���̃C�X���G����SIT�@��USIT�͈Ⴄ�̂ł����H
A. �Ⴂ�܂��BSickafus�́C�C�X���G����SIT�@�ƃ��V�A��TRIZ�Ƃ�����������ŁCSIT�@���x�[�X�ɂ��āC�V��������`�̕��@���蕪�͂̕��@�Ȃǂ����낢��ƍH�v���āC��т����������̃v���Z�X����肠���܂����B�����C�����̃t�H�[�h�Г��ł̌Ăі���SIT�@�iStructured Inventive Thinking�j�ł����B1997�N�ɎЊO�����ɋ��ȏ����o�ł��C���̂Ƃ��ɍ���USIT�Ƃ������O���g�����̂ł�
�B
Q. ����Œ��삳��͂ǂ̂悤�ɂ���USIT��m�����̂ł����H
A. 1998�N11���ɕč��ŏ��߂Ă�TRIZ�̍��ۉ�c
���J����āC�o�Ȃ��܂����B���̉�c�ŁCSickafus�̔��\
������C�F�l�ɂȂ�܂����B���̌�C�ނ�USIT���ȏ���ǂ݁C�����Əڂ����m�肽���Ǝv�����̂ł��B�����ŁC���N�R���̑�P��TRIZCON�i�č�Altshuller Institute��Â̍��ۉ�c�j
�ɍ����āC�t�H�[�h�K���Őf������C�t�H�[�h�ɓ����킯�ɂ����Ȃ����C�ЊO������USIT�R���ԃZ�~�i�[���J������Q�����Ȃ����ƌ����Ă���܂����B
Q. Sickafus�����USIT�Z�~�i�[�͂ǂ�Ȃ��̂������̂ł����H
A. �Q����10�l�ł����B�����ƊȒP�ȉ��K��������ŁC�Q���ڂɂ͎Q���҂������������S�����Q�\�R�l���̃O���[�v�ʼn��K���C�R���ڂ��ʂ̎����S�������K���܂����B���ɑ����e���|�ŁC���ɖL���Ȃ��̂ł���
�B
Q. �����USIT����{�ɓ��������̂ł����H
A. �����ł��B���K����������̃z�[���y�[�W�Ɍ��\��
�CSickafus�ɗ�܂���āC���{��USIT�̂R���ԃg���[�j���O���n�߂܂���
�B
Q. �Ƃ���ŁC���삳��TRIZ��m�����̂͂��Ȃ̂ł����H
A. ����́C1997�N�T��31���ł��B���܂��ܓ�����MIT�̎Y�w�����v���O�����̃Z�~�i�[������C�����m��Ȃ���ԂłQ���ԗ]��TRIZ�̘b���܂����B��ϊ������āC������E�������悤�Ǝv�����̂ł��B�����͕x�m�ʌ������ŃX�^�b�t�Ƃ��Ďd�������Ă��܂����̂ŁC�����w�͂����C���̌�1998�N�S�����獡�̑��w�@��w���w���Ɉڂ��āCTRIZ�̌����������Ƒ����Ă��܂��B
Q. ���R�̏o��������̂ł����B
A. �����ł��B�^���������̂ł��ˁB���͑�w�ŕ������w�̌��������C��ƂŃ\�t�g�E�F�A�W�̌����ƃ\�t�g�E�F�A�i������^���Ɋւ��C�����č�TRIZ�̌����E���y�����Ă��܂��B�v�����������C�傫�ȓ]�@���Q�x�������̂ł��B
Q. ����ō��C���삳���TRIZ����USIT�𐄐i���Ă���̂ł����H
A.�uTRIZ�����v�Ƃ����ƌꕾ������܂��BUSIT��TRIZ�����ǂ������̂ł����CTRIZ�̑傫�ȑ̌n�̒��̂P�̎��H�@���ƍl���Ă���̂ł�����BTRIZ�S�̂����i���C���̒��œ���USIT�𐄐i���Ă���̂��Ɨ������ĉ������B
Q. �ǂ����āC����USIT�𐄐i����̂ł����H
A. ����́CTRIZ�̑̌n���c��ŁC���G�ɂȂ肷���Ă��邩��C�{����TRIZ�̎��H�y������ɂ́C�����Ƃ������肳���C���H���₷�����邱�Ƃ��K�v���ƍl���邩��ł��BUSIT�����̂��߂̍ł��悢���@���Ǝv���Ă��܂��B
Q. ����ŁCUSIT�͂��̌���ǂ���Ă����̂ł����H
A. �����ł��BUSIT�͓��{�łQ�i�K�̑傫�ȉ��ǂ�����܂����B
�P�́CTRIZ���n�肠�������ׂẲ����������@�i���Ƃ��C40�̔��������Ƃ��C76�̔����W�����C�Z�p�i���̃g�����h�Ȃǁj���ĕҐ����āCUSIT�̉����������@�̑̌n�i�uUSIT�I�y���[�^�v�F�T��32�T�u��@�j��n��グ�����Ƃł�
�BUSIT�̂��Ƃ��u�₳����TRIZ�v�ƌĂ�ł��܂����C����́C�������肳���ė������₷�������̂ł����āC�ꕔ�������𒊏o���Ăق����폜����ȗ����ł͂���܂���B
Q. ���{�ł̉��ǂ̑�Q�i�Ƃ����͉̂��ł����H
A. �����USIT�̃f�[�^�t���[�}�����C�u�n���I�������̂U�������v�Ƃ����T�O�����Ƃł�

�BUSIT�ɂ�����������̉ߒ����������߂ɁCSickafus���������������t���[�`���[�g���g���Ă��܂����B�t���[�`���[�g�́C�������@�̖��O�������āC���̏�����_������ȂǂŎ����܂��B�f�[�^�t���[�}�Ƃ����̂͏��Ȋw�ł悭�m���Ă���\���`���ŁC���́i�����j���C���ԏ��C�o�͏���������ƋL�q���āC�����̊W����i�Ə������@���j�łȂ��Ŏ����܂��BUSIT�̃f�[�^�t���[�}��`�����Ƃɂ���āC�v���������Ȃ������قǂ̖L�x�Ȏ���������ꂽ�̂ł��B
Q. ���ꂪ����Ȃɏd�v�Ȃ��ƂȂ̂ł����H
A. �����ł��BTRIZ�̖������̊�{�����́C�T�O�I�ɂ́u�S�������v�ƌĂ�Ă���C�Ȋw�Z�p��ʂ̊�{�����Ɠ����ł��B���̕����́C�u�����̋�̓I�Ȗ����C���f���̖��ɒ��ۉ����C���̃��f���̉�����āC���ꂩ�玩���̖��̉�����Ƃ��ċ�̉�����v�Ƃ������̂ł��B���̕������g����悤�ɑ��푽�l�ȃ��f��������C�m���x�[�X�Ƃ��Ē~�ς���Ă����̂ł��B�����C���̒m���x�[�X������Ėc��ɂȂ�ɂ�āC���̕������ώ����܂����B�܂��ǂꂩ�̃��f����m���x�[�X����I�����C���̃��f�����g���ėޔ�v�l�����邱�ƂɂȂ��Ă����܂��B���̖{���𑨂��āC�̌n�I�ɕ��͂���Ƃ����C�{���̒��ۉ����������Ă��܂��̂ł��B
Q. �ł��V������{�����͗L���Ȃ̂ł����H
A. �L���ŁC���ɂ킩��₷�����̂ł��B���l�Ȗ��ɑ��Ă��C��{�I�ɓ����l�������g���ĕ��́i���ۉ��j���C�̌n�I�ȕ��@�iUSIT�I�y���[�^�j���g���Ĕ��z�𑣂��C����ꂽ�A�C�f�A��������R���Z�v�g�ɑg�ݏグ�C������������Ă������̂ł��B������Ă݂�ƁC���R�̂��Ƃ��Ǝv����قǂł�
�B
Q. �����USIT�͕��y���Ă��Ă���̂ł����H
A.���{�Œ����ɕ��y���Ă��Ă��܂��B�ڂ����͂����ƌ�Řb���܂��傤�B
�}2. TRIZ�i�����USIT�j�̔��W�̊T�v
3. USIT�̏�Ƌ��ȏ�
Q. USIT�ɂ��Ă����ƒm�肽���Ǝv������C��������Ƃ悢�̂ł����H
A.USIT�̏��́C�����n�݂��C�ҏW���Ă���Web�T�C�g�wTRIZ�z�[���y�[�W�x
�����Ă��������̂��x�X�g�ł��B����́C1998�N11���ɑn�݂������̂ŁC�{�����e�B�A�Ƃ��Ď��P�l�ʼn^�c���Ă��܂����C����������C�C�O�������e������C�����̓ǎ҂����āC�����I�ŐM���ł����Ƃ��ĕ]�����Ă�����Ă��܂��BURL�́Chttp://www.osaka�\gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/�ł��B�a���y�[�W�Ɖp���y�[�W����s���č��悤�ɓw�͂��Ă��܂��B
�}3. �wTRIZ�z�[���y�[�W�x�̃V���{���}�[�N (1998 ����)
Q. ����Web�T�C�g�ɂ͂ǂ�ȏ����̂ł����H
A. TRIZ�����USIT�Ɋւ���C�_���C�K�p����C����C���ށC�j���[�X�C�����N�W�C���ۉ�c�Q���C�ӌ���e�ȂǁC��������̂�����܂��B���쎷�M�̂��̂������ł����C�����̗D�ꂽ�_�����f�ڂ��C�C�O�̏d�v�Ș_���𑽐��a�Čf�ڂ��Ă��܂��B
Q. �ǂꂭ�炢�̕p�x�ōX�V���Ă���̂ł����H
A. �s����ł����C�Q�T�ԁ`�P�J�����x�ōX�V���C����Q�`�T�����x�̐V�����L�����f�ڂ��Ă��܂��B�f�ړ��t��K�������āC�J�ݎ�����̂��ׂĂ̋L�����펞�f�ڂ��Ă��܂��B�J�e�S�����ނ��������ڎ������C���ׂĂ̋L���������N���b�N�ŎQ�Ƃł���悤�ɂ��Ă��܂��B
Q. USIT�̋L�����L�x�Ȃ̂ł����H
A. �����ł��B�O�q�������낢��Ȃ��Ƃ��C���ׂĂ��́wTRIZ�z�[���y�[�W�x�ɁC���̐܁X�̋L���Ƃ��āC���邢�͂܂Ƃ܂����_�������Ƃ��Đ�������Ă��܂��B���́w�@�B�v�x�ł̘A�ڂ��C���łɕҏW���̋��܂����̂ŁC�����x��ŁwTRIZ�z�[���y�[�W�x�Ɍf�ڂ����Ă��������܂��B�����ɂ͑����̎Q�Ƃ̃����N�����ł��B
Q. �܂��ǂނƂ悢�L���͂���܂����H
A. USIT�̃o�b�N�ɂ���TRIZ�ɂ��ēǂ�ł�������Ƃ悢�ł��傤�B���́CTRIZ�ɂ��Ă̂₳����������wInterLab�x���i�I�v�g���j�N�X�Ёj�ŁC2006�N�P�������璷���A�ڂ��Ă���C���̑S�҂��wTRIZ�z�[���y�[�W�x�ɍĘ^���Ă��܂��B�u�Z�p�v�V�̂��߂̑n���I�������Z�@��TRIZ�v�Ƃ����薼�ŁCTRIZ�S�̂ɂ��ĉ�����C���̒���USIT�ɂ��Ă����т��ѐ������Ă��Ă��܂�
�B�����ō���́w�@�B�v�x���ł̘A�ڂ́CUSIT�ɍi���āi�ʏ�̎��̐�������TRIZ�ւ̌��y�����Ȃ����āj�C�������Ă�������ł��B
Q. Sickafus�����USIT���ȏ�������Ƃ̂��Ƃł������B
A. 1997�N�Ɏ���o�ł��ꂽ���ȏ�������܂��BEd Sickafus�F�gUnified Structured Inventive Thinking�\How to Invent�h, Ntelleck LLC, Grosse Ile, MI, USA�i1997�j�B488�ł̑咘�ŁC�a��ł��Ă��܂��� [Sickafus ��USIT Web�T�C�g: http://www.u-sit.net/ ]�B
Q. �����ƃR���p�N�g�ȃe�L�X�g������܂����H
A. Ed Sickafus�F�gUSIT eBook�h�Ƃ����̂�����C45�ł̂��̂ŁC2001�N10���̎��M�ł��B���̘a��i��ʌb�i�E�z���d�b�E����O��j���wTRIZ�z�[���y�[�W�x�Ɍf�ڂ��Ă��܂�
�B�����ł����C�_�E�����[�h�ɍۂ��āCSickafus����ƒ���ɁC������email�A�h���X�����[���Œm�点�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��BUSIT�̍l�������܂Ƃ߂����̂ŁC����Ȃǂ͏����Ă��܂���iUSIT���ȏ����Q�Ɖ������j�B
Q. ���{��ł�USIT�̋��ȏ��͂���܂��H
A.�P�s�{�̈ꕔ�ɂȂ��Ă�����̂����C�܂�����܂���B�P�́C�w���̂Â��苳�ȏ��@�v�V�̂��߂̂V�̎�@�x�C���oBP�ЁC2006�N�W�����C�ł��BTRIZ��USIT�̍ŐV�̗����𒆐삪35�ł��菑���Ă��܂��B[���̖{�̌��ɂȂ����w���o���̂Â���x����̘A�ڋL���u�Ȃ�ق�the���\�b�h: �V����TRIZ�v ���wTRIZ�z�[���y�[�W�x�Ɍf�ڂ��Ă���
�B]
�Ȃ��CUSIT�Ƃ������O�������ɓ����Ă���B��̒P�s�{�Ƃ��āC���J�F�w���̂Â���Z�p�A�h�o���X�g�@�}���@����Ŏg����TRIZ�^USIT�x�C���{�\������}�l�W�����g�Z���^�[�C2006�N�T�����C������܂��B���̖{��TRIZ�̎���Ȃǂ҂����W���Đ}�����Ă���C�킩��₷���L�q�ł��BUSIT�ɂ��ẮC�����1999�N�̌��\���Ⴈ��ђ��҂̕x�m�[���b�N�X�Ђł̎���Ȃǂ������C��͂�35�Œ��x�̊ȒP�ȋL�q�ł��B
4. USIT�̃��`�[�t�Ɠ���
Q. USIT�͂ǂ̂悤�ȖړI�Ɏg������̂ł����H
A. ��{�I�ɂ́C�Z�p�I�ȕ���ŁC�ʏ�̋Z�p�I�ȉ������ł����ɍ���ɂԂ������Ƃ��ɁC�V�����ϓ_����l���邽�߂̋ؓ����������@����C������̃R���Z�v�g���C�v���ɓ��悤�Ƃ�����̂ł��B
Q. �ǂ�ȋZ�p����ł��悢�̂ł����H
A. ���܂��܂���B���܂ŁC�@�B�E�@�\�E�d�C�n�C�V�X�e���E���n�C�ޗ��n�Ȃǂ̕���ŁC���܂��K�p���Ă������т�����܂��B���Ƃ��Ă���V�X�e�����ł̃��J�j�Y��������ł���قǁC���m���ɓK�p�ł��܂��B�ł�����C��w��_�w�Ȃǂł����Ȃ艞�p�ł���͂��ł��B�܂��C��Z�p�́C�l�Ԃ�Љ�ւ����ł��C�œ_���i�������ɂ͓K�p�ł��܂��B
Q. �@�u�@�B�v�v�Ƃ�������Ƃ͂ǂ������W�ɂ���̂ł����H
A. ���炩�̐��i�ɂ��ċ@�B�I�i���J�g���I�j�Ȗʂ���v���s���Ƃ����悤�ɋ@�B�v���l���܂��ƁCUSIT�͑��`�I�ɂ́C�ǂ�Ȃ��́C�ǂ�ȃ��J�j�Y���̂��̂�v���ׂ����Ƃ����ۑ�ɑ��āC�T�O�I�ȉ������^������̂ł��B�ł�����C�@�B�v�̑O�i�K�ɂ���C���邢�͋@�B�v�̊T�O�v��������ƍl�����܂��B
Q. ����ƁC�Z�p�J���⏤�i�J���̏㗬�i�K�Ŏg�����@���Ƃ����Ă悢�ł����H
A.�����C�K���������E�\�z�Ȃǂ̏㗬�i�K������ΏۂƂ��Ă���̂ł͂���܂���B�v�E���Y�E�^�p�ȂǁC�ǂ�Ȓi�K�ɂ��Z�p�I�ȉۑ�͂���C�V�����l���������č������Ȃ��Ƃ����Ȃ���肪����܂�����C���̂悤�Ȗ��Ɋւ��āC�Z�p�I�ȉ�����̕������l���悤�Ƃ�����̂ł��B�����CUSIT���n��o��������́C�܂��T�O�I�Ȓ萫�I�Ȃ��̂ł�����CUSIT�̌�ł����������ƕ]�����C��ʓI�ɂ��C�v������C����E���������肷�邱�Ƃ��C���̉�����̎����ɂ͕K�v�Ȃ̂ł��B
5. USIT�ɂ������̃v���Z�X
Q. �@�u�V�����ϓ_����l���邽�߂̋ؓ����������@�v�Ƃ́C�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H
A. ����͂܂��C���m�ɂ��邱�Ƃ���X�^�[�g���܂��B�����]�܂����Ȃ���肩�H����ŁC�����������̂��H�i�ڕW�E�ۑ�j�m�ɂ��܂��B���̐}���Ȍ��ɕ`���C�l�����錴�����@�艺���܂��B�ꌩ������O�̕��@�ł����C�����̍���Ȗ�����������ɂ́C���̖���`�̒i�K���������肷�邱�Ƃ��d�v�ł��B
Q. ����ł��̖����ǂ̂悤�ɍl���Ă����̂ł����H
A. �܂��C���̋�ԂƎ��ԂɊւ����������������l���C���낢��Ȑ}��O���t�ŕ\�����܂��B�܂��C���݂̃V�X�e�����C�I�u�W�F�N�g�i�\���v�f�j�C�����i�����̃J�e�S���j�C�@�\�Ƃ����T�O���g���ĕ��͂��܂��B�V�X�e���̖{���̐v�Ӑ}���@�\���͂ŕ\�����C���Ɋւ���Ă��鑮������č��{�������͂�⋭���܂��B
Q. �����ăA�C�f�A�o���ɐi�ނ̂ł����H
A.�����C���̑O�ɁC���̉ۑ�ɂƂ��Ă̗��z�͂ǂ��������Ƃ��낤�ƍl���܂��BParticles�@�Ƃ��������ŁC�������@�̗��q�i���邢�͏��l�j�������āC�Ȃ�ł�����Ă����̂��Ƃ�����C�������Ăق����̂��C���̖��@�̗��q������ׂ��]�܂����s���ƁC�����Ă���Ƃ悢�����͂Ȃ낤�ƍl����̂ł��B
Q. ���ꂪ���͒i�K�Ȃ̂ł����H
A. �����ł��BUSIT�ł̕��͕��@�͂��̂悤�ɕW�������ꂽ���@���g���C���݂̃V�X�e���ɂ��āC��ԂƎ��Ԃ̓����C�I�u�W�F�N�g�Ƒ����Ƌ@�\�Ƃ����T�O�ōl���C�����ė��z�̃V�X�e�����C���[�W����̂ł��B���߂͏������ۓI�ŗ������ɂ����Ǝv����������܂��C���̂������łǂ�ȕ���̂ǂ�Ȗ��ɂ��K�p�ł���̂ł��B���낢��Ȑ}����`���Ȃ���l���܂��B
Q. ����Ŏ����A�C�f�A�o���ł����H
A. �����ł��B�A�C�f�A�o���̂��߂�USIT�ł͂T��32�T�u��@����Ȃ�uUSIT�I�y���[�^�̑̌n�v
�������Ă���C����������K�p���Ă����܂��B���Ƃ��C�u���܂���\���v�f�̂P���C�Q�ɕ������C���ꂼ��̐������Ⴆ�āC�Ăшꏏ�ɂ��ėp����v�Ƃ����̂��T�u��@�̂P�ł��B���̂悤�Ȏw���ɏ]���čl����ƁC�������ɗ��A�C�f�A���o�Ă���̂ł��B
Q. ���̂悤�Ȏw�����q���g�ɂ���̂ł��ˁH
A. �����ł����C�q���g�Ƃ����悤�Ȕ��R�Ƃ������̂łȂ��C���̗�̂悤�ɂ����Ɩ��m�Ȏw���i���邢�́C����j�ɂȂ��Ă��܂��B
Q. ����ŁC�T��Ƃ����͉̂��ł����H
A. �܂��C�I�u�W�F�N�g�i�\���v�f�j�������鑀��C�����i�����j�������I�ɕω������鑀��C�@�\���Ĕz�u���鑀��̂R�킪����܂��B���ꂼ��̓��e�͍��͐������܂��C�V�X�e�����L�q�����R��̊T�O�̂��ꂼ��𑀍삵�Ă���̂ł��B���ꂩ��C�Q�̉������g�ݍ����鑀��C���������ʉ����đ̌n�����鑀�삪����܂��B����łT��ł��B
Q. ������������@���o����̂ł����H
A. �ȒP�Ȉꗗ�\������C����̎w�����Ȍ��ɏ����Ă���܂�����C�o����K�v�͂���܂���B�����C���ꂼ��̑���̈Ӗ��𗝉����Ă������Ƃ͕K�v�ł��傤�B���炵�������ɂȂ��������g�ɂ��āC�w�ԂƂ悢�̂ł��B
���ꂩ��C���ۂɂ́C��قǂ̕��͂̒i�K�łǂ�ǂ�A�C�f�A���o�Ă��܂��B�����̃A�C�f�A���ȒP�Ȑ}�ɕ`���āC�\��o���C����ɐG������Ă܂��A�C�f�A���o�܂�����C�������i��ʉ��@���g���āj�K�w�I�ɑ̌n�����Ă����Ƃ悢�̂ł��B
Q. ���������i�K�œ���A�C�f�A�Ƃ����̂́C������Ƃ����v�����Ȃ킯�ł��ˁB
A. �����ł��B�A�C�f�A�̒f�Ђł����C���ꂪ������̒��j�ɂȂ��Ă����̂ł��B�W�F�[���X���b�g�̏��C�@�ւȂǂ̑唭���ł��C���j�̃A�C�f�A�͏����Ȃ��̂ł��B���܂ł̕��͂�������Ƃ��Ă��邩��C���̃A�C�f�A�̒f�Ђ�L���Ɏg�����@���l���o����̂ł��B
Q. ���̃A�C�f�A����������g�ݗ��Ă�̂ł����H
A. �����ł��B���̉�����̑g���Ă̒i�K�ɂ́C����Ȃ�̋Z�p�I�ȑf�{���K�v�ɂȂ�܂��B�@�B�v�ł����T�O�v�ɋ߂����̂ł��傤����B������ƃC���[�W���āC����������܂��������낤�Ƃ����f�āi������̃R���Z�v�g�j�����̂ł��B�����܂ł�USIT�̔C���ł��B
Q. ���̌オ����̂ł����H
A. ���̉���������ۂ̐��i�Ȃǂɑg�ݍ��ނ��߂ɂ́C�V�����A�C�f�A�̎��؎����Ƃ��C����Ƃ��C�F����̐��̐v�Ƃ����K�v�ł��B����Ȍ�̉ߒ���K�v�ȏ����@�͊F���悭�������̂��Ƃł��B
�}4. USIT�ɂ��������̑S�̃v���Z�X�i�t���[�`���[�g�j
6. USIT�̎��H�@
Q. �Ƃ���ŁCUSIT�͂P�l�ōl������@�Ȃ̂ł����H
A. �������C�O���[�v�ł̍�ƂɎg�����������ƌ��ʓI�ł��B���̖��̒S���ҁC�Z�p�̑f�{�̂���l�C�Ⴄ���ꂩ�猩�邱�Ƃ��ł���l�C������USIT���}�X�^�[�����l�ŃO���[�v��Ƃ����܂��BUSIT���}�X�^�[�����l���C�K�Ȏ�������āC�l����ߒ������[�h����̂��C�悢�̂ł��B
Q. USIT�̏n���҂���������o����������̂ł͂Ȃ��̂ł����H
A.�����ł͂���܂���B���͂̒��g���C������̑g�ݗ��Ă��C���̖���m��C���̕���̋Z�p��m��l������Ă����̂ł��B���͂̂������C�A�C�f�A�̏o�����Ȃǂ̍l�����������������̂�USIT�Ȃ̂ł��B
���̐}���Z�@�G�L�X�p�[�g�̖������f���Ƃ��āC�悭���錤���ϑ��^�̃G�L�X�p�[�g�̖����ƁCUSIT�ł̃G�L�X�p�[�g�̖�����Δ䂵�Ď����Ă��܂��B
�}5. �Z�@�̃G�L�X�p�[�g�̖������f��
(���}�͓T�^�I�Ȍ����ϑ��ɂ�����Z�@�̃G�L�X�p�[�g�̖����A�E�}��USIT�ɂ�����Z�@�̃G�L�X�p�[�g�̖���)Q. TRIZ�ł́C��R�̒m���x�[�X���g���C�\�t�g�E�F�A�c�[�����g���ƕ����Ă��܂����B
A.�����ł��B�c��Ȓm���x�[�X���C�����g�ݍ��֗��ȃ\�t�g�c�[����TRIZ�̍��Y�ł���C�͂̌��ł��B�������CUSIT�͂����ɗ��炸�C�v�l�v���Z�X�����[�h���ċZ�p�҂������g�̍l����͂������o�����Ƃ���̂ł��B����ł��CUSIT�ł̋�����ƂƂ͕ʂ̎��ԑт�TRIZ�̒m���x�[�X���g���čl����⋭���邱�Ƃ́C��ϗL���ȕ��@�ł��B
���ɁC�u����ꂽ�A�C�f�A�̒f�Ђ��C���͂ق��̋Z�p�E�Y�ƕ���ł͊����̕��@�̖{���I�ȍl�����Ƃ��Ďg���Ă����v�Ƃ������Ƃ�TRIZ�m���x�[�X����킩�邱�Ƃ������̂ŁC�������������\���ɑ��đ傫�Ȏw�j�Ǝ��M��^���Ă���܂��B
Q. USIT�ł̖������͒����Ԃ�����܂����H
A. �������C�v���ɁC�\���悭�C�Ƃ����̂�USIT�̂˂炢�ł��BUSIT�̂Q���ԃg���[�j���O�ł́C�R�O���[�v�Ŏ����R�����s���ĉ������Ă����܂��B���n�̖������ł��C�����v�̂ł�邱�Ƃ��ł��܂��B���邢�́C�ߌ�̂R���Ԃ��ƂтƂтɂR�`�T����x�Ƃ�������������ł��傤�B
Q. ����ʼn�����R�o��̂ł����H
A. �o�܂��B�Q���Ԍ��C�̏ꍇ�ɂ́C�A�C�f�A�̐��ŁC���\�C�g�ݗ��Ă�������Ő�������\�����炸�Ƃ����̂��C���ۂ̏ł��B���n���ŁC�ƂтƂтɂ��ꍇ�ɂ́C�Ԃŏh��Ȃǂ����܂��ƁC���S���̃A�C�f�A�Ȃǂ������܂��BUSIT�́C�P�̃x�X�g�A�C�f�A���o�����Ƃ���̂łȂ��C��R�̃A�C�f�A���o���āC��őI������Ƃ��������ł��B
7. USIT�̕��y�ƈӋ`
Q. ���ۂɎg���Ă����Ƃ͂���܂����H
A. ����܂��B���{��TRIZ�����Ă����Ƃ́C�������̕��@�����s���Ă��Ă��܂����C���̒���USIT�̔�d�������ɑ傫���Ȃ��Ă��Ă��܂��BTRIZ�̓`���I�ȕ��@�����₳�����C�L��������ł��B
Q. �����Ƌ�̓I�ɕ������Ƃ͂ł��܂����H
A. �����畷�������C��Ƃ̐l�������璼�ڕ������Ƃ悢�ł��傤�B���{�ł́C���{TRIZ���c���Â��āC���N�ĂɁuTRIZ�V���|�W�E���v���J�Â��Ă��܂��B���N����R��ŁC2007�N�W��30���i�j�`�X���P���i�y�j�ɁC�V���l�̓��Ō��C�Z���^�[�ŊJ�Â��܂�
�B�����R���ăv���O�����ψ��������Ă���C���傤�ǂ��Q���ҕ�W�����Ă��܂��B�`���[�g���A���Q���C���҂̍u���T���C��ʔ��\30��������C�S�̂̂�����10�����C�O����̔��\�ł��B���{��TRIZ�V���|�W�E���́C���[�U��Ƃ��甭�\���������Ƃ������ł��B�Q���҂͍�N157���i�����C�O18���j�ł����B
Q. ���E�ł�USIT�͂ǂ��ł����H
A. �č��ł͎�����t�H�[�h�����̂悤�ł��B2000�N��Sickafus���t�H�[�h�����ނ������߁C���̌�p�����Ă͂��܂����C������܂��Ă���悤�Ɏv���܂��B���{�ł�USIT���C���ܐ��E��TRIZ���[�_�����ɏ��X�ɔF������C���ڂ���Ă��Ă���Ƃ����i�K�ł��B
Q. �ǂ������Ӗ��Œ��ڂ���Ă���̂ł����H
A. ���E�̂��낢��ȗ�����z���E�������āC�Ǝ��̂��̂����グ��̂����{�̓��ӌ|���Ɣނ�͒m���Ă��܂��B�����āC���E��TRIZ�̗���̒��ɓ��{�����P���m�Ɍ���Ă����Ɗ����Ă���Ǝv���܂��B
Q. TRIZ��USIT�̐��E�I�Ӌ`�͉��ł����H
A. �L���Ӗ��ł̕i���Ǘ��̉^�������60�N�̐��E�̋Z�p�v�V�����[�h���Ă����킯�ł����C����̓f�[�^��́i���v�w�j�Ƒg�D�_���x�[�X�ɂ��Ă���C�Z�p�_�������Ȃ������B������TRIZ�����m�ȋZ�p�_���������B������CTRIZ�͏����̋Z�p�v�V��S�����̂ɂȂ邾�낤�Ǝv���܂��B
| �{�y�[�W�̐擪 | ��1��TRIZ FAQ (1)�͂��߂� | (3) ��Ƌ��ȏ� | (4) ���`�[�t�Ɠ��� | (5) USIT�ɂ������̃v���Z�X | (6) USIT�̎��H�@ | (7) ���y�ƈӋ` |
| USIT�A�ڐe�y�[�W | ��1�� USIT�Ƃ͉���? FAQ | ��2�� �₳�����K�p���� | ��3�� ����`�ƕ��͂̕��@ | ��4�� ������̐����@ | ��5�� ���H�@ | TRIZ�A�ڐe�y�[�W |
�p���y�[�W |
�ŏI�X�V�� : 2007.12. 9 �A����F�@���� �O nakagawa@utc.osaka-gu.ac.jp