札寄せ用具と図的思考: 札寄せ用具の開発の意図、操作法、使い方、使用実践例、図的思考の有効性
片平 彰裕(第一考舎)、中川 徹 (大阪学院大学)
第2部: 「札寄せ用具」の使用実践例: 片平が行っている札寄せ法
片平 彰裕、2016年 7月28日
掲載:2016. 9.29
札寄せ用具と図的思考: 札寄せ用具の開発の意図、操作法、使い方、使用実践例、図的思考の有効性 |
|
|
|
|
|
掲載:2016. 9.29 |
Press the button for going to the English page.
編集ノート (中川 徹、2016年 7月25日)
札寄せ用具と図的思考に関する、片平・中川の共同論文の第2部です。第1部
では、「札寄せ用具」の開発者である片平が、その開発の意図、操作法、「札寄せ法」と総称する使い方の基本的考え方について、記述しました。
この第2部では、片平自身の実践事例について、個人用に行う場合の実践法と、会議などでその場で作っていく場合の実践事例を記述します。7月1日にできていた原稿に、会議用の使い方の実例画面4件を追加しました(2016.7.28)。
| 本ページの先頭 | 論文先頭 | 個人使用の手順 | 札の並べ方の観点 | 個人使用の実施例 | 会議での使用の手順 | 会議での使用の実施例 | 英文ページ |
||
| 札寄せ用具と第一考舎の紹介(片平、2015. 1) |
札寄せしながら考える(5) (中川、2015. 9) |
札寄せ用具と図的思考(第1部) |
同(第2部) |
同(第2部)PDF |
同(第3部) |
同(第4部) |
論文 ==> PDF(第2部)
札寄せ用具と図的思考:
札寄せ用具の開発の意図、操作法、使い方、使用実践例、図的思考の有効性
片平 彰裕(第一考舎)、中川 徹 (大阪学院大学)
第2部: 「札寄せ用具」の使用実践例: 片平が行っている札寄せ法
執筆: 片平 彰裕、2016年 7月 1日
片平は、個人用として考えの整理や、気づきの促進のために、また会議用として発言の促進と議論集約を促進のために、札寄せ法を行なっている。
4.1 個人用
4.1.1 手順
大まかな手順は次の通り。
(1)そのとき札寄せをする目的を書き出す
今なぜ札寄せをするのか、頭の中にあるその目的は漠然としていて言葉になっていない場合もあるが、それを言葉で表現して書き出すことによって、曖昧な部分が整理され、そして強く意識することになる。
(2)集めた情報などを札に記入する
目的に関連して自分が見たり聞いたり調べたことや、感じたこと思いついたことについて、一つの事柄を一枚の札に記入する。基本的には主語と述語、そしてそこに条件があるならその条件も同じ札に記入する。
たとえば、例として次の文がある場合、
「札寄せ法をやれば、いつも解決するというわけではないのですが、別の観点でやったり、翌日にまたやってみるなど何回か繰り返していると、いい考えが浮かぶことがあります。」
この文を札寄せ法の情報として札に記入する場合は、次のように4枚の札に分けて書くことになる。
「札寄せ法をやれば、いつも解決するというわけではない」、
「札寄せ法をやって解決しない時は、別の観点で札寄せ法をやると良い考えが浮かぶことがある」、
「札寄せ法をやって解決しない時は、翌日にまたやってみると、良い考えが浮かぶことがある」、
「札寄せ法をやって解決しない時は、何回か繰り返していると、良い考えが浮かぶことがある」。(3)札を並べ替える
全ての札を一通り読んでみて、それらの札をどう並べれば納得のいく配置になるのか、あるいは気持ちのいい配置になるかを考えてみる。こう並べたら良いかもしれないという思いが現れたら、先ずはその思いの通りに、札を並べてみる。札を動かしている途中で、これではうまくいきそうもないと思えば、方針を切り替えて、別の並べ方に変えて見る。
札を並べ替えることによって頭の中が変化する。なぜなら札を動かしている最中に、札の内容を読み取ったり、別の札と並んだ状態を眺めたりするからで、こういった刺激による頭の中の変化が良い案を誘発することがある。ただし、そのときの札の並び具合と、思いついた案とは直接は関係がないように思えることもある。
もし札を並べたときの全体像を納得のいく配置、あるいは気持ちのいい配置などのように事前に想像できないなら、全体像は考えずに、個々の札同士の相互関係で並べてみる。
この様に、全体像のことはしばらく忘れて、部分的に個々の札同士の関係だけで、札を並べてみると、その結果現れる全体像が重要なヒントになることもある。札を並べ替えるときの観点は、さまざまなものが考えられる。こんな分類ができるかもしれないと思うなら、先ずその通りに分類してみる。そのような札寄せをしているときに、その並べ方で良かったと感じたり、並べ方に違和感を感じたりすることがある。そのように良いと思ったり、違和感を感じることが、頭を刺激することになる。このように既に並べ替える観点を思いつくなら、それを札で表してみることによっても、頭の中を刺激することになる。
自分がはじめに思いついた並べ方を一通り試しても考えが進展しないときは、別のワークシートを使って、札同士を近づける観点を決めて並べ替えてみると効果を得ることもある。
よく使う並べ方の観点を4.1.2項に示した。
(4)札寄せ中に気づいたことを札に記入する
この一連の手順を行っている最中に答えにつながることに気づくことがある。 気づいたアイデアや気づきを忘れてしまわないために必ず札に記入して、他の札と同じように扱う。
(5)集まった集団を枠で囲み名前をつける
思いにまかせて札を動かしていると、札の集団ができてくる。この集団を枠で囲って、一つの集団として妥当か確認する。
集団として妥当と確認できれば、その集団を枠で囲って名前を記入する。集団も一枚の札のように扱って札寄せを続けるので、集団の名前は他の札と同じ表現方法とする。
集まった札と枠をグループ化して、一度に動かせるようにする。(6)ひとつの集団を一枚の札の様に扱って札寄せを続ける
集団が出来ても、集団の名前を一枚の札とみなして、札寄せを続ける。 この時は集団内の一枚一枚の札に書かれている言葉は無視する。
札寄せを続けていると、集団と集団からなる集団や、集団と札からなる集団を作ることがあるが、これも一つの枠で囲い名前を記入し全体をグループ化する。
(7)7枚くらいになったら、札同士の関係を読み取って、文章にする
一番外側の集団を一つの集団と考えれば、何重にも集団を作ることで、札寄せに使う札と集団の数が減ってくる。
以上のような手順で沢山あった札の内容が、少ない数の言葉に集約できたことになる。
札と集団が7枚程度になったら終了して、そこから全体像を読み取る。
前述の(1)〜(7)が札寄せ法の概略の手順である。
片平は、札寄せをしている間に答えが思い浮かべば、そこでやめるが、それまでの段階で答えが思い浮かばないときは、次項の(1)〜(4)のように札の並べ方の観点を変えて何回も行っている。
また一連の手順の中のどこかをやっている時に、「別の観点で並べた方が良さそうだ」という思いが浮かぶことがある。
この思いがそれほど強いものでなければ、そのまま最後まで続けて行い、その時に求めるような考えが浮かんでいなければ、別の観点で「(3)札を並べ替える」からやってみる。
続けてやる場合もあれば、一旦別のことをしてからやることや、日を改めてということもある。
4.1.2 よく使う並べ方の観点
(1) 何について書かれているか
例えば機械について書かれている札を一か所に集め、人について書かれている札を別の場所に集めるというように、分類の枠を決める方法である。
全ての札を見渡していると、「機械と人に分かれそうだな」などと何となく分類項目を一つ二つ思いつくことがある。とりあえず枠を作り、その項目を記入する。そこに分類できると思う札を枠内に並べる。このような札寄せをしている内に、「場所についての札も多いな」などと更に別の項目を思いついたり、分類した幾つかの札を更に分類して、徐々に札を分類する方法である。
この方法では、いくつかの分類枠が決まってしまうと、その枠に札を振り分けることに意識がいき、札の言葉を十分読み取ることがおろそかになりがちという欠点がある。
しかし、後述の類似性で寄せる方法に比べて意外性は少ないけれど、速く分類できるので、この方法で目的を達成できるなら、その方が良いと思っている。
(2) 時間の順序
例えば、実施する時間や、発生した順番で札を並べる方法である。札同士を矢線で結ぶことにより時間感覚が増長する。
それまで時間的な要素を意識せずに考えていた時は、これをやると意外なことに気づくこともある。
(3) 説明できる類似性
分類するというよりも似ていると思う札同士を、それらが何故似ているかを言葉に表して確認しながら近くに配置する。その札の集団を枠で囲み、何故にているかを表す言葉を枠に記入する。ひとかたまりの札と枠をグループ化して一度に動かせるようにする。
前述の (1)のように表面的な共通点で分類枠を決めてしまうのではなく、機能の類似のような見えにくい類似性に着目して寄せるので意外なことに気づくこともある。
説明できる類似性で寄せるので、何人かで話し合いながら行うことも可能である。
(4) 説明できない類似性
何となく近いと思う札同士を近くに置く方法であり、前述の(3)と似ているが、なぜ近いと思うのかをあえて考えずに、感覚的に寄せる方法である。
後で、集まった集団に名前を付ける段階で、集まっている理由を考えて、その理由がわかるように名前を付ける。
札同士を寄せるときに理由を説明できないので、他の人と相談しながら進めることは不可能である。
4.1.3 効果
個人用の場合は、結果が残るのは頭の中であって、札寄せをした図に結果が現れるわけではない。
このように札寄せ法を繰り返していると、札を動かしている最中や、札寄せ法を終えて別のことをしているときに、頭に問題の解決策が浮かんだり、分からなかったことが理解できたりすることがよくある。
片平が行っている札寄せ法は、必ずしも終えると同時に、頭に自動的に解決策が浮かんだり理解できているということではない。
札寄せ法が思いつきや気づきを促進する理由は、
頭の中の色々な情報や考えを「言葉で書き出す」こと、それらを一面に並べるので絵や図の様に「視覚も利用して脳を刺激する」ということ、そして、それらの札を動かして並べ替えるという「動的な刺激を脳に与える」という三つの要素が大きく影響していると考える。4.1.4 実施例
(1) 受講メモ
下図は、社会心理学の学習過程で、理解を深めるために行った札寄せの結果である。
教科書の各章ごとにワークシートに分けて札寄せをした。このシートには2つの異なるテーマで札寄せをした図を上下に記入している。上段のテーマは、「ポジティブイリュージョン」であり、下段は「自己開示」である。片平の場合は、自分が納得した段階で打ち切ってしまうので、他人が見ると中途半端で分かりにくいかもしれないが、出来上がった図に意味があるのではなく、札寄せをしている過程で、気づきや理解が進むことを重視している。
この図も、社会心理学の受講が終了した後に再び見返すことは、ほとんどないと考えている。
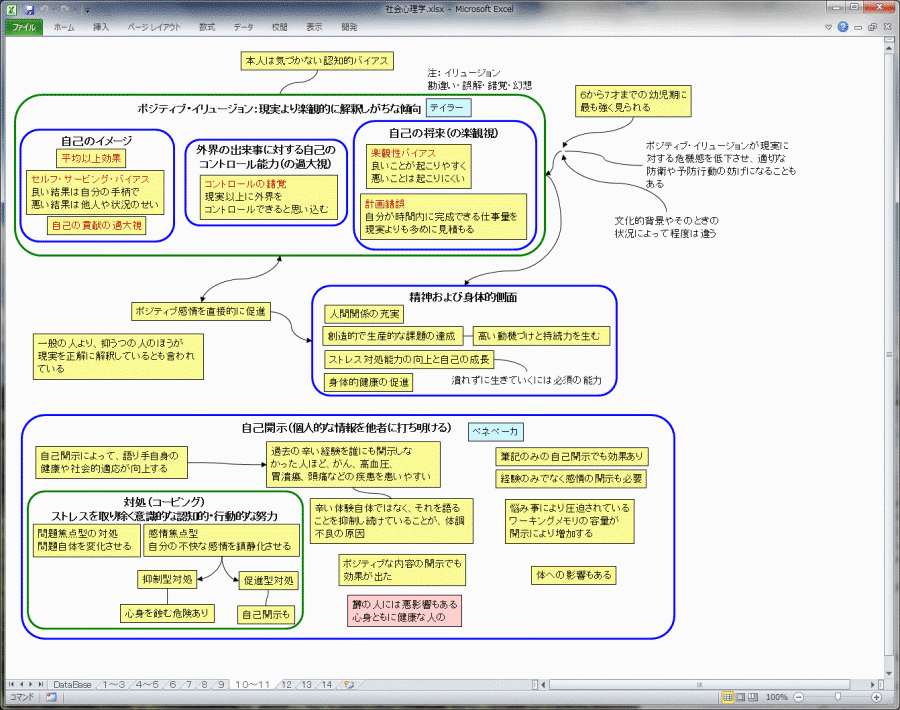
(2) 考えの整理
下図は、「札寄せ法とは何か」について自分の考えを整理しようとして、過去に行った札寄せの結果である。関連のテーマでの札寄せは、何回も行っており、その都度少しずつ自分の理解が変化している。このような図は人に何かを伝えるのが目的ではなく、札寄せをするという行為によって、自分の中の考えを進めようとしているので、参考に例示できる図は少なく、その中でも、比較的整った図を示した。
この札寄せでは、札を並べ替える観点が一つではなく、それぞれの部分毎に異なる観点で思いつくままに寄せている。
このテーマは、一過性のものではなく永続的に考え続けているので、関連するテーマで行った札寄せの結果を、一つのエクセルブックにワークシートを分けて保存している。
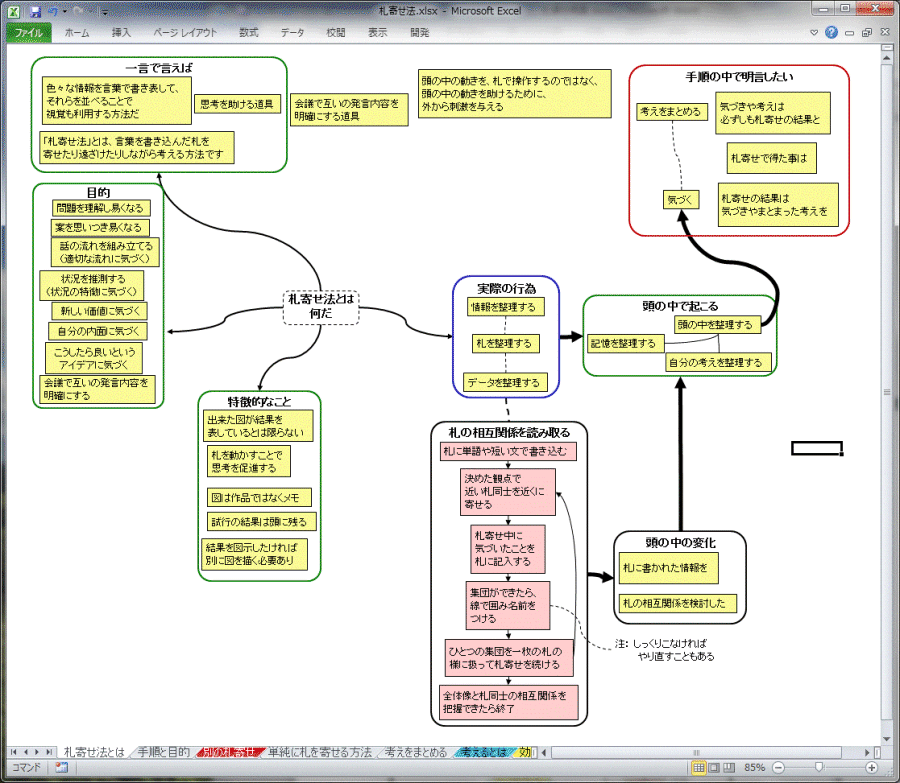
4.2 会議用
視点の統一と認識の統一が容易になるように、画面が全員に見えるように映して行う。
会議での発言を札に書き留めて、各発言同士の関連がわかるように札を並べながら会議を進めるが、このとき各出席者の認識の違いを話し合いで修正しながら文言と札の配置を決めていく。
4.2.1 手順
大まかな手順は次のとおり、
(1)会議の「テーマ」を真ん中に書き出す
明記することで何について議論しているのかの共通認識を持つことが出来る。
(2)発言を札に記入する
会議が始まったら参加者の発言を要約して札に記入して、テーマの周りに置く。
次々に発言が出る場合は、発言を一旦ワークシートに一覧表の形で記入して、発言が一段落したら、一括して札に書き出すこともできる。
(3)決めた観点で札を配置する
最初の札は、どこに置いてもかまわない。2番目以降は、既に置かれている札との内容の近さを考慮して配置する。
札寄せをする観点は、例えば、時系列、因果関係、共通性、類似性などから選ぶ。
(4)集団を囲み、名前をつける
発言が一段落したら全体を見渡して、札が集団のように集まっている場合は、その集団全体を枠で囲み、その集団全体として何を表しているのかを話し合って表題をつける。この表題によって札同士が集まった理由を参加者全員で再確認する。集団の枠と札をグループ化する。
複数の集団が、大きな集団として考えられるときは、元の集団を解消せずに、札や集団が含まれた複合集団として更に枠で囲い表題をつける。
(5)ひとつの集団は一枚の札の様に扱って、札や集団同士の配置を決める
(6)共通認識の書き出し
会議が終了したら、画面に現されている全体像を参加者全員で読み取って共通認識として全体の表題を画面に記入する。
前述の(1)〜(6)が札寄せ法の概略の手順である。
4.2.2 会議用の札寄せをやって得られる事
情報交換や議論を行う会議で、発言の促進と議論集約の促進をすることができる。
会議では、参加者の発言を表示しないで議論を進めたり、たとえ表示しても箇条書きで書かれていると、それぞれの発言同士の関連を把握しにくいことがある。
一方、札寄せ法では発言を書出して、発言同士の関連を札の配置で表現するので、個別の発言だけでなく議論の全体像を視覚的に把握しやすくなる。言い換えれば、発言を記入した札の位置を他の発言との兼ね合いで動かすことによって、「複数の発言の関係を全員で共有できる」ということである。また札の配置を決めるために札に書かれている内容を理解しなければならないので、参加者が必然的にアイデアやデータの意味をよく吟味することになる。
このため、発言に対する誤解が減って、誤解による無駄な論争を避けることができ、新しい意見が出やすくなる。札の配置を決める観点を変更して、札を並べ替えると新たな発見をすることがある。
発言した時点では、他の参加者から賛同を得られない発言も、いろいろな発言が増えてきて発言間の関連が見えてくると評価が変わり、脚光を浴びる発言もある。
4.2.3 実施例
(1) 考えのすり合わせ
下図は、テーマに対する発言を札寄せしながら、参加者の考えを自由気ままに出した例である。発散思考の段階の一場面であり、こうしている内に、参加者同士のお互いの考えに対する理解が深まる。発散の段階が終われば、その段階でいったん打ち切り、後日の会議の材料にしたり、そのまま収束思考に入り、何らかの結論に達する場合もある。
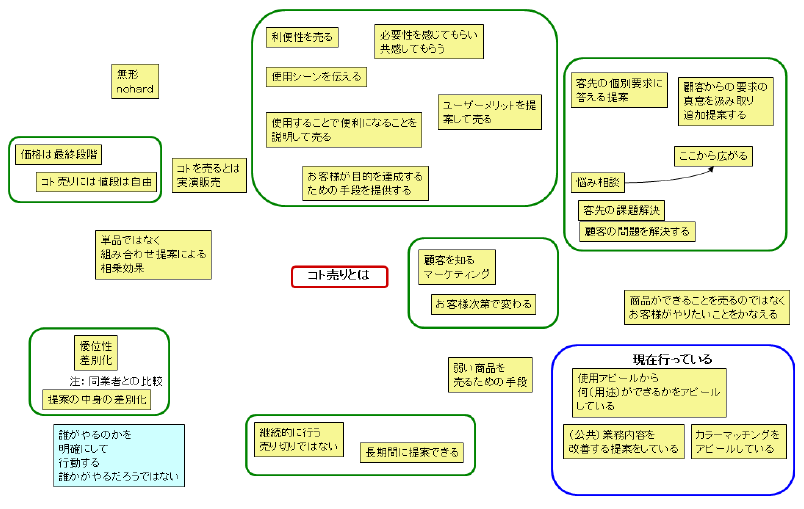
(2) 原因の抽出
下図は、問題に対して考えられる原因を札寄せしながら、出し合っているときの例である。この段階では、原因と対策案が分離されておらず、関連のありそうな項目同士が、線で結ばれている。
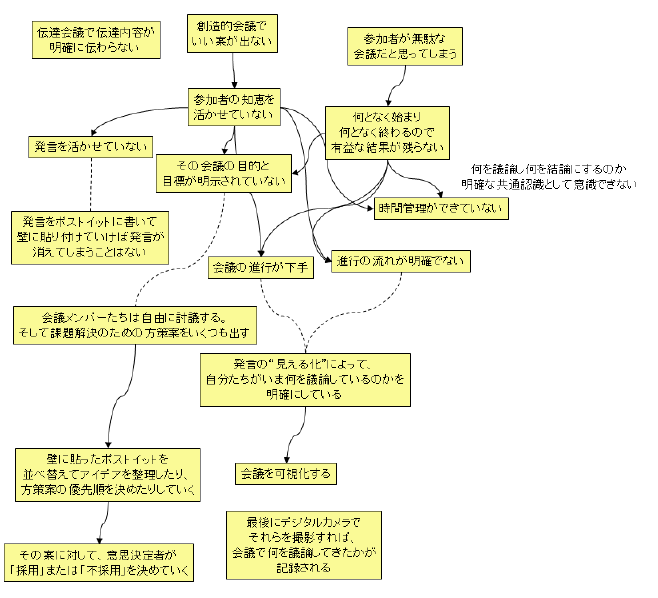
(3)理解の促進
下図は、NM法の理解を深めるために、札寄せをしながら話し合った例である。
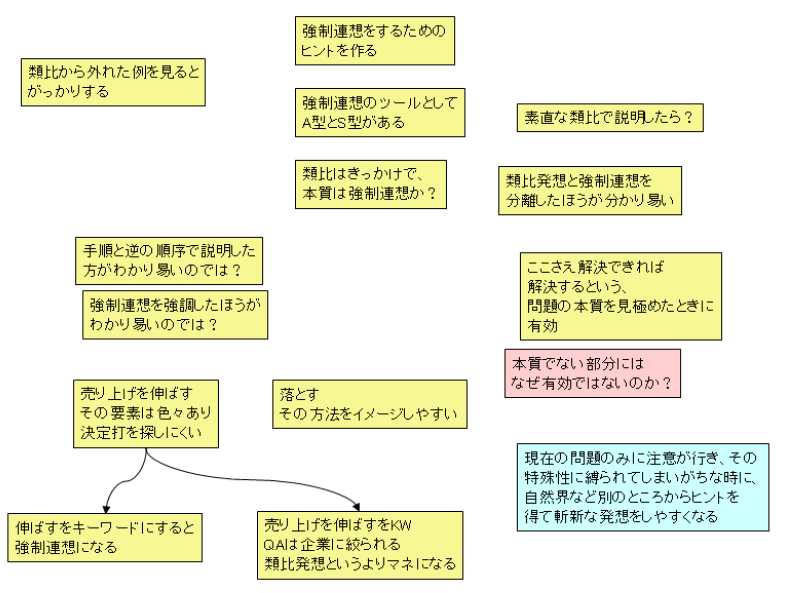
(4) 説明文のアイデア出し
下図は、会議用札寄せ法の説明文を作るためのアイデア出しを行なった例である。
ここで得た内容は、この文にも活かされている。
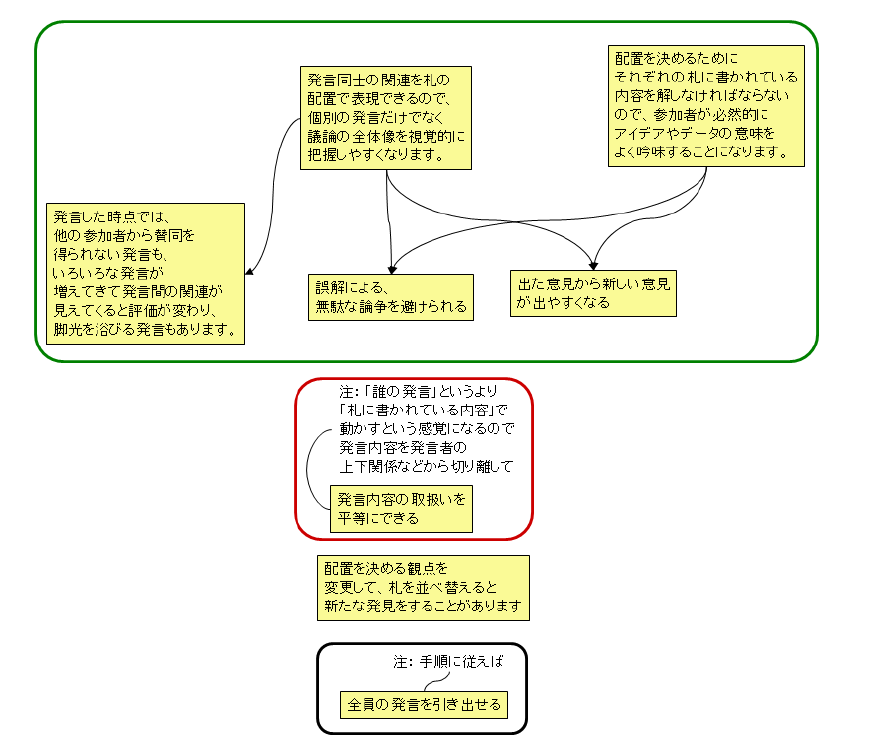
| 本ページの先頭 | 論文先頭 | 個人使用の手順 | 札の並べ方の観点 | 個人使用の実施例 | 会議での使用の手順 | 会議での使用の実施例 | 英文ページ |
||
| 札寄せ用具と第一考舎の紹介(片平、2015. 1) |
札寄せしながら考える(5) (中川、2015. 9) |
札寄せ用具と図的思考(第1部) |
同(第2部) |
同(第2部)PDF |
同(第3部) |
同(第4部) |
総合目次  |
(A) Editorial | (B) 参考文献・関連文献 | リンク集 | ニュース・活動 | ソ フトツール | (C) 論文・技術報告・解説 | 教材・講義ノート | (D) フォーラム | Generla Index |
||
| ホー ムページ |
新着情報 |
子ども・中高生ページ | 学生・社会人 ページ |
技術者入門 ページ |
実践者 ページ |
CrePS体系資料 | USITマニュアル/適用事例集 | サイト内検索 | Home Page |
最終更新日: 2016. 9.29 連絡先: 中川 徹 nakagawa@ogu.ac.jp