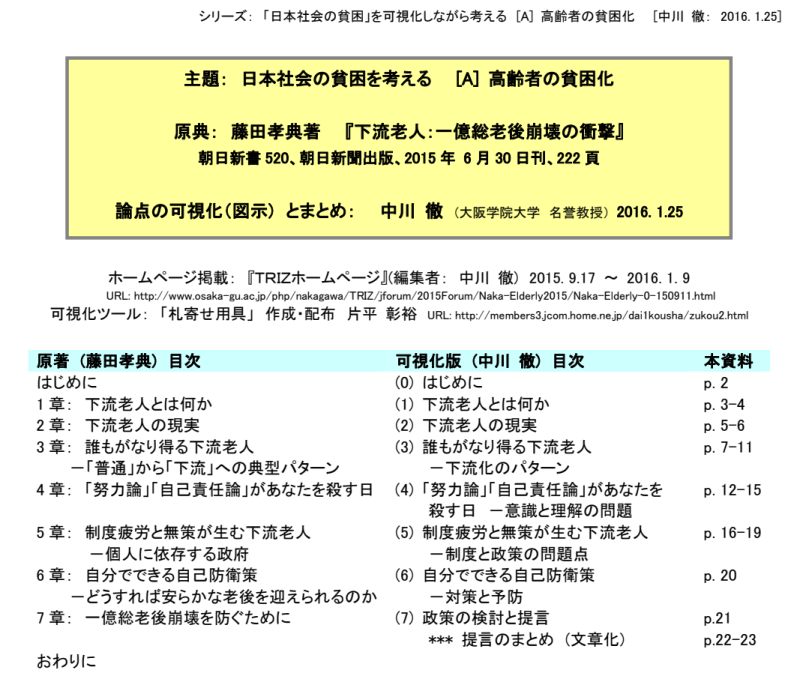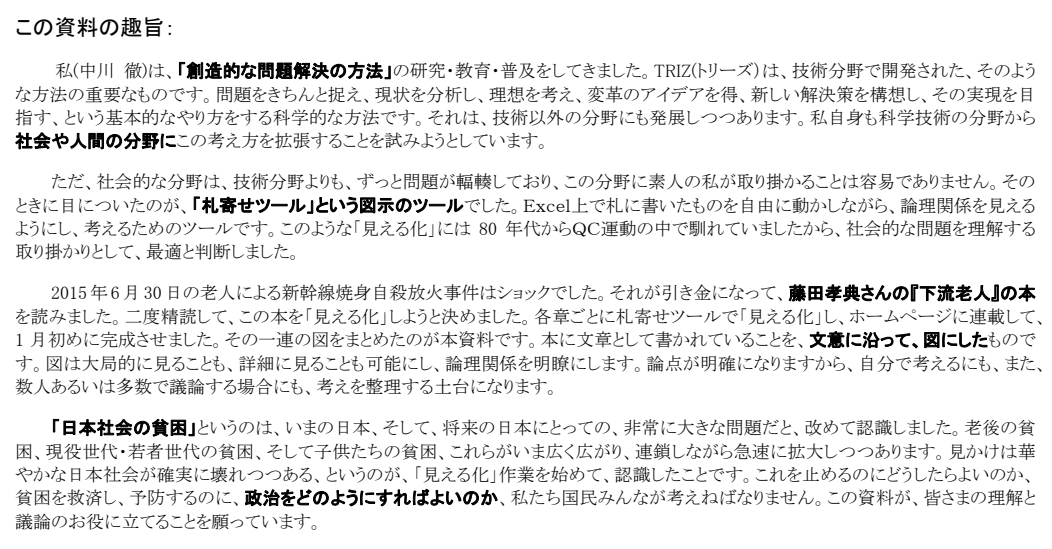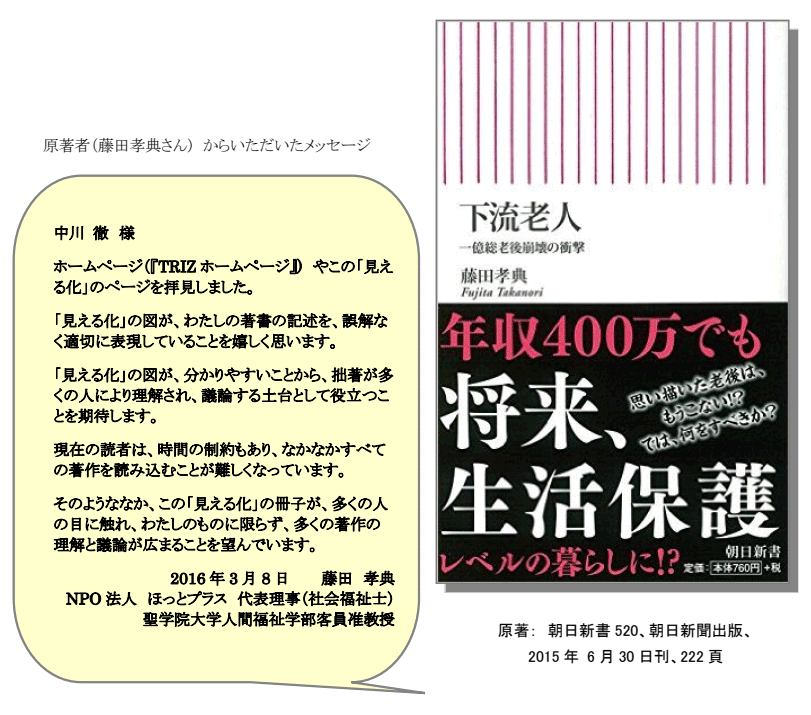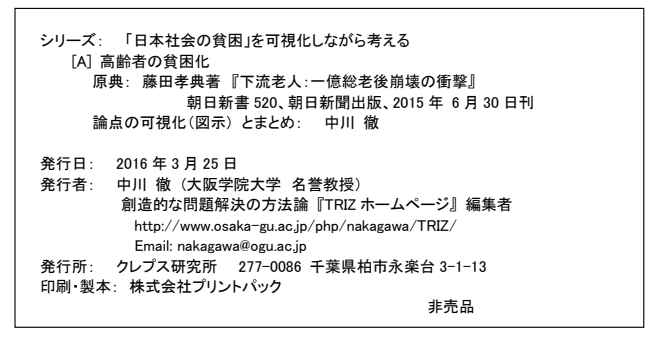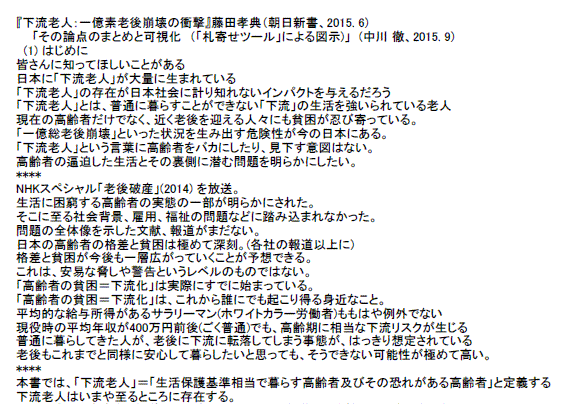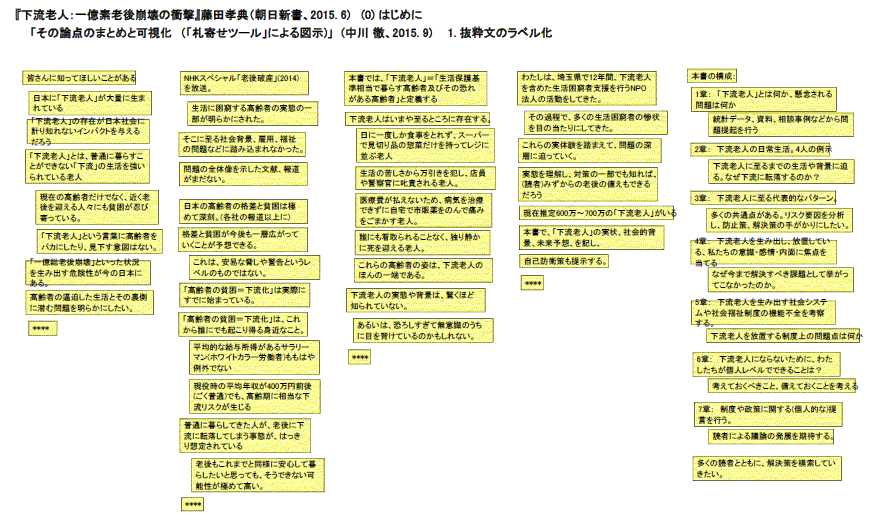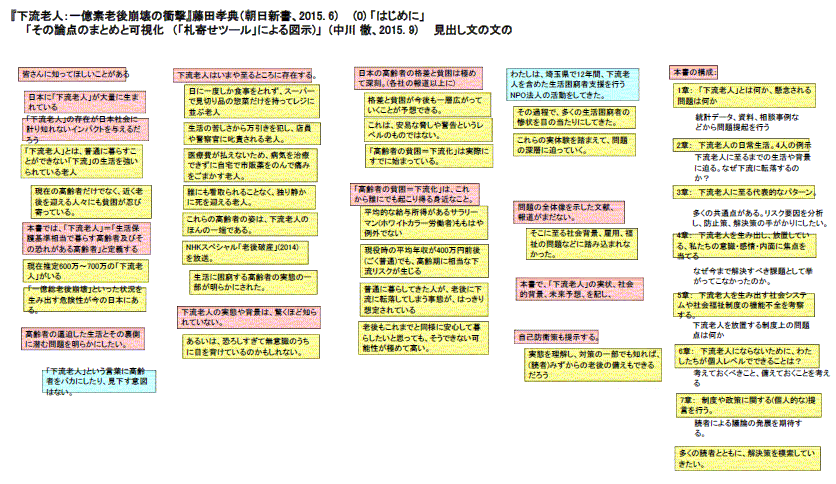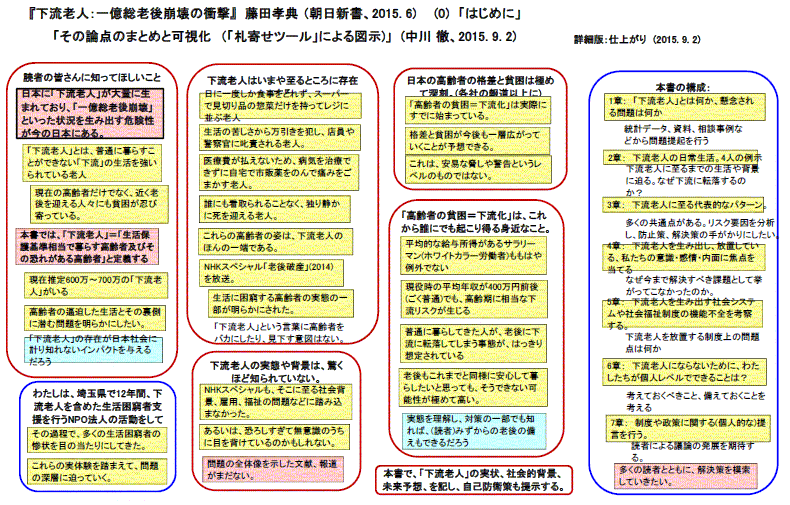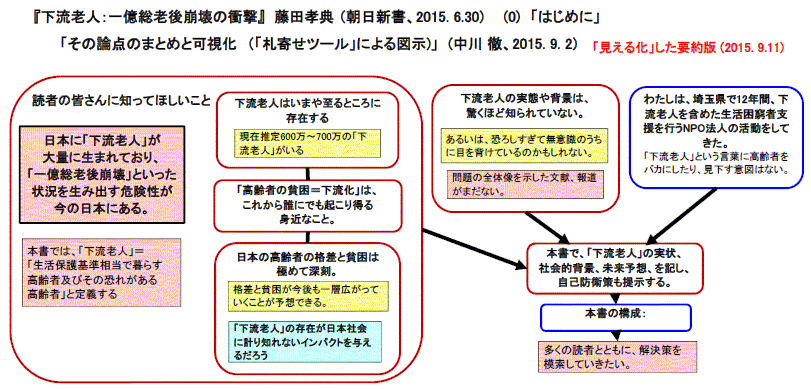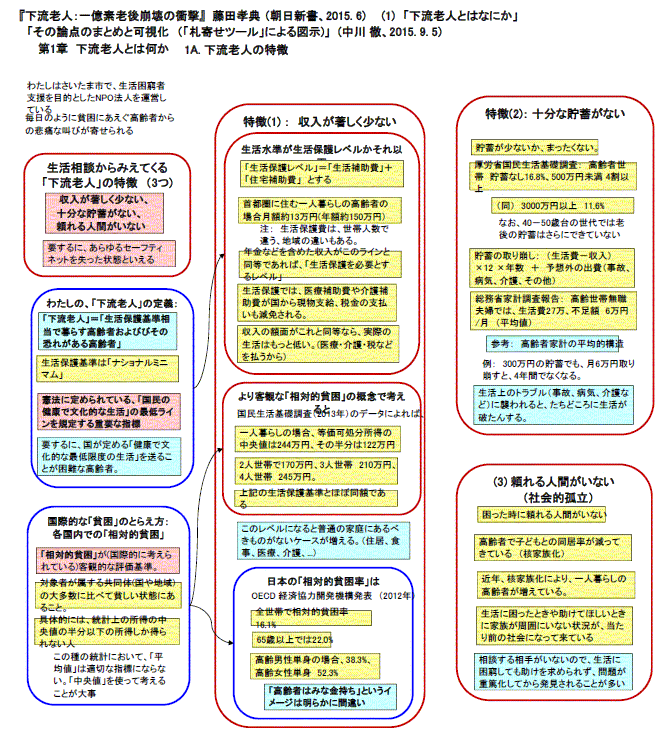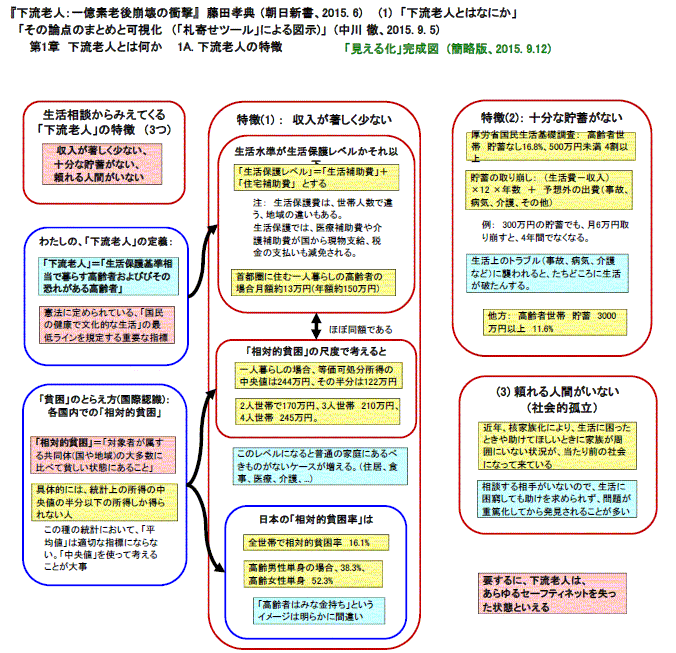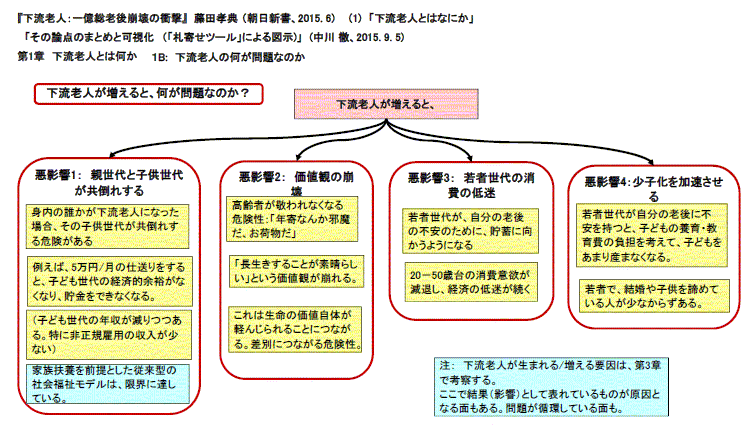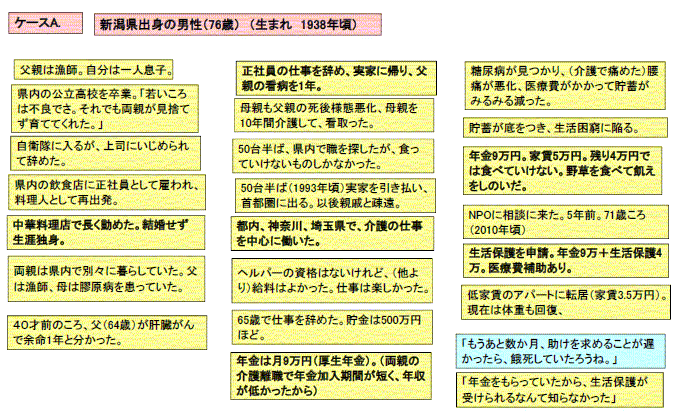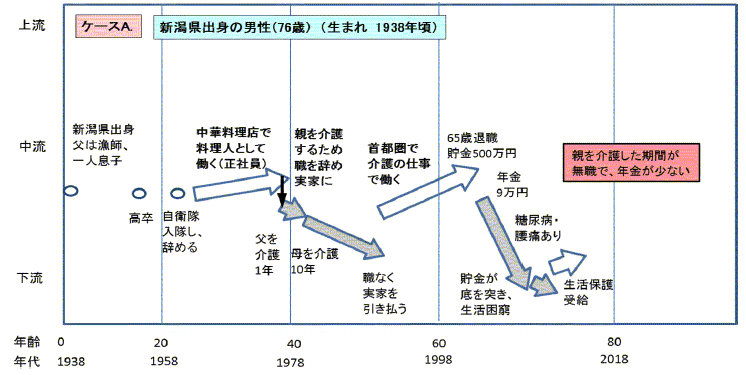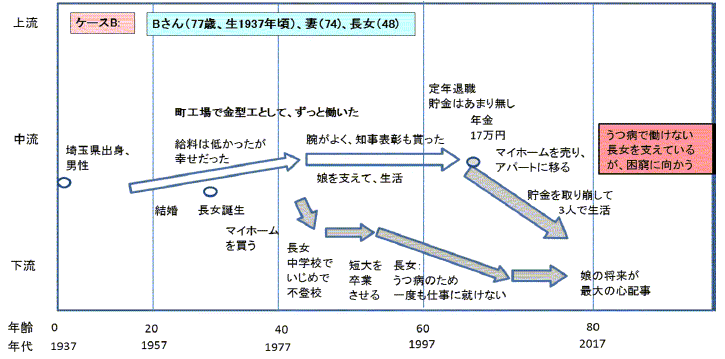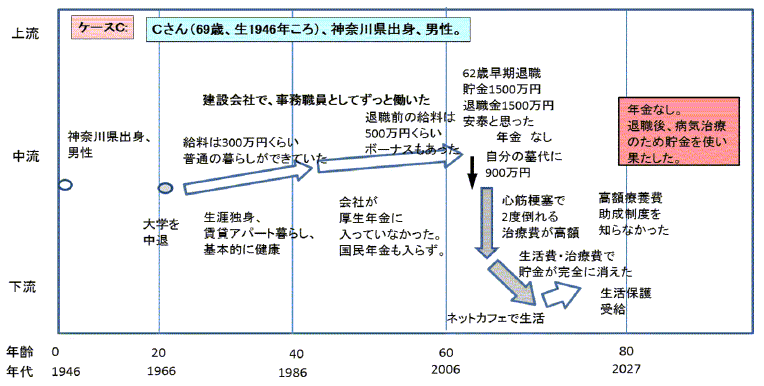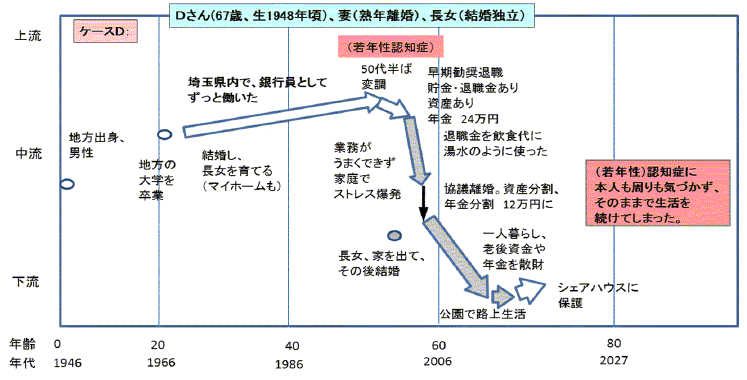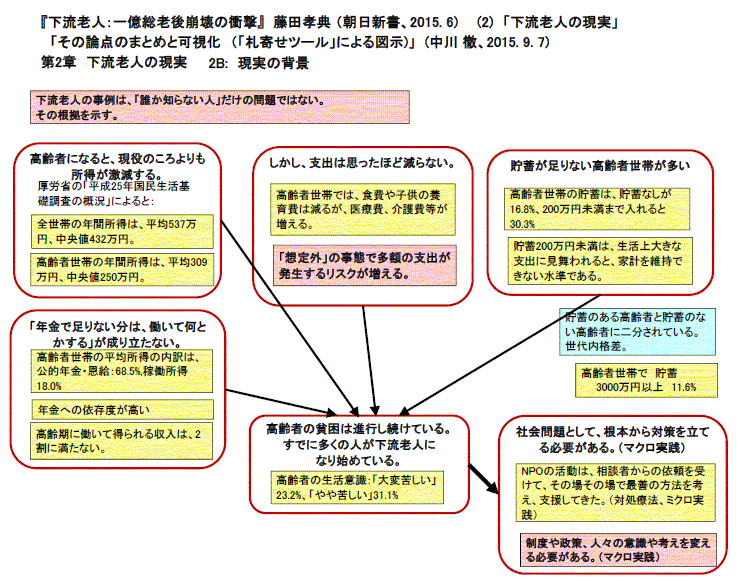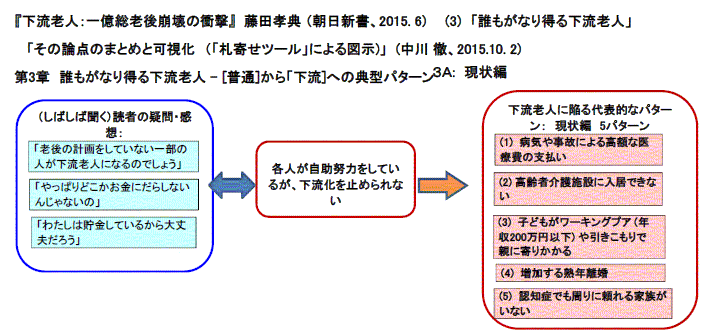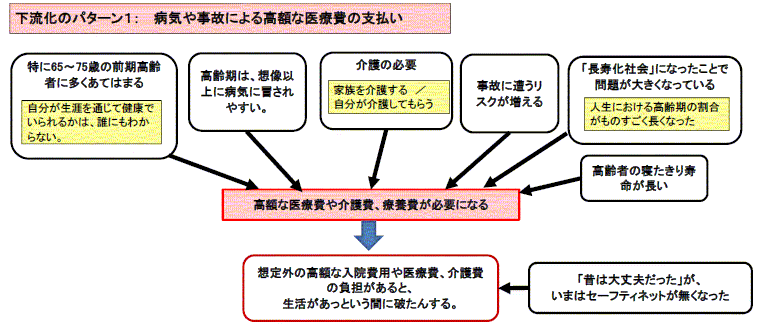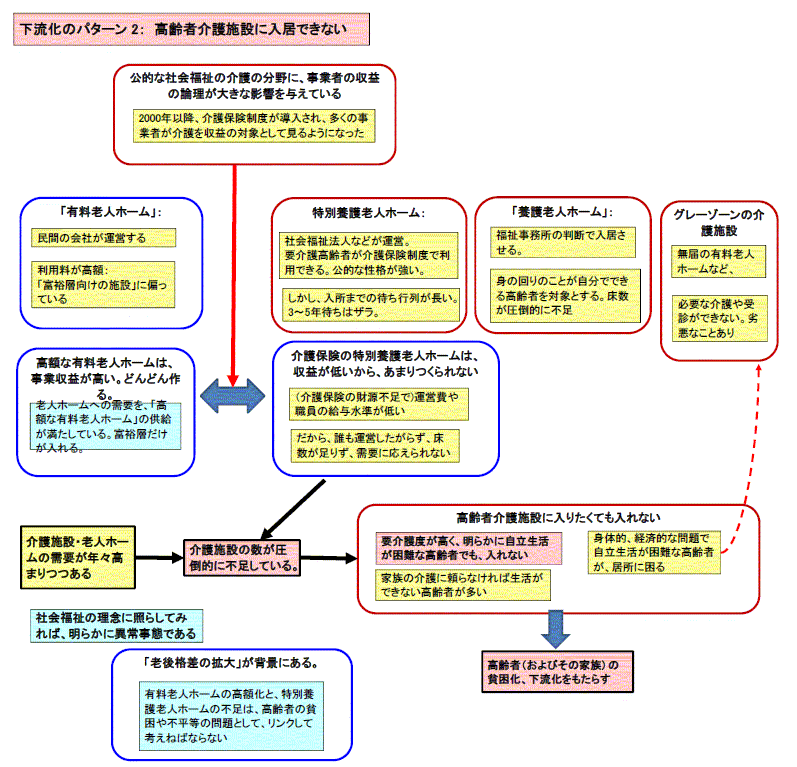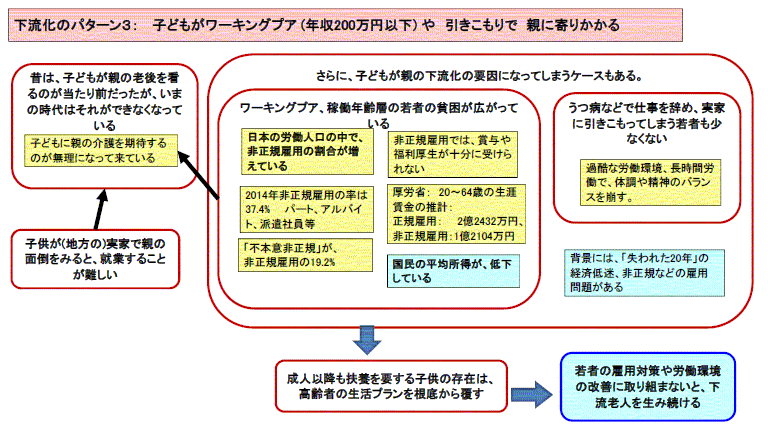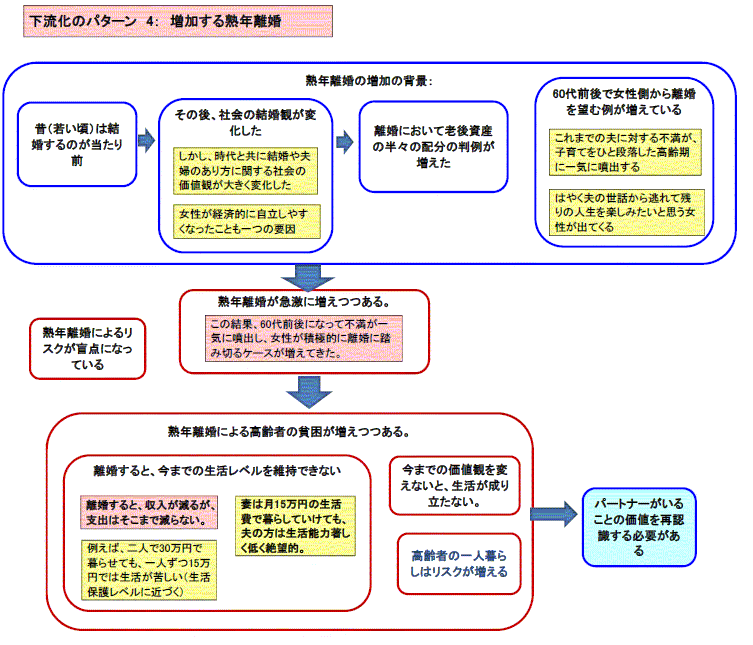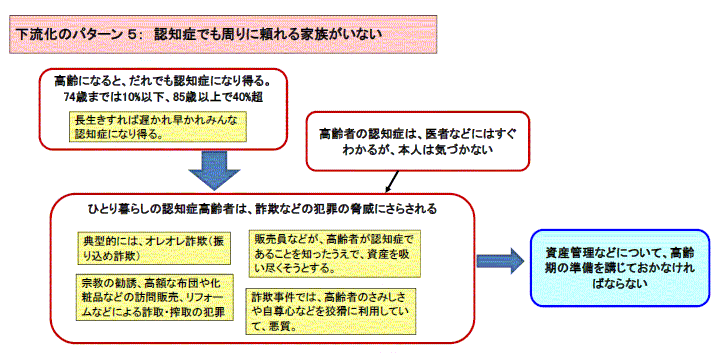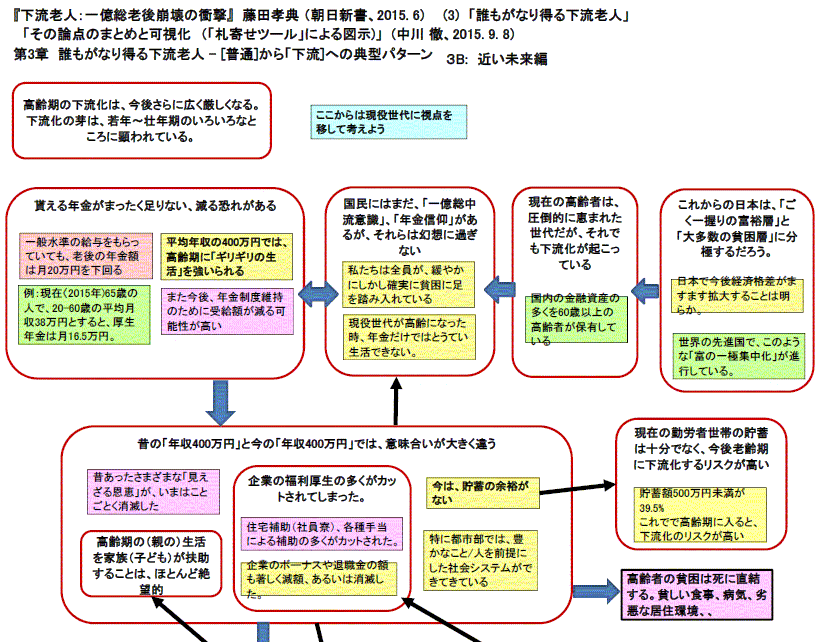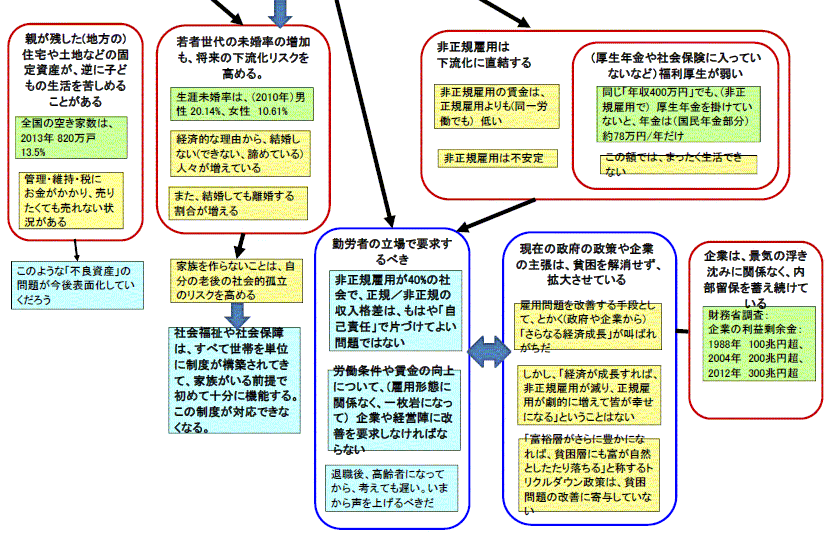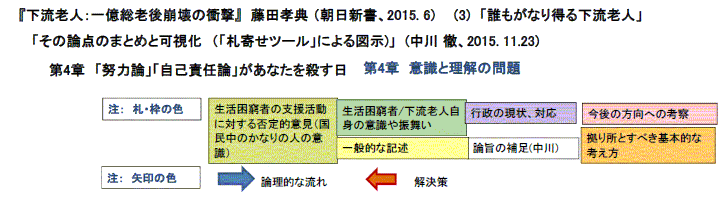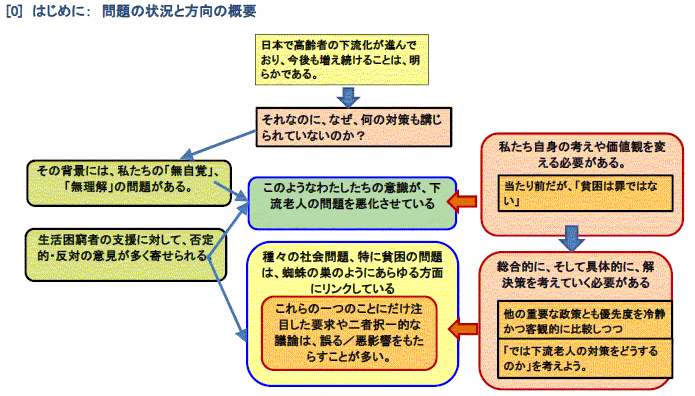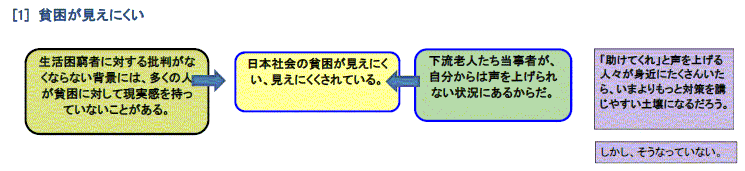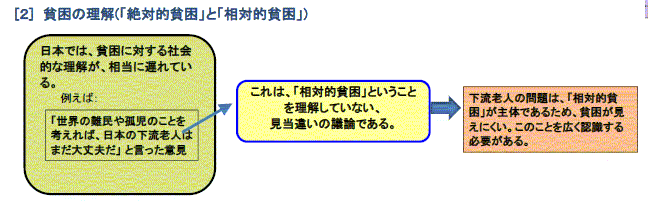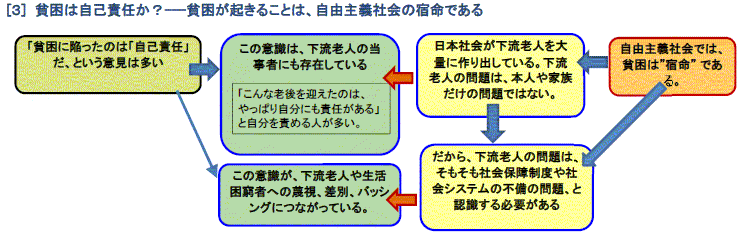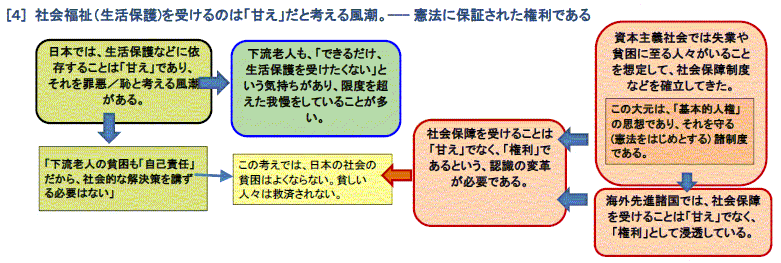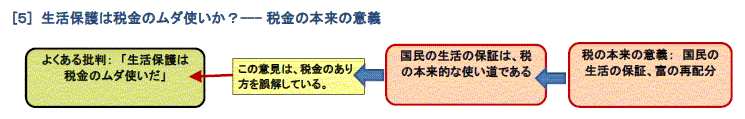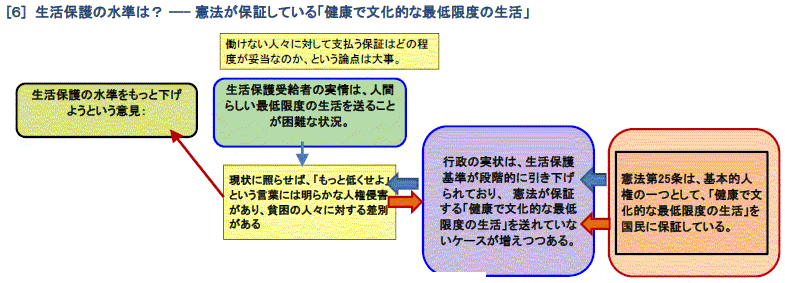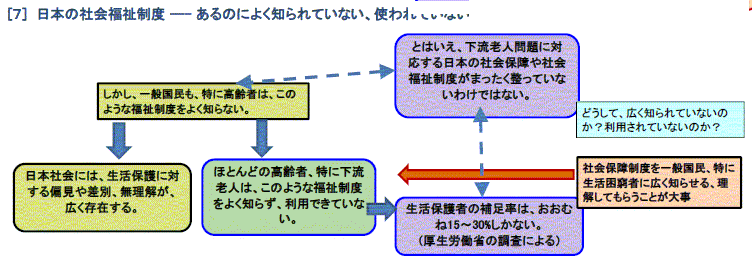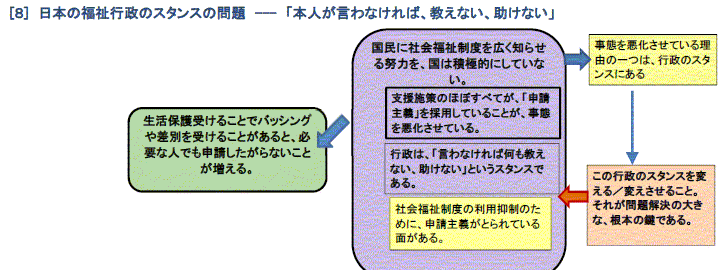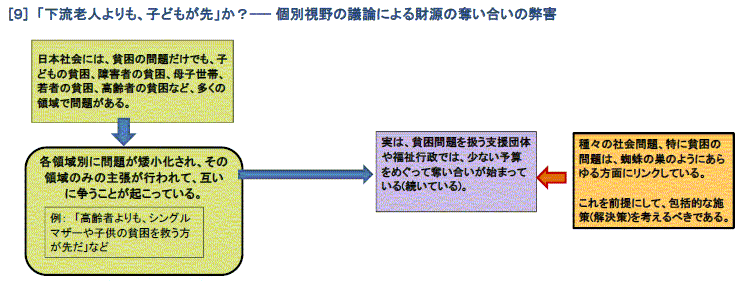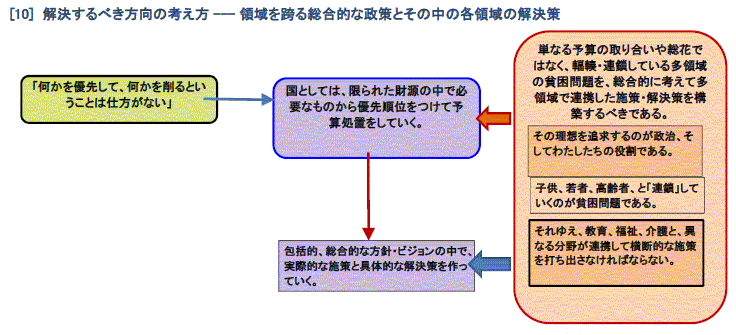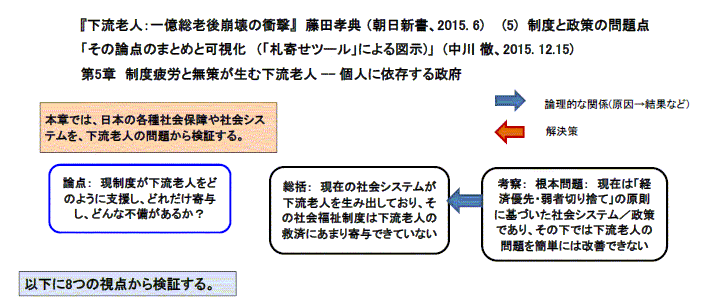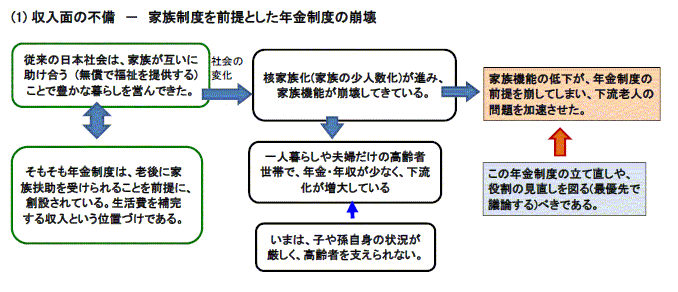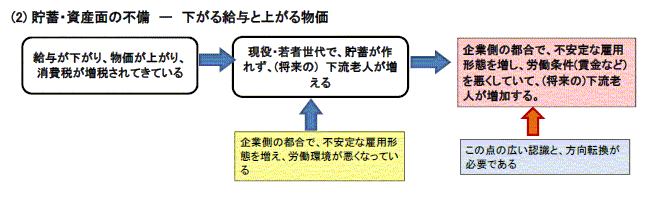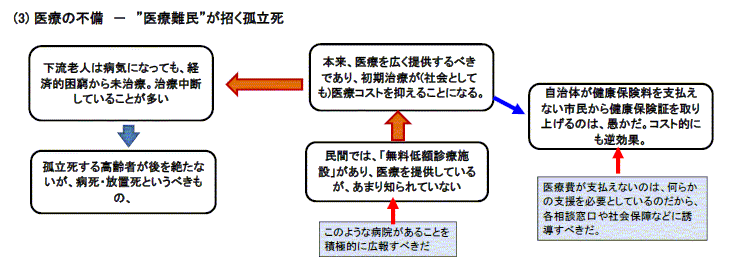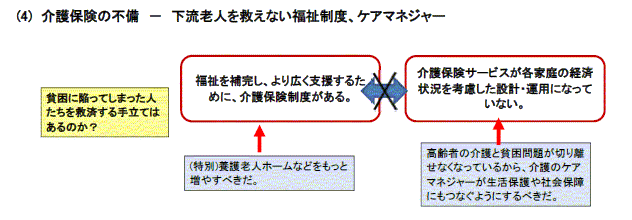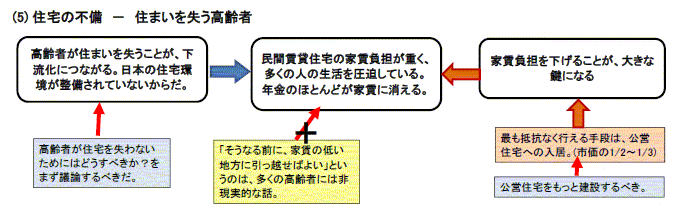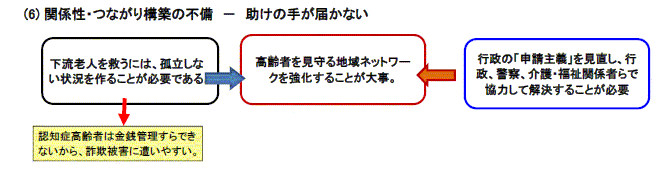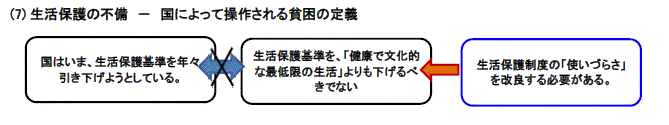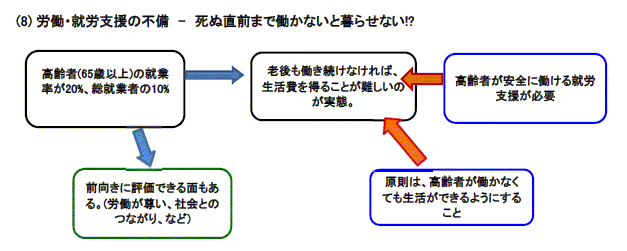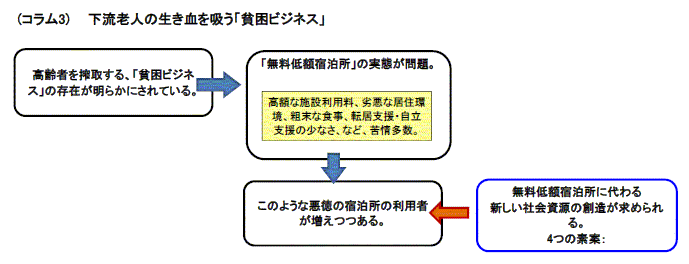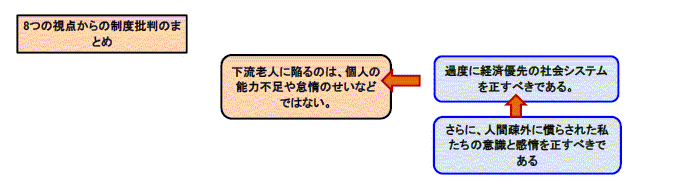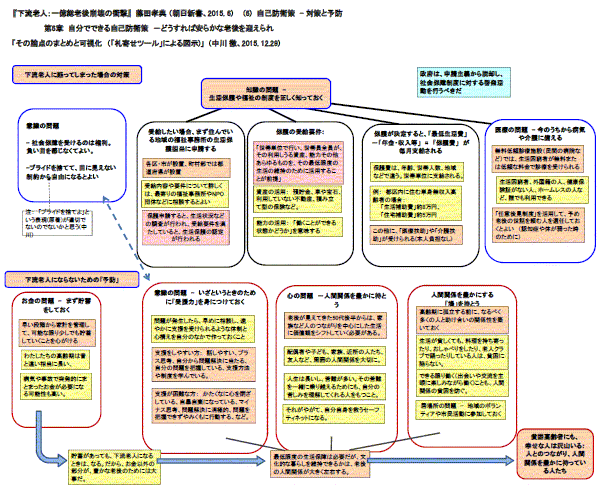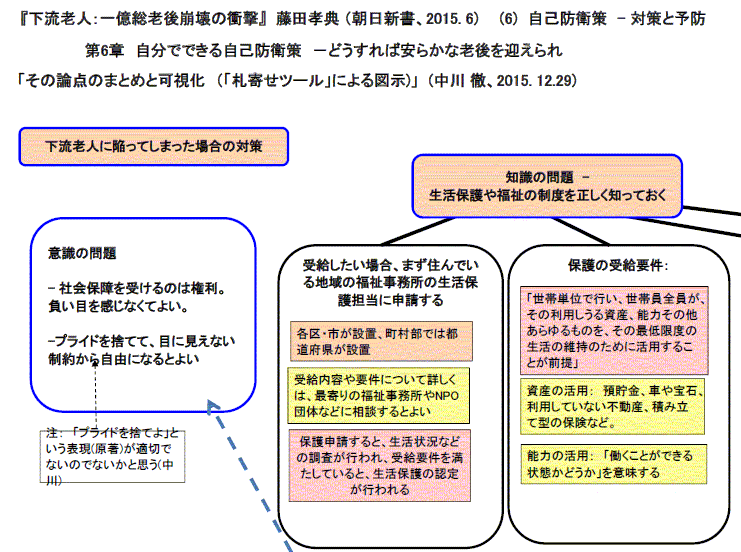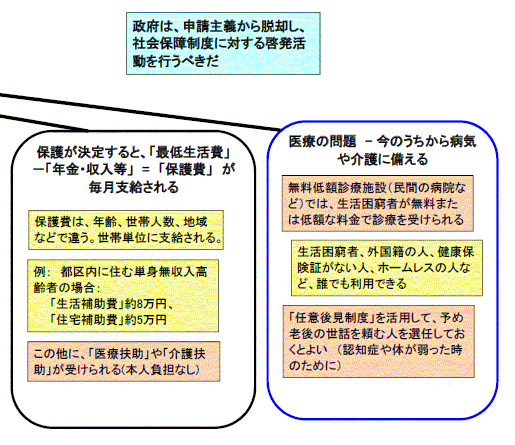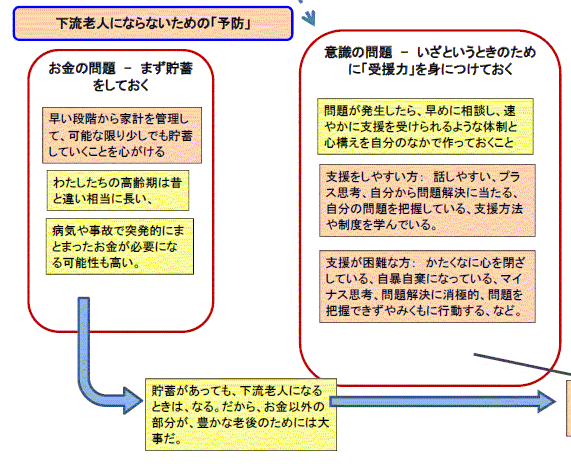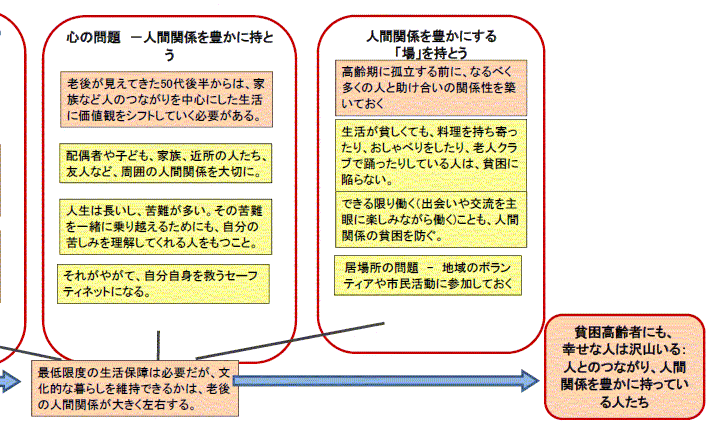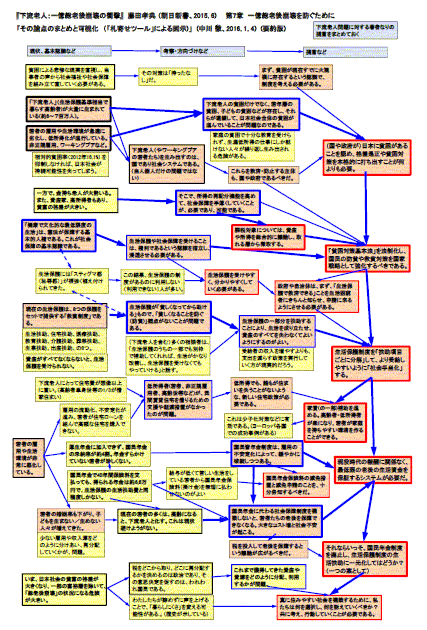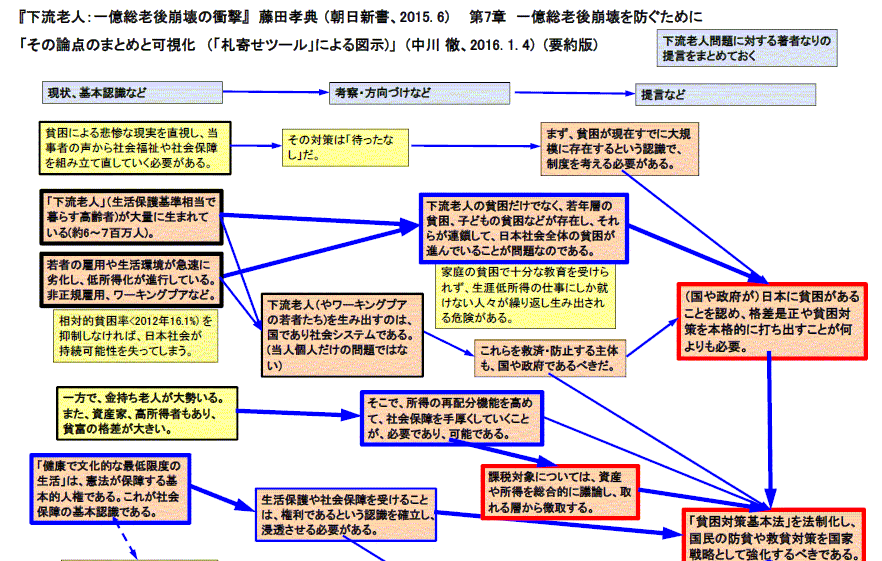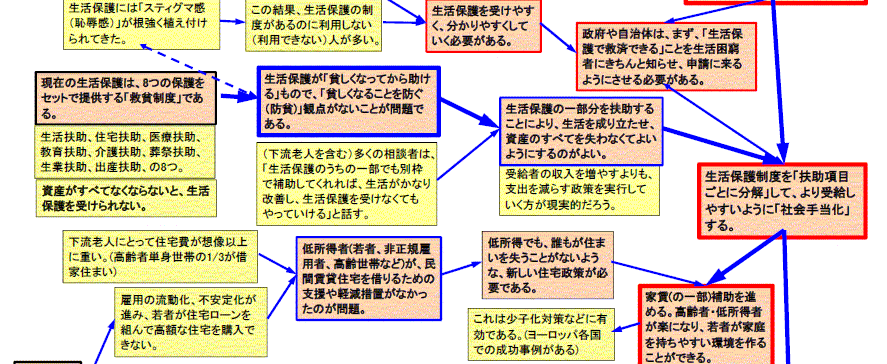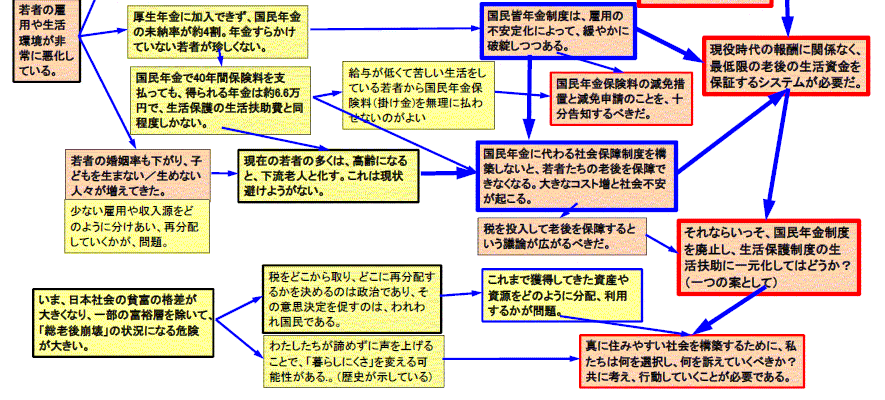jSW-TN-G1-ThinkingPoverty-withVisualization �w���� �O�@����I�W�x�@G1 jSW-TN-G1-ThinkingPoverty-withVisualization �w���� �O�@����I�W�x�@G1
|
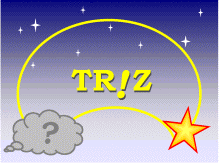 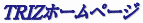  |
�u���{�Љ�̕n���v���������Ȃ���l����: ���c�F�T���w�����V�l�x���������l�@���� |
���� �O (���w�@��w ���w��)
|
�wTRIZ�z�[���y�[�W�x�A�ځA
�e�y�[�W (2015. 9.17)�@�{�e�͂̃y�[�W (2015. 9.17 �`�@2016.1.28) (2015. 9.17)�@�{�e�͂̃y�[�W (2015. 9.17 �`�@2016.1.28) |
�w���� �O�@����I�W�x�@���^ G1�@2025. 6. 6
|
�f�ځF 2025. 6�D8; 7. 3; 7.16; 7.25 |
Press the  button for going back to the English top page.
button for going back to the English top page.
 �ҏW�m�[�g�@(����@�O�A2025. 6. 6)�@�@�@
�ҏW�m�[�g�@(����@�O�A2025. 6. 6)�@�@�@
���̃y�[�W�́A�����u�n���I�Ȗ������̕��@�i�_�j�v���A�]���̉Ȋw�Z�p�̕��삩��A���L���Љ�I�E�l�ԓI�ȕ���ɓK�p���悤�Ǝ��݂��A�����̍l�@�̃v���Z�X�Ƃ��̌������L�q�������̂ł��B��ނƂ��ẮA���c�F�T���w�����V�l�F�ꉭ���V�����̏Ռ��x�i�����V���A2015)��I�сA�Е����T�́u�D�p��v�Ƃ����\�t�g�E�c�[�����g���āA�{�̘_�����������Ȃ���l�@���܂����B2015�N9�����痂�N1���܂ŁA�{��1�͂����������A�l�@���������A�wTRIZ�z�[���y�[�W�x��8��ɂ킽��A�����܂����B2016�N1��25���ɁA���̑S�̂��܂Ƃ߂āAA4��24�y�[�W�̍��q�����A��R�̕��ɔz�z���܂����B�i���q�͂܂��c������������܂��̂ŁA����]�̕��ɂ͂����肵�܂��B�j
�{�y�[�W�ł́A�啔�̎����ɂȂ�܂��̂ŁA�܂��S�̂��i���q�̕\���Ɨ��\���̌`�Łj�����A���̌�Ɍ����́u�͂��߂Ɂv����u�I���Ɂv�܂ł��e�͂��Ƃɏ��������Ă����܂��B�e�͂̋L�q�́A�ҏW�m�[�g�A�{�������������}�A�l�@�i����j����\�����Ă��܂��B
�@�����̍\���Ɩ{�z�[���y�[�W�ł̐}�����A�֘A�L���̈ꗗ�@�@==> ���q�Łi24��)PDF�@ �@
�@
 �@�@���q�̕\���@�Ɓ@���\��
�@�@���q�̕\���@�Ɓ@���\��
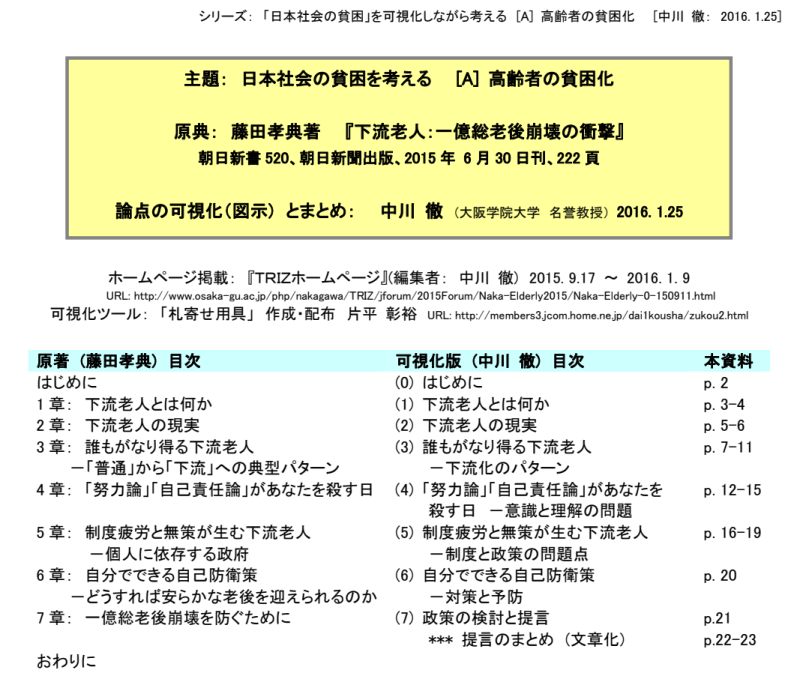
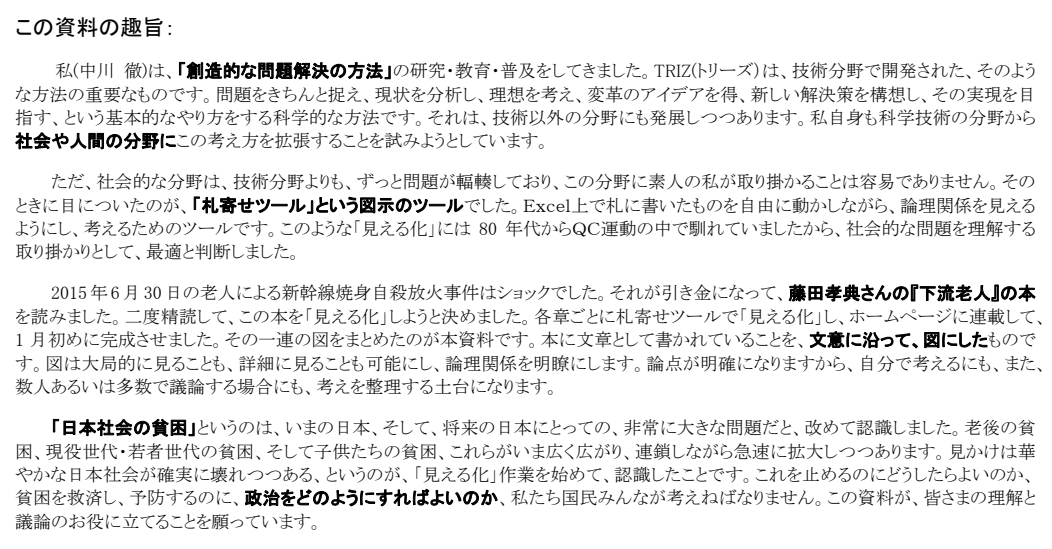
���\��
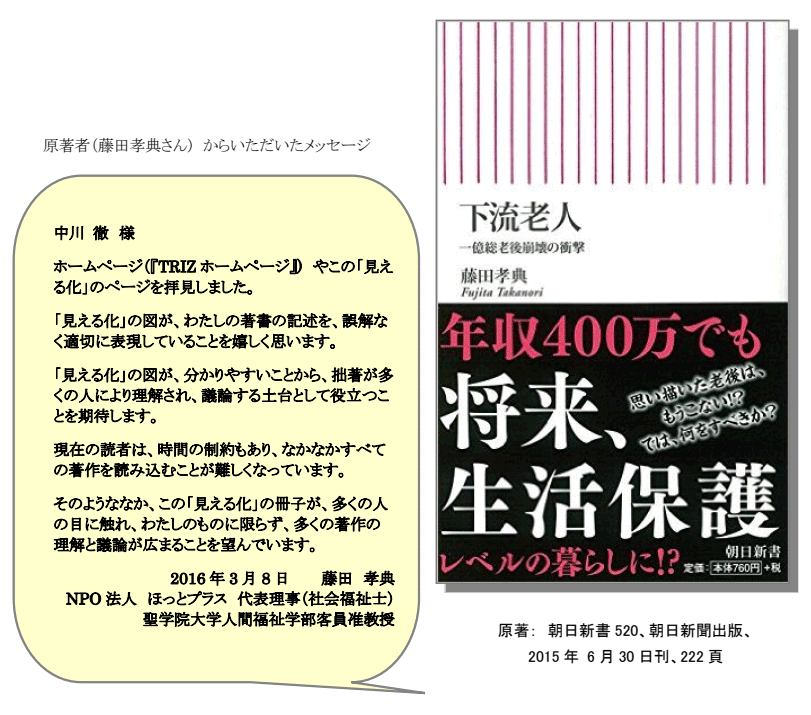
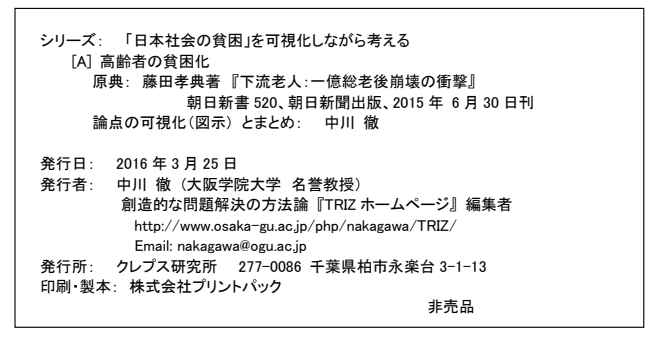
 �{�V���[�Y�̊J�n�̈Ӑ}�@�F�@�i�e�y�[�W�j�@�ҏW�m�[�g (���� �O�A2015�N 9��10��) �@�@
�{�V���[�Y�̊J�n�̈Ӑ}�@�F�@�i�e�y�[�W�j�@�ҏW�m�[�g (���� �O�A2015�N 9��10��) �@�@
�{�y�[�W�͕\��̂悤�ɁA���ɑ傫�ȁA�t�s�����A�����ďd�v�ȃe�[�}�ɂ��āA�������荘�����낵�āA�l���Љ�Ɋ�^���Ă��������Ǝv���Ďn�߂���̂ł��B������n�߂�ɂ������ẮA���낢��Ȏv�����o�b�N�ɂ���܂��̂ŁA��������������ɏ����Ă��������Ǝv���܂��B
(1) �܂���́A�{�z�[���y�[�W�̎��ł���܂��A�u�n���I�������̕��@�_�v�iTRIZ => USIT => CrePS) �̓W�J�Ɋւ��邱�Ƃł��B���̌����e�[�}�́A�Z�p����ł̖�����(������Z�p�v�V)���傽��ΏۂƂ��A�܂������ɁA�u���̏œ_���i���āA���͂��A��������l���o���v���Ƃ��傽��A�v���[�`�ɂ��Ă��܂����B����ł�2012�N�ɁATRIZ�Ƃ�USIT�Ƃ��̌ʋZ�@���z���āA�����ƈ�ʓI�ȑn���I�������̕��@�_���Љ�狁�߂��Ă��邱�ƂɋC�����A�����CrePS�ƌĂԐV�����ڕW�ɂ����̂ł�
 �BCrePS�Ō����Ă��܂��̂́A�u�v�l�̐��E�v�ł̈�ʓI��(�ėp�A�W����)���@���A(��{�I�ɂ�USIT�Ɠ��l�̃A�v���[�`��)�m�����A���낢��ȁu�����̐��E�v�̖���������Ղ���낤�Ƃ������Ƃł��B
�BCrePS�Ō����Ă��܂��̂́A�u�v�l�̐��E�v�ł̈�ʓI��(�ėp�A�W����)���@���A(��{�I�ɂ�USIT�Ɠ��l�̃A�v���[�`��)�m�����A���낢��ȁu�����̐��E�v�̖���������Ղ���낤�Ƃ������Ƃł��B
�ł́A���̂Ƃ��A���܂��܂ȁu�����̐��E�̖��v���ǂ̂悤�ɂ��đ����A�u�v�l�̐��E�v�Ɏ������߂�̂��H���傫�Ȃ��Ƃł��B�Z�p�����łȂ��A�Љ��l�Ԃ��܂ޖ��́A���G�ɗ��ݍ�����(�t�s����)�傫�ȍL�����������ł��邱�Ƃ��A�����ł��B���̂悤���t�s�����傫�Ȗ���������ƈ������Ƃ����H���A���̕��@���K�����A����Ă����Ȃ���Ȃ�܂��� �B���ۂɂ���čs���Ă݂悤�A�Ƃ����̂��A����̈�̓��@�ł��B
�B���ۂɂ���čs���Ă݂悤�A�Ƃ����̂��A����̈�̓��@�ł��B
(2) �t�s����������������@�ɂ͂��낢�날��܂����A���낢��Ȏ�����l���̊֘A��}�Ɏ������u�����鉻�v�������Ƃ́A�厖�ȕ��@�ł��B�]�����玄���g���AKJ�@�A�}�C���h�}�b�v�A�������ʐ}�ASouthbeach�@Modeller���A���낢��g���Ă��܂������ATRIZ�֘A�ł����낢��Ȑ}�����̕��@������܂��B���̒��ŁA��N���ȗ��A�Е����T�����ꂽ�u�D�c�[���v�̊ȕւ��ƗL�p���Ɋ������܂��� �B������g���ƁA���낢��Ȃ��Ƃ���₷���A�����͂��������}�ɍ�邱�Ƃ��A�e�Ղɂł��邱�Ƃ�������܂����B���̎D�ɂ��}���̕��@�́A�Љ�I�Ȗ��Ȃǂ��t�s�������Ɏ��|����Ƃ��̏d�v�Ȏ�|����ɂȂ�Ǝv���܂����B�V���ȗ��Е�����ƈꏏ�ɂ������̐}��`���Ă݂āA������g���čs���ړr�𗧂Ă邱�Ƃ��ł��܂����B
�B������g���ƁA���낢��Ȃ��Ƃ���₷���A�����͂��������}�ɍ�邱�Ƃ��A�e�Ղɂł��邱�Ƃ�������܂����B���̎D�ɂ��}���̕��@�́A�Љ�I�Ȗ��Ȃǂ��t�s�������Ɏ��|����Ƃ��̏d�v�Ȏ�|����ɂȂ�Ǝv���܂����B�V���ȗ��Е�����ƈꏏ�ɂ������̐}��`���Ă݂āA������g���čs���ړr�𗧂Ă邱�Ƃ��ł��܂����B
(3) �u�����̐��E�̖��v�ɂ��A������܂��܂ȃe�[�}������܂��B�Z�p�J������̂Â���Ɋւ��邱�ƁA�E�����̕���A�Đ��G�l���M�[/�ȃG�l���M�[�A�����A�n�k�\�m�����A�����āA����Љ�A�F�m�Ǘ\�h�A���q�����A�o�ϖ��A���ۖ@���̈ጛ���A���{�����̕n���A�ȂǂȂǁA�����ς�����܂��B���܂܂łɂ��A�����̖��ɏ������S�������A�w��A�l�����肵�Ă��܂������A�����g�̋�̓I�Ȋ����ɂȂ��Ă�����̂͂��܂肠��܂���B
(4) ���̂悤�Ȓ��ł��܂��o����āA�Е�����ɐ}�����Ă����������̂��A�u�V�����Đg���E���Ύ����v�̘V�l�̐S���Ɣw�i�ł��� �B���̌��͂���������Љ�I�w�i���l����K�v������Ǝv���ēǂ̂��A�w�����V�l�|�ꉭ���V�����̏Ռ��x(���c�F�T���A�����V���A2015�N�U����)�ł����B�����̌��Ɋ�Â��A��������ƍl�@�E�L�q�����{�ł��B���݂��łɍ���҂�(�n�x�̊i�������債��) �n���E���������L�����Ă��邱�Ƃ��L���Ă��܂��B��N�w�̒Ꮚ���A����w�̕N���A�q�ǂ��̕n���Ȃǂ��A�����āA���̂܂ܐi�ނƓ��{�Љ���ɕs����ɂȂ�A�����ȘV����߂������Ƃ������̐l�ɕs�\�ɂȂ�ƁA�x�����Ă��܂��B-- �����Ŏ��́A���̂悤�����݊֘A����Ղł���悤�ɂ��A�l�@�E�c�_�̃x�[�X��������Ƃ��A�n�߂悤�ƍl��������ł��B����҂̕n���������ł��傫�Ȗ��ł����A����͓��{�Љ��(������)�n�����̈ꑤ�ʂɂ����߂��Ȃ��A�����Ă܂���������{�̎Љ�E�����E�o�ςȂǂ̈ꑤ�ʂł���A�����Ă܂��A���E�̖��̂����ꕔ�ɂ����߂��Ȃ��B���̂��Ƃ����m�̏�ŁA���͂��܁A�u���{�Љ�̕n���v�Ƃ������A�����Ă��̉����̂��߂̍l�������A�l���Ă������Ƃ��Ă��鎟��ł��B
�B���̌��͂���������Љ�I�w�i���l����K�v������Ǝv���ēǂ̂��A�w�����V�l�|�ꉭ���V�����̏Ռ��x(���c�F�T���A�����V���A2015�N�U����)�ł����B�����̌��Ɋ�Â��A��������ƍl�@�E�L�q�����{�ł��B���݂��łɍ���҂�(�n�x�̊i�������債��) �n���E���������L�����Ă��邱�Ƃ��L���Ă��܂��B��N�w�̒Ꮚ���A����w�̕N���A�q�ǂ��̕n���Ȃǂ��A�����āA���̂܂ܐi�ނƓ��{�Љ���ɕs����ɂȂ�A�����ȘV����߂������Ƃ������̐l�ɕs�\�ɂȂ�ƁA�x�����Ă��܂��B-- �����Ŏ��́A���̂悤�����݊֘A����Ղł���悤�ɂ��A�l�@�E�c�_�̃x�[�X��������Ƃ��A�n�߂悤�ƍl��������ł��B����҂̕n���������ł��傫�Ȗ��ł����A����͓��{�Љ��(������)�n�����̈ꑤ�ʂɂ����߂��Ȃ��A�����Ă܂���������{�̎Љ�E�����E�o�ςȂǂ̈ꑤ�ʂł���A�����Ă܂��A���E�̖��̂����ꕔ�ɂ����߂��Ȃ��B���̂��Ƃ����m�̏�ŁA���͂��܁A�u���{�Љ�̕n���v�Ƃ������A�����Ă��̉����̂��߂̍l�������A�l���Ă������Ƃ��Ă��鎟��ł��B
(5) ���݂̓��{�̐����͖{���ɕn�����Ǝv���܂��B���ɁA���{�W�O�̐����p���͂Ђǂ��B���{���u���������͊��S�ɃR���g���[�����ɂ���v�Ƌ����������A���̋��\���x�[�X�ɂ���������i�߂Ă��āA���݂́u�ϋɓI���a��`�v�Ƃ����܂₩���̘_�@�̂��ƂɌ��@�̕��a��`�ɔ�����@����ʂ����Ƃ��Ă���B�����̑����������A���@�w�҂̑������ጛ���ƌ����Ă���̂ɁA�����}������ɂ�����Ɣ��ł��鍑��c�����قƂ�ǂ��Ȃ��B���{�̐����́A�{���ɕn�����B���́A2014�N�̐V�N���A �̈ꕔ�ł��̂悤�Ȑ����ᔻ�������܂������A���̌�͂��܂菑���Ă��܂���B���̃z�[���y�[�W�́A�����I�Ȉӌ��ڕ\�������łȂ��ƍl���邩��ł��B����ł��A���ق��邾�����]�܂������Ƃł͂Ȃ��ƁA�l���Ă��܂��B���{�̎Љ�ɂ��āA���̏����̂�����ɂ��čl����Ƃ��A���������ɂ��čl���邱�Ƃ͂ł��܂���B�{�y�[�W�ŁA���{�̎Љ�̖����u�����鉻�v���悤�Ƃ����̂́A�������ɂ��Ă� (������ϔO�_�łȂ�) �������肵���_�����x�[�X�ɂ��āA�݂��ɔ������A�c�_��[�߁A����������o���čs�������ƍl���邩��ł��B
�̈ꕔ�ł��̂悤�Ȑ����ᔻ�������܂������A���̌�͂��܂菑���Ă��܂���B���̃z�[���y�[�W�́A�����I�Ȉӌ��ڕ\�������łȂ��ƍl���邩��ł��B����ł��A���ق��邾�����]�܂������Ƃł͂Ȃ��ƁA�l���Ă��܂��B���{�̎Љ�ɂ��āA���̏����̂�����ɂ��čl����Ƃ��A���������ɂ��čl���邱�Ƃ͂ł��܂���B�{�y�[�W�ŁA���{�̎Љ�̖����u�����鉻�v���悤�Ƃ����̂́A�������ɂ��Ă� (������ϔO�_�łȂ�) �������肵���_�����x�[�X�ɂ��āA�݂��ɔ������A�c�_��[�߁A����������o���čs�������ƍl���邩��ł��B
�ȏ�̂悤�Ȏ�|�ŁA�u���{�Љ�̕n�����l����v�Ƃ����e�[�}�ŁA���낢��ȕ������x�[�X�Ɂu�D�v�Łu�����鉻�v�����}������āA�����f�ڂ��Ă��������ƍl���Ă���܂��B�����z�E���ӌ��E����e�Ȃǂ������������܂��ƍK���ł��B�F���܂���̂��ӌ��Ȃǂ��A�u�����鉻�v���Ă������Ƃɂ���āA�[�݂ƍL���肪������̂ɂ��Ă�����Ƃ悢�Ǝv���Ă���܂��B
 �����e�L�X�g�w�����V�l�x�ɂ��āF�@�@�ҏW�m�[�g (���� �O�A2015�N 9��11��) �@�@
�����e�L�X�g�w�����V�l�x�ɂ��āF�@�@�ҏW�m�[�g (���� �O�A2015�N 9��11��) �@�@
�{�y�[�W�́A���̕������x�[�X�ɂ��Ă���܂��B���̖{���x���ǂ��������ŁA�l�@�̃x�[�X�ɂ���̂ɓK���Ɣ��f���܂����B
�w�����V�l�|�ꉭ���V�����̏Ռ��x�A���c�F�T���A�����V��520�A�����V���o�ŁA2015�N 6��30�����A222��
�Ȃ��A�����ɂ����҂̃v���t�B�������̂悤�ɋL�q���Ă��܂��B
���c�F�T (�ӂ����@�����̂�)
1982�N���܂�BNPO�@�l�ق��ƃv���X��\�����B���w�@��w�l�ԕ����w���q���y�����B���n���l�b�g���[�N��ʑ�\�B�u���b�N��Ƒ�v���W�F�N�g������\�B�����J���ȎЉ�ۏ�R�c����ʕ���ψ��B�\�[�V�������[�J�[�Ƃ��Č���Ŋ����������A�����ی��������Ҏx���݂̍���Ɋւ�����s���B�����Ɂw�ЂƂ���E�����Ȃ��x(�x�V���o��)�ȂǑ����B
�����{�������E�v�����o���A�����g����������Ƃ���ɏ]���āA�u�D�v�c�[��(�Е����T�쐬) ��p���āA�}��(�u�����鉻�v)�������̂ł��B��L�̖{�̏ڍׂȓǏ��m�[�g�ł����ƁA�������������B�L�q�̊�{�����₻�̘_���\���͌����ғ��c�F�T���̂��̂ł����A�S�̂̕\���A���ɐ}�����\���͎��ɐӔC������܂��B�����g�̊��z��ӌ��́A�����҂̋L�q�Ƃ͋�ʂ��ċL�q����悤�ɂ������܂��B
��p���āA�}��(�u�����鉻�v)�������̂ł��B��L�̖{�̏ڍׂȓǏ��m�[�g�ł����ƁA�������������B�L�q�̊�{�����₻�̘_���\���͌����ғ��c�F�T���̂��̂ł����A�S�̂̕\���A���ɐ}�����\���͎��ɐӔC������܂��B�����g�̊��z��ӌ��́A�����҂̋L�q�Ƃ͋�ʂ��ċL�q����悤�ɂ������܂��B
 �w�����V�l�x(���c�F�T��)�@�u�͂��߂Ɂv�@�Ɓ@�u�����鉻�v�̂�肩���@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015. 9.15)
�w�����V�l�x(���c�F�T��)�@�u�͂��߂Ɂv�@�Ɓ@�u�����鉻�v�̂�肩���@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015. 9.15)
�{���Ɋւ���u�����鉻�v�y�[�W�̍ŏ��ł��̂ŁA���̃m�[�g���쐬������������悤�ɂ��Ă����܂��B
(1) �������E�v��̃e�L�X�g���
�{��ǂ݂A(�_����\���ł���悤�ɒ��ӂ���)�@���������邢�͗v���A����Excel�t�@�C���ɏ����o���Ă����B�i�傫��)�i���̋��ɁA****�̍s����ꂽ�B
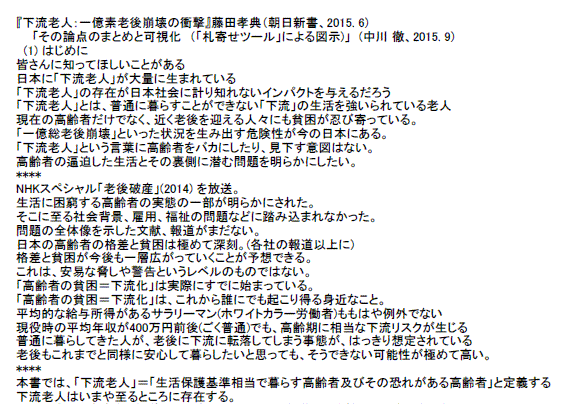
[�㗪]
(2) ���x����
�����o���������A�D�c�[���ŁA[�ꊇ����] �D(���x��)�ɕϊ������B�D�̉����߂��A�d�Ȃ�Ȃ��悤�ɕ��ׂ�B���Ԃ͏����o�����܂�(���Ȃ킿�A�����̋L�q�̂܂�)�B(�傫��)�i���̋��ł܂Ƃ߁A�t�������̕��̓��x���������E�ɂ��炵�ĕ�����₷�����Ă���B
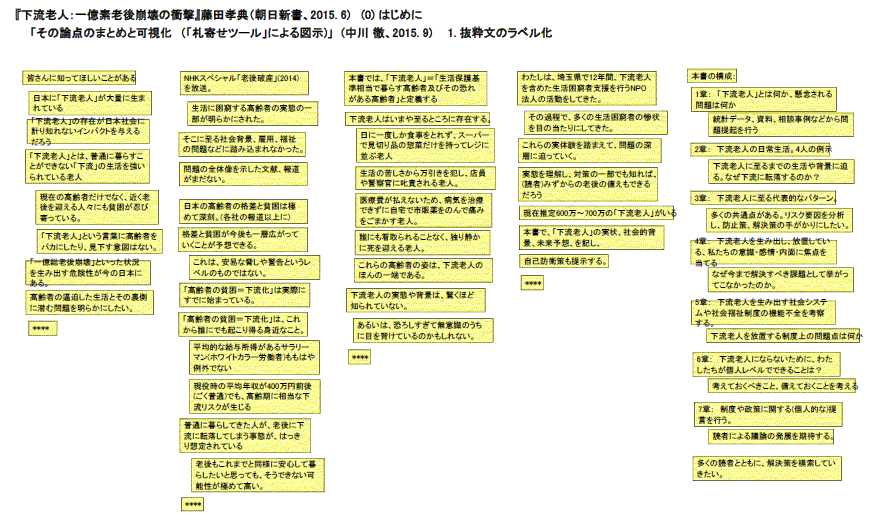
(3)�@���o�����ƃO���[�v�\��
�_�_�m�ɂ���悤�ɒ��������B��̘_�_���܂Ƃ߂Ă�����ƌ����Ă��镶��I��(���邢�͂��̂悤�ȕ��������)[�ԐF�̎D�ɂ�]�A���̘_�_�ł̎D���W�߂ăO���[�v�ɂȂ�悤�ɔz�u����B�{�̋L�q���O�サ�Ă�����̂Ȃǂ��W�߂āA�����������B
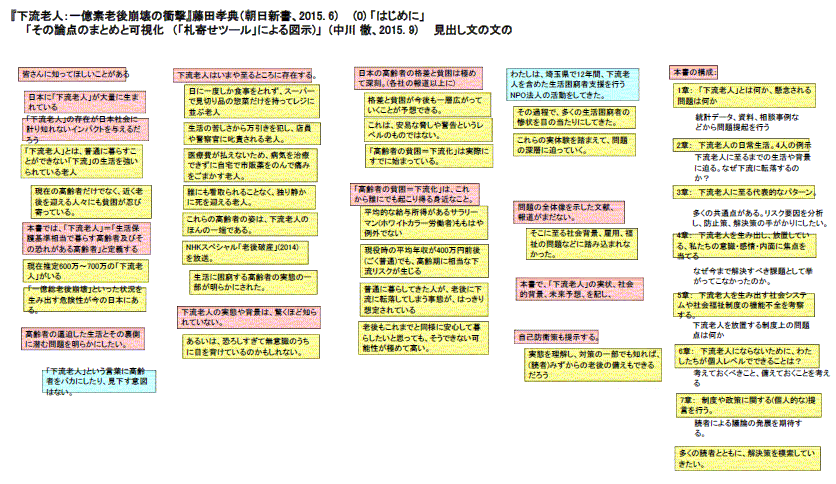
(4) �d�グ(�O���[�v���ƑS�̍\��)�A�ڍהł̊���
�_�_�̎啶�������ԐF�̎D���A�͘g�ɕϊ����A���̘_�_�̎D���O���[�v�Ƃ��ĕ\������B�S�̘̂_�������m�ɂȂ�悤�ɁA�O���[�v(�͘g)�@�����ݔz�u�������B�S�̂��ēx�������āA(�ڍהłƂ���)�@�d�グ��B
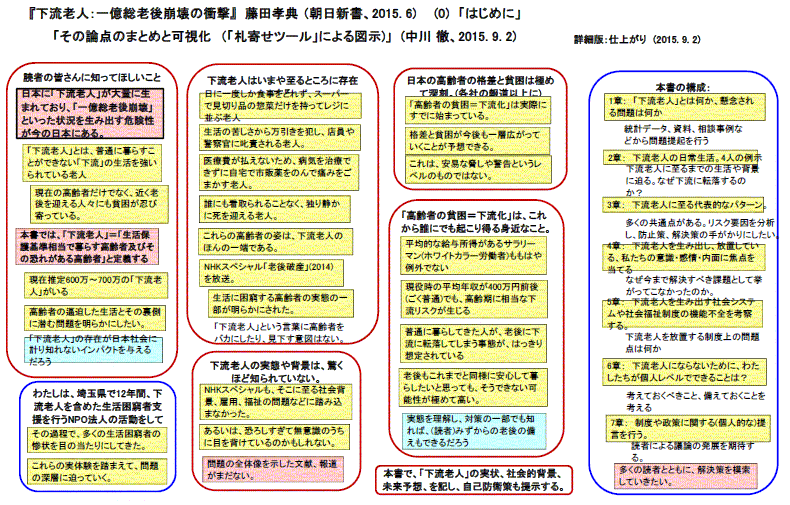
(5) �ڍׂ������A�_���̖��m���B�v��ł̊���
�_�_����w���m�ɂ��邽�߂ɁA�ו��̎D���ȗ����āA�u�v��Łv�����B�O���[�v�P�ʂœ������āA�S�̘̂_���m�ɂ��A�����g���Ę_���W��}�������B�ꕔ�̎D�́A�ʂ̃O���[�v�Ɉړ������Ă���B
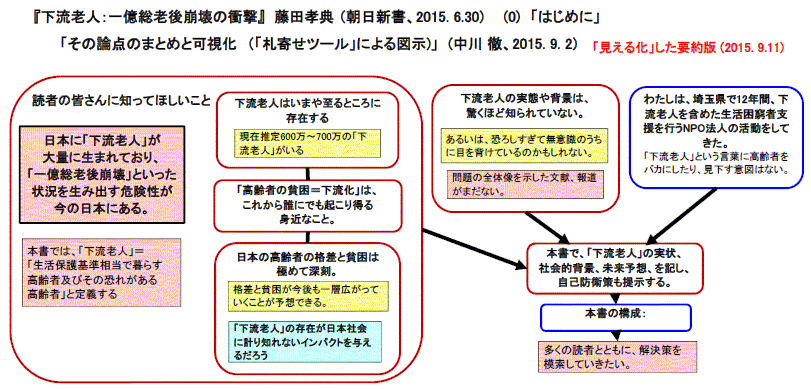
(6) �u�����鉻�v�����}��ǂݎ���āA���̗v�|�͉�����
���̐}���ȒP�ɕ��͉������ƁA���̂悤�ł��B
���{�Ɂu�����V�l�v����ʂɐ��܂�Ă���A�u�ꉭ���V�����v�Ƃ������ݏo���댯�������̓��{�ɂ���B�{���ł́A�u�����ی������ŕ�炷����ҋy�т��̋��ꂪ���鍂��ҁv���u�����V�l�v�Ƃ����B���̎��Ԃ�w�i�͋����قǒm���Ă��Ȃ��B�{���ł��̑S�̑���`���A�����̓ǎ҂ƂƂ��ɂ��̉�������l���Ă��������B
���̊�{�p���ňȉ��ɖ{���̊e�͂�ǂ݉����A�u�����鉻�v���Ă����܂��B
 �w�����V�l�x�@�u��1�́@�����V�l�Ƃ͉����v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015. 9.12)
�w�����V�l�x�@�u��1�́@�����V�l�Ƃ͉����v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015. 9.12)
�u�͂��߂Ɂv�̃y�[�W�ŏ��������̂Ɠ��l�̕��@�ŁA�u�����鉻�v�����܂����B�{�y�[�W�ɂ͎d�オ�������̂������f�ڂ��܂��B
(1) ��1�͑O���A�u�����V�l�Ƃ͂������������A��̓I��3�̎w�W�v�ɂ��ẮA�����鉻�}(�ڍה�)�B
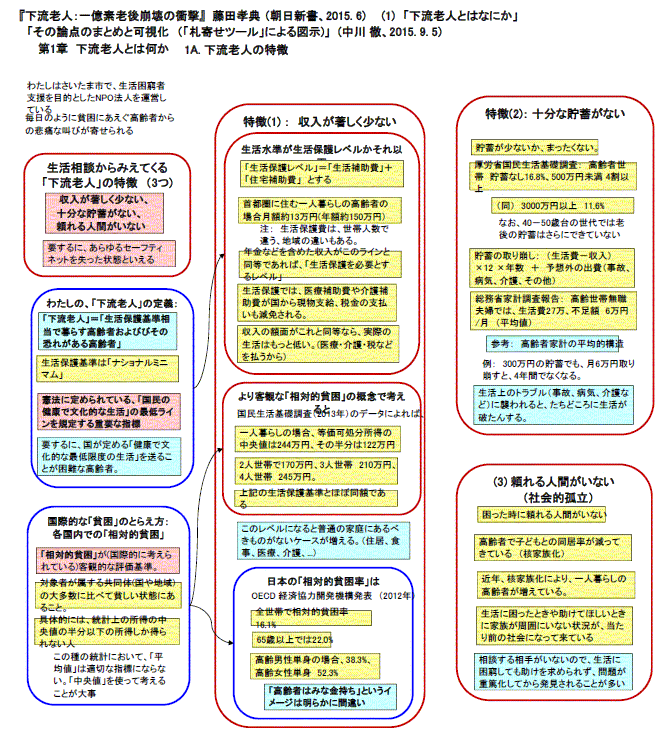
(2) ��1�͑O���A�u�����V�l�Ƃ͂������������A��̓I��3�̎w�W�v�ɂ��ẮA�����鉻�}(�ȗ���)�B
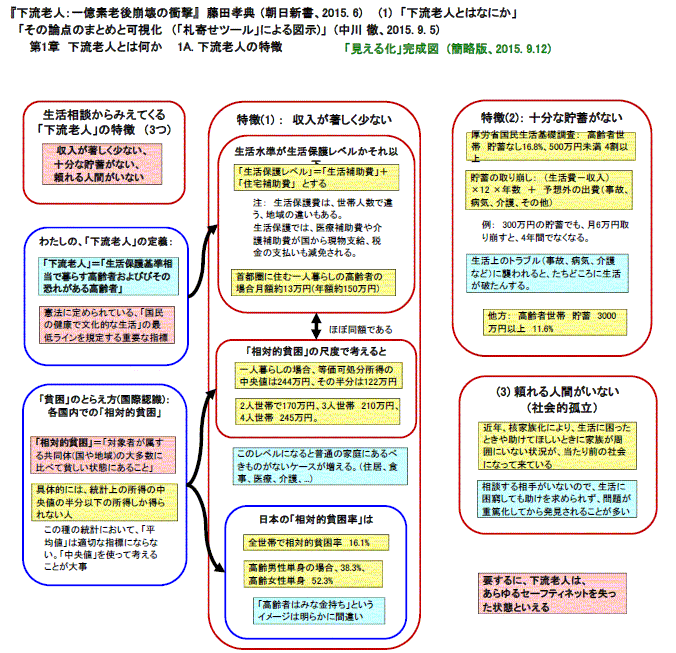
���̐}���ȒP�ɕ��͉�����ƁA�ȉ��̂悤�ł��B
���́A�u�����V�l�v���u�����ی������ŕ�炷����҂���т��̋��ꂪ���鍂��ҁv�ƒ�`���Ă���B�������k���猩���Ă���u�����V�l�v�̓����͂���3�_�ł���B
�i1�j�@���������������Ȃ��B�����ی샌�x�����⏕��{�Z��⏕��Ƃ���ƁA��s���ɏZ�ވ�l��炵�̍���҂̏ꍇ���z��13���~�i�N�z��150���~�j�ł���B���ۓI�ȕn���̂Ƃ炦���Ƃ��āA�u���ΓI�n���v�Ƃ����T�O������B�Ώێ҂������鋤���́i����n��j�̑命���ɔ�ׂĕn������Ԃɂ��邱�Ƃ������A��̓I�ɂ͓��v��̏����̒����l�̔����ȉ��̏������������Ȃ��l�������B���̊T�O�ł́A��l��炵�̏ꍇ�N��122���~�ƂȂ�A��L�̐����ی샌�x���Ƃقړ����ł���B���̃��x���ɂȂ�ƁA�Z���A�H���A��ÁA���ȂǂŁA���ʂ̉ƒ�ɂ���ׂ����̂��Ȃ��P�[�X��������B
�i2�j�@�\���Ȓ��~���Ȃ��B�����i�N���Ȃǁj���Ⴂ�ƒ��~�����������ƂɂȂ邪�A���ꂪ���Ȃ�/�����ƁA������̃g���u���ɏP����ƁA�����ǂ���ɔj����B
�i3�j�@�����l�Ԃ����Ȃ��i�Љ�I�Ǘ��j�B�ߔN�̊j�Ƒ����ɂ��A���͂ɗ����Ƒ������Ȃ��̂����ʂɂȂ��Ă���B
�v����ɁA�u�����V�l�v�͂�����Z�[�t�e�B�l�b�g�������āA���@�ŕۏ���u���N�ŕ����I�Ȑ����v���ł��Ȃ��Ȃ��Ă������ł���B���݁A��600���l�`700���l�́u�����V�l�v������Ɛ��肳��Ă���B
(3) ��1�͌㔼�A�u�����V�l�̉������Ȃ̂��H�v�ɂ��ẮA�����鉻�}�B
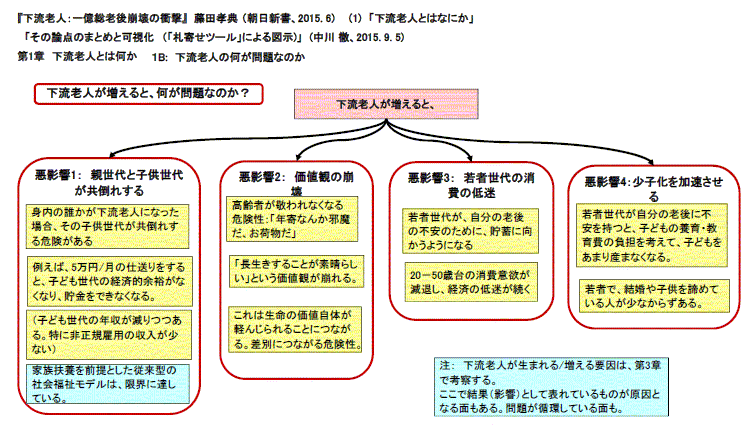
���̐}���ȒP�ɕ��͉�����ƁA�ȉ��̂悤�ł��B
�u�����V�l�v�������Ă��邱�Ƃ̖��́A�����҂����̂��ƂłȂ��A�ȉ��̂悤�Ȉ��e���������炷���Ƃ����ł���B
���e��1. �e����i����Ґ���j�Ǝq�ǂ�����i���𐢑�j�����|�ꂷ��B
���e��2.�@�������K���A�h�V�A���̑厖���Ȃǂ̉��l�ς�����
���e��3.�@��ҁE���𐢑オ���~����K�v������A�������A�o�ς��������B
���e��4. �@���q��������������B
�Ȃ��A�����V�l�����܂��/�����錴���́A��3�͂ōl�@����B�����ƌ��ʂ��z���Ă���ʂ�����B
�@
 �w�����V�l�x�@�@�u��2�́@�����V�l�̌����F ����Ɣw�i�v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015. 9.27)
�w�����V�l�x�@�@�u��2�́@�����V�l�̌����F ����Ɣw�i�v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015. 9.27)
��2�́@�����V�l�̌��� (�ڎ��j
���������҂̌���A�ٌ������Ɂu�z��O�v
�P�[�X1�@�i���H�X�Ȃǂœ������A�쑐�ŏ�����̂���������i����)): ���Ј��̎d�������߁@�e�̉��A�u����ȂɔN�������Ȃ��Ƃ͎v��Ȃ������v
�P�[�X�Q�@�i���a�̖����x����i�c����i����))�F�@�u�N�������������̖��j�v�A�����͏��������ł������ȊO�́u�z��O�v��
�P�[�X�R�@�i�����E�������Ă����R������(����)�j�F �u3000���~�Ȃ�Ă����Ƃ����Ԃɏ�����������v
�P�[�X�S�@�i�n����s�ɋ߂Ă�����������(����)): ��s���E���Ƃ̎Ј�����O�łȂ�
�����V�l���߂��邢�����̎�������A�����ĉ҂��ł���z�͑S�����̂�������2���A�x�����Ă�����Ȃ������V�l
���̑�2�͂́A�O���́i�܂������Ɓj��̓I����@4�P�[�X�̏Љ�A�����āA�㔼�̌����̔w�i�̂܂Ƃ߂��琬���Ă��܂��B������u�����鉻�v�����v���Z�X��������A���̌��ʂ��f�ڂ��܂��B
A.�@�����V�l�̌����F�@��̓I��4�̃P�[�X�@�@
(1) ����̋L�q�̔������ƁA���Ԍo�߂ɂ�鐮���A���̃��x�����B
�e�L�X�g�̑�1�̎���ɂ��āA���x�����������̂����̐}�Ɏ����܂��B
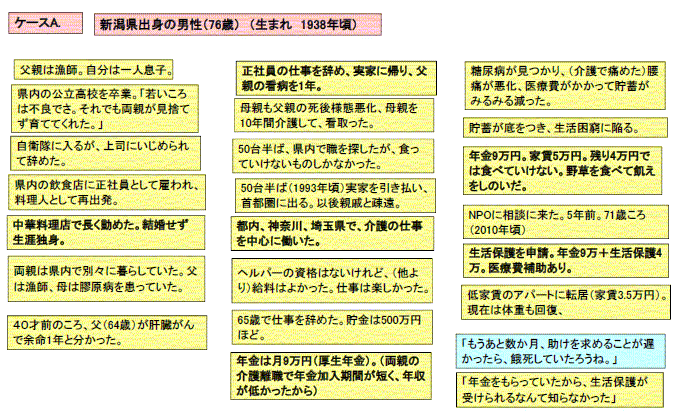
�i2�j�@�e����ɂ��āA�l�̐��U�������u�����̃��x���Ɖ������v�̊ϓ_�œƎ��ɐ}���������B
�e�L�X�g�̋L�q��ǂݎ���āA�萫�I�ł͂��邪�A�Ǝ��ɐ}���������B�i���̐}���͒���̃A�C�f�A�j
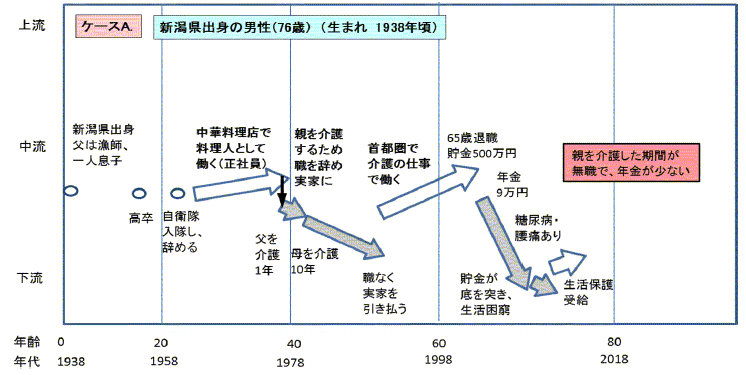
���̐}���ł͈ȉ��̂悤�ɕ\�����悤�Ƃ��Ă���B
�c���́A�u�����̎��v���A��Ƃ��Čo�ϓI�Ȉ��萫�̖ʂ���A�萫�I�Ɂi��G�c�Ɂj�\������B�����ƒ��~�Ǝ��Y�A����т����̏����̉\���i�Ⴆ�A�\�́A���N�A�E�ƁA�Ȃǁj�Ɋ�Â������̂ł���B������~�ςɌ��������x�o������A�������s���Ă��邱�Ƃ�z�肵�Ă���i���邢�́A���̂悤�ȈӖ��ł́A�x�o�\�ȃ��x�������̏c�����\�����Ă���ƍl���Ă��悢�j�B�����̍����A�h�肳�A���f���Ȃǂ�\�����̂ł͂Ȃ��B�㗬/����/�����̒l�́A��܂��Ȃ��̂ł���B�{���ɏ]���āA�u�����ی샌�x���v�ȉ����u�����v�Ƃ��A�����́i�����l�łȂ��j���ϒl��2�{�ȏ�̒��x���u�㗬�v�ƍl���Ă����B��{�I�ɁA�}�{���鐢�т̒P�ʂōl����B
�����́A���̐l�̔N���������B�N��l�̐��U�Ƃ��̐������ł���{�I�ɋK�肷�邩��ł���B�܂����̂������ɁA�N��i����j�������A����w�i���l���邽�߂̎肪����ɂ���B���l����܂ł̊��Ԃ́A�e�́i�q�ǂ���{�炷��j�������x����\�����邱�ƂɂȂ�B
��̔��u���b�N���ŁA�p�����Ă��鐶�������������B�����̏㏸��A���~�E���Y�Ȃǂ̒~�ς��i�߂i�����j�E�オ��ŕ\�������B�E�Ƃ�Ƒ��Ȃǂő傫�ȕω�������A�V�������ŕ`���B�D�F�̃u���b�N�́A�����̎������~���Ă���������B���̏◝�R�́A�����𒍋L���Ă���B�������̍����́A�Z���Ԃ̑傫�ȕω��i����)��\���B
�i3�j�@���́@3�P�[�X�ɂ��Ă��A���l�̐}�������s�����B�}�������B�@�@
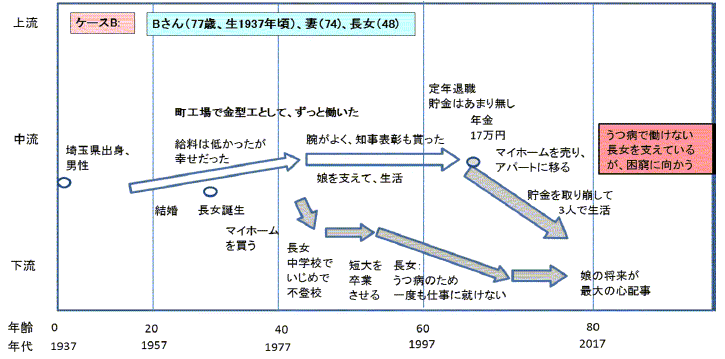
���̃P�[�X�ł́A���������v�w�̐������x���ɑ��āA���l������̒������������Ă��Ȃ����Ƃ��傫�ȉe����^���Ă���B�����ŁA�v�w�̐������x���������u���b�N����ƁA�����̐������x���������u���b�N����ƂL�����B
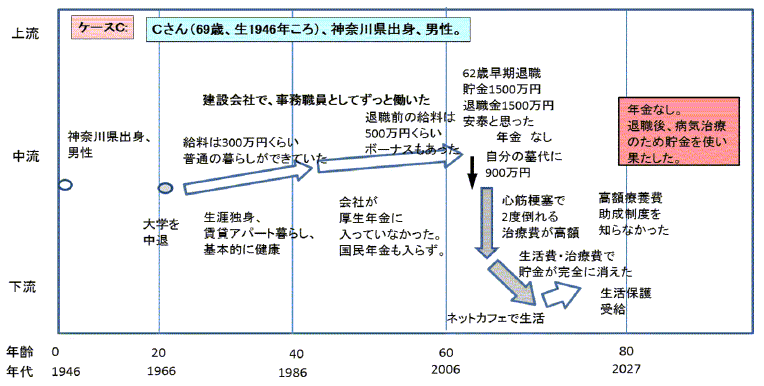
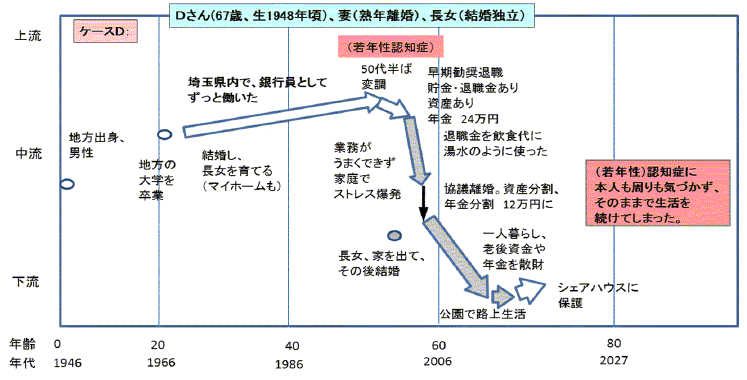
���̃P�[�X�ł́A�ސE��ɎU�����A�n�N�����ɂȂ��Ă���B�����ł́A�u��l�ł͐H�ׂĂ����Ă��A��l�������ł͐H�ׂĂ����Ȃ��v�ɂȂ�̂ŁA���F�����Ŏ����Ă���B
�����i����A2015. 9.27�j�F�@���̐}���́A���ɖ��āE�Y�قł����B���̂悤�Ȑ}�����A�����Ƃ��낢��ȃP�[�X�ō���Ƃ悢�B
-- �{���́A�����̐l�����̐}���d�ˍ��킹�āA���{�Љ�̑S�̓I�ȑ傫�ȓ�����������Ƃ悢�Ǝv���B�������A����ɂ́A�c�����ʓI�ɕ\������K�v������A�\���̒�`�������Ȃ��A��Βl(���邢�͑��Βl) �������Ȃ��A���~�E���Y�Ȃǂ̌l�f�[�^�������Ȃ��Ȃǂ́A�������B
--�@���邢�́A�萫�I�f�[�^�̂܂܂ł̊��p�@���l��������ǂ��̂�������Ȃ��B��G�c�ł��邱�Ƃ܂��������ł�(������)�w�W���l����Ƃ悢�̂�������Ȃ��B���̂悤�Ȏw�W�����A���l���̐l�����ɁA�C���^�r���[���āA�}�������Ă݂�Ƃ悢�̂�������Ȃ��B�܂��A�����̐}�̂悤�ɐ�����t�L���邱�Ƃ��厖�ł��낤�B
B.�@�����V�l�̌����F�@���̏Ɣw�i�@�@�@
��2�͂̌㔼�̕������u�����鉻�v�����m�[�g���ȉ��Ɏ���
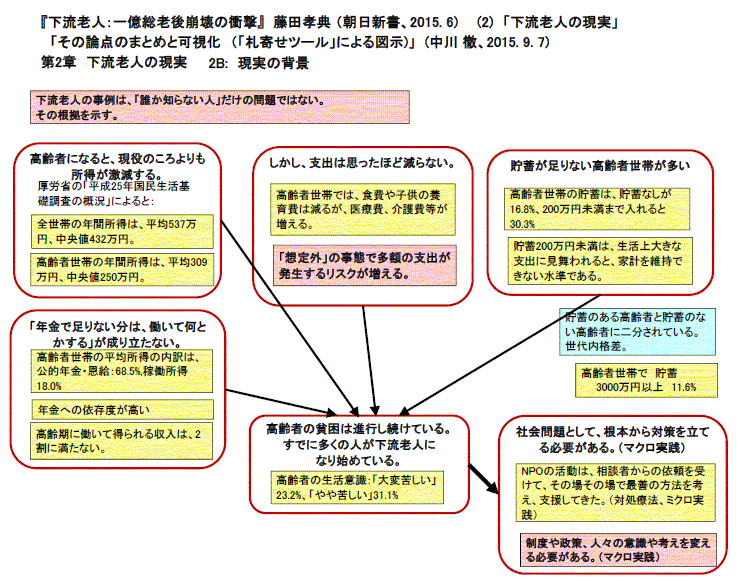
�����i����A2015. 9.27�j�F�@���҂��������̓��v���������p���Ȃ���A�����̔�r�I�Z���܂Ƃ߂������Ă���B���̈��̍��ڂ́A�N�ł����m���Ă���B�u���߂Ēm���ċ������v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�������A���̂悤�ȑS�̑���������Ɨ������A�ӎ����Ă������ƁA���K�v�ł���B����҂̐������A60�i���邢��65�j����75����܂��A�����Ă���ɁA���̌��20�N�Ԓ��x�𐄗����čl���邱�Ƃ��A�l�ɂƂ��Ă��A�Љ�ɂƂ��Ă��厖�Ȃ��ƂƎv����B
���҂��A�u�Љ���Ƃ��āA���{�����𗧂Ă�K�v�������v�ƌ����Ă���̂́A�厖�Ȃ��Ƃł���B
 �w�����V�l�x�@�@�u��R�́@�N�����Ȃ蓾�鉺���V�l�|�������̃p�^�[���v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015.10.10)
�w�����V�l�x�@�@�u��R�́@�N�����Ȃ蓾�鉺���V�l�|�������̃p�^�[���v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015.10.10)
��3�́@�N�����Ȃ蓾�鉺���V�l�|�u���ʁv����u�����v�ւ̓T�^�p�^�[�� �i�ڎ��j
�@�@�@�@�@�u���ʁv����u�����v�֊ׂ邢�����̃p�^�[��
�@�@�y����ҁz
�p�^�[���T�F�@�a�C�⎖�̂ɂ�鍂�z�Ȉ�Ô�̎x�����F�@�@
�l���ɂ�����u������v�̒�����
�p�^�[���Q�F�@����҉��{�݂ɓ����ł��Ȃ��F�@�@�����܂����V��i���A�����Ȃ���܂Ƃ��ȉ������Ȃ�
�p�^�[���R�F�@�q�ǂ������[�L���O�v�A(�N��200���~�ȉ�)�����������Őe�Ɋ�肩����:�@�@�q�ǂ����u�u���b�N��Ɓv�ɁA�u�B�̂Ȃ��S���v�Ɖ���������
�p�^�[���S�F�@��������n�N�����F�@
�n�N�����̖ӓ_�A�@�d����ł����Ȃ�Εv�͍Ȃɂɂ����Ă͂����Ȃ�
�p�^�[���T�F�@�F�m�ǂł�����ɗ����Ƒ������Ȃ�:�@
�F�m�ǁ{��l��炵�{�����Ǝҁ@==> �����V�l
�R�����P�F�@�J�l�̐�ڂ��������u�̃X�C�b�`����!?
�@�@�y�߂������ҁz�@
�u�ꉭ���V�����v�̎���A�@�@�@���炦��N�������鋰��A�@�@�@�N��400���~�ȉ��͉������̃��X�N�������A�@
�i�u�ꉭ�������v�̎��オ����Ă���)�A�@�@�@����Ȋi���̍s������A�@�@�̂ƍ���400���͉��l���S�R�Ⴄ�A�@
4���̐��т͘V��̎������قƂ�ǂȂ�!? �@�@�K�͉����ɒ�������A�@�@�K�͐��K��3���̂P�������炦�Ȃ��A�@
�Ƌ��V�l�\���R�𑝂₷�������̑����@
�R�����Q�F�@�e���c�����s���Y�ɎE�����!? (�Ɩ��)�A�@�@����������Ă�������ʁu�s�ǎ��Y�v
���̑�R�͂́A�O���́u����ҁv�ƌ㔼�́u�߂������ҁv�Ƃ���\������Ă��܂��B�u�����鉻�v�����v���Z�X�́A���܂łƓ��l�ł��̂ŁA�ȒP�ɐ������A�d�グ���}�̊ȗ��ł��摜�Ōf�ڂ��܂��B
A.�@�������̓T�^�p�^�|���@(�����) �@�@
(1) �e�L�X�g�̗v�_�̔������ƁA���̃��x�����B
(2)�@���x���̎D�A�S�̍\���̔c��
(3)�@�D�ɂ��u�����鉻�v�����}���d�グ��B(�ڍה�)�@
(4)�@�D�ɂ��u�����鉻�v�����}���ȗ������Ďd�グ��B (�ȗ���)�@
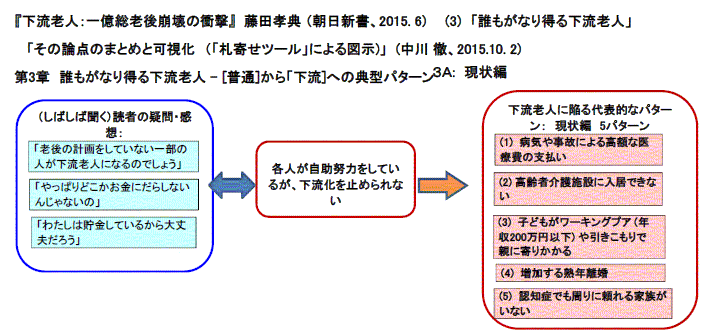
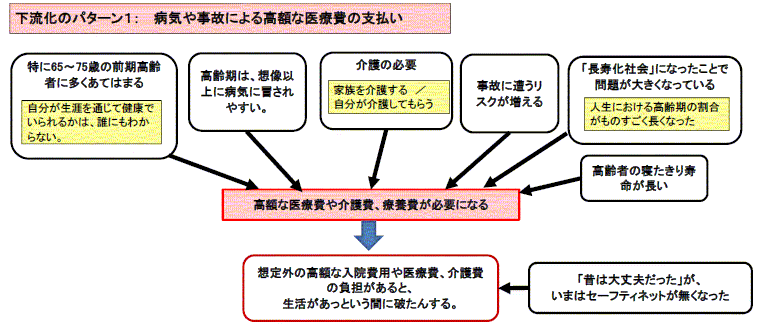
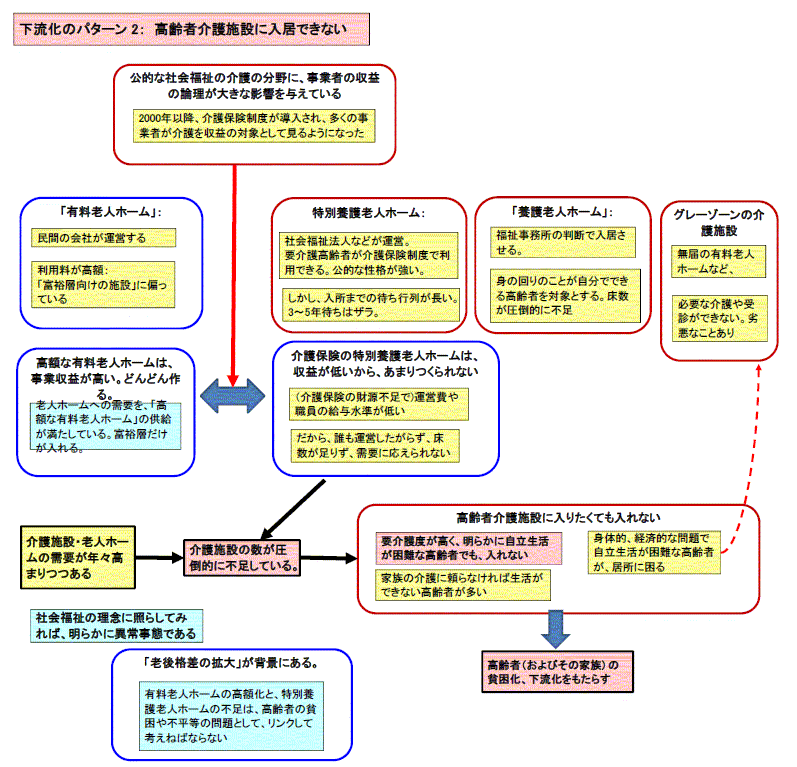
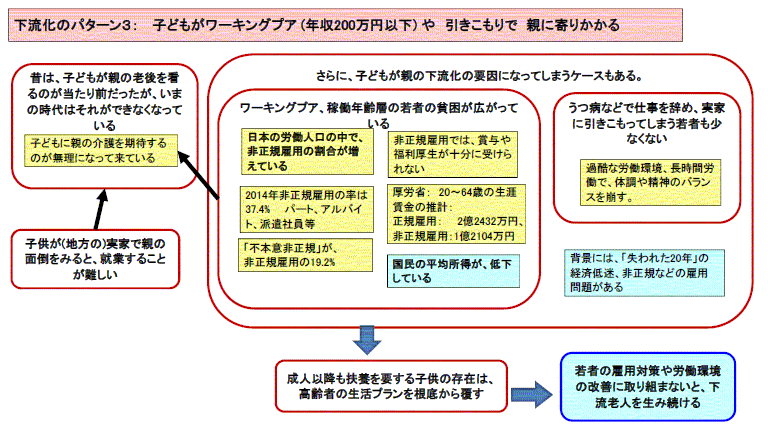
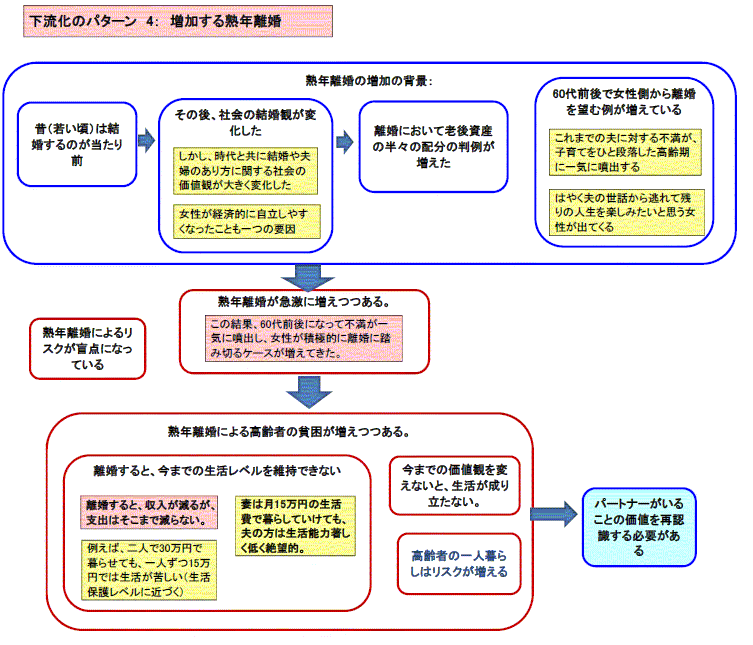
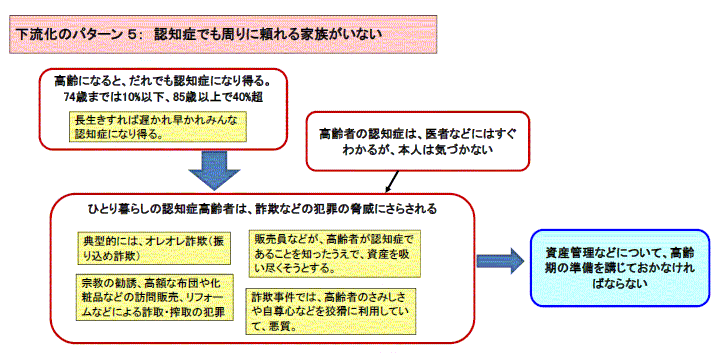
B.�@�������̓T�^�p�^�|���@(������) �@�@
(1) �e�L�X�g�̗v�_�̔������ƁA���̃��x�����B
(2)�@���x���̎D�A�S�̍\���̔c��
(3)�@�D�ɂ��u�����鉻�v�����}���d�グ��B(�ڍה�)�@
(4)�@�D�ɂ��u�����鉻�v�����}���ȗ������Ďd�グ��B (�ȗ���)
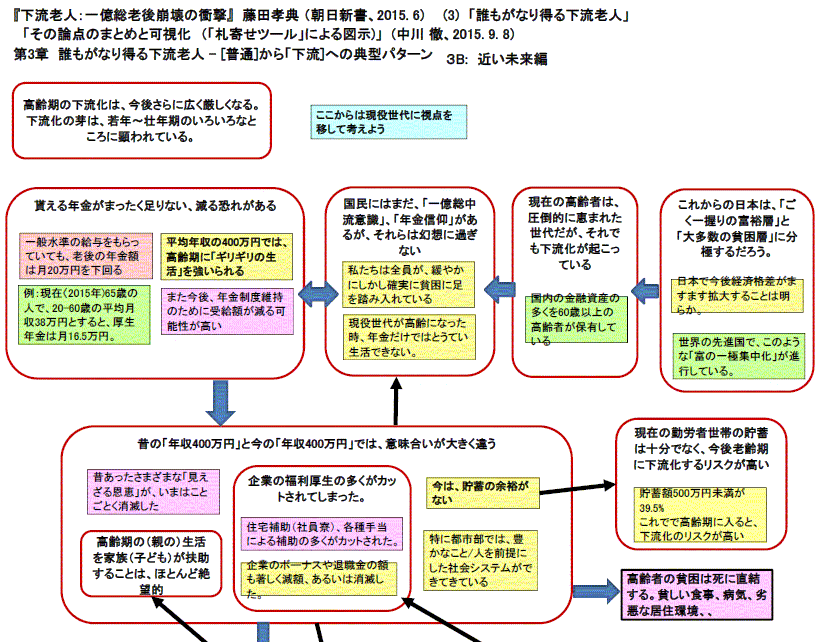
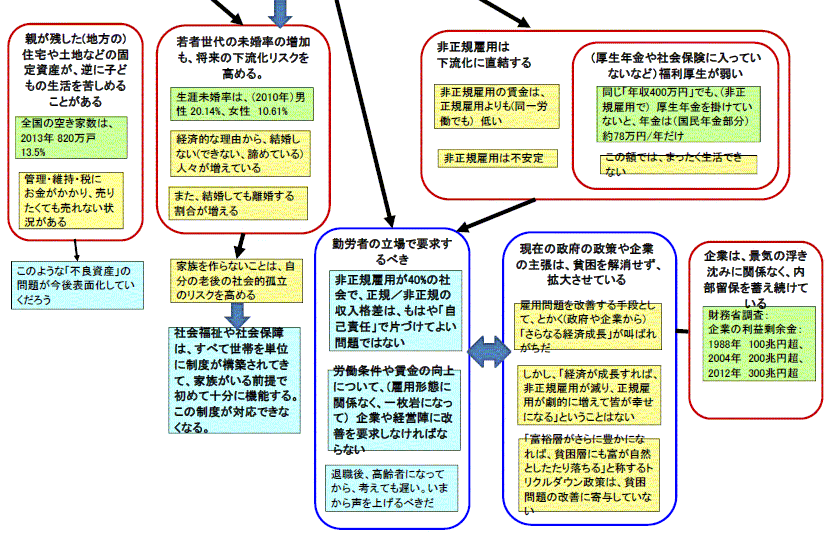
�����i���� �O�A2015.10.10�j�F�@
��3�͂ɓ����āA����(���c�F�T����)�́A���܂܂ŕ��ʂɐ������Ă����l�������A�����Ɋׂ�T�^�I�ȃp�^�[�����Љ�Ă��܂��B���N�Ȃ��A����ɂȂ��ĔF�m�ǂ��o�Ă���A�Ȃǁu�����͑��v�v�Ǝv���Ă��Ă��A���v�̕ۏ͂���܂���B�Ⴂ����̃��[�L���O�v�A�A�n�N�����̑����A���{�݂̕s���A�ȂǁA�{���ɂ��̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B
���̋`��̓A�p�[�g�Ō��C�ɂЂƂ��炵�����Ă��܂������A13�N�قǑO�ɁA�X���̏����Ȓi���T���č��ܓ��@���Ă���A�a�@�ŔF�m�ǂǂ��A�I��E���グ����̖ϑz���o�āA�Ȃ͂��̉��ɑ�ςł����B��1�N�ԉ��{�݂ɓ��邱�Ƃ��ł����A�A�p�[�g�ł̉��͍ȂɂƂ��Ēn���̐����ł����B�V�������ʗ{��V�l�{�݂��ł��āA�����ł����͎̂��Ƀ��b�L�[�ŁA�`��͔�r�I���₩��2�N�Ԃ��߂����āA���E���܂����B������̑�ς��A���T�[�r�X�̂��肪�����A�{�݂̏[���̕K�v�Ȃǂ��A������������ł��B
�����āA���x�́A���������v�w�����b���|����Ƃ���������������ė���̂��낤�Ǝv���Ă��܂��B���܂�(���N�ł���) ���̎���ɏZ��ł�����̂��낤���Ǝv�����A��̓I�ȏ����͉����ł��Ă��܂���B
����҉��{�݂̕s���ɂ��āA���҂́A�u���z�ȗL���V�l�z�[�����ǂ�ǂ����邱�ƂƁA���ی��K�p�̓��ʗ{��V�l�z�[�������܂�����Ȃ����ƂƂ́A(�o�c�̘_���Ƃ���)�@�A�����Ă���v�ƋL���Ă��܂��B���{�̐��� (����ѐ��{�̖���) �����̏������点�Ă��܂��B�܂��A����ґw�̕n�x�̓�ɉ���������������Ă���̂��Ƃ����܂��B���̌����͎��ɂƂ��Ă͐V�������̂ŁA����̖������̎肪������������Ă���Ă���Ǝv���܂��B
�{�͂̌㔼�ŁA�u���݂̌����E��N����ɂ͉������̊댯�������Ƒ傫���v�Ə����Ă��܂��̂́A�m��Ȃ��������Ƃł͂���܂��A��͂�V���b�L���O�Ȃ��Ƃł��B�u�̂̔N��400���~�ƁA���܂̔N��400���~�Ƃ́A�Ӗ��������Ⴄ�v�ƒ��҂������Ă��܂��̂͑厖�Ȃ��ƂƎv���܂��B��Ƃ̕����������ǂ�ǂ�J�b�g����Ă��܂��Ă���A�K�ٗp�ɂ�������A��ۏ�A�s���肪�傫�Ȗ��ł��B�����Ċj�Ƒ����ɂ��Ƒ��x���̎�̉��A�����̑����ƔӍ���������傫�����Ă������낤���Ƃ��悭�킩��܂��B���{�Љ�̖��́A����҂̕n���������łȂ��A����w�A��N�w�A�q�ǂ��������ꂼ��̕n�����ɘA�����āA�傫�ȁA�̂��҂��Ȃ�Ȃ����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���̖{��ǂ�ʼn��߂Ċ����Ă��܂��B
���́u�����鉻�v�̍�Ƃ��悤�₭�{���̔����܂ŗ��܂����B������̖{���A�������l����ׂ����Ƃ̏œ_�ɔ����Ă��Ă��܂��B�_�_�E�ϓ_���t�s���Ă��Ă��܂��̂ŁA�K�ȁu�����鉻�v�ɓw�͂��Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�ǂ������ӌ������������B
 �w�����V�l�x�@�@�u��S�́@�u�w�͘_�v�u���ȐӔC�_�v�����Ȃ����E���� --- �ӎ��Ɨ����̖��v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015.11.25)
�w�����V�l�x�@�@�u��S�́@�u�w�͘_�v�u���ȐӔC�_�v�����Ȃ����E���� --- �ӎ��Ɨ����̖��v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015.11.25)
��4�́@�u�w�͘_�v�u���ȐӔC�_�v�����Ȃ����E�����@�@ �i�ڎ��j
1. ���u����鉺���V�l
2. �w�͂ł��Ȃ��o�����Ȃ��́A���ʂׂ��Ȃ̂��H
3. �C�M���X�A���|�́u�n���Ҏ��e���v�@
4. �����V�l���~�ς��邱�Ƃ͐ŋ��̃��_�H
5. �S�̑����c���ł��Ȃ��Ɖ����V�l�͍��ʂ���Č��E���ɂ����
6. �Ђ�����Ǝ���ł��������V�l����
7. �����Ȃ���Ώ����Ȃ��Ƃ������x�v
8. ��ΓI�n���Ƒ��ΓI�n���̈Ⴂ
9. �����ی�o�b�V���O�Ɍ���u�Â��v�������Ȃ��Љ�
10. ���ȐӔC�_�̖����Ɗ낤��
11. �u�^�Ɂv�~���ׂ��l�ԂȂLj�l�����Ȃ�
�{�͂Œ��҂́A�u�����V�l�̖�肪(���܂ŏq�ׂ��悤��) �[���ɂȂ��ė��Ă���̂ɁA�ǂ����ĉ��̑���u�����Ă��Ȃ��̂��낤�H�v�Ɩ���N�����Ă��܂��B�����āA���̔w�i�ɁA�����������̖������^�����o������A���ꂪ�����V�l�����ɉ䖝�������Ă���A�����s���́u�����ė��Ȃ���Ώ����Ȃ��v�Ƃ����X�^���X�������������Ă���ƁA�w�E���Ă��܂��B���҂��s���Ă���NPO�̐����ی�Ҏx�������ɑ����A�i��܂��̈ӌ������邪) �����̔ے�I�A���Έӌ������Ă���Ƃ����A�����̐��Ɉ��Ή����Ę_���Ă��܂��B�������肵���c�_�ł����A�W�҂���������A�c�_���t�s���Ă��܂��B
�{�͂́u�����鉻�v��Ƃ́A���܂ł͈̏ȏ�ɓ�q���܂����B�����Ŏ��{�������@�́A�ȉ��̂悤�ł��B
(a) �����̂悤�ɁA�{����ǂ�Ŕ���������B�������̏ڂ����́A���܂܂ł̔{���x�B
(b) �������̊e�����D(���x��)�ɂ���B�ے�I�ӌ��A�����V�l�����҂̍l���E�U�����A�s���̗���A���҂̉����A�_���Ƃ����{�I�ȍl�����A���̑��u�n�̕��v�Ȃǂ��F�������ĕ��ނ����B�_���W�������悤��(�Ǐ�)�z�u����B
(c) �S�̍\�������s�����藈���肵�Ă���̂ŁA�ꕔ�̑O���g�ݑւ����A���_���I�ɁA������₷���A�S�̂��ĕҐ�����B
(d)
�g���g���ĎD�̃O���[�v�����s���A�_���I�ȊW(����-���ʁA���f�Ȃ�)�A�܂����Ɖ�����̊W�Ȃ����A���Ŗ�������B[���̒i�K�ŁA�S�̂̏ڍׁu�����鉻�v�ł��ł����B
�ie) �ڍL�q�̎D(���x��)���폜���āA�ȗ������A�S�̘̂_������蕪����₷������B�ȗ��ŕ�����₷���u�����鉻�v�v��ł����������B
(f)�@�{�y�[�W�ɁA���������u�����鉻�v�����}���AHTML(�摜�A�v��)�Ł@�Ŏ����B
�ĕҐ����āu�����鉻�v�����\���́A�ȉ��̂悤�ł��B
��4�́@�@�u�w�͘_�v�u���ȐӔC�_�v�����Ȃ����E���� --- �ӎ��Ɨ����̖��
[0] �͂��߂ɁF�@���̏ƕ����̊T�v
[1] �n���������ɂ���
[2] �n���̗����F�@�u��ΓI�n���v�Ɓu���ΓI�n���v
[3] �n���͎��ȐӔC���H --- �n�����N���邱�Ƃ́A���R��`�Љ�̏h���ł���
[4] �Љ��(�����ی�)����̂́u�Â��v���ƍl���镗�� --- ���@�ɕۏ��ꂽ�����ł���
[5] �����ی�͐ŋ��̃��_�g�����H --- �ŋ��̖{���̈Ӌ`
[6] �����ی�̐����́H --- ���@���ۏ��Ă���u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v
[7] ���{�̎Љ�����x --- ����̂ɂ悭�m���Ă��Ȃ��A�g���Ă��Ȃ�
[8] ���{�̕����s���̃X�^���X�̖�� --- �u�{�l������Ȃ���A�����Ȃ��A�����Ȃ��v
[9]�@�u�����V�l�����q�ǂ�����v���H --- �ʎ���̋c�_�ɂ������̒D�������̕��Q
[10] ��������ׂ������̍l���� --- �̈���ׂ鑍���I�Ȑ���Ƃ��̒��̊e�̈�̉�����
�u�����鉻�v�����}(�v���)���A�ȉ���HTML(�摜)�łŌf�ڂ��܂��B
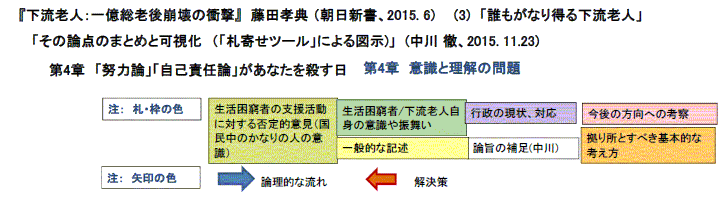
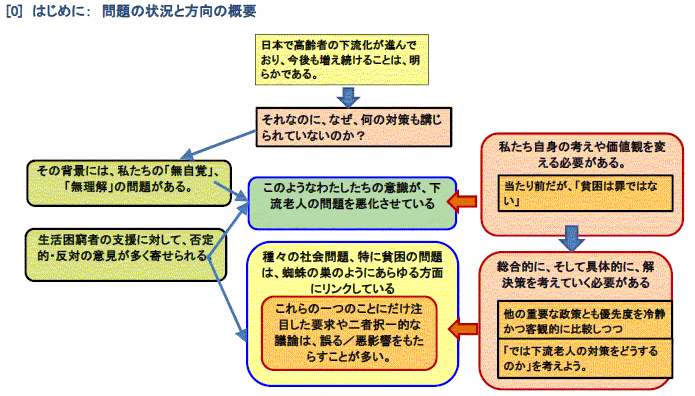
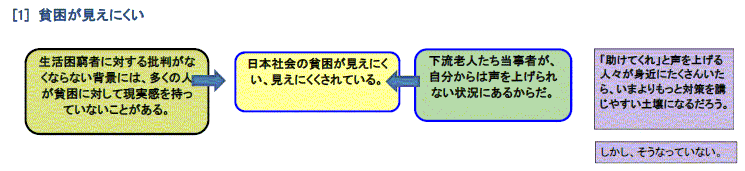
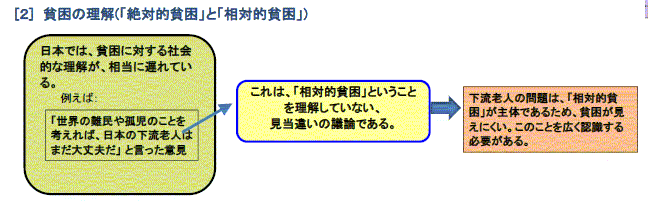
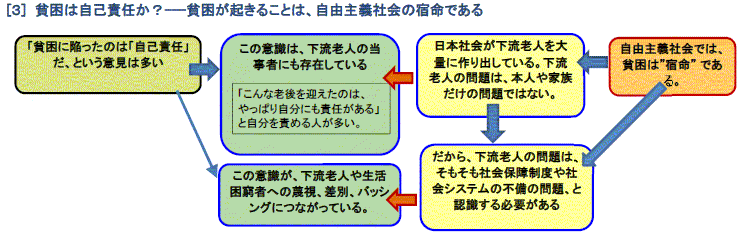
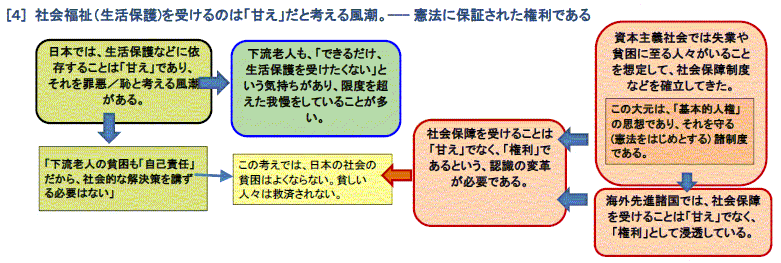
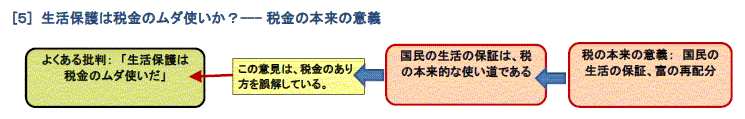
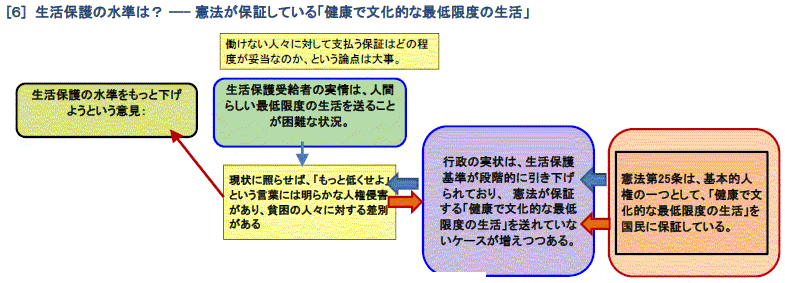
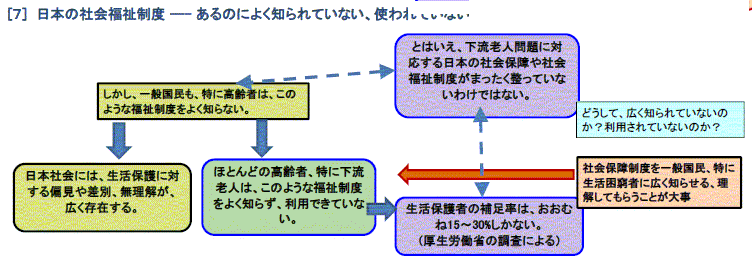
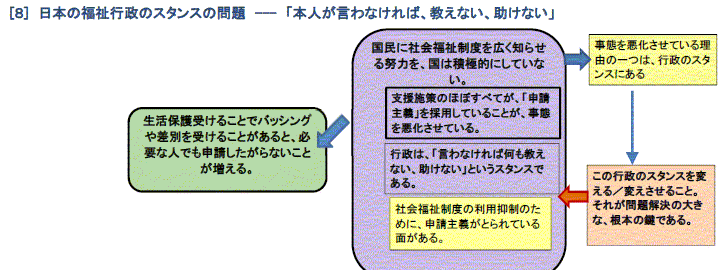
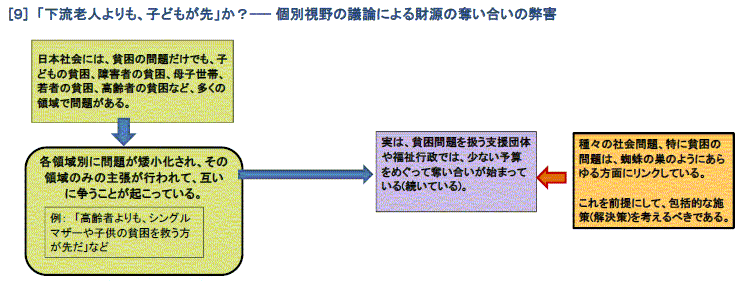
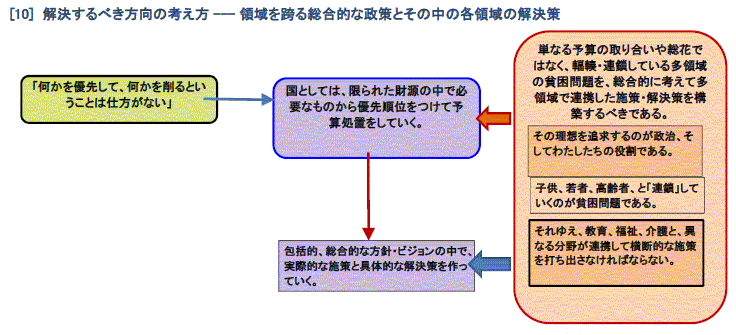
 �@�܂Ƃ߂Ɗ��z�i���� �O�A2015.11.26�j�F�@
�@�܂Ƃ߂Ɗ��z�i���� �O�A2015.11.26�j�F�@
������ǂ��̑�4�͂ł����A�u�D�v���g�����u�����鉻�v�������A���҂������Ă��邱�Ƃ����߂Ė��m�ɗ������邱�Ƃ��ł��܂����B�܂Ƃ߂Ɗ��z�͈ȉ��̂悤�ł��B
(1) ���҂�NPO��ʂ��Ď��H���Ă��銈���ɁA��ʂ̐l�X���炢�낢��Ȉӌ��A���ɔᔻ�I�Ȉӌ������Ă����B���҂͂����Ɉ��������āA�����V�l�i����ѐ��������҈��)���~�ς��ׂ����Ƃ��q�ׂĂ���B���̉����́A���J�ł��A�������肵���l�����ƐM�O�Ɋ�Â��Ă���B
(2)�@�����Ƃ���{�I�Ȃ��Ƃ́A�u�����������������A���������L���Ȑ��U�𑗂�v�Ƃ����Љ�I�K���i����)������A���̂��߂ɁA���N�E����E�ƒ�E�E�ƂȂǂ����邱�Ƃɓw�͂��A����E�E�ς��Ă��Ă���̂��A���������ׂĂ̓��X�̐����ł���A���U�ł���B�������A���ꂪ���낢��ȗv���ňÓ]���A�g�̓I�E���_�I�E�ƒ�I�E�Љ�I�E�o�ϓI�Ȃǂ̖ʂŔj�]���A(���Ɍo�ϓI��) ���������������ł��Ȃ��Ȃ�l���o�Ă���B���̂悤�Ȑl�ɑ��āA�u���̐l���w�͂��Ȃ��������炾�v�u���̐l�̎��ȐӔC���v�u�����Ă��炨���Ƃ���̂͊Â����v�ƍl����̂́A���������{�Љ�ł͍L���L�����Ă���B���̈ӎ����A�����V�l�Ȃǐ��������҂�̎����邱�ƂɂȂ�A���̐l�������Љ�̋��ɉ������A�Ǘ��������Ă��܂��B
(3)�@���̂悤�ȏ��A�u�����Ҍl�l�̊ϓ_�łȂ��A�Љ�S�̂���̊ϓ_�Ō������ׂ����v�Ƃ����̂��A���̒����̍ŏd�_�ł���B���{��`�̐��E�A���R�Љ�E�����Љ�ł́A�n����������̂͏h���ł����B�x�߂�҂��ł��A(���ΓI��)�n����҂��ł���B�������A��荪�{�̐l�ނ̋K�͂Ƃ��āA�u��{�I�l���v�d����ׂ��ł���B���{�����@�ł͍����Ɂu���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v��ۏ��Ă���B������������邽�߂ɁA(�x�߂�҂���n�������̂ɕx���Ĕz�����邽�߂�)�Ő�������A�i�~�ς̋�̓I�Ȃ������K�肷��)�Љ�����x�������Ă���B������A�����V�l�Ȃǐ��������҂́A�u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v���c�߂邾����(�����ی�Ȃǂ�)��������u�����v������̂��B�Љ�ɁA�n���҂��~�ς��邱�Ƃ�ϋɓI�ɋ��߂Ă������Ƃ��ł���̂��A�Ƃ����B�����S�̂ɂ��̂悤�Ȉӎ����v���ł��邱�Ƃ��厖�Ȃ��Ƃł���B
(4) ���{�̎Љ�����x�́A����ɓn���č���Ă���̂�����ǂ��A�����ɏ\���ɒm���Ă����A���p����Ă��Ȃ��B���������҂̐��x�ߑ����́A�����J���Ȃ̒����ł�15�`30%�����Ȃ��Ƃ����B�L���g���Ă��Ȃ��傫�ȗ��R�́A�s���̏��ɓI�ȃX�^���X�ɂ���Ƃ����B�������x�̂قƂ�ǂ��ׂĂ��A�u�\����`�v�ɂȂ��Ă���A�u�{�l�������Ă��Ȃ���A�����Ȃ��A�����Ȃ��v�Ƃ����X�^���X�ɂȂ��Ă��邩�炾�Ǝw�E���Ă���B���̃X�^���X�́A�u�����\�Z��}���������v�Ƃ��������\���Ă���B
(5)�@�����̍����͌����Ă���B�����āA�����V�l����̖�肾���łȂ��A����w�̌ٗp�̕s����A�A�E��ƔK�ٗp�̑���A�V���O���}�U�[�̍����A�q�ǂ������̕n���ȂǑ����̖�肪�����ɐ����Ă���B�����̊e�̈悲�Ƃɗv��������A�\�Z�̒D���������N���Ă���B�u�����V�l������A�q�ǂ��̕n���̋~�ς��悾�v�Ȃǂ̈ӌ�������B�����́A�u�ʗ̈�̎���ł̗v���Ƌc�_�͊Ԉ���Ă���v�ƒ��҂͂����B���l�Ȗ��͑��݂Ɋ֘A���Ă���̂�����A���̑S�̂��l����������(����)���K�v�Ȃ̂��A���̂��߂̑S�̓I�ȍl�@�ƃV�~�����[�V���������Ă����ׂ����A�ƒ��҂͎咣���Ă���B--- ���̂Ƃ��肾�ƁA�킽���͎v���B
(6) ���́u�����鉻�v�̍�Ƃ���4�͂܂ŗ����B7�����߂ɁA�u���C���V�����Đg���E���Ύ����v�̘V�l�̐S�����ȒP�Ȑ}�ɂ����Ƃ������ׂ�A�����Ɩ��̗������[�܂������A�u�����鉻�v�̕��@�����p�ł��Ă����B���c�F�T����̖{���́A���ɂ������肵���\���Ɠ��e���������{���ƁA�ĔF�����Ă����B���Ƃ����������グ�āA����҂̕n���̖���������Ɓu�����鉻�v���āA�����̐l�����̍l�@�Ƌc�_�̂����ɗ��Ă�悤�ɂ������Ǝv���B
 �w�����V�l�x�@�@�u��5�́@���x��J�Ɩ����މ����V�l --- ���x�Ɛ���̖��_�v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015.12.17)
�w�����V�l�x�@�@�u��5�́@���x��J�Ɩ����މ����V�l --- ���x�Ɛ���̖��_�v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015.12.17)
��5�́@���x��J�Ɩ����މ����V�l -- �l�Ɉˑ����鐭�{ �i�ڎ��j
1. �����ʂ̕s���@�|�@�Ƒ����x��O��Ƃ����N�����x�̕���
2. ���~�E���Y�ʂ̕s���@�|�@�����鋋�^�Əオ�镨��
3. ��Â̕s���@�|�@"��Ó"�������Ǘ���
4. ���ی��̕s���@�|�@�����V�l���~���Ȃ��������x�A�P�A�}�l�W���[
5. �Z��̕s���@�|�@�Z�܂������������
6. �W���E�Ȃ���\�z�̕s���@�|�@�����̎肪�͂��Ȃ�
7. �����ی�̕s���@�|�@���ɂ���đ��삳���n���̒�`
8. �J���E�A�J�x���̕s���@-�@���ʒ��O�܂œ����Ȃ��ƕ�点�Ȃ�!?
8�̎��_����̐��x�ᔻ �|�@�܂Ƃ�
(�R����3)�@�����V�l�̐��������z���u�n���r�W�l�X�v
���̑�5�͂Œ��҂́A�Љ���Ɋ֘A���錻�݂̐��x�Ɛ���̖��_���������Ă��܂��B���̊ϓ_����L�̂悤�ɂW�����Ă��ꂼ����c�_���Ă��܂��B�e���ڂ̋c�_�͔�r�I�Z���ł�����A�u�����鉻�v�̍�Ƃ͑O�͂قǓ������܂���ł������A�\��ȏ�̓������������Ă��܂��܂����B���낢��ȋc�_���ǂꂾ�����k���ċL�q���āA���̘_�|��(���͂��ȏ��)���m�ɂł��邩����S�������Ƃł��B�ȉ��ɂ܂��u�����鉻�v�����}���f�ڂ��āA�{�y�[�W�����Ɏ��̂܂Ƃ߂Ɗ��z���L���܂��B
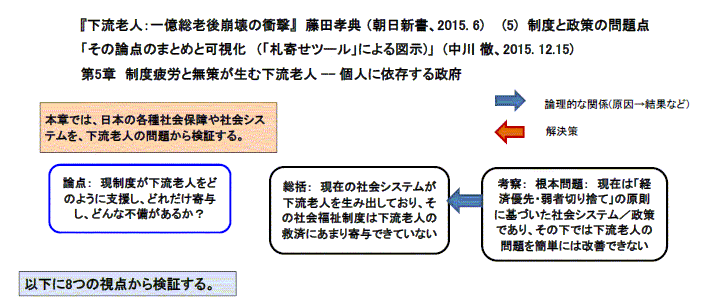
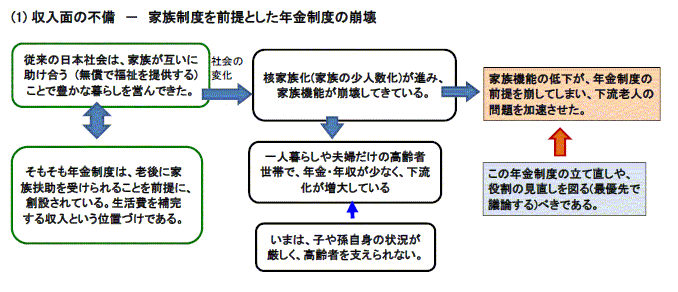
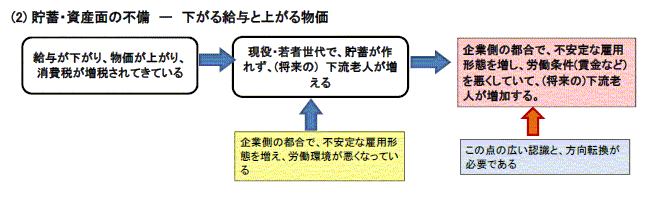
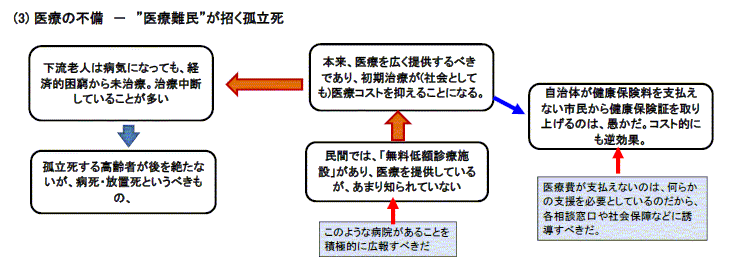
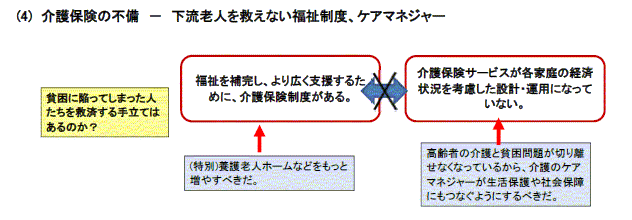
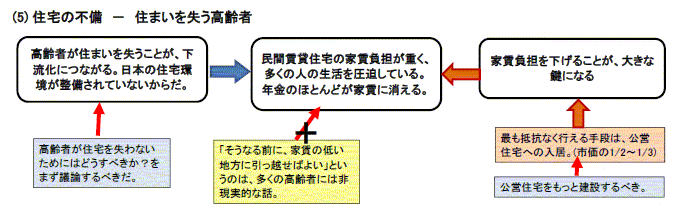
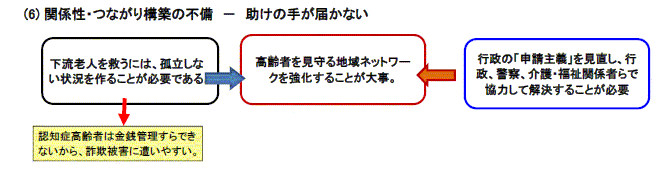
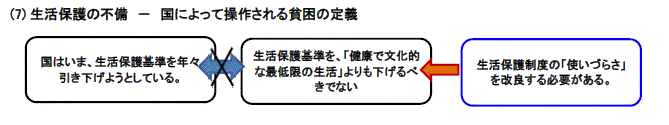
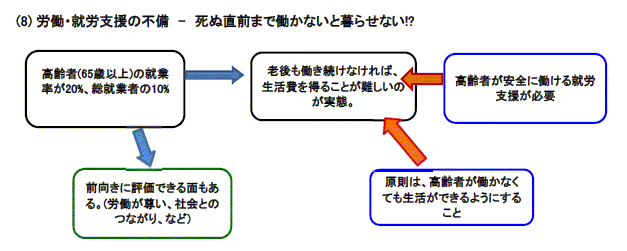
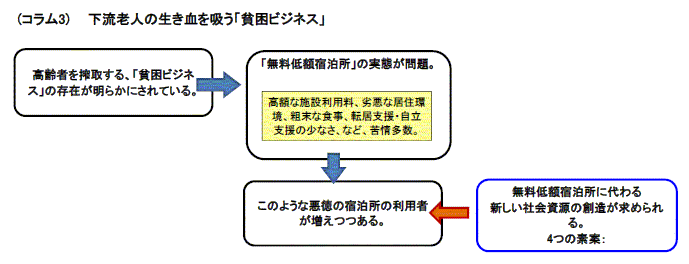
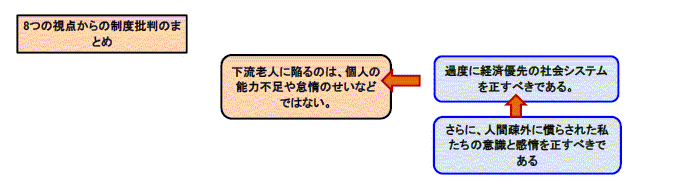
 �@�܂Ƃ߂Ɗ��z�i���� �O�A2015.12.17�j�F�@
�@�܂Ƃ߂Ɗ��z�i���� �O�A2015.12.17�j�F�@
8�̌������ڂ̂����A���҂��ŏ��ɂ������Ă���̂�����҂̎����̖ʁA���Ȃ킿�N���̂��Ƃł��B�{���ł��܂܂ł��т��ыc�_���Ă���悤�ɁA�K�v�Ȏx�o�z�ɔ�ׂāA�N���͋͂��ł��B���~��O��ɂ��Ă�����ȏ�ɁA�q�⑷�Ȃǂ̉Ƒ��Ƌ��ɁA���邢�͉Ƒ��Ɏx�����Đ������Ă��邱�Ƃ�z�肵�����x�v�ɂȂ��Ă��邩�炾�Ƃ����܂��B
�������ɁA�Ƒ��̏͐����ƕς��܂����B����70�N�ԂŁA�_���Ȃǂ���s��ւ̐l���ړ�������A�j�Ƒ������i�݁A�����������܂����̎q�ǂ���������ꂼ��̐E�Ƃ����߂ēƗ��E�������čs���܂����B��Ɗ����E�o�ϊ������L�扻����ɔ����āA�����������A�q�ǂ�������e�ʂ������A(�S����C�O�ɂ܂�)���U���ďZ�ޏ��N�����Ă��܂��B����҂�������Ƒ������̉Ƒ��E�e�ʂ��痣��ČǗ����Ă��邱�Ƃ͂������A����Ґ��т�(��l���邢�͕v�w������)�Ǘ����ĕ�炵�Ă����̂͂�����܂��̂��Ƃł��B���҂������悤�ɁA�Ƒ����݂��Ɏx���������ƁA�Ƒ��̐����Ŏ��R�ɍs����u�����̕����v���A�Ƒ������o�[�����Ȃ��Ȃ�ɂ�Č������Ă��܂��B
����ɖ��Ȃ̂́A���܁A���𐢑�A�����Ă���Ɏ�Ґ��オ�A�o�ϓI�Ɍ������ɂ����A����҂��x���鐶����E�o�Ϗ�̗]�͂������Ȃ����Ƃł��B�ٗp���s����ɂȂ�A(�]�܂Ȃ�)�K�ٗp�����債�āA���ϋ��^���������Ă��钆�ŁA�����E��Ґ��㎩�g�����������̘V��̂��߂̔������܂������s�\���ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���̂悤�ȏ́A��Ƒ���(��������`��)�_�����A����ɏ���Ă��鐭�{�̐����݂����Ă��܂��B�|�\���̓_�̍L���F���ƕ����]�����K�v���ƒ��҂͌����܂��B���������ł��B
��Â̍��ŁA�u������z�f�Î{���v�Ƃ����̂����邱�Ƃ��A���͏��߂Ēm��܂����B���݁A�S���Ŗ�600�̕a�@�Ȃǂ����̃T�[�r�X����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B-- �����J���Ȃ̃z�[���y�[�W�ł��̃L�[���[�h�Ō������Ă����̂悤�Ȑ��x�A�T�[�r�X�̐����͂قƂ�ǂ���܂���B�s���̏��ɓI�X�^���X��������܂��B
�Z��̍��ŁA�u����҂��Z�������Ȃ��悤�ɂ���ɂ͂ǂ����ׂ����A���܂��������悤�v�Ƃ����w�E�́A�厖�Ȃ��ƂƎv���܂��B�ƒ����S���y���Ȃ�A���������҂������Ɗy�ɂȂ�A��N���ł�����Ă�����悤�ɂȂ�A�Ƃ����̂͂��̂Ƃ���ł��傤�B�S���ŋƂ����̂����������Ă���i�V���ɂP��)�A����Ȃ̂ɍ��z�̃��[����g��ŐV�z�}���V���������Ă��A���Ԃ̒��݉ƒ��������đ����̐l�������ɍ������Ă���B�����Z��ł����t�����s�ł͂��܃^���[�}���V������(�����~�n��)�ˌ��Z��̐V�z���b�V�����ڗ����܂��B����Ȃ̂ɁA����҂����S���ďZ�߂�悤�ȁA(�����łȂ�)�W���Z���{���͂Ȃ��Ȃ��ł��܂���B�{�͂̍Ō�ɒ��҂������Ă���u������z�h�����v�̕n���r�W�l�X�̎��Ԃ��A�{���ɂЂǂ����Ƃł��B�\�\�����̂��Ƃ́A�l�����Ɛ����ς���A�����ȉ�������͂��̂��ƂƎv���܂��B
�J�����E�J�������̌����d�v�Ȃ��Ƃł��B��{�I�Ȍ����͘J����@�Ŏ���Ă���͂��Ȃ̂��A�J���Ҕh���@������ɔ�����������Ă��܂����B��Ƃ̉c����`�A�l���g���̂Ăɂ���l�����A���{�̑����̍�����n���ɂ��Ă��܂��Ă���B--�\�ŋ߂̃j���[�X�ŋ����̂́A�O�H�Y�Ƃ̗Y�ł���}�N�h�i���h�̃p�[�g�̎�����������߂�(�n��ʂ�)�Œ�����������Ƃ̂��ƁA�܂��n�Ӕ����Q�c�@�c���̌o�c����a�����V���Ј������g�����ЂQ�����Ŏ��E�ɒǂ���������ƁB�����Ɨ��ł�����u���b�N��Ƃ��������Ă��邱�Ƃ������Č�����ł��B
�����҂��{�͂̍ŏ��ƍŌ�ɏ����Ă���܂Ƃ߂́A���ɖ��m�ł��B���҂͌��Ǔ������Ƃ������Ă��܂��B
�E�@�����V�l�ݏo���Ă���̂́A���݂̎Љ�V�X�e���ł���A�l�̔\�͕s����ӑĂ̂����ł͂Ȃ��B
�E�@���݂́u�ߓx�Ɍo�ϗD��A��Ґ�̂āv�̎Љ�V�X�e���Ɛ���𐳂��Ȃ�����A�����V�l�����{�̕n�������������Ȃ��B
�E�@����ɁA�l�ԑa�O(�l������)�ɂȂ炳�ꂽ�A�킽�������̈ӎ��Ɗ���𐳂��K�v�������B
���̌�A��U�́u�����łł��鎩�Ȗh�q��v(�����ی�̒m�����܂�)�A��V�́u�ꉭ���V������h�����߂Ɂv(����̌l�I�A�C�f�A)���L�q���Ă��܂��B�����́u�����鉻�v��i�߂�ƁA���̑S�̑���������A�����̂��߂̋c�_�E�l�@���ł���悤�ɂȂ�ł��傤�B
 �w�����V�l�x�@�@�u��U�́@�����łł��鎩�Ȗh�q��|��Ɨ\�h�v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015.12.30)
�w�����V�l�x�@�@�u��U�́@�����łł��鎩�Ȗh�q��|��Ɨ\�h�v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2015.12.30)
��6�́@�����łł��鎩�Ȗh�q��@�|�ǂ�����Έ��炩�ȘV����}������̂� �i�ڎ��j
�y�m���̖��(����)�z�@-�@�����ی�𐳂����m���Ă����F�@�@
�ی��̎x���z�Ɠ��e�A�@�ی�̎v��
�y�ӎ��̖��(����)�z�@-�@���������Љ�ۏᐧ�x�Ƃ͉���
�y��Â̖��(����)�z�@-�@���̂�������a�C����ɔ�����
�y�ӎ��̖��(����)�z�@-�@�������܂��v���C�h���̂Ă�
�y�����̖��(�\�h��)�z�@-�@�����璙�߂�ׂ���
�y�S�̖��(�\�h��)�z�@-�@�n��Љ�ϋɓI�ɎQ������
�y���ꏊ�̖��(�\�h��)�z�@-�@�n���NPO�����ɂ��R�~�b�g���Ă�������
�y�����Ƃ����Ƃ��̖��(�\�h��)�z�@-�@�u�́v��g�ɂ��Ă���
�K���ȉ����V�l�̋��ʓ_
���̑�6�͂Œ��҂͂܂��A�����V�l�̏Ɋׂ��Ă��܂����ꍇ�ɁA�m���Ă����Ƃ悢���ƁA����Ƃ悢�������A�������Ď����Ă��܂��B�����ی�ɂ��Đ������m�邱�Ƃ��܂����ł���A�����ی�̐\���̂������A�̗v���A�x������鐶���ی��̓��e�Ɗz�Ȃǂ�������Ă��܂��B�������邢�͒�z�ň�Â����邱�ƁA�ӎ�(�C����)�̎������ɂ��Ă��q�ׂĂ��܂��B
�{�͂̓��F�͌㔼�́A�u�\�h�ҁv�i�����V�l�ɂȂ�Ȃ����߂̗\�h�̕��@)�ɂ���܂��B�܂��u���~���Ă����Ȃ����v�Ƃ����͓̂�����O�ł����A���������厖�Ȃ̂́A�V��̐l�ԊW���Ƃ����܂��B�u�l�ɋ~���Ă��炢�₷���l�v�Ƃ����łȂ��l������Ƃ����A�O�҂̐l�́A���߂ɐl�ɑ��k�ł��A�v���X�v�l�̐l���Ƃ����܂��B�܂��A�����납��l�ԊW��L���Ɏ����A���������́u��v�������Ă����̂��悢�Ƃ����܂��B�܂��A�{�͂̌��_�͈�ۓI�ł��F�u�n������҂ɂ��A�K���Ȑl�͑�R����B�l�Ƃ̂Ȃ���A�l�ԊW��L���Ɏ����Ă���l�����B�v�@- �{�͔͂�r�I�P�������ł�����A�ȏ�̊ȒP�ȋL�q�ŁA�u�܂Ƃ߂Ə���(����)�v�͏ȗ��������܂��B
�S�̐}
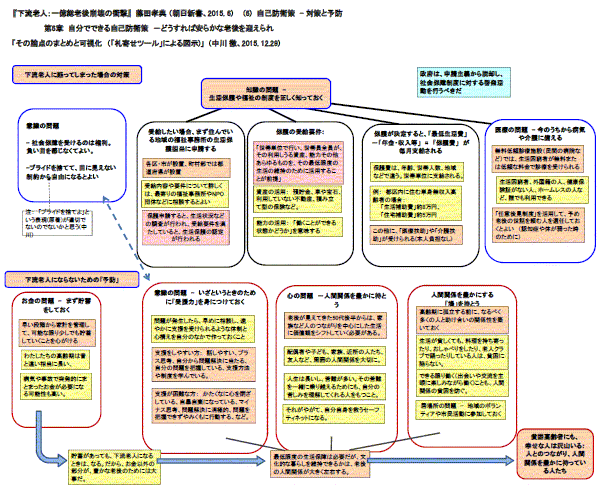
�@����
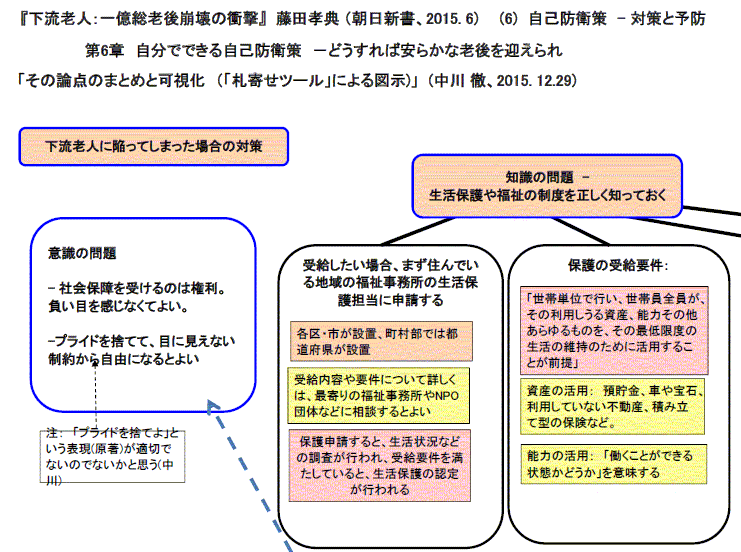
�E��
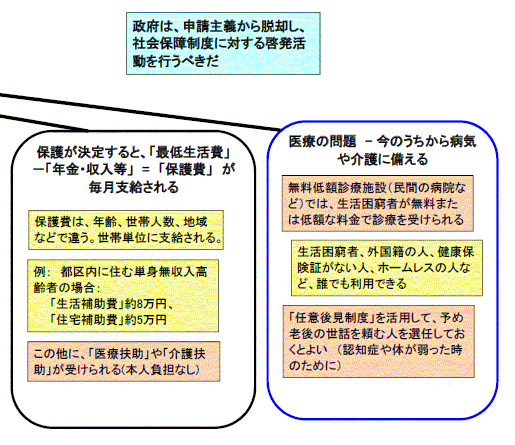
����
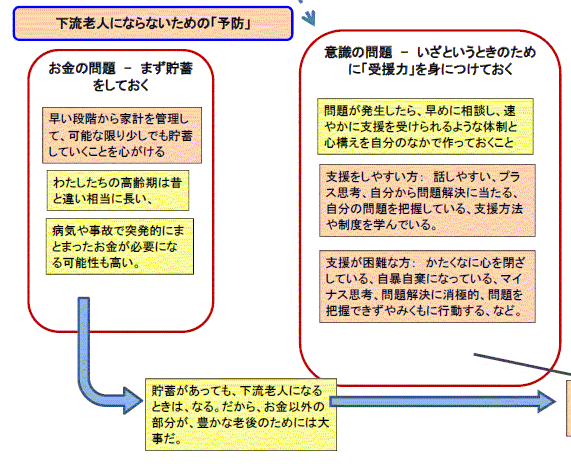
�E��
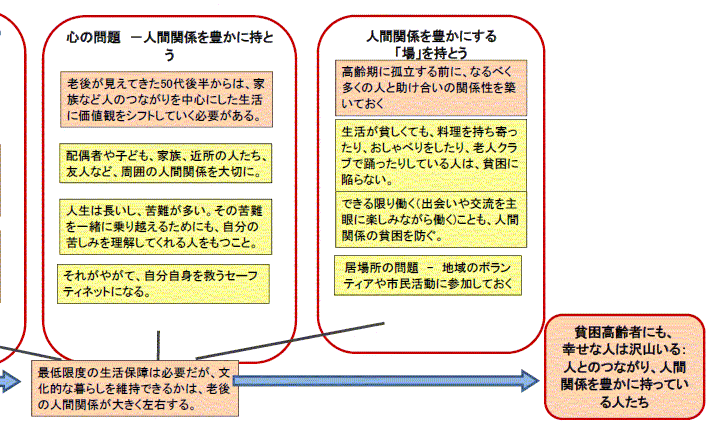
 �w�����V�l�x�@�@�u��V�́@����̌����ƒ� (��)�v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2016. 1. 4)
�w�����V�l�x�@�@�u��V�́@����̌����ƒ� (��)�v�@�@�i�u�����鉻�v�m�[�g�A���� �O�A2016. 1. 4)
��7�́@�ꉭ���V������h�����߂� �i�ڎ��j
�����V�l�͍���Љ���ݏo������
���{�̕n�����~�߂����́H
���x����₷���A�₷��
�����ی��ی������Ă��܂��H
�����̈ꕔ���܂��Ȃ����̂Ƃ��Ă̐����ی�
�Z�܂��̕n�����Ȃ�������
�����̉����V�l���Ȃ����|��҂̕n���ɉ������
�����V�l�̖��Ɋ�]�͂���|�n���E�i���ƕs�����̐�����
�l�Ԃ���炷�Љ�V�X�e��������̂͂킽�������ł���
���̍ŏI�͂ɂ����Ē��҂́A�u�Ō�ɁA�킽���Ȃ�̉����V�l�ɑ�����܂Ƃ߂Ă��������B�E�E�E�킽�������̎Љ���ǂ̂悤�ɍ\�z�������Ă����悢�̂��A��⒧��I�A���s�I�ɏq�ׂ����B�v�Ə����Ă��܂��B
�����̂����Łu�����鉻�v�����݂܂����B�ŏI�͂ł̘_���� (���т��Ȃ�) ���m�ɂ��邱�Ƃ�S�����܂����̂ŁA�������̖��x�����������Ȃ��Ă��܂��B
�D�̐}�ł́A�u���̔F���E��{�F�� → �����E�l�@ → ��(�ƕ⑫)�v�Ƃ������҂̍l�@�̉ߒ���������E�ւ̗����ŕ\�����A�܂��A���g�̒i�K�I�ȏ��ԂƓ����\���̘_���I�����i���������āA���̒̃x�[�X�ɂȂ������̔F���ƍl�@�̑Ώۍ���)���ォ�牺�ւ̗���Ƃ����A���I�ɕ\�����܂����B�i���̂悤�ȕ\���@�́A���Ȃ�����グ�����̂ł��B)
�D�}�̏ڍה�(3��)���������ŁA�����ƑS�̂���]�ł���K�v������ƍl���v����i1��)�����̂ɋ�J���܂����B�Ō�ɁA�����v��ł����Ȃ���u�܂Ƃ߁v�͉����܂����B
����HTML�y�[�W�ɂ́A�܂��A�v��łɂ��āA�k���S�̐}�������A���̌�ɁA������ǂ߂�T�C�Y�ɂ����g��摜���f�ڂ��܂��B
�܂��A�Ō�ɁA����̂܂Ƃ�(�u�����鉻�v�̐}�͉���������)�A������������L�q���܂����B
�S�̐}(�v���)
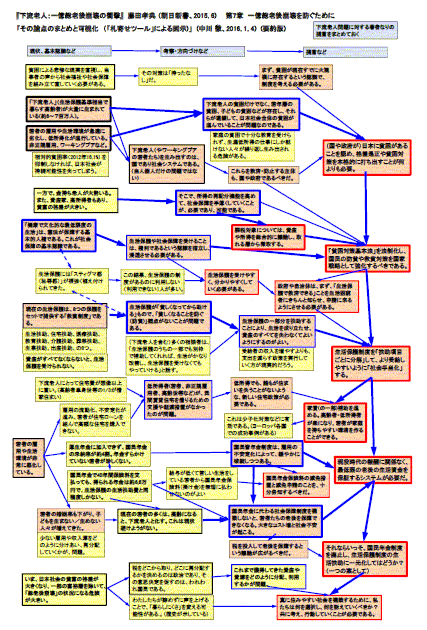
�g��}�@(�v���)�@(��E���E��)
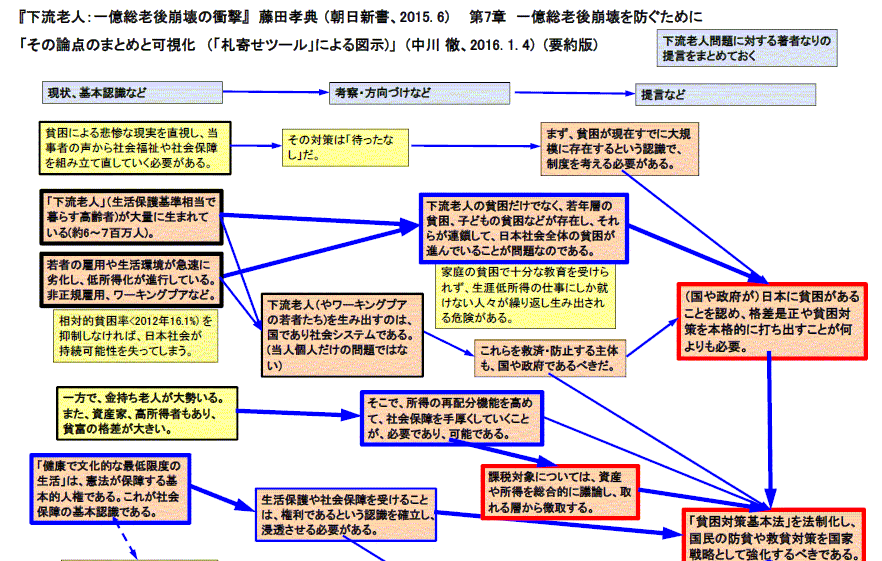
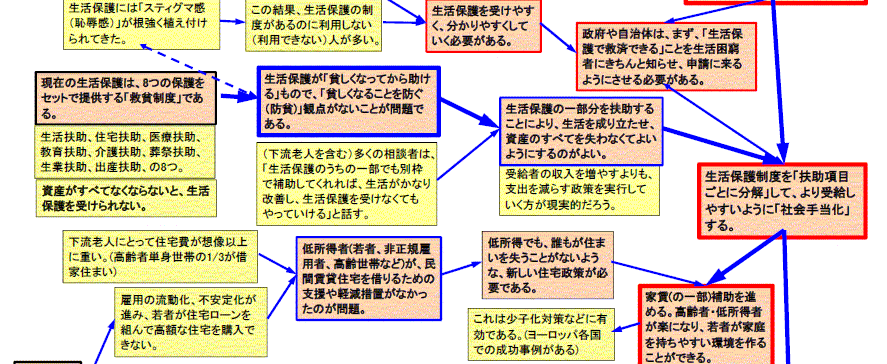
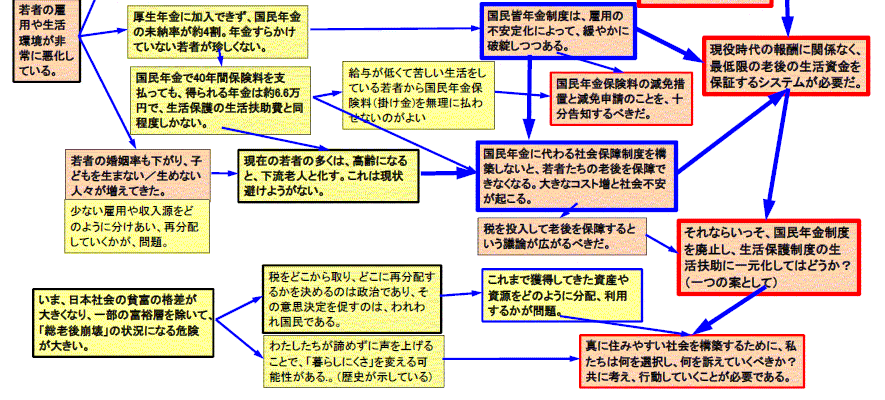
 �@�܂Ƃ߁@(�u�����鉻�v�����}�͉�����)�@�i���� �O�A2016. 1. 5�j�F�@
�@�܂Ƃ߁@(�u�����鉻�v�����}�͉�����)�@�i���� �O�A2016. 1. 5�j�F�@
����(���c�F�T��)���{�͂ɋL�q���Ă����(�Ƃ��̘_��)���܂Ƃ߂ĕ��͉������ƁA�ȉ��̂悤�ł��B(�u�v��Łv�̐}�����Ȃ���A����ɊȒP�ɂ��Ă��܂��B)
(1)�@���܁A�u�����V�l�v�i�����ی������ŕ�炷�����)����ʂɐ��܂�Ă���A��U�`�V�S���l�Ɛ��肳���B�܂��A��҂̌ٗp��������}���ɗ�(�K�ٗp��[�L���O�v�A�Ȃ�)�A�Ꮚ�������i�s���Ă���B�����V�l�̕n�������łȂ��A��N�w�̕n���A�q�ǂ��̕n���Ȃǂ��L�����݂��A����炪�A�����āA���{�Љ�S�̂̕n�����i��ł��邱�Ƃ��A���Ȃ̂ł���B�����̉����V�l��[�L���O�v�A�̎�҂����ݏo���̂́A���ł���A�Љ�V�X�e���ł���i���l�l�����̖��ł͂Ȃ�)�B
==> ����{���A���{�ɕn�����L����A�i�s�����邱�Ƃ�F�߁A�i��������n�����{�i�I�ɑł��o�����Ƃ��A�������K�v�ł���B
(2)�@�u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v�́A���@���ۏ����{�I�l��(�̈��)�ł���B���ꂪ�Љ�ۏ��i�߂邽�߂̊�{�F���ł���B���̈Ӗ��ŁA�����ی���͂��߂Ƃ���Љ�ۏ���邱�Ƃ́A�����ł���Ƃ����F�����m�����A�Z��������K�v������B�����V�l����������Ɠ����ɁA�x�T�ȘV�l����������A���Y�ƁE�������҂������āA�n�x�̊i�����傫���̂�����ł���B����́A(�Ő��ɂ��)�����̍ĕ��z�@�\�����߂āA�Љ�ۏ����������Ă������Ƃ��A�K�v�ł���A�܂��A�\�ł��邱�Ƃ��Ӗ�����B�ېł̂������ɂ��ẮA���Y�⏊���𑍍��I�ɋc�_���āA���߂�ׂ����Ƃł���B
==> ��L�̊�{���O�̂��ƂɁA�u�n�����{�@�v��@�������A�����̕n������\�h���A�n������~�ς��邽�߂̕�����A���Ƃ̏d�v�헪�Ƃ��Č��Ă�ׂ��ł���B
(3)�@���łɂ��鐶���ی�̐��x���邱�Ƃɑ��āA������(�����ł͂Ȃ�)�u�p�����������Ƃ��v�Ƃ����ӎ����A�������Ă���B��L(2)�̗��O�Ɋ�Â��A���x����₷���A�₷�����邱�Ƃ��A�܂��ŏ��ɕK�v�ł���B
==> ���{�⎩���̂͂܂��A(�����V�l�Ɍ��炸)���������҂ɑ��āA�u�����ی�ŋ~�ςł���v���Ƃ�������ƒm�点�A�ی�\���ɗ���悤�ɗU�����邱�Ƃ��A����ׂ��ł���B
(4) ���݂̐����ی�́A(�������āA���Y�Ȃǂ����ׂĎg���ʂ������̂��Ɂr8��̕}���i�����A�Z��A��ÁA����A���A���ՁA���ƁA�o�Y)���Z�b�g�Œ���u�~�n���x�v�ł���B�u�n�����Ȃ��Ă���~����v���̂ŁA�u�n�����Ȃ邱�Ƃ�h��(�h�n)�v�ϓ_���Ȃ����Ƃ����ł���B���ہA�������k�ɗ��鑽���̐l�́A�u�����ی�̂����̈ꕔ�ł��⏕���Ă����A���������Ȃ���P���A�����ی���Ȃ��Ă�����Ă�����v�Ƙb���B
==> �����ی쐧�x���u�}�����ڂ��Ƃɕ����v�����A�Љ�蓖�̌`�ŁA�����Ǝ��₷������B����ɂ���āA(������)�����ی�̈ꕔ����}�����邱�Ƃɂ��A�����𐬂藧�����A���Y�̂��ׂĂ�����Ȃ��Ă��悢�悤�ɂ���B
(5) �����V�l�ɂ͏Z���̕��S���z���ȏ�ɏd���B�܂��A��҂������Z��[����g��ō��z�ȏZ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B�Ƃ��낪���܂܂ŁA(�Z��w���̎x�����x�͂��邪)�Ꮚ���҂����Ԓ��ݏZ�����邽�߂̎x�����x���Ȃ��B�Z�������߁A�Ꮚ���ł��N�����Z�܂�������Ȃ��ł��ނ悤�ɂ���ׂ��ł���B
==> �ƒ���(�ꕔ)�⏕��i�߂�i����͏�L(4)�̕}���̈��ł���)�B����҂�Ꮚ���҂��y�ɂȂ�A��҂��ƒ�������₷��������邱�Ƃ��ł���B����́A���q����ȂǂɗL���ł���A���[���b�p�e���Ő������Ⴊ����B
(6) ��҂̌ٗp������̈����̂��߁A�����N���ɉ����ł����A�����N���̖��[�҂���4������B�܂��A����40�N�ԍ����N�����|�������Ă��A����������N���͖�6.6���~�ŁA�����ی�̐����}����Ɠ����x�����Ȃ��B�����̂��Ƃ́A�����N�����x���A�j�]�����邱�Ƃ������Ă���B���̏ł́A���^���Ⴍ�ċꂵ�����������Ă����҂ɁA�����N���̊|�������ɕ��킹�Ȃ��̂��ǂ�(�������ێ���������厖)�B
==> �����N���ی����̌��Ƒ[�u�����邱�Ƃ����m���A(���̖͂��[�ł͂Ȃ�) ���Ɛ\����E�߂�ׂ����B
(7)�@��L(1)(6)�̏ŁA���݂̎�҂̑����́A����ɂȂ�Ɖ����V�l�Ɖ��� (����́A����ł͔����悤���Ȃ�)�B���܂̍����N�����x�͔j�����邩��A����ɑ���Љ�ۏᐧ�x���\�z���āA��҂����̘V���ۏႷ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����łȂ��ƁA�����ɑ傫�ȃR�X�g���������A�Љ�s�����N����B
==> �����N�����x�ɑ���V�������x���\�z���A�V��̐������Œ���i���Ȃ킿�A���@����߂�u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v)�ۏ���悤�ɂ��Ȃ�Ȃ�Ȃ��B����́A��������̕�V�ɊW�Ȃ��A(������������l���܂߂�)���ׂĂ̐l�ɕۏႷ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B
(8) ��L(7)���������邽�߂ɂ́A�ŋ��𓊓����āA���ׂĂ̐l�̍Œ���x�̐�����ۏႷ�邱�Ƃ��l����������Ȃ��B
==> ����͌��ǁA�����ی쐧�x�̐����}���ɑ�������B����Ȃ炢�����A�����N�����x��p�~���A�i��L�i4)�ŏq�ׂ��悤�ȐV����)�@�����ی쐧�x�̐����}���Ɉꌳ�������Ƃ悢�̂łȂ����B
(9) ��L��(1)(6)(7)�Ō����Ă���̂́A�u���A���{�Љ�̕n�x�̊i�����傫���Ȃ�A�n�����g�債�āA�ꕔ�̕x�T�w�������āA�u�ꉭ���V�����v�̏ɂȂ�댯���傫���v���Ƃł���B��L�ɒ�Ă��Ă��邷�ׂĂ̑�ẮA�ŋ��Řd���č�����x�o���邱�Ƃ��܈ӂ��Ă���B�ŋ��ɂ���āA�x�̍ĕ��z��}��A�x��ł��鏊�E�l���璥�����āA�n�������E�l�ɕ��z����B���̂悤�Ȓ����E���z�E���p�̂��������߂�̂͐����ł���A���̈ӎv����𑣂��̂͂킽�����������ł���B
==> �^�ɏZ�݂₷���Љ���\�z���邽�߂ɁA����I�����A����i���Ă����ׂ����H�������Ƃ��ɍl���A�s�����Ă������Ƃ��K�v�ł���B
 �@�����@�i���� �O�A2016. 1. �U�j
�@�����@�i���� �O�A2016. 1. �U�j
��N7���ȗ��A���c�F�T����́w�����V�l�x��������ǂ݁A�u�����鉻�v�̐}�������Ă��āA���܁A�ŏI�͂̐}�����グ�A�܂Ƃ߂̕��͉������܂����B���c����̂��̖{�́A���H�Ɋ�Â��A���ɂ�����ƍl�@���ď�����Ă����ƁA���߂Ďv���܂��B�ŏI�͂̒��A�����͂�����܂��B�^�����܂��B
�܂��A�Е� ���T����́u�D�c�[���v���g�킹�Ă������������ƂŁA�{���̘_������ɖ��m�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B���͂����ŗ������悤�Ƃ��A�܂Ƃ߂ĕ\�����悤�Ƃ�������A�͂邩�ɖ��m�ɂł��܂����B�����g�����m�ɗ����ł��܂������A���̗�����ǎ҂̊F����ɕ�����₷���������Ƃ��ł����ƍl���Ă��܂��B�c�_�̓y��Ƃ��Ďg���Ă���������K���ł��B
�u�D���Ȃ���l����v�Ƃ����V���[�Y���n�߂��Ӑ}�́A���܂܂Ŏ������������y��}���ė��܂����u�n���I�Ȗ������̕��@(TRIZ → USIT → CrePS)�v�̓K�p������A�Z�p���삩��A�Љ��l�Ԃ��܂������ƍL������Ɋg���鎎�݂��������Ƃł����B���{�Љ�̕n�����Ƃ����傫�����t�s�������Ɏ��g�݁A���s���Ă��܂����B�u�D�c�[���v���g�����Ȃ��āA���G�Ȗ����u�����鉻�v�ł��Ă������Ƃ��傫�Ȑ��ʂł��B�����A����͂܂��A�����ɂ��������܂���B
���܁A�l���Ă��邱�����ȒP�ɗ��܂��ƁA���̂悤�ł��B
(a) �u�����V�l�v�̖��ɂ����āA�ŏ��ōŌ�̖��́A�������́u�ӎ��̖���v���Ǝv���܂��B�����V�l�i���邢�͐���������)�ɂȂ����̂́A�u�l���E�w�͂�����Ȃ��̂��v�A�u���ȐӔC���v�Ƃ����ӌ�(�ӎ��E����)�ł��B---- ��N12���Ɂu�ǎ҂̐��v�̃y�[�W�Ɍf�ڂ��܂������[���ł̓��_�����ǂ݂��������B
����͔��ɐ[���A���{�I�Ȗ����܂�ł��܂��B�u�����Љ�ɂ�����i�Œ����)�ۏ��v�A����ɂ́A�u�����ƕ����������v�A�u�����ƈ��v�Ȃǂ̖����W�ƌ��������邱�Ƃ��ł��܂��B�u���������̐��E�̒��ł̈��̗ϗ��v�̖��ł�����A�u��{�I�l���v�̖��ł�����܂��B
���̂悤�ȁu�����v�́ATRIZ�Ŋw�u�Ǘ��I�����v�A�u�Z�p�I�����v�A�u�����I�����v�̂ǂ�ł��Ȃ��B�����Ɛ[���A�l��Љ�̖�蒆�ɂ͂���Ӗ��łǂ��ɂł����邪�A�{���ɂ�(�l�ގЉ)�悭�����ł��Ă��Ȃ�(������悭�Ώ��ł��Ă��Ȃ�)�ʂ̌`���́u�����v�ł���悤�Ɏv���܂��B
�i��) (���{�Љ��)���ۂ̕n���̖����l����ƁA����1990�N�ȍ~�̐��{�̌o�ρE�Љ�A�o�ϊE�̗v�����āA��L�́u�����v�𒆐S�Ƃ������̂ł��������Ƃ��A�����ł��B���̒��ŁA���{�Љ�ɕn�����g�債�Ă������B���̕n���̊g���}�~���邱�Ƃ́A��{�I�l������邱�ƂƓ����ł��B���^�̌���A�J�������̉��P�A�x�̍ĕ��z�Ȃǂ��l����K�v������܂����A����͒����Ɍo�ς̖��A��Ɨ��v�̖��ȂǂɊ֘A���܂��B�o�ϊE�̐l�����́A(�{���̒Ȃǂ�)�u�o�ς�m��Ȃ���ʐl�̗��z�_�ɉ߂��Ȃ��v�Ƃ����ł��傤�B����Ȃ�A�u��{�I�l���i��l�Ԃ̍K��)��������ƍl�����A�o�ς̂�����v���o�ϐl����Ɋւ��l�����ɕ����������̂Ǝv���܂��B
(c) �u���{�Љ�̕n�����l����v�Ƃ����e�[�}�̎��|����Ƃ��āA���́A����҂̕n�����܂����グ�܂����B�{�����c�F�T���w�����V�l�x�́A���̑S�e��������ƂƂ炦���D�ꂽ�e�L�X�g�ł���܂����B���́A���ɁA���𐢑�E��Ґ���́i�J�����𒆐S�Ƃ���)�n���̖�����l���悤�Ǝv���܂��B�h�L�������^���[�ȋL�q�����łȂ��A�����A�w�i�A���x�A�l�@�E�Ȃǂ�������Ɖ�������e�L�X�g��T���Ă��܂��B�K�ȃe�L�X�g������܂�����A�����Ă��������B����ɂ��̌�ŁA�q�ǂ������̕n�����l�������ł��B������Ō�ɂ���̂́A�q�ǂ������̕n���͂��̐e�����̕n���f�������̂�����ł��B
(d)�@���{�Љ�̕n����}�~�E�������邽�߂ɂ́A�u���E���{�ɂ�鐭���ɕK�v�ł���v�Ƃ����{���̒͂��̂Ƃ���Ǝv���܂��B�����A���̐���̂��߂̍����ƂȂ�x�����̂́A��ƁE���Y�ƂƁi�����Ắu�������v�ȏ��)����ґw�ł��B���̈�ʂ́i���Ȃ킿�u�����v(�ȏ�)�ƈӎ����Ă���)����҂������A���̕x�i�̈ꕔ)��L���ɎЉ�ɊҌ�����������Ȃ����낤���ƁA�l���n�߂Ă��܂��B���L���Y�Ƃ��Ď����̎q�ǂ��⑷�ɑ���������͈̂ꕔ���A�ŋ��ɕ����č���n�������̂̈�ʓI�Ȏg�r�i�K�������������œK�Ǝv��Ȃ��g�r)�ɔz�������̂��ꕔ���ł悢�B���̑��̈ꕔ���ŁA�����̔��f�ƈӎv�ŎЉ�ɗL���ɊҌ������i�����Ă�������̘V����m�ۂ���)�ǂ����������Ȃ����낤���ƍl���n�߂Ă���̂ł��B����͎��������̂悤��(�����ȏ��)����ґw�ɑ����Ă���A�����̘V��̂��Ƃ�؎��ɍl���Ȃ�������Ȃ��ɂ��邩�炱���ł��邱�Ƃł��B
(e)�@�Ƃ������A��L(a)�`(d)�̂��ׂĂ̂��Ƃ́A �u�n���I�Ȗ������̕��@�v�̌����Ǝ��H�ɂȂ��邱�Ƃƍl���Ă��܂��B���̈Ӗ��ŁA���́wTRIZ�z�[���y�[�W�x�ň�������(���̃e�[�}�Ƃ��D������Ȃ���)�f�ڂ��Ă��������ł��B
�ŏI�X�V�� : 2025. 7.25 �A����F�@���� �O nakagawa@ogu.ac.jp
jSW-TN-G1-ThinkingPoverty-withVisualization �w���� �O�@����I�W�x�@G1
(2015. 9.17)�@�{�e�͂̃y�[�W (2015. 9.17 �`�@2016.1.28)