「自由」vs「愛」と「倫理」:
人類文化の主要矛盾とその解決の方向
中川 徹 (大阪学院大学 名誉教授 & クレプス研究所 代表)
ICCI2018 (International Conference on Creativity and Innovation)、 日本創造学会&近畿大学ICMI 共催、2018年 9月10−12日、大阪市 (英文発表予定)
掲載:2018. 8.14; 追加掲載: 2018.11.11
Press the button for going to the English page.
編集ノート (中川 徹、2018年 8月12日)
7月15日に私は新しい英文論文を仕上げて、9月に大阪で開催予定の日本創造学会主催の国際会議ICCI2018に提出しました。この3年間研究してきました「自由」 vs 「愛」の主要矛盾についての第3報(あるいは第3年度の主論文)と位置づけているものです。その主題は、昨年秋に書きました拡張論文
に対しての査読者コメント:「参考文献(特に倫理学)との対比・考察ができていない。提出仮説が新規かどうか分かっていない、また仮説検証ができていない」という批判に対応しようとしたものです。この半年ばかりかけて学んだ倫理学の諸理論との対比・検討結果を、考察の節に書きました。詳細は、概要と本文7.節を参照いただきたいのですが、私が提案している基本仮説の新規性・妥当性・有効性について、さらに確信を深めました。要点は以下のようです。
(1) 「倫理」の内的指令の真の根源は何か?−メタ倫理学は、「事実記述「である」から指令記述「べき」を論理的に導くことはできない」と結論づけました。直観主義は(社会から教えられた)「(常識的)道徳規則」を根源と考えますが、それを批判する(現代の)功利主義は、「善(=「快」)を最大にする」という評価基準を示すだけで、道徳規則の体系を示さず、便宜的に「常識的道徳規則」を中間原理として容認します。本研究は、先天的な「良心」を仮定しましたが、それは、「生き物としての数十億年の進化の結果」であり、「生きる(生き残る)こと、子孫を作り増やすこと、種を繁栄させること」の方向づけを持つと理解しました。
(2) 倫理の原理/規則の性格は?−従来、「義務」、「指令」、「法則・原理」、「規則」などと理解されていますが、本研究は「指導原理、方向づけ、方向提示」と理解しました。「指導原理」は多面的であり、根元は明確だが、先端部は発散的で、適用にあたっては矛盾を調整・解決していかねばなりません。
(3) 功利主義者シジウィックは、利己主義(=自己利益型功利主義)を(普遍的)功利主義から倫理の論理として排除できないと結論し、これを「(倫理的)実践理性の二元性」と呼びました。(それをどうにもできなかったのです。)本研究はもっと明確に、「自由」と「愛」の指導原理が実際の場で矛盾として現れているのだと捉えました。そして、その根底を考え、諸現象を考え、解決の方向性を提案してきたのです。
(4) 功利主義は、「われわれの倫理的行為における究極の目的」として「善」を定義し、それが「快」(広い意味での望ましい感情)であると結論づけました。それは、抽象的であり、また、「善」の方向への倫理的行為の諸案を考える方法を持ちません。本研究は、「自由」を伸長する、「愛」を拡張(普遍化)する、そしてその基礎となる「倫理」を深化させる、という方向性を示し、また、内在する矛盾を調整・解決する方向性と方法を提示しようとしています。
(5) 本研究は、「善」の概念を予め定義せずに進んだのですが、最後に、「「善」とは、人類文化の三つの主要指導原理が指し示す「全体としての方向」である」 との結論に到達しました。すなわち、「倫理」を深化する、「自由」を伸長する、「愛」を拡張することを、同時に行うことです。これら三つの指導原理の一部分だけでは「善」ではありません。一部分に固執すると、矛盾が増大・深刻化するからです(その事例は一杯あります)。
(6) また、「幸福」とは、結局、 「その人自身とその周りで、(上記の定義の)「善」が満たされている(守られている)状況」と言えます。任意の社会組織についての「幸福」も同様です。
(7) 三つの主要指導原理「自由・愛・倫理」とその関係を知り、本質的矛盾「「自由」 vs 「愛」」とその「倫理」による解決を深く理解し、世界に広め、世界で実践していくことが、人類文化にとって非常に大事なことと考えます。
本論文の構成は、下記の目次のようです。導入部(1.節)、基本仮説の内容(2.〜6.節)は前報(拡張論文(2D)
) と同様ですので和訳を省略します。概要、7.考察、8.結論、参考文献の部分を和訳掲載します。なお、文中の [ ] 内は、和訳に際しての補足です。英文ページは、とりあえず概要と7.節の目次だけ掲載し
、国際会議での発表後に本文を掲載する予定です。
編集ノート追記 (中川 徹、2018年11月 7日)
9月11日に国際会議 International Conference of Creativity and Innovation (ICCI 2018)で発表しました。大部分の参加者は技術・ビジネス・教育に関わる「創造性とイノベーション」に興味を持っておられますから、本研究のように社会問題に「創造的な問題解決の方法」を使って「人類文化の主要指導原理間の根本矛盾」を見出したという発表は非常に例外的なテーマでした。3会場並行の発表のため、私の講演を聞いて下さった方は非常に少なかったのですが、その方々からは高く評価していただいたのはうれしいことです。
ICCI2018から正式に掲載許可をいただきましたので、英文ページに論文
および 発表スライド
を掲載し、この和文ページには発表スライドの和訳版
を掲載します。きちんと説明するために、30分の発表に42枚のスライドを作っています。基本仮説のスライドなどでは、青太字の部分だけを読み上げるようにしました。また、重要なスライドは淡黄色のバックにして区別しています。2015年から始めたテーマの、現段階での総まとめの論文です。スライドを見ていただけば、論文そのものよりも全体の論旨が分かりやすいことと期待しております。ご感想などいただけますと幸いです。
論文 (部分訳)目次
1. はじめに ―― 和訳省略
2. 人類文化の第0原理:「倫理」 ―― 和訳省略
3. 人類文化の第1原理:「自由」 ―― 和訳省略
4. 人類文化の第2原理:「愛」 ―― 和訳省略
5.「自由」と「愛」の対立・矛盾 ―― 和訳省略
6. 「自由」と「愛」に対する「倫理」の役割 ―― 和訳省略7. 考察: 倫理学と哲学の従来の/標準的な諸理論と対比した、本研究の仮説の意味
7.1 「倫理」の指令の真の根源は何か?
7.2 倫理の原理/規則の性格
7.3 現代倫理学、特に功利主義、に関するコメント
7.4 シジウィックの「実践理性の二元性」に代わる「自由」vs「愛」の矛盾
7.5 ロールズの『正義論』についての考察
7.6 自由、平等、博愛
7.7 本研究における「善」と「幸福」の概念
| 論文部分和訳PDF |
|
|
|
論文 (部分和訳) PDF
(8頁、279 KB)
「自由」vs「愛」と「倫理」: 人類文化の主要矛盾とその解決の方向
‘Liberty vs Love’ and Ethics: Principal Contradiction of Human Culture and Solution Directions
中川 徹 (大阪学院大学 名誉教授)
Toru Nakagawa (Osaka Gakuin University, Professor Emeritus)
International Conference on Creativity and Innovation (ICCI2018)、
日本創造学会&近畿大学ICMI 共催、2018年 9月10−12日、大阪市 (英文発表予定)部分和訳 (概要、7. 考察、8. 結論) 『TRIZホームページ』 2018年 8月14日掲載
概要
筆者はいままで科学技術の分野において、TRIZ(発明問題解決の理論)を、さらに発展させて、「6箱方式」という新しいパラダイムに基づく「創造的問題解決の一般的方法論(CrePS)」の開発をしてきた。その応用分野を広げるために、TRIZ/CrePSを社会的問題、すなわち日本における下流老人の問題に適用した。社会保障が必要だという意見や政策は、いつも「貧しくなったのは自己責任だ」という反対論に遭遇する。TRIZ/CrePSの創造性思考を使って、筆者はこの問題を「自由」vs「愛」という基本的な矛盾として捉え、以下のような基本仮説を導いた。
「自由」(すなわち、自分で判断・行動し、生きること)が人類文化の第一の指導原理であり、「愛」(すなわち、子と家族を愛し、隣人を愛し、助け・守ること)が第二の指導原理である。「自由」を伸長させ、「愛」を拡張する(普遍化する)ことが重要であり、望ましい。しかしながら、本質的な矛盾が、「自由」の内部に、「愛」の内部に、そして「自由」と「愛」の間に存在する。このことをまとめて、「自由」vs「愛」が人類文化の主要矛盾である、と表現している。主要矛盾は、あらゆる所に存在し、発生している。個人の生活でも、社会問題でも、国際案件でも。人類文化はその歴史を通じて主要矛盾を軽減・解決することを試みてきたが、成功しなかった。
「倫理」が人類文化の第0指導原理であると認識される。「倫理」は「何が善で、何が悪か」をわれわれに示してくれるものであると考えられる。本研究では、善/悪を学び識別する先天的な(DNAに組み込まれた)能力(「良心」)を仮定し、「倫理」の内容は生後に社会から教えられる。「倫理」は「自由」と「愛」の両方を動機づけることができ、したがって、それらを調整して「自由」vs「愛」の矛盾を軽減できる。基本的人権の概念が、人間関係の面での「倫理」の中核である。
従来の/標準的な倫理学の理論をレビューした結果、先天的な「良心」の仮説が新規かつ妥当であることに、筆者は確信を深めた。「良心」は生き物の永年の進化の結果であり、生きるための動機を含んでいる。すなわち、生きる・生き残ること(「自由」)、子孫を残すこと(「愛」)、種を繁栄させること(「愛」、コミュニケーション、殺さない、など)。このように、先天的な「良心」は、常識的な道徳規則よりも深いレベルで、人生への動機づけの確固とした根源をなしていることが分かった。
三つの主要指導原理の全体的な方向づけ(すなわち、「自由」の伸長、「愛」の普遍化、「倫理」の深化の全体)が、「善」(への方向付け)であると理解される。われわれは、そのような全体的な「指導原理」(「義務」でなく、「法則・規則・原理」でなく、「指令」でない)に、「自由」と「愛」と「倫理」の適切なバランスをもって従っていくべきである。なぜなら、これら三者のどのような一部分をとりそれに固執する(主張する)なら、三者に本質的に内在する矛盾をより深刻化させるからである。
まとめると、科学技術分野での創造的な問題解決の方法論を貧困という社会問題に適用して成功し、人類文化の哲学的な根底に関し、独自の体系的な理解を創出した。「自由」、「愛」、「倫理」を十分に理解することが、人類文化の将来にとって決定的な重要性を持っている。
注: 前半部分は、前報 [5] とほぼ同様なので、和訳を省略。
1. はじめに
2. 人類文化の第0原理:「倫理」
3. 人類文化の第1原理:「自由」
4. 人類文化の第2原理:「愛」
5.「自由」と「愛」の対立・矛盾
6. 「自由」と「愛」に対する「倫理」の役割
7. 考察: 倫理学と哲学の従来の/標準的な諸理論と対比した、本研究の仮説の意味
上記の1-6節に記述した本研究の仮説は、科学技術の研究者である筆者が、倫理学および哲学についての常識的な理解だけから得たものである。[その後、最近] 倫理学と哲学の数件の参考文献 [6-9] を日本語で読んだ。ここに、倫理学と哲学の分野の従来の/標準的な諸理論と対比して、筆者の理解が意味することについて考察・議論しておきたい。シジウィック [10, 8] は、最も典型的な倫理学の方法として、(教義的)直観主義、利己主義、(普遍的)功利主義の三つを取り上げている。本節の議論は、これらの方法を主な対象とする。
7.1 「倫理」の指令の真の根源は何か?
人々の常識的な理解はつぎのようであろう。われわれの心の中の深い所で、われわれは「良心」を持っていて、それが直観的に善/悪を見分けることができ、われわれが従うべきある種の指令を「善」として示すことができる。その「良心」はわれわれが社会から教えられた常識的道徳規則を反映している。[注:ここで「常識的道徳規則」というのは、その社会で見識のある人たちが一般に認めている道徳規則を意味する。]
(教義的)直観主義はつぎのようにいう。われわれは「良心」によって道徳規則を直観的に感じることができ、それらに忠実に従っていくべきである。道徳規則は常に正しく、一貫しており、矛盾はない。だから、それに従って行動することが常に「善」であり、その行動の帰結を心配する必要はない。
他方、功利主義はつぎのようにいう。われわれは、いろいろな行為案の帰結を考えた上で「善」の行為を行うべきである。何が「善」であるかは自明ではない。そこで、人々が「究極的に望ましいもの」として何を追求するかを研究した結果、究極の「善」は「快」(すなわち、広い意味での望ましい感情)であるとの結論を得た。道徳判断をする場合、われわれはいくつかの行為代替案を考え、それぞれの行為が帰結としてどれだけの「快」をもたらすかをまず評価するべきである。そして、利己主義(すなわち、自己利益型功利主義)なら、自分自身に最大の「快」をもたらす行為を選ぶ。他方、(普遍的)功利主義なら、関連しているすべての人に最大の「快」をもたらすであろう行為を選ぶ。
直観主義は、行動の帰結を問題にせずに絶対的に従うべきだという点が、しばしば批判される。なぜなら、常識的道徳規則は、社会から(時には宗教的な教義として)教えられるものであるが、硬直的でさまざまな矛盾を含んでいることがあるから。
功利主義は「快」(後には「選好」)を評価する点に困難がある。そのような批判に対応して、功利主義は常識的道徳規則を中間的公理として許容することを選ぶことがある。
20世紀のメタ倫理学 [6, 11] は、「「べき」という語を含む道徳宣言文を、「である」で記述される事実宣言文だけから導くことは論理的にできない」との結論を得た。どんな道徳宣言文でも、その根底には、指令を含意する何らかの根源的な「べき」宣言文を必要とする。それでは、もしわれわれが、常識的道徳規則に頼らないとすれば、根底の指令としてどんなものを見出せるのだろうか?
本研究は、「われわれの内面にあって善/悪を判断できる先天的な心の能力」を仮定した。そして「良心」を、その先天的能力をさすものと定義し直した。われわれは、「倫理」(すなわち、何が「善」で何が「悪」であるかの内容)を、両親や社会や体験などを通じて学ぶが、それらを受容できるのは「良心」という先天的な能力をベースとして持っているからである。
このアイデアは言語学習の人間の能力との類比から得た。すなわち、どんな赤ん坊でも、0歳〜3歳のときに、言葉を学び話すようになるが、[生みの親から離されて、異国の異言語の環境で育てられた場合を想定すればわかるように、]話すのは育ての親とそのコミュニテイの言葉であり、赤ん坊の遺伝特性に基づく(生みの親の)言葉ではない。われわれの脳の諸機能(推論や身体運動など)もまた同様に [先天的な能力をベースに、後天的な習得で] 学習している。
「良心」は先天的だから、すべての人間に共通であり、われわれの内面において非常に安定している。しかし、それをきちんと書き出すことは難しい。
ところで、この先天的な「良心」は、善/悪に関してまったく白紙であると、仮定するべきだろうか?それよりも、なんらかの基本的な指令あるいは指導原理があって、その上に道徳指令を作り上げることができる、と仮定するのがもっと適当であろう。それらは、生き物としての進化に起源を持っているに違いない。すべての生き物がもっているそのような指導原理は、次のように特徴づけられるであろう。
(a) 生きること、生き残ること。すべての力を使って、自分で。
(b) 子孫を作り、増やすこと。生殖により、子どもを育て、など。
(c) 種を繁栄させること。メンバーを助け、メンバーを殺さず、コミュニケーションをして、など。わわれはまた、道徳感覚において何らかの階層構造を仮定してもよいかもしれない。先天的「良心」、社会から教えられた常識的道徳規則、そして、実際的個人的な道徳感覚で人生経験や感情を通じて作られ日常の振る舞いなどに実際に現れるもの、の三層が考えられる。
7.2 倫理の原理/規則の性格
義務論においては、倫理的規則は与えられたものであり、疑問や議論の余地はなく、実行するべき「義務」である。常識的道徳規則は、多くの場合、社会における固い規則の体系であるとみなされ、人々の考えはそれらの規則に強く縛られている。それらを否定することは悪、あるいは宗教的な罪であるとみなされる。
他の多くの倫理学の立場では(功利主義も含めて)、倫理的体系は「規則、法則、原理」などとみなされ、忠実に従うべきものと考えられている。ただ、功利主義は道徳的規則の具体的な体系を作り上げようとはしない。そこでは、究極の望ましい目標として「善」の概念を作り、その評価プロセスを作っているので、暗黙的に何らかの倫理的規則を仮定している。[その倫理的規則の体系を各個人が作ることは困難なので、前述のように、常識的倫理規則を中間公理として便宜的に認める場合がある。]
倫理的規則/原理の上記のような理解は、共通して以下のような弱点を持っている。
(a) 直観的な道徳思考はしばしば、社会から教えられた常識的道徳法則を反映し、人々に批判的思考をせずに従順に従うように促す。
(b) それらの規則/法則は、いつも正しく、一貫しており、欠陥がなく矛盾がないものと仮定されている。そこで、さまざまな場合にも適用できるように、詳細にわたって定式化されていなければならない。その結果、法則はさまざまな限定や例外を含んだ詳細・煩瑣なものになる。
(c) 実際には、さまざまな新しいまた古い適用場面において、困難・対立・矛盾が現れる。特に、法則が、社会の歴史的な変化に適応できず、新しい状況に適用できないことが起こる。
(d) それらはなんらかの正当化、権威付けを仮定している。政治的あるいは宗教的な権威など。そのような権威づけは、権威を与えている勢力(すなわち、本研究でいう社会的勝者)の利害を(その道徳規則に)反映する。
(e) そのような正当化にも関わらず、常識的道徳規則は、歴史的に見ると、また全世界的に見ると、さまざまに違っている。それらの道徳規則は、世界の国やコミュニティで違い、歴史的な時代で違う。それらのどれ一つも標準、絶対的ではない。そのような相対的な立場であることを受け入れなければならない。
(f) 道徳的規則の違いは、実際の場合の行為に異なる指令を与える。その結果、個人的なあるいは社会的な振る舞いにおいて、異なる立場を作り出し、さまざまな主義や文化を作る。このような違いを認識することは、一方では、相互理解のために相対的な立場であることを理解する鍵になる。しかし、もう一方で、既存の道徳規則に疑問を持ち改革をするトリガーにもなり得る。
本研究では、われわれは「倫理」の原理を、「指導原理」と捉え、われわれが進むべき基本的な、幅のある方向を示しているものと、理解している。その土台はしっかりしており、根元では明確であるが、その先端部はオープンであり、詳細には定義されていない。われわれは、そのような基本的な方向(方向づけ)を、倫理的推論を用いて、問題の実際の状況に適用していかなければならない。
その土台は、根元は先天的であり、生き物としての数十億年の進化の結果である。そして土台の第二層には、人類文化と社会の歴史的進化によって蓄積されたものがある。この第二層は必ずしも単純でなく、欠陥のない一貫性のあるものでもない。これらの土台の層、とくにその第一層は、明確に存在するが、その内容を書き出すことは(先天的能力の場合の常として)容易でない。
「倫理」指導原理は多面的であり、複数の構成要素からなる。それらは、全体として、われわれが進むべきかなり広い幅のある方向づけを示し、収束的ではなくむしろ発散的である。それらの指導原理を適用するにあたって、われわれはさまざまな困難に出会う。われわれはそれらを検討し、いくつかの代替案を見つけ、矛盾を妥協(最適化)あるいは解決し、ベストの解を選んで、何をするべきかを決めなければならない。これが本研究での基本的な知見であり、人類文化の主要矛盾「自由」vs「愛」として定式化したことである。
多様な従来の/標準的倫理学は、一貫して矛盾を含まないような、なんらかの倫理原理・法則を見出そうと試みて失敗してきた。本研究が提唱したのは、人類文化はその根底において「倫理」指導原理のしっかりした体系に基礎づけられているが、その体系は本質的な矛盾を内包したものだということである。倫理学だけでなく人類文化はこの点を認識してこなかった。そのため、多くの [諸問題の根本を論ずる] 哲学的な分野で、問題の本質を間違って理解する結果になってきた。問題状況の中の本質的な矛盾を見つけることは、TRIZ/CrePS方法論 [1] の重要なアプローチである。
7.3 現代倫理学、特に功利主義、に関するコメント
功利主義において「善」の概念は、「われわれの倫理的行為における究極の目標/目的」として抽出されたものであり、その結果、人々の内面での倫理的動機づけにおける感情に比べてあまりにも抽象的なものになった。われわれは、なにかもっと明確な指針で実際に動機づけられていると感じる。本研究での三つの指導原理(すなわち、「自由」「愛」「倫理」)は、ずっとはっきりとわれわれを動機づけ、方向を示してくれる。
功利主義が、行為の帰結を考慮に入れて [複数代替案の中から倫理的] 行為を選択することは、適切である。それは、可能性のある諸代替案を行った時の帰結を評価し、行為を選択決定することである。行為(案)を評価するにあたって、功利主義は「快」という尺度を使う。他方、本研究では、三つの指導原理の基本的な方向づけ、すなわち、「倫理」の深化、「自由」の伸長、および「愛」の拡張(普遍化)、を使う。
行為の代替案を考え出すにあたっては、功利主義は何の方法をも提供しない。他方、本研究のTRIZ/CrePS方法論 [1] は、矛盾を克服する代替解決策のアイデアを生成する多くの方法と実績を持っている。
7.4 シジウィックの「実践理性の二元性」に代わる「自由」vs「愛」の矛盾
Henry Sidgwickの『倫理学の諸方法』 [8,10] は特に重要である。同書は倫理学の主要な3方法について論じている。すなわち、
(a) (教義的)直観主義、
(b) 利己主義(すなわち利己的功利主義)、そして
(c) (普遍的)功利主義、である。
(b)と(c) の両者は、究極の「善」が「快」であるという概念、人々の平等性、倫理的行為を評価するのに「善」の最大化を使うこと、の諸点で一致している。ただ、(c) が自分の「快」だけでなく人々の「快」を最大化することを追求するのに対して、利己主義 (b) は、自分の「快」だけを追求し、関連するすべての人々に対して公正であろうとする立場を取らない。シジウィックは、利己主義(b)を理論的に棄却できないことを見出し、その結果、「[倫理判断を行う] 実践理性は、利己主義と功利主義の二つに分裂する」と結論し、これを「実践理性の二元性」と呼んだ。本研究の観点から言えば、利己主義(b) は指導原理「自由」の主張に近く、他方、功利主義(c)は指導原理「愛」(およびいくらかの「自由」)の振る舞いに近い。そこで、シジウィックの「二元性」の認識は、本研究の「自由」vs「愛」の矛盾の概念の近くまで来た、と言ってもいいだろう。シジウィックは、功利主義についての長い旅程の後に「二元性」の概念に到達しているが、その根本原因やそれを克服する鍵については、何も見出していない。現代の功利主義は、この「二元性」の問題について多少の議論をしているが、重要な知見を何も得ていない、という [8]。
それに対して、筆者は、貧困の問題の議論の中で直接に、「自由」vs「愛」の矛盾の概念に到達した。「自由」vs「愛」の矛盾の性格と問題状況について詳細に議論し、その矛盾を克服/軽減するための鍵となる方向づけについても、本研究で示している。
7.5 ロールズの『正義論』についての考察
John Rawls は、功利主義を発展させて、1970年代に『正義論 (公正の原理)』を提唱した [9,12]。彼の二つの原理は:
第一原理: 各人は、基本的自由に対する平等の権利をもつべきである。その基本的自由は、他の人びとの同様な自由と両立しうる限りにおいて、最大限広範囲にわたる自由でなければならない。
第二原理: 社会的・経済的不平等は、次の二条件を満たすものでなければならない。
(a) それらの不平等が全員の利益になると無理なく予期しうること。
(b) それらの不平等が全員に開かれている地位や職務に付随するものでしかないこと。これらの原理は社会の望ましい規則について明確に言及している点で注目に値する。この文脈で本研究が言うなら、つぎのようである。
すべての人は、自分の幸福と利益を追求する権利を持っている(第0指導原理「倫理」)。
よって、[そのような人々の権利を侵害しないように最大限配慮したうえで]、
すべての人は自分の幸福と利益を追求するべきであり(第1指導原理「自由」)、
そして同時に、(すべての人、および社会全体が)すべてのメンバーの幸福と利益を追求するべきである(第2指導原理「愛」)。ロールズの理論は現代社会の格差を減少させるための明確な方向を示すのに大きな寄与をした。そして本研究は、そのような方向を、人類文化のより一般的な理解から、支持するものである。
7.6 自由、平等、博愛
フランス革命の三つのスローガン (すなわち、「自由、平等、博愛」) が、多数の現代国家のさまざまな憲法に大きな影響を与えたことは、よく知られている。それらの強調点は、身分制度(王制や貴族制)からの自由と、(身分に関わらない、市民や農民など [を含めたすべての人々] の平等)にあった。「博愛」が第三のスローガンの地位を [フランス憲法上で正式に] 得たのは、(愛が長らくキリスト教の主テーマであったにも関わらず)遅れて19世紀の半ばであったという。フランス革命では、三つのスローガンは、両立するものとして、一緒に掲げられていた。
本研究では、三つのスローガンはそれぞれ、第1指導原理「自由」、第0指導原理「倫理」の一部、第2指導原理「愛」の中に、ずっと拡張された意味を持って含まれている。そして本研究では、それらを人類文化の三つの主要な指導原理という位置づけに高め、それらが内部に本質的な矛盾を持つ構造であることと、その矛盾を解決する可能性のある鍵とを示した。
7.7 本研究における「善」と「幸福」の概念
本研究においては、「善」の概念も「幸福」の概念も、最初には定義されていないことに注意されたい。
本研究の含意を議論してきた結果として、筆者はいま、「善」の概念の定義を得るに至った。すなわち、
「善」とは、人類文化の三つの主要指導原理が指し示す「全体としての方向」である。
すなわち、第0指導原理「倫理」を深化すること、第1指導原理「自由」を伸長すること、第2指導原理「愛」を拡張(普遍化)すること、[を一緒に行うこと] である。三つの主要な指導原理は、人類文化を一貫して並立可能なやり方で指導(ガイド)する一つのシステムをなしている。しかしそれでもなお、さまざまな状況に適用する途上においては内在する本質的な矛盾に直面する。われわれが特に注意するべきことは、この全システムの(どんな一部でも)一部だけを取り出してそれに固執する(強く主張する)と、しばしば(内在する)矛盾をより深刻化させ、問題状況を悪化させる、ことである。この意味で、この三つの主要指導原理から成る全体システムの任意の一部分を「善」とみなすことはできない、[重ねて言うと、「自由」が(それ自体で)「善」ではない、「愛」が「善」ではない、「倫理」が「善」ではない。「自由」と「愛」と「倫理」が全体として(相互を尊重して)行われることが「善」なのである] ということをわれわれは理解しなければならない。
指導原理全体のどこかの一部分だけを取り出して不適切に主張する(固執する)という誤りの事例はいたるところにある。例えば、
資本主義経済で、ビジネス第一のアプローチで、社会の格差を増大させている(「自由」の固執)
利己主義で、個人の利害と個人の財産に固執する(「自由」の固執)
政治や組織運営で、少数意見を無視して多数者が決定する(「愛」の固執)
「愛」を説く宗教組織において、個人の意思決定や「自由」を無視する(「愛」の固執)
社会ルールや社会システムにただ従順に従うことを教える(「倫理」の固執)
三つの主要指導原理から成るこのシステムは、個人レベルに適用されるだけでなく、全世界のさまざまな社会レベルにも適用できることに、われわれは留意するべきである。
本研究では、「幸福」についても当初には全く定義していなかった。図1、図2で、指導原理による方向づけのエッセンスを示したときに、「幸福と利害」という語を定義なしに使った。
まとめをしている現時点で、われわれは「善」を「三つの主要指導原理の全体系によって導かれる全体的な方向づけ」と定義したので、「幸福」をも次のように定義するとよいであろう。すなわち、
個人レベルでの「幸福」とは、「三つの主要指導原理の全体系によって導かれる全体的な方向づけが、その人自身についても、また、その人の周りにおいても、満たされている(守られている)状況」と定義される。
同様に、社会レベルでの「幸福」とは、「三つの主要指導原理の全体系によって導かれる全体的な方向づけが、その社会的組織についても、また、その周りにおいても、満たされている(守られている)状況」と定義される。
結論として、われわれが理解したことは、以下のようである。
「人類文化は、三つの主要指導原理の全体系によって導かれる全体的な方向づけに沿って常に前進するべきである。すなわち、(第0指導原理)「倫理」を深化すること、(第1指導原理)「自由」を伸長すること、(第2指導原理)「愛」を拡張(普遍化)すること、を一緒に行うこと」である。
その途上において、人類文化はさまざまな矛盾に直面するであろう。主要指導原理に内在する「自由」vs「愛」の矛盾から生じてくる諸矛盾である。
それらを解決する方向づけは、主として第0指導原理「倫理」を鍵として見出されるであろう。「倫理」は「自由」と「愛」の両方を動機づけ調整できるものだからである。
われわれがこれらのことを深く理解し、その知見を広く広め、全世界のすべての活動に適用していくことが、極めて重要・有意義である。
8. 結論
前節で議論したように、2〜6節に提示した本研究の基本仮説は、従来の/標準的倫理学の諸理論に対比して、大いに新規で創造的であること、またそれらの大きな欠陥を満たすこと、が示された。筆者は、科学技術分野の研究者であり、人文・社会科学の専門的なトレーニングを受けていない。[そのために、不十分なこと、理解できていないことも多々あることと思う。ご批判いただきたい。]
だから、本研究が創出した結果は、当該分野外の研究者が持ち込んだ革新的な研究の一つの顕著な事例とみることができよう。そのような側面から見た鍵になる諸点を、前報 [5] での議論をベースにしてここにまとめておく。
(1) 本研究は、科学技術分野における一般的な問題解決の方法論 [1] を、人文/社会分野の問題に適用することを目指して開始した。適用できる理論も研究方法もこれら二つの分野では非常に違っているように見えるけれども、思考の科学的な方法、特にTRIZ/CrePS [1] で培われた方法、は新しい対象分野でも有効であることが分かった。
(2) 図的思考(「見える化」思考)、すなわち、多くの項目(事実、課題、構成要素、など)を図上で「見える化」し(例えば、図1、図2)それらの輻輳した関係を見やすくすること、は社会的問題の状況を理解することを助け、仮説を含んだアイデアを作り上げるのを助けた。
(3) 社会保障に関する人々の賛否の議論を見て、それらが「自由」を求める議論と「愛」を求める議論との矛盾であると理解した。「自由」vs「愛」の型の矛盾は沢山の例があることに注目した。「自由」も「愛」も人類文化において重要な目標だから、「自由」vs「愛」の矛盾は人類文化にとって致命的な重要性を持ち、詳しく研究する必要があると判断した。
(4) 「自由」と「愛」について、その性格、特徴、振る舞い、帰結、などを書き出した。この段階で、「自由」を「自分で判断し、行動し、生きること」と定義し、「愛」を「子を愛し、家族を愛し、隣人を愛して、助け、守ること」と定義した。ここでは生き物としての基本的な動機づけが念頭にあった。「自由」と「愛」の個人レベルと社会レベルでのさまざまな観察事項を順次書き出していった。「自由」にも「愛」にも、プラスの面だけでなくマイナスの面があることに注目した。
(5) 「自由」の中、「愛」の中、そして「自由」と「愛」の間の、対立のさまざまなフェーズを記述した。これらのすべてが「自由」vs「愛」の矛盾を構成している。
(6) 人の心の根底に、われわれは良心と倫理があると考える。「倫理」(あるいは道徳規則)が「自由」vs「愛」の矛盾を軽減する鍵であると分かった。基本的人権の概念が重要であると分かった。人の心の内部構造を理解するのは難しい。感情、欲望、善の心と悪の心、動機、理由づけなど、いろいろなレベルと側面があるから。善/悪を学び判断する先天的な能力を仮説として導入し、「良心」と呼んだ。言語学習の先天的な能力との類比を考えた結果である。
(7) このようにして、「自由」「愛」「倫理」からなる、人類文化の三つの主要指導原理の全体構造が作り上げられていった。これらの過程で、システム思考、矛盾の概念とその解決法、などが、最も重要な役割を果たしている。
(8) 倫理学の参考文献を学んで、本研究はその哲学的な基礎がずっと強化された。その内容は7節に記述したとおりである。先天的能力の「良心」の仮説は、その導入の必要性と妥当性を確信した。本研究での三つの主要指導原理のすべてが、生き物としての遺伝的進化に強固な基礎を持っていることを理解した。
(9) 先天的「良心」は、(後天的に)社会が蓄積した常識的道徳規則とは分離されている。これは、倫理学における直観主義と功利主義との論争を解決して、新しい明確な理解を提供している。倫理的指示の(性格の)理解として、本研究での「指導原理、すなわち、導く方向(方向づけ)」という考えは、「義務」、「指示、指令」、(功利主義での)「帰結を評価してのちに決めるべき行為の代替案」などの考えよりも明確である。
(今までの倫理学が求めてきて得られなかった)「矛盾のない道徳規則の体系」の代わりに、本研究は、「自由」、「愛」、「倫理」が関わる新しい「倫理」の体系を見出した。「自由」の伸長、「愛」の拡張(あるいは普遍化)、および「倫理」の深化は、「人類文化を導く方向(方向づけ)」として安定して強力であり、個人レベルに適用できると同時にさまざまな社会レベルでも適用できる。指導原理を適用するにあたっては、内在する矛盾を解決していく必要がある。
(11) 最後に、「善」が、「「自由」と「愛」と「倫理」(という三つの指導原理)で示される方向づけの全体」として定義された。指導原理の全体から一つの部分を取り出して固執することは、(それがどんな部分であっても)決して「善」ではない。なぜなら、それは(内在する)矛盾を一層厳しくし、さまざまな望ましくない結果をもたらすからである。また、「幸福」は、「指導原理の全体系が導く方向づけの全体が、その人自身と周りとで満たされている(守られている)状況」として理解された。
上記の (1)〜(11)のステップのすべてが、科学的洞察と推論を順次導入することによって、スムーズに達成できたことは、注目に値する。さらに一層の研究が、個人レベルについても、さまざまな社会レベルについても、必要である。
参考文献
[1] 中川徹、「創造的な問題解決のための一般的な方法論CrePS: TRIZを越えて:なに?なぜ?いかに?」、TRIZCON 2016、2016年3月3-5日、米国ニューオーリンズ; 和訳: 『TRIZホームページ』掲載, 2016. 6.20
。
[2] 中川 徹: ‘TRIZ/CrePS approach to the social problems of poverty: 'Liberty vs. Love' is found the Principal Contradiction of the Human Culture’, ETRIA TRIZ Future Conference 2016 発表、2016年10月24-27日、ポーランドWroclaw; THPJ 掲載、2016.11. 7
。『Selected Scientific Papers from ETRIA TRIZ Future Conferences 2016 and 2017(仮題)』, Gaetano Cascini, Leonid Chechulin, et al.編, Springer, 出版予定(2018年秋)。
[3] 中川徹:「人類文化の主要矛盾「自由vs愛」を考察する (2) 個人における「自由vs愛」の矛盾・葛藤と「倫理」、日本創造学会第39回研究大会発表、2017年9月9−10日、横浜市。同予稿集。『TRIZホームページ』 掲載、2017.9.28
。
[4] 中川 徹: ‘ 'Liberty vs. Love': The Principal Contradiction of Human Culture (2) The 'Liberty vs. Love' Contradiction and 'Ethics' at the Personal Level’, ETRIA TRIZ Future Conference 2017 発表、2016年10月4-6日、フィンランド Lappeenranta。 Gaetano Cascini, Leonid Chechulin編, Journal of the European TRIZ Association, INNOVATOR, ISSN 1866-4180, 02/2017 Volume 04, pp. 97-104 . http://www.etria.eu/innovator/ETRIAjournal2017vol04.pdf
。『TRIZホームページ』 掲載、2018.6.25

。
[5] 中川 徹:「人類文化の主要矛盾「自由 vs 愛」を考察する (2) 個人における「自由 vs 愛」の矛盾・葛藤と「倫理」」(拡張・推敲論文):『TRIZホームページ』初出掲載、2018.6.25
.英訳掲載、2018. 8.14
。
[6] 小松光彦・樽井正義・谷寿美 編:『倫理学案内―理論と課題』、慶応義塾大学出版会、(2006)、312頁
[7] 品川哲彦:『倫理学の話』、ナカニシヤ出版、(2015)、276頁。
[8] 奥野満里子:『シジウィックと現代功利主義』、勁草書房、(1999)、313頁。
[9] 川本隆史:『ロールズ 正義の原理』、現代思想の冒険者たちSelect、講談社、(2005)、303頁。
[10] Henry Sidgwick: “The Methods of Ethics”, (1st Edition)、(1874)
[11] R. M. Hare: “The Language of Morals”、Oxford (1961)
[12] John Rawls: “A Theory of Justice”、(1971)
注:THPJ: 『TRIZホームページ』、中川徹編集、URL: http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/
| 論文部分和訳PDF |
発表スライド(和訳) PDF
(掲載: 2018.11.11)
1. はじめに
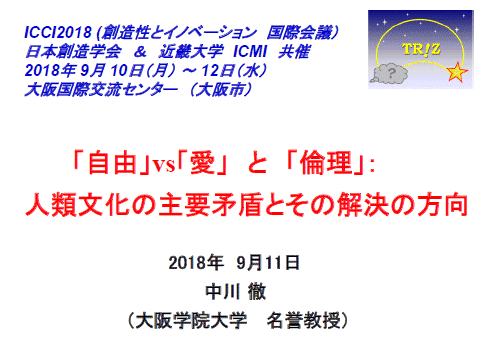
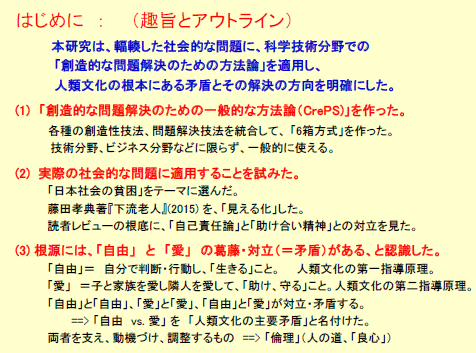
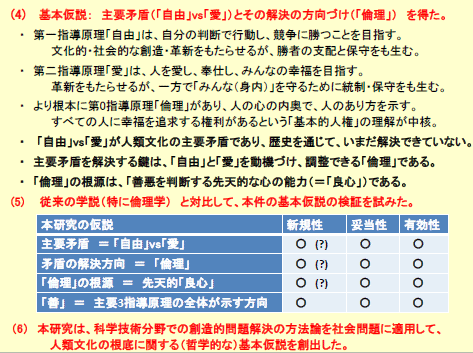
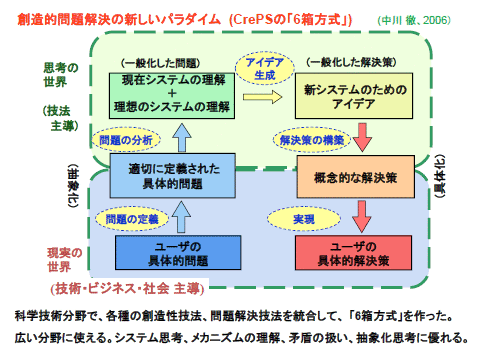
2. 社会的問題への適用の試み: 初期の知見 (2015- 2016)
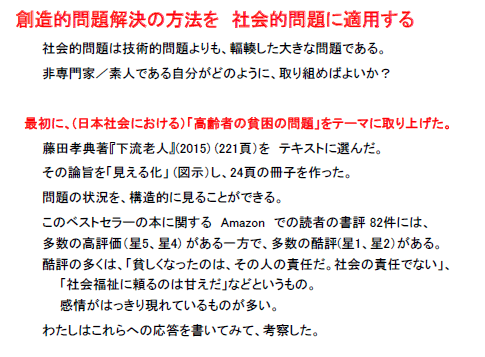
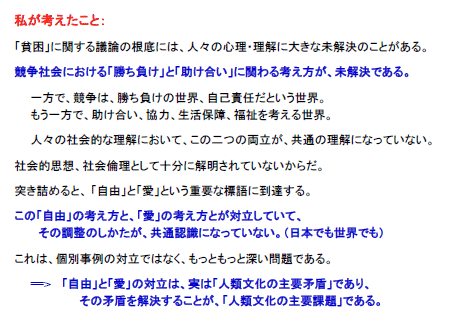
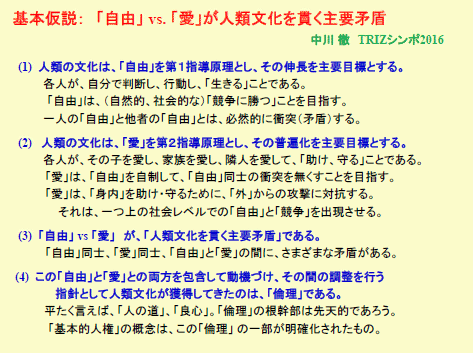
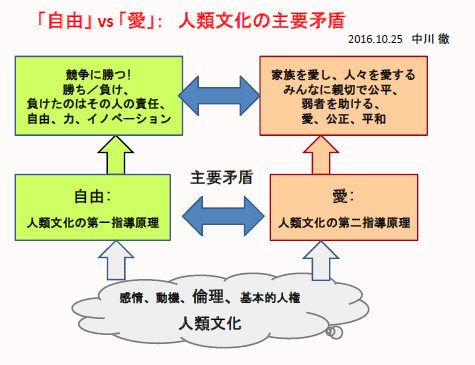
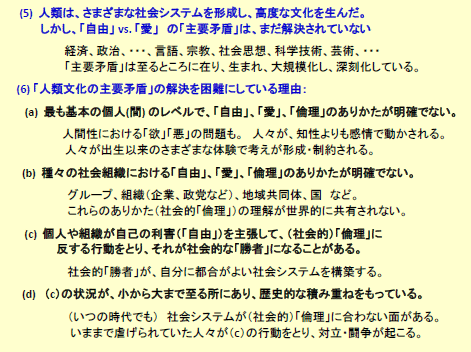
3. 探求を深める (2017 - 2018)
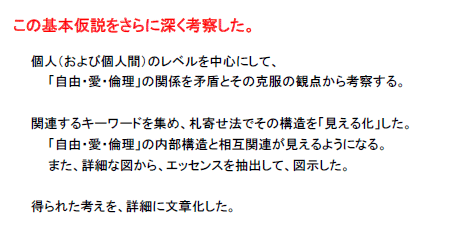
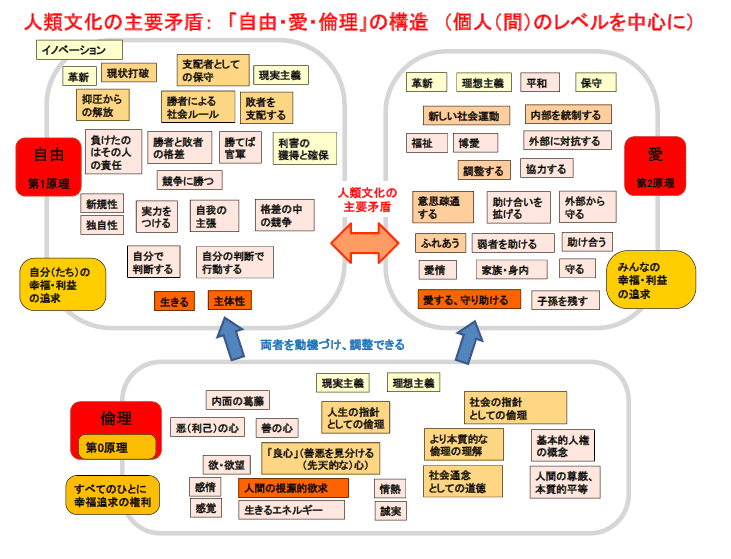
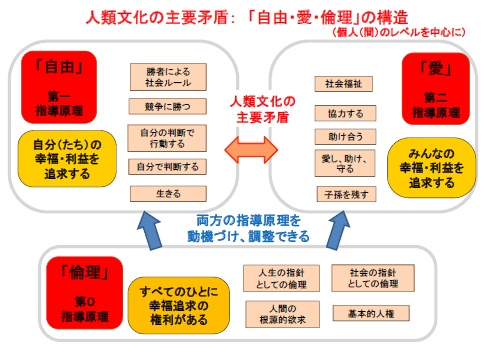
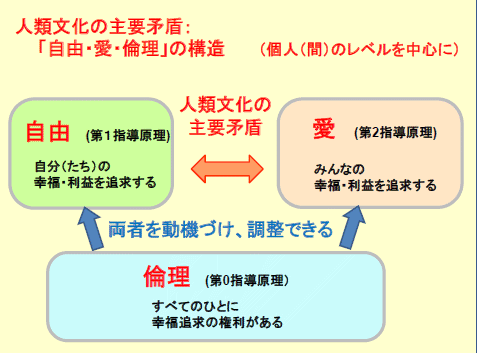
4. 人類文化の主要矛盾に関する基本仮説
4.1 第0指導原理: 「倫理」
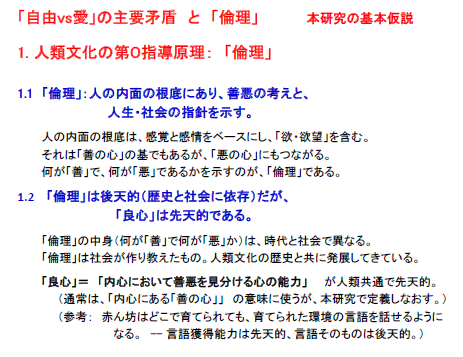
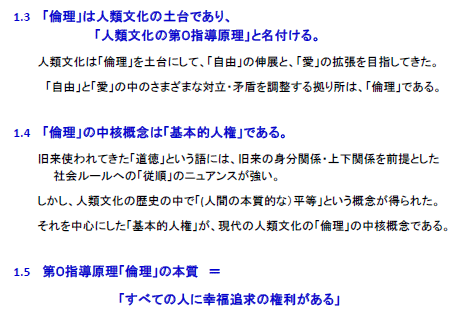
4.2 第1指導原理: 「自由」
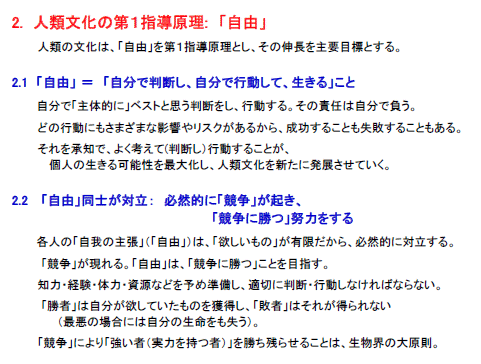
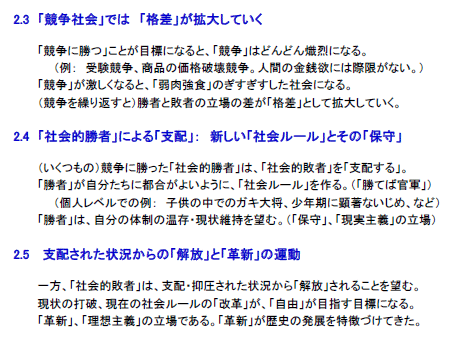
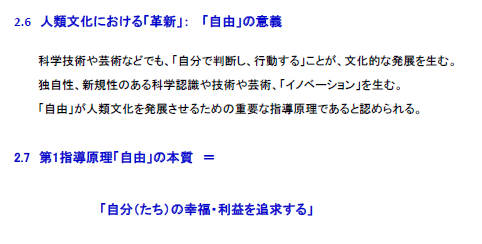
4.3 第2指導原理: 「愛」
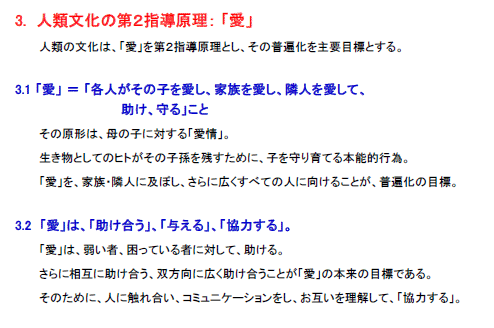
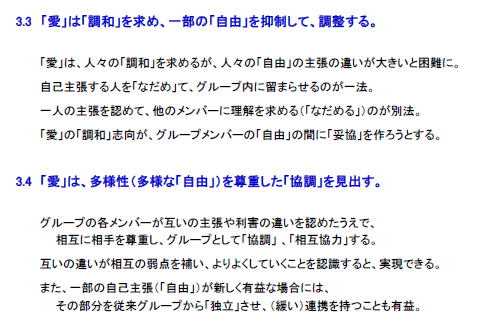
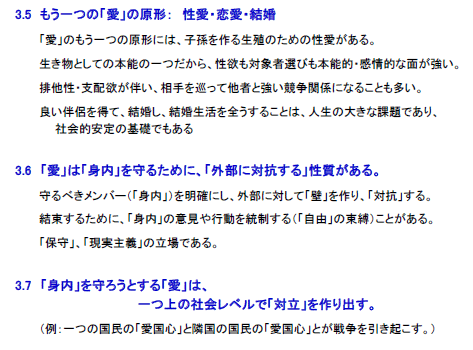
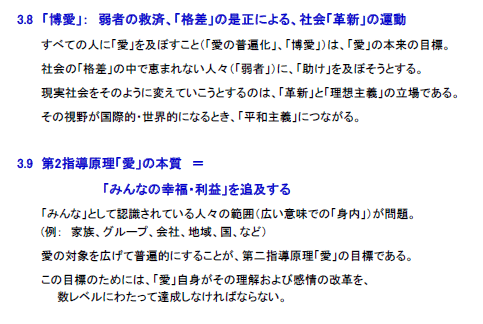
4.4 「自由」と「愛」との矛盾
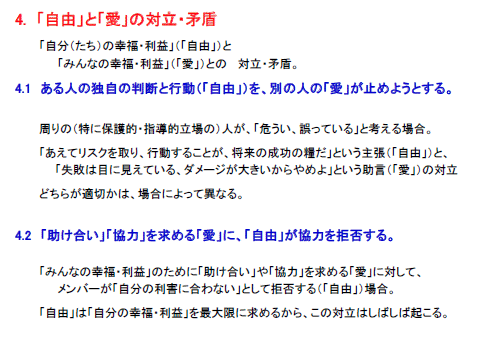
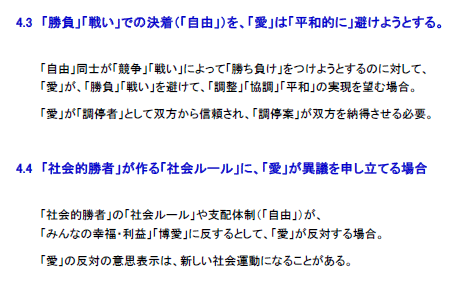
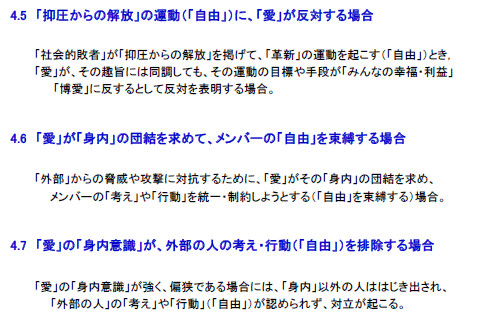
4.5 「倫理」の役割
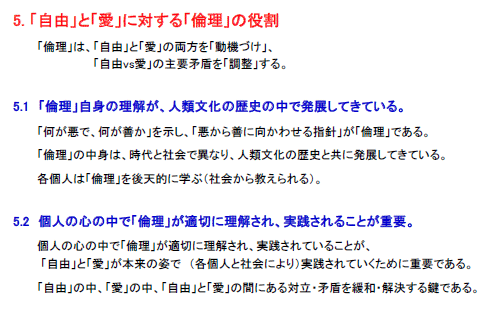
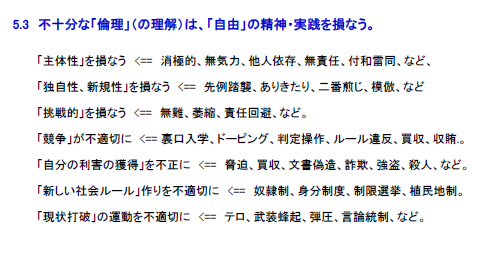
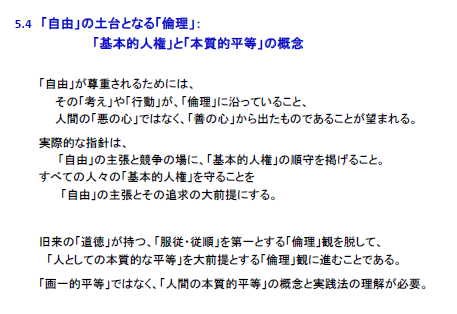
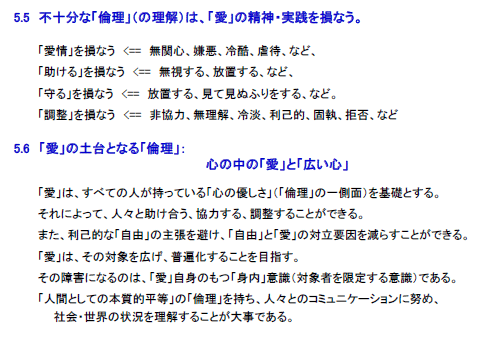
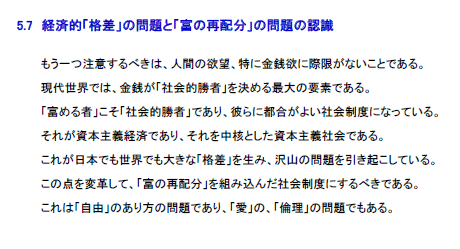
5. 考察
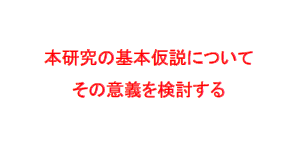
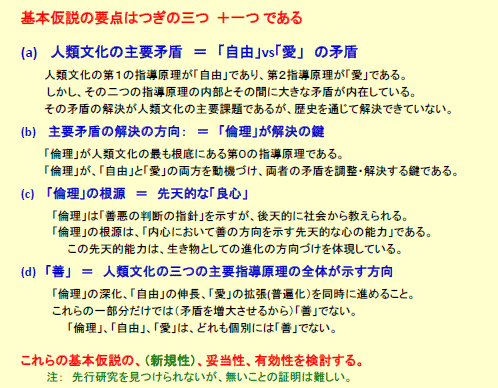
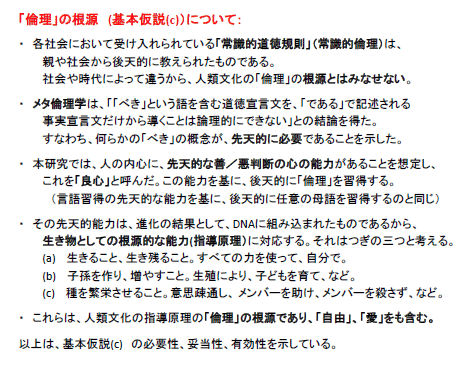
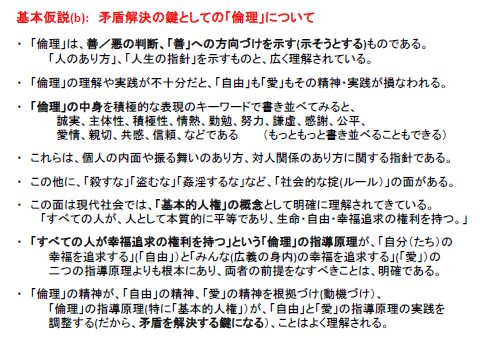
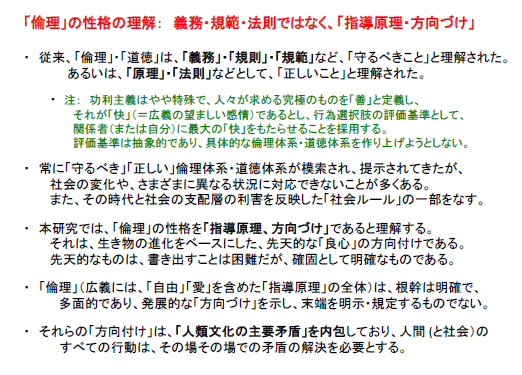
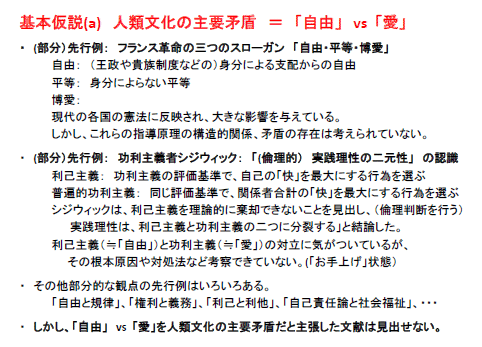
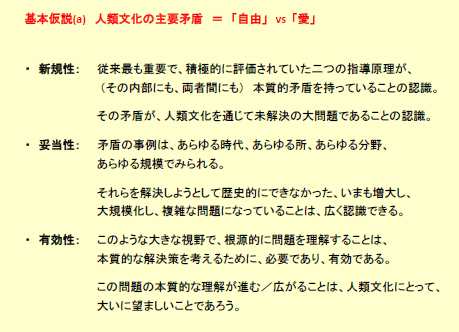
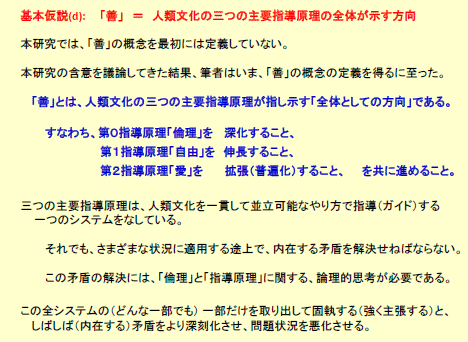
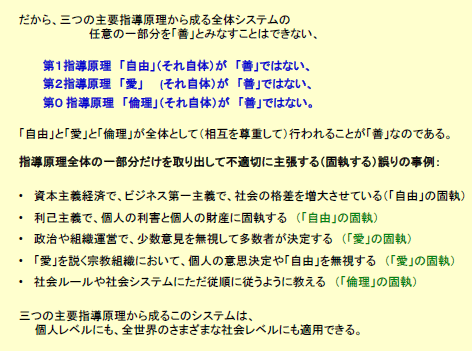
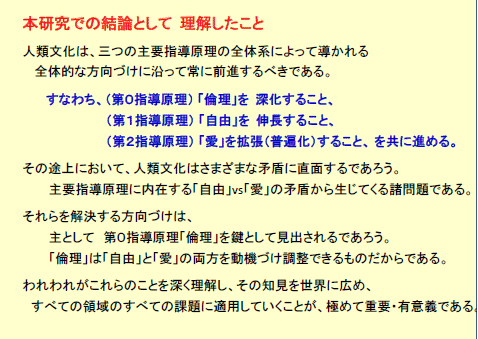
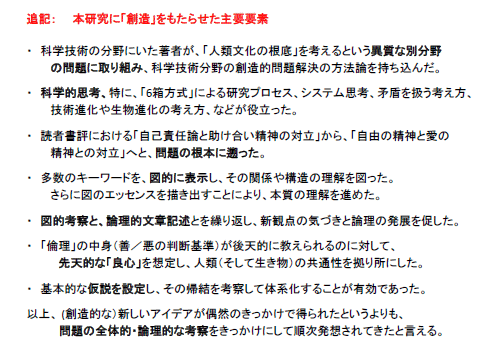
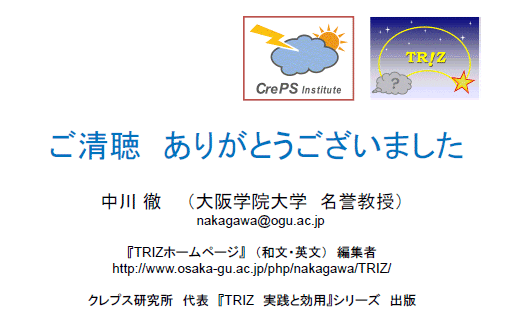
| 論文部分和訳PDF |
|
|
|
最終更新日: 2018.11.11 連絡先: 中川 徹 nakagawa@ogu.ac.jp