『OHM』誌 (オーム社)、2010年11月号、10-11頁 (2010年11月5日)
| 技術革新のための問題解決の方法論「TRIZ」 | |
| 中川徹 (大阪学院大学) 『OHM』誌 (オーム社)、2010年11月号、10-11頁 (2010年11月5日) |
|
| 掲載:2010.11.12 |
Press the button for going to the English page.
編集ノート (中川 徹、2010年11月12日)
本稿は「TRIZ」に関する2ページの紹介記事です。「TRIZ」ははじめてという方に読んでいただけますと幸いです。
『OHM』誌に掲載されましたままの形のPDF版
をご覧いただけます。また、「目に入りやすさ」を考えて、本ページにHTML でも掲載しています。
TRIZについての紹介をさらに読みたい方は、本ホームページの「TRIZ紹介のページ」
を参照下さい。
| 本ページの先頭 | 『OHM』誌 PDF版 |
本文記事の先頭 | 後記 | 『InterLab』誌TRIZ連載 |
TRIZ紹介のページ |
英文ページ |
[1] 『OHM』誌掲載 PDF 版
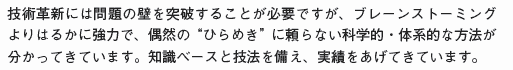
==> PDF 版
(2頁、639KB)
[2] HTML 版
技術革新のための問題解決の方法論 「TRIZ」
大阪学院大学 中川 徹
『OHM』誌 (オーム社)、2010年11月号、10-11頁 (HEADLINE REVIEW欄)
技術革新には問題の壁を突破することが必要ですが、ブレーンストーミングよりはるかに強力で、偶然の“ひらめき”に頼らない科学的・体系的な方法が分かってきています。知識ベースと技法を備え、実績をあげてきています。
Q: 「TRIZ」とは何でしょうか
TRIZ(トリーズ)は、約60 年前に旧ソ連のゲンリック・アルトシュラー氏が開発・樹立し、冷戦終了後に西側諸国に拡がっていった技術開発の方法論です。TRIZ は、「発明問題解決の理論」を意味するロシア語の頭文字語“ТРИЗ”を英字綴りにしたものです。
特許を始めとする科学技術の知識を整理分析した多様で膨大な知識ベースを持ち、それを便利なソフトツールにし、創造的な問題解決のための思考技法を持っています。もともとは機械・電気・化学工学などの分野でスタートし、今やソフトウェアなどを含むすべての科学技術分野をカバーし、ビジネス・経営などの非技術分野でも適用されてきています。それはツールや技法のレベルを超えて、(技術)思想のレベルにまで達しています。
Q: どのような知識ベースを持っていますか
TRIZ の特長は、世界の特許を内容的に分析し、そのエッセンスを多様な形式の知識ベースにしたことです。これはアルトシュラー氏が始めた基本的なアプローチで、TRIZ のツールの各ベンダーが継承発展させています。
一つは、科学技術の原理・現象・技術を網羅した「科学効果」の知識ベースで、インベンションマシン社のツールでは9千件あまりを収録しています。特許や技術文書を自然言語の意味解析ツールで自動解析して、常時最新の知識をこの知識ベースに蓄積しています。この知識ベースを使えば、目的とする機能を実現するための原理や応用例を、自分の業界や専門分野にしばられずに、即時に知ることができます。
そして、多数の特許のアイデアのエッセンスを抽出して濃縮した「発明原理」があります。これは、“分割する”、“分離する”、“場所によって性質を変える”など「40の発明原理」として親しまれています。ソフトウェア/ IT 分野、ビジネス分野などでも適用例が集められており、理解に役立っています。
Q: 知識ベースをどのように使うのでしょうか
もっとも単純なのは百科事典やヒント集として使うことですが、もっと高度な使い方として、次の二つがあります。
技術開発でしばしば直面する問題は、ある解決策を使ってシステムの一つの面を改良しようとすると別の面が悪化してうまくいかないことです。二つの側面のトレードオフの状況で、工学では普通“最適化”を目指しますが、TRIZ ではトレードオフの壁を突破した事例を優れた特許の中に見出そうとします。
アルトシュラー氏は39 の側面を選び、改良しようとする側面39 ×悪化する側面39 のマトリックスで、各マス目の問題を解決した特許が使った発明原理を整理しました。この膨大な表(矛盾マトリックス)を1970 年代初めに作ったのです。その後、ダレル・マン氏らは1985 年以降の米国特許全件を分析して、2003 年版、2010年版の矛盾マトリックスを作成しています。図1のように、自分の問題をこの表の一つのマス目として位置づけ、そこに記されている発明原理を解決策へのヒントとするのです。
アルトシュラー氏は、「さらに問題を突き詰めて、システムの一つの側面に対して、反対の要求が同時にあるという矛盾を見出せ」と言います。通常はどうにもならないと思う状況ですが、それを確実に解決できるというのがTRIZです。矛盾する要求を分離できる時間・空間または条件を見つけ、そのような矛盾を今までに解決した多数の発明原理を参考にします。
Q: TRIZ では、どのように問題解決をするのですか
知識ベースを基礎にした方式(図2)は、TRIZ でも科学一般でも同様で、問題を一般化して知識ベースに当てはめ、解決策へのヒントを得ます。
TRIZ にはさらにたくさんの問題解決技法がありますが、それらを統合し直して最近新たに提案されている方式が図3の「6箱方式」です。
この方式の特長は、第2箱から第3箱に進むとき、標準的なシステム分析の技法を使うことです。現システムを構成要素、その性質、機能および空間と時間で分析し、さらに理想を考えます。第4箱はヒントではなく、新しいシステムの核になるアイデアです。第3箱から第4箱に進むには、TRIZ の発明原理を再整理した多数の方法がありますが、それらの方法を知り、第3箱への分析を確実に行うと“自然に”出てくることが多いのです。第5箱へ進むには、その技術分野での基礎素養が必要です。
この図の下半分はTRIZ が直接担当する領域ではありません。現実の複雑な問題(第1箱)の中から解くべき問題を抽出するには、QFD(品質機能展開)が有用です。また、解決策のコンセプト(第5箱)から、実装された解決策(第6箱)に具体化するには、CAE(Computer Aided Engineering)や品質工学などを使うべきです。QFD−TRIZ−CAE/ 品質工学の連携が有効で必要だというのは、特に日本で強調されているやり方です。
Q: 適用と普及についてはいかがですか
今年9月に、第6回日本TRIZシンポジウムが3日間開催されました。日本TRIZ 協会(NPO)が主催している、全国的かつ国際的な学会で、発表40 件(うち海外13 件)、参加者165 名(うち海外46 名)でした(詳しくはWeb をご覧下さい [1]、[2])。
日本では、製造業、特に電機・情報関連の主要企業のほとんどが1997 年頃から程度の差はあれTRIZ を導入しています。活動が最も組織的なのは、日立、パナソニックおよびパナソニックコミュニケーションズです。
世界的に見ると(ロシアを別にして)、1990 年代後半から米・欧・日・韓の順に普及してきましたが、現在最も活発で組織的に活用しているのは韓国です。サムスン、LG、現代自動車、POSCO などがトップダウンで活用し、新製品開発にTRIZ が多大の実績をあげています。1970 〜 80 年代の日本の品質管理運動を彷彿させるのが、現在の韓国の大企業での導入です。技術の問題解決、技術予測、特許戦略などにTRIZ が活用されているのです。
以上のように、TRIZ は単なる発明の技法ではありません。科学的な基盤を備え、今後も着実に発 展していくであろう技術革新のた めの方法論なのです。
参考文献
[1] 日本T R I Z 協会公式サイト,URL:www.triz-japan.org/
[2] TRIZ ホームページ(中川徹編集),URL:www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/
編集ノート後記 (中川 徹、2010年11月12日)
本稿の執筆は、8月初旬にオーム社の編集部の方から依頼を受けました。オーム社は、理工学の専門書やコンピュータ関係での有力な出版社で、月刊の技術総合誌『OHM』(主要読者は電気関連の技術者) を出しています。その巻頭の解説記事 (HEADLINE REVIEW) に、TRIZについての解説を執筆して欲しいとのことでした。喜んで書かせていただきたいと返事して、もう少し意図をお聞きしたときに、つぎのようなメールをいただきました。
「弊社発行の『OHM』は、扱う内容が幅広く、色んな情報を掲載しているつもりですが、これまで扱ったことのないテーマを探していて、TRIZを見つけました。中川先生のHPも拝見しました。... 2頁なので、あまり突っ込んだ内容は難しいと思いますが、技術者にとって、何がどう有効なのかということを具体的にご解説頂ければと思います。」(8月初旬)
TRIZシンポジウムを終えた 9月17日に本稿の原稿 (字数を収めるのに苦労したのですが) を仕上げて、送りました。そのときにつぎのような返信をいただきました。
「実はご執筆をお願いするまで「TRIZ」を知らなかったのですが、ホームページを拝見し、そして今回、原稿を拝読させて頂き、だいぶ分かったように思います。原稿(図含め)はとても分かりやすい記述だと思います。 ありがとうございます。」(9月18日)
この後、編集部の方で仕上げていただき、11月号として11月5日に発行されました。HEADLINE REVIEWは5分野に各1編掲載とのことで、TRIZの解説は「教育・知財」分野に入りました。そして、オーム社の許可をいただき、早々に本ホームページに再掲載させていただきます。本件の執筆の機会を与えて下さり、また再掲載を許可いただきましたオーム社に感謝いたします。
やはりまだまだ、TRIZが知られていないことを再認識しました。もっともっと積極的に紹介して行く必要があると思っています。前回『InterLab』誌にTRIZ連載をして、「はじめてのTRIZ FAQ」
を書いてからもうすでに5年経っていることにびっくりしています。いくつもいくつもTRIZについて書いているつもりですが、ほんとうにはじめての人たちへの紹介というのが、まだまだ手薄になっていたと反省しています。
英訳も作成したいと考えていますが、取り敢えず和文だけでここに掲載します。
| 本ページの先頭 | 『OHM』誌 PDF版 |
本文記事の先頭 | 後記 | 『InterLab』誌TRIZ連載 |
TRIZ紹介のページ |
英文ページ |
| 総合目次 |
新着情報 | TRIZ紹介 | 参 考文献・関連文献 | リンク集 | ニュー ス・活動 | ソ フトツール | 論 文・技術報告集 | 教材・講義ノート | フォー ラム | Generla Index |
| ホー ムページ |
新 着情報 | TRIZ 紹介 | 参 考文献・関連文献 | リ ンク集 | ニュー ス・活動 | ソ フトツール | 論文・技 術報告集 | 教材・講義 ノート | フォー ラム | Home Page |
最終更新日 : 2010.11.12 連絡先: 中川 徹 nakagawa@ogu.ac.jp