(事例:液晶ウォッチ用高効率DC−DCコンバータ)
投稿 2000年10月19日; 掲載: 2000年11月 1日
編集ノート:
(中川, 2000年11月 1日)
2週間前の10月19日に, シャープ株式会社の森久光雄氏から, 下記のようなメッセージとともに,
本稿の原稿を電子メールにて受け取りました。
大阪学院大学 中川先生
2000年10月19日 シャープ株式会社 森久光雄先般は滋賀での日本IMユーザグループミーティングでは、USIT(統合的構造化発明思考法)のお話、大変有難うございました。SickafusのUSIT教科書を持っていないので、その後先生のホームページを教材に勉強をしています。大変役立ちます。ほんとに有り難いと思います。
ところで昨年、中川先生ホームページへのボランテイア投稿のお薦めを三菱総研様より戴いておりました。その後Web化は、三菱総研様の協力を得て、このたび絵入り詳細説明付きの、大変立派なものが完成致しました。中川先生ホームページご創設1998年11月 1日より2周年目を目前とし、感慨深いものがあります。世界の多くの人が見ている中川先生のTRIZホームページへ掲載戴ける事は名誉なことです。
投稿の題材は、過去の私の特許をもとに「発明のプロセスとTRIZとの関連」を詳細説明したものです。素材は昨年10月のボストンでのIM社主催第3回北米ユーザグループミーテイングでの発表「TechOptimizer Implementation Example (High efficiency DC-DC converter for liquid crystal watches)」です。生まれたばかりにしてはよく出来ているTRIZのソフトに対する私の感動と評価と、これを使いこなして仕事をする場合の、技術者の主人公としての役割りについて述べさせて戴いております。
森久さんとは, 三菱総合研究所の研究会やセミナーなどを通じて, もう 3年近くも一緒にTRIZを学んできております。本ホームページの
2周年に当たって, 森久さんの力作の原稿を投稿下さり, 掲載させていただけるのは,
ありがたいことです。
本稿はもともと, 上記のメッセージにも述べられていますように, 1999年10月17-19日にアメリカで研究発表されたもので, その発表のスライドをもとに日本語の論文としてきちんと記述されたものです。企業内での最新の事例を発表するのが難しい状況の中で, 自分自身の1970年代前半の (当時の最前線の) 仕事を綿密に分析して, TRIZの使い方の教育用の事例としてまとめ, 公表されたものです。技術者としての当時の開発の過程を自分自身で分析し, もしその当時にTRIZのソフトウェアツールがあったとしたらどのように使えたかの有効性を検証しています。このような具体的な事例で検証したものが, 日本の企業の中であちこちにできてきているのはすばらしいことです。技術レベルが上がり, 進歩が速くなっている現在こそ, TRIZのような「考えるための方法」が重要になっているのだと思います。
投稿いただきました著者の森久光雄氏とシャープ株式会社に感謝しますとともに, きちんと編集したHTMLおよび画像ファイルを送っていただいた三菱総合研究所の大久保泰宏氏に感謝いたします。本稿は, シャープ株式会社の社内TRIZホームページにも最近掲載されたとのことですし, 三菱総研のホームページにも同時に掲載されます。また, 本サイトの英文ページには, 取り敢えず昨年の発表Abstractと編集ノートとを掲載いたします。
著者の電子メールアドレス:
morihisa@cspc.ptdg.sharp.co.jp
森久 光雄 (シャープ株式会社)
[注 (2001. 8.23): 著者は 2001年3月に定年退職されました。新メールアドレス:
mc393-g7@myy.sst.ne.jp
]
[追記 (中川, 2000.11.10) : リンクの一部訂正,印刷時の不具合を一部訂正]
[追記 (中川, 2001. 2.28): 本論文の英文版がTRIZ Journal の2001年1月号に発表され,
本サイトの英文ページに再掲載しました。]
[追記 (中川,
2001. 8.23): 著者からの依頼に基づき, 参考文献の著者名を詳しくし,
著者の連絡先を変更しました。]
| 発明のプロセスとTRIZとの関連
(事例:液晶ウォッチ用高効率DC−DCコンバータ) |
|
シャープ株式会社 生産技術開発推進本部
設計システム開発センター システム企画室 森久光雄 |
目 次
| 本ページの先頭 | 論文先頭 | 1. はじめに | 3. TOPEJ | 4. 事例紹介 |
| 4-4 TOPEJの効果(1) | 4-6 具体化設計 | 4-7 TOPEJの効果(2) | 5. まとめ | 英文ページ |
当センターでは、その有力ツールの一つとして、TOPEJ(三菱総研扱いTRIZ日本版ソフト)を導入した。
TOPEの考え方はもともとロシアの技術文化の発想で、日本においては技術者にとって親しみ難いところがあった。そのため、技術者から教育的な事例サンプルが望まれていた。
この検証事例は、TRIZ無しで行われた過去の発明のプロセスをベースに、もし発明の行われたその時点でTRIZツールが有ったとしたらどのような点で役立ったであろうかを分析したものである。事例は旧世代の製品に関するものであるが、電子回路のシステムの分野に於いてもTOPEが有効なアイデア発想を与えることが示された。当センターではこのプレゼンは技術者へのTRIZ紹介用に使っている。
TRIZそのものの効用を明確にする上で、TRIZを活用した場合とそうでない場合の差(発明に至るまでの時間や質、発明そのものがTRIZなしでもできたのか、等)という形態で客観的に明確に比較出来るデータとして蓄積することが望ましい。しかし、この場合、新規発明では公開上の障害や、発明の有効性の判断の困難さの問題もある。
そこで、TRIZの有効性を自ら実体験する方法として、既に解決した実際の技術問題、ないしは発明的な問題にTRIZを当てはめ評価してみること、特に自ら行った発明で検証を行うのが効果的であると思う。人はいくら他者の体験、事例発表を聞いても、完全な納得には到達しえないが、わが身で体験したことは納得出来るからである。
このように、自らの発明を対象にすれば発明のプロセスを熟知しているがゆえに、TRIZが得意なこと、TRIZが不得意なために技術者がフォローしなければならないこと、を自らつかむことが出来る。またその体験を積むことによって、次のステップ、つまり新規の問題へ自らTRIZを適用してみようとする意欲が起きてくる。
勿論、TRIZの効用が自らの発明をもとにしたとはいえ、客観性の上で正しく評価出来るよう、私はこの検証事例では発明時のプロセスを詳述した。TRIZそのものも日進月歩の改善、進歩を遂げつつあり、またTRIZを発明の創出や研究開発に活用しようという世界の波動も否定出来ない。従ってロシア米国を中心に生まれてきた、この異文化の創造手法、技術を、自ら確かめていただきたいと思う。
その際、TRIZ検証の教育に適した発明事例の条件としては、
1. 実際の製品に使われる事により有効性が証明された発明であることが望ましいと思われる。
2. 発明当時の発想状況がインタービューないしは確認出来るものであること
3. 公開上の障害が無いこと(発明の権利が既に終了している等)
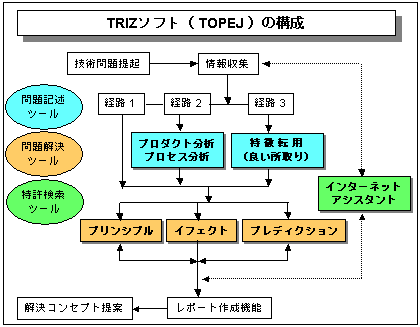
第1図:TRIZソフト(TOPEJ)の構成 |
発明や技術開発のプロセスに於いては従来は技術問題の提起から解決コンセプトの提案までが一貫して属人的作業であった。TRIZソフトはこれを、問題記述ツール及び解決問題ツール、特許検索ツール等で支援する。つまり、TRIZは、技術者個人の感性によることの多かった、技術開発における問題解決を、科学的手法とソフト化されたツールを活用して創造性支援することを目指している。
問題記述及び問題解決ステップに於けるTRIZの3つの主な狙いと、それに役立つTOPEJモジュールは以下の通りである。
1. 心理的惰性(Psychological Inertia)の排除:プロダクト分析(Product Analysis)なお、TRIZをツールとして技術開発に活用するといっても、仕上げる主体者は人間である。TRIZとの共同作業のなかで技術者は自らの価値、尊厳さをも確認出来ると思う。その意味で、TRIZは技術者の良き友となるものである。
2. 妥協的解決策(Trade Off's & Compromises)の回避:プリンシプル(Principles)、プレディクション(Prediction)
3. 知識の幅(Limited Breadth of Knowledge)を拡げる:イフェクツ(Effects)
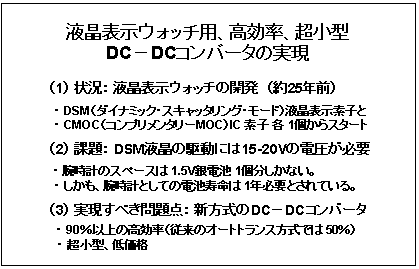
第2図:超高効率DC−DCコンバータの実現 |
本レポートでは、私はTRIZソフトの有効性を、TRIZを使わずに行われた過去の発明(特公昭60−28232号[文献1]米国特許第4,279,010号[文献2])を通じて説明する。
(1)状況
1970年頃、液晶表示素子の黎明期、米国RCA社のハイルマイヤーが1968年に開発した、DSM(Dynamic
Scattering Mode)液晶表示素子が主流であった。
(2)課題
これには少なくとも15−20Vの駆動電圧が必要であった。これを使って腕時計として製品実現するには、1.5Vの銀電池一個で、電池寿命1年を実現する必要があり、そのためには、100%近い高効率のDC−DCコンバータが必要であった。つまり、ここでの技術課題は液晶表示素子そのものではなく、微小電流を超高効率で動かすDC−DCコンバータに係るものであった[文献3]。当時の技術では50%以下の効率しか得られなかった。これでは電池寿命は3ヶ月程度になってしまい、ユーザの視点からは大変不便な商品ということになる。従来の昇圧回路方式で様々に実験を重ねて効率改善の努力をしたが、50%以上の効率を得ることが出来ず、目標特性の90%以上は夢であった。明らかに、ここにはブレイクスルーが必要であった。

第3図:DSMモード液晶表示ウォッチの初試作サンプル |
DSM液晶表示素子の文字は乳白色である。現在は殆ど使われることの無くなった古いタイプの液晶である。
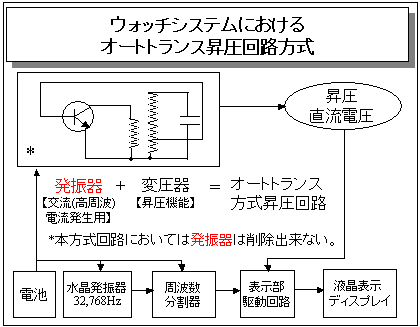
第4図:ウォッチシステムにおける回路方式 |
このウォッチシステムの中には発振器の機能を持つものが二つある。ウォッチシステムという観点から見ると、本当に必要なのは時刻を創りだす水晶発振器である。オートトランス方式昇圧回路は、交流発生の為の発振器と昇圧の為の変圧器という2つの機能がある。そしてこの二つは一体化されていて分離困難となっている。昇圧回路はこんなものだという既成概念が心理的惰性となって革新的な案や指針は出て来なかったが、私はこの発振器がガンになっていると感じていた。
このオートトランス方式で発振器を削除(トリミング)するアイデアはないものだろうか?
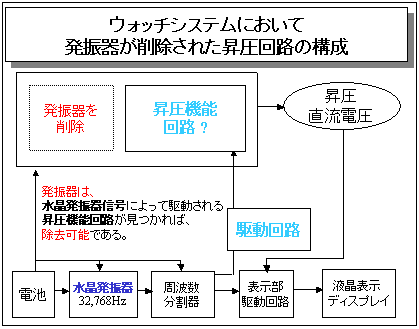
第5図:発振器が削除された昇圧機能回路の構成 |
オートトランス方式昇圧回路の発振器を削除せねばならない。しかし、交流方式の昇圧回路以外には良いアイデアはなかった。それで発振器の代替として、水晶発振器の信号をもとに駆動される、昇圧機能の自立した新原理の昇圧回路を発見することにした。
従い、もし発明考案の時にTOPEJがあったと仮定したら、プロダクト分析(Product Analysis)モジュールは、下記のように水晶発振器(発振器A)をもとに、分周器で適宜周波数に落とした駆動信号回路の提案をしたであろう。
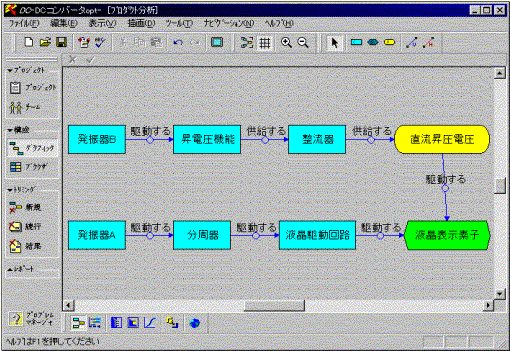
第6図:初期の機能モデル(TOPEJ[プロダクト分析モジュール]の画面) |
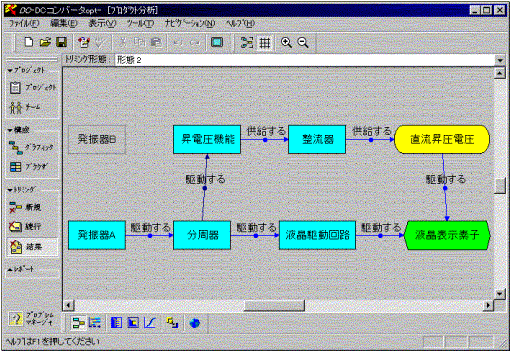
第7図:トリミング後の機能モデル(TOPEJ[プロダクト分析モジュール]の画面) |
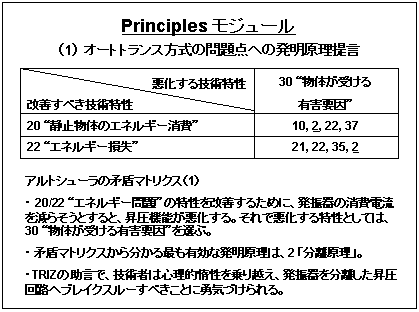
第8図:オートトランス方式の問題点への発明原理提言 |
もし発明考案の時にTOPEJがあったと仮定したら、前節のプロダクト分析モジュールに加え、本プリンシプル(Principles)モジュールに於いても、分離つまり削除すべきであるとの提案が出て来るであろう。従い、もし発明時にTOPEJがあったと仮定したら、我々は昇圧回路の中の発振回路をもっと確信を持って削除したであろう。
なお、本プリンシプル(Principles)モジュールの場合「削除したらどうですか?」とは出てくるが、あくまで抽象的な提案であって、それ以上の示唆はない。その点、前節のプロダクト分析モジュールの場合、より指針は具体的である。
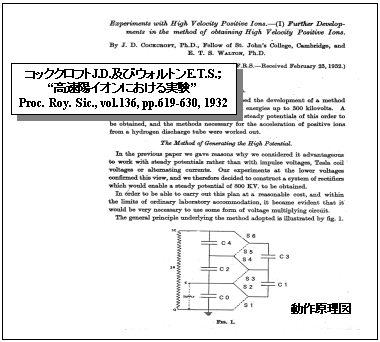
第9図:コッククロフト及びウォルトンのProc.Roy.Soc.の論文
|
Cockcroftは英国のWaltonはアイルランドの物理学者で、原子核を破壊する実験(後にノーベル賞を受賞)を行うため、800KVの高電圧発生回路を開発した。図で示されているようにこの回路はコンデンサー群とスイッチ群から構成されている。まず最初にコンデンサーC1はスイッチS1,S3を経由し、電源に対して並列接続により充電される。次にC1に充電された電荷は、スイッチS2,S4を経由しコンデンサーC0に直列に接続されたコンデンサーC2へ移される。この動作が繰り返されることによって、直列接続されたコンデンサーC0,C2,C4上に昇圧が得られる。
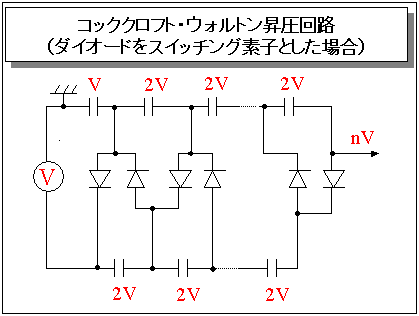
第10図:コッククロフト・ウォルトン昇圧回路
|
図はPNダイオードをスイッチング素子として用いたCockcroft and Walton型DC-DCコンバータである。超高電圧の世界で開発された原理であるが、電圧は原理としては関係なく、普遍的に使える回路である。
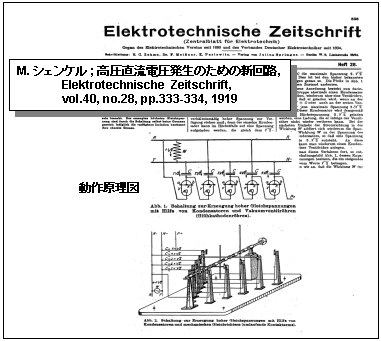
第11図:M.シェンケルのElektrotechnische
Zeitschriftの論文
|
Cockcroft,WaltonはProc.Roy.Soc.の論文の中で、ドイツの技術者M.Schenkelが1919年に、同じく超高圧発生のために発明した倍電圧回路を紹介している(この回路はコンデンサーとスイッチからなるという点でコッククロフト、ウォルトンの回路に似ているが、倍電圧の後段に行くほど、コンデンサーに印加される電圧が高くなるという欠点があるため、超高圧発生のためには余り使われなかった)。
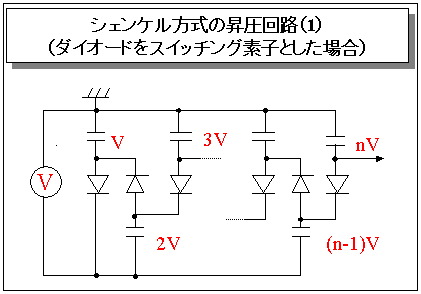
第12図:シェンケル方式の昇圧回路(1)
|
本回路はスイッチング素子にダイオードを用いたSchenkel方式のDC−DCコンバータ回路である。
Schenkel方式はCockcroft-Walton方式に比べ、後段のコンデンサーほど印加される電圧が高くなる点が低電圧に於いては欠点とならず、優れている。その為、我々はシェンケル回路を採用した。
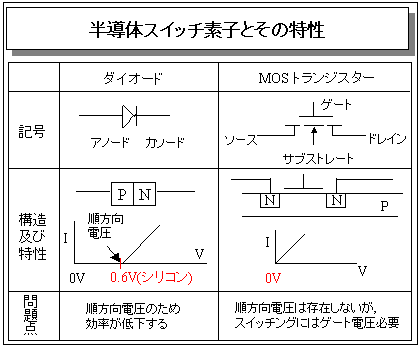
第13図:半導体スイッチ素子とその特性 |
スイッチング素子として、2種類の半導体素子、ダイオードとMOSトランジスターを示している。ダイオードには順方向電圧ロスがある。MOSトランジスターにはそれが無い為、低電圧回路用のスイッチング特性としては、MOSトランジスターのほうが優れている。しかし欠点として、ゲートを制御する必要がある。従い、ゲートを制御する回路の設計を行わなければならない。
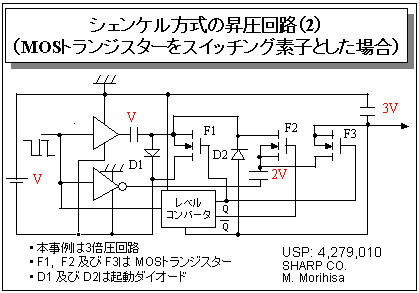
第14図:シェンケル方式の昇圧回路(2)
|
これは、MOSトランジスターをスイッチング素子として使った、実際の完全なSchenkel方式の3倍圧のDC-DCコンバータ回路である。
しかし、TOPEJで、現在最も改善の上で力点の置かれている部分は「イフェクツ(Effects)モジュール」の部分であり、今後大きく改善が期待される部分である。イフェクツ(Effects)モジュールの思想は、必要な機能から、その機能を実現する「効果、原理」を引く言わば機能の逆引き辞典である。役に立つ機能、事例のナレッジベースとして充実していくことにより、革新的設計の具現化に大きい役割を果たすと思われる。
この資料を作成するにつけ、かつて倍電圧回路のルーツを探るため通い、超高圧電圧の発生に開発されたCockcroft-Walton(1932)とM.Schenkel(1919)の論文を発見した、阪大工学部の図書館へ行ってみた。そこには100年前からの、主に欧州の古い科学技術文献が今でも沢山保管されていた。おそらく今は閲覧する人も少ないであろう。私はその静かな図書館の空間で、Cockcroft-Walton(1932)とM.Schenkel(1919)の論文を再読しているとき、当時の野心的な科学者がにぎやかな討論をしている錯覚に陥った。この図書館に限らず、各研究機関では古くても画期的なアイデアにつながる文献が、多く活用されることなく、貯蔵(ないしは古いというだけで死蔵)されているであろうと直感した。
イフェクツ(Effects)モジュールの思想の具体化はまだ、始まったばかりであり、今後膨大なナレッジが追加されていく予定であることは喜ばしい。
アルトシューラは、「貴方の問題は既に他の人が解決していますよ」というのが口癖であったと聞く。多くの先人の知恵(時代の古今を問わず)をもっと活用していくとの思想をツール化したことにイフェクツ(Effects)モジュールの意義があると思われる。当面、TOPEJが不十分なところは、人間(技術者)がカバーすれば良いと思うのである。
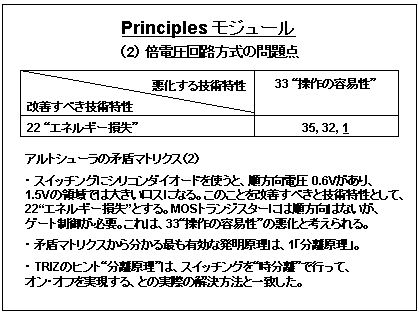
第15図:MOSトランジスターをスイッチング素子とした倍電圧回路の問題点 |
ここで出て来た、発明原理1「分割原理」の概念は「物体を個々の部分に分割する」、「物体を容易に分解できるようにする」、「物体の分裂または分割の度合いを強める」であると、サブ原理に説明されている。ここから、スイッチングを時分割で行ってオン、オフを実現するという考え方は、電子技術者である私には、比較的容易に出来た。
4−9.TOPEJ[プレディクション(Prediction)モジュール]の効果
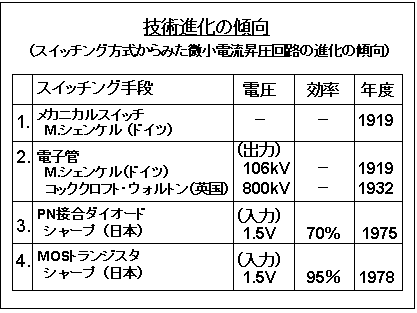
第16図:技術進化の傾向 |
アルトシューラが見出した技術進化の普遍性とは、無秩序なプロセスのように思える技術の進化も、実は規則性を持っていて、あらゆる分野において同じパターンで技術進化が起こっているというものである。
第16図に示すように、技術進化の傾向からみて、80年以上前に超高電圧の分野で使われていた発明の原理が低電圧の分野に於いても革新的に使えることが分かった。そして、ここで半導体工学の進歩に伴う、新しい原理のスイッチングデバイスの進歩が大きく寄与してきていることがわかる。
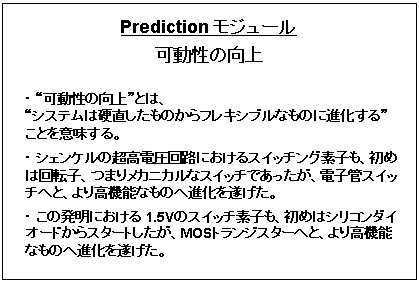
第17図:技術進化の傾向観点(8.可動性の向上) |
TOPEJ[プレディクション(Prediction)モジュール]の、14の技術進化の傾向観点から見て、本事例紹介では、8.可動性の向上、11.制御性の向上が良い一致を示している。8.可動性の向上とは、より柔軟性のある高機能なシステムとするよう、発明者に示唆を与える。
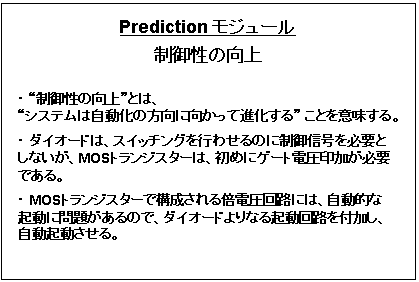
第18図:技術進化の傾向観点(11.制御性の向上) |
TOPEJ[プレディクション(Prediction)モジュール]の、14の技術進化の傾向観点から見て、本事例紹介では、8.可動性の向上、11.制御性の向上が良い一致を示している。11.制御性の向上とは、発明者に、自動化をしていくべきであるという、当然の示唆を与える。
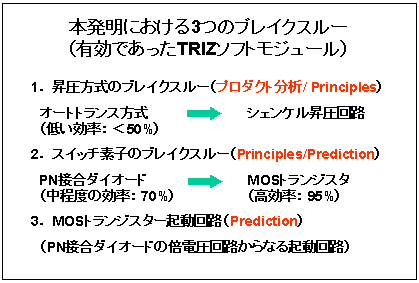
第19図:本発明における3つのブレイクスルー |
問題記述及び問題解決ステップに於けるTRIZの3つの主な狙いと、それに役立つTOPEJモジュールについては、「第3章TRIZソフト(TOPEJ)の構成と効用」で述べた。
TRIZは、技術者個人の感性によることの多かった技術開発における問題解決を、科学的手法とソフト化されたツールを活用して創造性支援することを目指している。TRIZをツールとして技術開発に活用するといっても、仕上げる主体者は人間である。TRIZとの共同作業のなかで技術者は自らの価値、尊厳さをも確認出来ると思う。その意味で、TRIZは技術者のブレイクスルーを助ける良き友であると確信する。
まとめとして、次のことが言える。
| [1] | 森久光雄 ;特公昭60−28232号,“DC−DCコンバータ” |
| [2] | 森久光雄;米国特許第4,279,010号,“DC-DC Converter for solid state watches” |
| [3] | 森久光雄、八村健二、佐々木丈彦、中村 功;“CMOSシェンケル型DC−DCコンバータ”,「日経エレクトロニクス」,1973年12月3日号 |
| [4] | Cockcroft, J.D. and Walton, E.T.S.; “Experiments with High Velocity Positive Ions,” Proc.Roy.Soc., vol.136, pp.619-630, 1932 |
| [5] | M. Schenkel; “Eine neue Schaltung fuer die Erzeugung hoher Gleichspannungen”, Elektrotechnische Zeitschrift, vol.40, no.28, pp333-334, 1919 |
| [6] | 三菱総合研究所知識創造研究部 編著;「図解TRIZ(革新的技術開発の技法)」,P.21,日本実業出版社刊,1999年 |
| [7] | 浜田和幸;「快人エジソン」,日本経済新聞社 |
| 本ページの先頭 | 論文先頭 | 1. はじめに | 3. TOPEJ | 4. 事例紹介 |
| 4-4 TOPEJの効果(1) | 4-6 具体化設計 | 4-7 TOPEJの効果(2) | 5. まとめ | 英文ページ |
| ホームページ | 新着情報 | TRIZ紹介 | 参考文献・関連文献 | リンク集 |
| ニュース・活動 | ソフトウェアツール | 論文・技術報告集 | TRIZフォーラム | English
Home Page |
最終更新日
: 2001. 8.23 連絡先: 中川 徹 nakagawa@utc.osaka-gu.ac.jp