講演: 技術開発から学んだこと (神原秀記)
技術開発から学んだこと (遺伝子解読装置の開発 → 研究・開発と人生の心がけ)
神原秀記 (日立製作所 名誉フェロー、フロンティアバイオシステムズ(株))
2025年5月8日、茨城県立水戸第一高等学校にて 講演、高校1年生の皆さんに
『TRIZホームページ』に寄稿 (2025. 8. 2)、掲載 (2025. 8.18)
掲載: 2025. 8.18
|
|
技術開発から学んだこと (遺伝子解読装置の開発 → 研究・開発と人生の心がけ) |
|
|
|
|
|
| 掲載: 2025. 8.18 |
Press the button for going back to the English page.
![]() 編集ノート (中川 徹、2025年 8月18日)
編集ノート (中川 徹、2025年 8月18日)
本稿は、表記のように、日立製作所名誉フェローの神原秀記さんから、寄稿いただきました素晴らしい講演の全資料です。
神原さんが、東京大学理学部化学教室の大学院に入ってこられたとき(1967年)、4学年上の私は森野米三先生の研究室の助手になったところでした。その後1969年に朽津耕三先生が物理化学第三講座を引き継がれ、(途中2年間は私の米国留学で留守があるのですが) 1972年に神原さんが博士課程を終えて日立中央研究所に移られるまで、私たちは同じ研究室で研究生活を送りました。テーマが違いましたのであまり仕事の議論はしていませんでした。森野研では、御殿下グラウンドでたびたび研究室対抗の野球をやりましたが、神原さんが剛速球の投手、私がその捕手をしました。その後約50年、森野研/朽津研の同窓会等で親交を続けており、神原さんの素晴らしい仕事の話をきいてきました。--- 最近(7月20日)、朽津耕三先生の(コロナ禍で3年越しの)「偲ぶ会」があり、私は最初のスピーチをしました。また、『中川 徹 著作選集』をホームページに掲載しました。きっとこれらのことをきっかけにして、神原さんが、今回の講演資料を寄稿して下さったのだと、感謝しています。
神原さんからのメールの一部を書かせていただきます。
「メールをありがとうございます。いつもアクティブに活躍されている姿はとても刺激になります。ウェブ資料の中に若い人たちの教育を兼ねた活動がありましたが、 私も最近、中学、高校、大学の人たちに元気になって欲しいと経験談などを話しています。」
「母校、水戸一高で話した時のスライドpdfと原稿を添付しました。 (森野先生が「人様に話をするときに原稿も作らずに話すのは失礼だ」とおっしゃっていたので、どんな場合でも原稿は作ることにしています。)
昔、人に頼まれて製薬会社でDNAシーケンサーの講演をしたことがあります。 感想文を皆さんが書いてくれたのですが、その中に「専門が違うので技術の話はよく分からなかったが、 いろいろな経験から学んだことを話したところは大いに参考になった。」と書いてくれた人がいました。
それ以来、技術開発では何を考えて行動してきたかなどを中心に話すようにしています。 今回のは高校生相手ですが、専門の違う大学生向けにも良いかと思っています。専門の近い人にはもう少し技術の内容を話します。」
「水戸一高では去年も話をしています。去年は付属中学の1年生相手でしたが、今年は付属中学の1年生と高校の1年生相手となりました。 入ってきたときに目標をきちんと持つようにとのことで校長先生が設定しているのではないかと思います。」講演の題材は、「ヒトゲノムの解読のためのシーケンサーの技術開発」を中心にした最先端の仕事なのですが、その基にある、考え方(考える心構え)を、中学1年生や高校1年生の人たちにもわかるように、丁寧に分かりやすく話しています。この講演は、もっともっと上級の人たち、大学生でも、院生でも、若手の研究者や技術者でも、熟達の研究者・技術者でも、ビジネスなど一般の社会人でも、そしてもちろん私自身にも、大変刺激になり教訓になります。その意味で、中川が副題「遺伝子解読装置の開発 → 研究・開発と人生の心がけ」を付けさせていただきました。この『TRIZホームページ』の中の最も人気のある記事の一つに成ることと、期待しています。
目次に替えて、講演の各スライドのタイトルを(少し補足しつつ)以下に示します。
1. 技術開発から学んだこと (タイトル)
2. 皆さんはどうしてお母さんやお父さんに似ているのでしょう?
3. 遺伝子ってなあに?
4. 遺伝子はどこにあるの?
5. 遺伝子工学の活用
6. 医療分野への応用
7. 予防医療への期待
8. ヒトゲノム計画
9. 予想より19年も早く解読完了 (「サイエンス」誌(2001年): その功労者の一人が神原秀記氏)
10. 「アジアのスターたち 25人」(「ビジネスウィーク」誌(2001年): (日本から、神原秀記氏と宮崎駿監督)
11. 私の生涯を、子ども時代、中学・高校時代までさかのぼって、お話ししましょう
12. いろいろな経験を積んだ子供時代・中学・高校(水戸一高)時代
13. 積極的にチャレンジした青年時代 ((東京大学)大学・大学院時代)
14. 「ケリをつける」大切さを知った若手時代 (日立製作所の研究員) (空気中の公害物質を高感度で計測する機械の開発)
15. 「10年一仕事」を決意した中堅時代 (数々の質量分析装置を開発、特許と論文多数)
16. 人生が一転!訪れた困難 (遺伝子解析装置の開発に踏み出した直後。「慢性肝炎中期」「まぁ、1年くらいなら」の余命宣告)
17. 一番重要な事は、何年生きるかではなく、どう生きるかである (中村天風の本に励まされて得た悟り)
18. 必ず成功する方法 (=成功するまでやめないこと) (この決意で遺伝子解析装置の開発に集中した。 趣味で木彫りの仏像彫刻をした)
19. 信念と根性が ついに実を結ぶ (遺伝子解析高速化の装置を開発・製品化(1998年)。世界中で使われ、ヒトゲノム計画に大きく寄与)
20. ヒトゲノム解読のカギを手に入れろ?神原秀記 DNAシーケンサーへの挑戦? (日立製作所作成のビデオ(13分半)、YouTube公開)
21. 遺伝子解析は新たなフェーズへ (2003年ヒトゲノム完全解析達成。次のフェーズは、解析の安価化(米国の「$1000ゲノムプロジェクト」)
22. 脱・二番手主義 のすすめ (NHK 21世紀ビジネス塾 の取材ビデオ。YouTubenikに公開あり)
23. 開拓者(1番手)であることの優位性 (1番手にはブルーオーシャン、2番手にはレッドオーシャン)
24. 新たに開拓すべき分野に (一人の人のすべての細胞は同じ遺伝子を持っているが、違った働きをしている。どうなっているのだろう?)
25. 一細胞分析に目をつけた (1細胞レベルで多数の細胞を一斉解析する。遺伝子の異常が見つかれば、病気と関係づけられるだろう。)
26. はじまりはいつも逆風 (2006年研究開始。当初逆風。国の研究費を得、毎年国際会議を開催。2009年一細胞解析技術が一部完成)
27. 時代が追いつき追い風に (2011年アメリカが「1細胞解析プログラム」を立ち上げ。否定的風潮が肯定的に逆転。)
28. 新しい事には 抵抗がつきまとう (2015年微小切片/一細胞を取り出す装置完成。70歳で退職。製品化してくれる所がない。)
29. チャレンジするのに遅すぎることはない (2017年、72歳で一人で起業。内径0.1mmのストロー状の針を自作するのに3か月。)
30. 逆境の中にこそチャンスがあった (お金も人手もない。自分でやるしかない。微小切片採取装置を完成、国内外10以上の大学が使用。)31. 経験から学んだこと (まとめの9項目)
32. チャンスを掴むための能力開発 (まとめの7項目)
33. 山あれば谷あり (成功したときは有頂点にならず次の手を打て。スピード、他人のしてないことをする。)
34. 苦しいときには (中村天風: 嘘でもよいから、「元気です、調子はいいです、最高です」と口にせよ。口にする言葉が心構えを作る。)
35. 明日を担う皆さんへ (未来には無限の可能性がある。自分の努力次第でいろいろな明日が開けてくる。大きな夢を持ちまず行動しよう。)
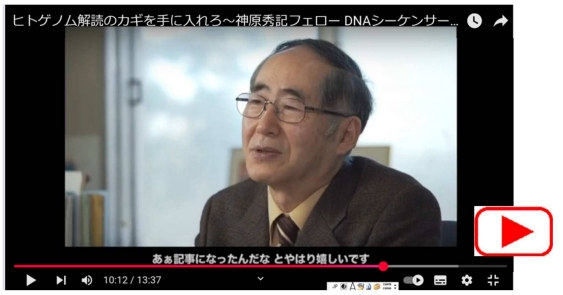
著者 神原秀記さんの写真を右図に示します。
ヒトゲノム解読のカギを手に入れろ?神原秀記 DNAシーケンサーへの挑戦??(日立製作所作成のビデオ)の一画面です。
ビデオは、本文のスライド20.からご覧ください。 (この画像をクリックしても、ビデオを最初から見れます。)
| スライド11(子ども時代から) | スライド19 (遺伝子解析装置の開発) | スライド25. (一細胞分析) | 英文ページ |
![]() 講演:
講演:
技術開発から学んだこと (研究・開発と人生の心がけ)
神原秀記 (日立製作所 名誉フェロー、フロンティアバイオシステムズ(株))
2025年5月8日、茨城県立水戸第一高等学校にて 講演、高校1年生の皆さんに
1.
こんにちは。私は62年前に水戸一高を卒業しました。
長年(45年間)、日立製作所という会社で新しい技術の研究開発を行ってきました。
本日は「技術開発から学んだこと」と題しまして、お話しします。
2.
さて、皆さんはどうしてお母さんやお父さんに似ているのでしょう?
わかるかたいますか?
● それはお父さんとお母さんから受け継いだ「遺伝子」を持っているからです。
3.
遺伝子ってなんでしょうか。
体の大きさや目の色、肌の色など、生き物の性質を決める「設計図」の働きをしています。
この遺伝子情報は、みなさんの体を作っている細胞の中に入っています。
お父さんとお母さんから赤ちゃんができるときには
お母さんの特徴とお父さんの特徴を両方持った「受精卵」という細胞ができます。
その1個の細胞が、2個に、2個が4個に、と、お母さんのおなかの中でどんどん分裂して増えてていって・・・
46回分裂を繰り返すと、たった1個の細胞だったものが、37兆個もの細胞になります。
そしてお母さんの特徴とお父さんの特徴を両方あわせもった赤ちゃんになるのです。
4.
みなさんの体を作っている細胞の中を顕微鏡で見て見ると
細胞の中には「核」というものがあります。
そのままでは見にくいのですが、色素で染めてやると、46本の塊が見えてきます。これを「染色体」と言います。
一本の染色体を伸ばしてみると、長いひものようになっています。これがDNAと呼ばれる物質です。
●
DNAは、A、T、G、Cの4種類の塩基というもので構成されています。
この塩基の並び順が遺伝情報になっています。
このDNAにはところどころ意味を持った遺伝情報が埋め込まれており、これを遺伝子と呼びます。
5.
最近はこの生命の設計図である遺伝子を活用して
病気に強い家畜や農作物を作ったり
農薬を使わなくても美味しくて大きな実がたくさん収穫できる作物を作ったりできるようになってきました。
さらに、医療の分野でも遺伝子はいろいろ活用され始めています。
6.
これは2000年に出た雑誌ですが、今世紀は遺伝子分野が大きく発展すると言っています。
実際、病気の原因が遺伝子情報を用いて解明され、治療に応用されたり、遺伝子の働きを利用して人工的に臓器を作ったりすることができるようになり始めています。
日本で開発された技術として有名なiPS細胞は普通の細胞に遺伝子を注入して刺激して種々の細胞に分化可能な細胞にしたものです。現在、様々な臓器に分化させる研究が進んでいます。
少し前には子供がさらわれて、臓器移植のドナーにされてしまうなどの犯罪が話題になりましたが、これもなくなることでしょう。
7.
今、大きな期待がかけられているのが予防医療への活用です。
実は、すべての病気には遺伝子が関係しているということがわかってきたのです。
生まれつきなりやすい病気があって、●そこに環境要因が加わって、病気を発症するのです。
●病気によっては、環境要因の方が大きく関係するものもあれば、生まれつきの遺伝要因が大きく関係するものもあります。
たとえば、病気ではありませんが、ケガについて考えてみましょう。
怪我は環境要因がもちろん大きいですが
怪我をしやすい人、しにくい人というのがいますので、やはり遺伝子も関与しているようです。
感染症について言えば、これも環境の要因が大きいものの 、免疫が強くて、風邪をひいても大したことなく終わる人と、生まれつき身体が弱くて、重症化してしまう人がいます。
ガンについては、たばこなど発がん性物質が知られていますが、がん関連遺伝子もたくさん見つかってきています。
高血圧や糖尿病などの生活習慣病も 、遺伝の要素が割と大きいことが知られています。
環境にかかわらず発病する遺伝病なども明らかになってきました。
個人の遺伝子を調べて、かかりやすい病気の予防をすることが今、大きく注目されています。
その、原動力となったのがヒトゲノム計画です。
8.
今から35年前、DNAに書き込まれた遺伝子の情報が少しわかり始めたころ、もっと遺伝子の情報を知って医療に役立てたいとヒトゲノム計画がスタートしました。
これにはアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、中国、日本が参加して国際協力と競争で解読が行われました。
「ゲノム」とは遺伝子全体をさす言葉です。
このプロジェクトでは、ヒトの細胞の核の中にあるDNAのすべての塩基配列を解読し、
どこにどんな遺伝情報が書かれているかを明らかにしよう、というものです。
それまでの手作業で配列を読むことからいかに早く機械で配列を読むかがキーポイントの一つでした。
これはアメリカ政府が大きな予算をつけて、アメリカ主導で、世界を巻き込む形で進められました。
なにしろ、DNAの持つ塩基は、なんと30億個あるのです。
そんな膨大な量を読み解くには、30年以上はかかるだろう、と言われていました。
9.
ところが、スタートして11年目に、ほぼ解読が終わると言う記事が有名な科学雑誌「サイエンス」に出ました。
技術が進歩して、予定よりも、19年も早く、遺伝子の解析を終わらせることができたのです。
そこになんと、私の名前が書いてあったのです。
私が開発した機械を使ったら、遺伝子を非常に高速に解析することができたため、ヒトゲノム計画を予定よりも大幅に早く終わらせることができたというのです。
さらに、アメリカのビジネスウィークと言う有名な雑誌社から
写真を撮らせてくれと連絡があり
記者が来て、写真を何枚も撮っていきました。
10.
数週間後、「アジアのスター」という特集記事を掲載した、ビジネスウィークが届いたのです。
開いてみると私が載っているではありませんか。
DNAの塩基配列と共に写った私が掲載されていました。
私の下には、皆さんご存知の、あの有名な宮崎駿監督も載っています。
世界で評価された「千と千尋」などのアニメなどを作った、宮崎監督も「アジアのスター」として選ばれていたのです。
--------------------------------------------------------------------------
11.
当時私は日立製作所の一研究員でした。
医療分野が専門でも、生命科学分野が専門でもありません。
1電機会社の社員の私がどうして
こんなことになったのでしょうか。
それをこれからお話ししていこうと思いますが、
その前に、私がどんな子供時代を送ったか
みなさんがこれから学生生活を送る
水戸一高でどんな生活を送ったかまでさかのぼって
お話ししましょう。
12.
私が子供の頃は、戦後間もない時代で、食べ物も足りないし、ものもないような苦しい時代でした。
でも、何もない日本なのだから、技術立国を目指そうという機運が盛り上がっていました。
その頃は「鉄腕アトム」や「鉄人28号」という科学漫画が大人気でした。
科学に対するあこがれもありました。
● 小学校では、ラジオ番組の放送の電波を拾って音が聞ける、鉱石ラジオを友達が作っていたのを見て、自分も作ってみたことがありました。
● その後、もうちょっと進化した、トランジスタを使ったラジオが出てきたので、部品をあつめてつくったことがありました。
こうした経験から、電子回路になじみが生まれました。
● 天体に興味がありました。望遠鏡はとても高価で、欲しかったのですが、買ってもらえませんでした。
そこで、自分でレンズを買ってきて、組み立てました。
自分で作った望遠鏡から見る宇宙は壮大でした。
目の前に広がる宇宙。 この広い宇宙の中にちいさな地球がある。
その小さな地球の中のちっさな日本という国に、さらにちっぽけな人間たちが住んでいる。
自分は何てちっぽけな存在なんだろう、広い宇宙の中では
そして小さなことで自分は悩んでいる。
宇宙は広いのだから、小さなことで悩まず、もっと、大きくなろうと、自分を勇気づけることができました。
こうした経験を経て、ないものは、何でも自分で作ってみよう、
ものづくりって面白い!と思うようになったのです。
それも、ものが今のようになかったおかげかもしれません。
●
また、ゲームも何もない時代なので、毎日鬼ごっこなどをして外を走りまわって遊んでいました。
そのおかげで、足がとても速くなり、中学では運動会の他にあった、クラスマッチで選手に選ばれることになりました。
でも、短距離走の選手、100m、200mを走る選手には早い人がいっぱいいました。また、マラソンなど長距離も得意な人がたくさんいました。
でも、走る距離が少し長い中距離になると、だんだん走る人数は減っていくんですね。
そこで私は400m走に出ることにしました。
運動能力の高い、早い人たちは、短距離走の他にいろいろとかけもちしていました。
いろいろな競技に出ていたりして、400m走の決勝を走る頃には、疲れちゃったんですね。
でも400m一本勝負の私には、まだ十分体力がありました。
● そのおかげで、なんと、私が優勝することができました。
この時に、あれこれやるよりも、一点集中の方が有利なんだなと実感しました。
中学時代は運動だけではなく、
●合唱部にも入っていました。先生が非常に熱心で、練習はとても大変でした。
夏休みも練習があるし、親睦ハイキングなんかもありました。
先生がいろんなコンクールを見つけては応募していました。
大変な練習を毎日頑張ったおかげで、茨城県の合唱コンクールで優勝し
NHKホールに行って歌うことができたのです。
今も実験中に歌を歌う事で、不思議と心が軽くなり、物事がスムーズにいくようになります。
合唱はやっていてよかったなと思える経験の一つです。
また草野球のピッチャーもやっていました。
その時に培った、仲間を広げるにはどうしたらいいかというスキルが
大きくなってから、役立ちました。
●中学の謝恩会では、手品をやる事になり 、本を買ってきては一生懸命練習しました。
この手品を通して、不思議に見える事にも、すべて理由があるんだな、と知ることができました。
それは科学の不思議を知る上で役に立ちました。
●高校時代は剣道部に入りました。また、夏休みには友達と、テントを担いで日光に行ったり、八幡平・十和田湖に行ったりしました。
厳しい山道を登った後に見える、美しい景色は何とも言えません。
さて、当時、数学の図形問題が苦手でした。
これを得意科目にしようと頑張ってみる事にしました。
まずは、あれこれやらず、一つの参考書を完璧にしようと努力しました。
参考書の図形をいろんな方向から考えてみるうちに だんだんと、解き方が思いつくようになりました。
ある時、先生が問題の解説を複雑な計算でしているときに、私が先生に
「先生、ここに線を1本引けば簡単にとけます」
と言うと、先生は 「あ、ほんとだ」 と驚いていました。
苦手な科目でも、粘り強く取り組むと先生も思いつかなかった解法を編み出すことができるものです。
●
こうして、いろいろな活動を通じて得た経験が
後になって、とても役に立っていくことになります。
13.
・大学時代:種々実験、工作機械などの扱い方も学びました。
・卒業研究:CO2レーザーを製作する(レーザーの黎明期)
・友人とかけをする (友人はそんなのできっこないと言っていた。じゃあかけをしよう)
●
・9月からスタートし、毎日夜遅くまで頑張って実験をしました。
12月29日の夜、9時ころ、ようやくうまくいきました。
次の日に先生が見に来て、「本当だ、お祝いに行こう」と建物を出るときに指を鉄のドアに挟まれて、そのまま病院行きになりました。
●
・学会で発表することにè発表時間10分のうち1分くらいで終わってしまう。どうしよう
・携帯用レーザーを作製。封じ切りで
●
・学会でいよいよ実演
・結果は・・・
●
・燃え上がった。大成功
●
・北アルプス、南アルプス、奥秩父縦走、甲斐駒他 野球同好会などいろいろなことをした
●
・大学院時代:分子の構造を決める(プログラミングの基礎を習得)
・装置の製作
・「なんでも作ろうと思えば自分で作れる 」という自信がついた
14.
そんな学生生活を終えて、私は日立製作所という会社に入りました。
日立と聞いて皆さんが知っているのは、冷蔵庫や洗濯機でしょうか。
そういった家電の他にも電車や工事のための重機、他にも病院で使うような医療機器など幅広い製品を作っています。
1970年代当時、日本では大気汚染が大変な問題となっていました。
私は、まず、大気汚染などの公害の対策のため、
空気中の成分を測定する機械を開発することになりました。
● 測定したいのは、空気主成分酸素や窒素に比べると、100万個に一つの割合しかないわずかな成分です。
私は、その成分が強調されて測定できる、ふしぎな機械をつくりました。
たとえば空気の粒100万個の中に公害の物質がたった1つしかないとします。
普通はこの比率に従って測定しますが、
●
でも私のこの機械を使うと、見たいものが強調されて
公害の物質が100万個見えて、空気の粒は1個に見えるのです。
これは使えるだろう、と思ったのですが、
●
製品化する部署の人は「そんなへんなものはいらない」「興味もない」というのです。
せっかく頑張って開発してきたのに、大変がっかりしました。
仕方ないので、研究をやめたいと上司に言うと
「やったことのケリをつけろ」というのです。
ケリをつけるというのは、企業ですから製品にするのもけりだし、製品にならないなら一流の雑誌にやってきたことをまとめて論文として投稿しろと言われました。私は論文を書くのが苦手できたが、頑張りました。
●
そこで私は論文にまとめて、論文発表しました。
●
すると偉い先生の目に留まり、「これはすばらしい技術だ!」と言うではありませんか。
それをきっかけに、日立技術展と言う展示会に出ることになり
科学朝日という雑誌にも「技術の先端を見る」といったタイトルで掲載され
社内の評価は180度変わってしまいました。
●
結局この機械は、関連会社から製品化することになり、
日刊工業新聞10大新製品賞までいただくこととなりました。
もしもわたしが、けりをつけて、やってきた内容をきちんと形にして残さずにいたら
えらい先生の目に留まる事も、製品化されることもなかったでしょう。●
周りから見ても、 なんかやってたね くらいで終わっていたでしょう。
わたしは、「けりをつける」ことの大切さを学びました。
15.
その後「ケリをつける」、つまり、自分がやった結果をちゃんと世の中に残すということを学んだ私は
質量分析という分野の研究において、研究するたびに次々と特許や論文を書いて行きました。
後に、島津製作所の田中耕一さんが
ソフトレーザーによる質量分析技術の開発によりノーベル化学賞を受賞しましたが
その先駆けとなる、研究もしてきました。
いろいろな技術を開発し、製品化につなげて
International Research & Development IR100 winner という海外の賞をいただいたりすることもできました。
●
それでも、人手もお金も全然たりませんでした。
ある日上司に、もっと研究費をください、人員を増やしてください、とおねがいしましたが 「だめだ。質量分析などという古い事でなく、新しい事をしろ」と言われました。
新しい分野と言っても、何をしてよいかわかりませんでした。
私は毎晩考えました。
これから発展する分野、まだ、人の行っていない分野がいいな
と思いました。
その頃、新聞などで、最初にお話しした、遺伝子が大きな注目を集めて、話題となっていました。
遺伝子の分野で、自分にできることは何だろう、
●
そうだ、「遺伝子を解析するための装置の開発をしよう」と私は決意しました。
といっても、未知の分野です。「不安との背中合わせ」でのスタートでした。
前例もないし、うまくいくかもわかりません。
障害にぶつかると、人は自分に都合の良い理屈を言って、自分を慰め、逃げていく傾向があります。自分もそうなるだろうなと思いました。
これを避けるためには「10年間は何があっても続けよう」と決心しました。
昔、大先輩から「10年ひとしごとだ」と言われたことを思い出しました。
「1年、2年頑張るくらいは他の人でもできる。でも、10年やってきたことには、他の人もそうそう追いつけない」
スタートして周りを見回すと、当時東大の和田先生という方が立ち上げた遺伝子解析プロジェクトがスタートしていました。これに参加して、解析装置の研究開発を始めました。
16.
ところがある日、急にひどく具合が悪くなり、病院に運ばれてしまいました。
慢性肝炎という肝臓の病気でした。
● すでに病気は中期で、医者に、50代で肝硬変、60代で肝がんで死にます、と担当医に言われてしまったのです。
ある時「あと5年は元気に活動できますか?」と聞きました。お医者さんは 「何とも言えません」と言います。 「では3年くらいは」 「それも何とも言えません」
目の前が真っ暗になりました。
10年は頑張ろう、そう思ったのに、私にはもう、残された時間がないのです。
私には君たち位の子供と、その下にもっと小さい子供達もいました。
「あと1年は元気に活動できますか?」
私が聞くと、医者は
「うん、まぁ、一年くらいなら・・・」
と言いました。
私は考えました。 世の中には元気溌剌の人がいる、しかし、ある時突然交通事故で死んでしまう人がいるかもしれない。
私はあと1年かもしれないけど、充実して過ごした1年ならその方が良い人生に違いないなどと自分を慰めたりしました。
そんな日々の中、
私は一冊の中村天風さんの本に出逢いました。
「人生は生かされてるんじゃない。生きる人生でなきゃいけない」
「嘘でもよいから、元気です、調子はいいです、最高ですと口にせよ」
「絶対に消極的な言葉は使わないこと。否定的な言葉は口から出さないこと。悲観的な言葉なんか、断然もう自分の言葉の中にはないんだと考えるぐらいでなきゃだめだ」
そんな言葉に励まされ、私はこの一年を誰よりも大切に生きよう、そう思ったのです。
絶対に結果を出すまでは生き抜くぞ。
そう思い、私は遺伝子解析機器を開発する仕事を
人生をかけて成し遂げるライフワークにしようと決心しました。
17.
一番重要な事は、何年生きるかではなく、どう生きるか、なんですね。
それからは、一日一日がとても大切に思えました。
それまで当たり前と思っていた、何気ない日常、
家族や仕事仲間と過ごす一瞬一瞬が
いかに大切なものであったか、痛感しました。
18.
私は生きているうちに成果を残そうと必死でした。
でも、研究というものは、そう簡単に結果が出るものではありません。
技術開発というのは失敗の連続なのです。
試行錯誤の日々が続き、「そんなことをして何の意味があるんだ」
周囲からの冷たい風当たりもありました。
でも、私はあきらめませんでした。
昔何かで読んだことがあります。
世の中には必ず成功する方法があると。
それは「成功するまでやめないこと」
失敗はただの経過点にすぎません。
1年を充実させて過ごしたら、また1年、と続けました。
その頃、私は趣味で、木彫りの彫刻をしていました。
余命宣告を受けてから、仏像彫りを始めたのです。
これは私が作った仏像の写真です。
彫刻を始めた最初の頃は、細かい部分に気を取られてしまって、全体がいびつになってしまうことがよくありました。
でも、経験を積んでくると、全体を見ながら部分も見ることができるようになったのです。
全体を俯瞰しながらものごとをすすめるという
この経験が、研究や技術開発にも役立ちました。
仏像を彫っていると不思議と心が落ち着いてきます。
そして気付きました。
同じ仏像でも自分の気持ち次第で見え方が違うのです。
それはいろんな物事と同じです。
同じ境遇でも、自分の持っているものに目を向け幸せと思う人もあれば
足りないものにばかり目を向け、不幸せだと嘆く人もいる。
うまくいかないことがあるなら、なぜうまくいかないのかを考えて手を打つことで
うまくいく方に一歩ずつ近づくことができます。
自分にはきっとできる、必ず実現してみせるとやる気になって努力するか、
できない理由を見つけて逃げていくかで大きな差が出てきます。
19.
余命宣告の日から8年たちました。
そしてついに、遺伝子を世界で一番高速に解析できる装置を開発できたのです。
「絶対に作ってやる。それまでは生き抜いて見せる」
強い意志でそう自分に言い聞かせ、開発を行ってきましたが、やっと実が実ったのです。
私の開発したその装置は、1998年に製品化され、世界中で使われ、ヒトゲノム計画は一気に進みました。
この分野の発展と共にDNA医療も発展し、良い肝炎の薬が出てきました。おかげで私の病気も良くなってきました。
●
そして2003年、ついに人間の持つ膨大な遺伝子を解読することができたのです。
「ヒトゲノム完全解読」というニュースが世間をにぎわせました。
そして、いろんな雑誌やNHKからも取材が来ました。
ここで、私がどんなものを開発してきたのか、わかりやすいビデオをひとつ紹介したいと思います。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ヒトゲノム解読のカギを手に入れろ?神原秀記 DNAシーケンサーへの挑戦?
https://www.youtube.com/watch?v=9EoCFfreClE
(画像をクリックして、Youtubeの動画をスタートできます。13分37秒)
こうして、新しい医療技術が発展して、新しい薬も出て来ました。
そのおかげで、私の肝臓は、肝硬変まで進みましたが、
遺伝子の情報を活用した薬のおかげで、安定した状態になりました。
21.
世の中ではヒトゲノム計画が終わり、新たな段階へと入ろうとしていました。
当初、ヒト一人の遺伝子を解析するのに、かかったお金は10億円でした。
医療分野に活用するにはお金がかかりすぎます。
そこで10万円くらいでできるようにする技術開発を目指してアメリカの国立衛生研究所が「$1000ゲノムプロジェクト」をスタートしました。
$1000ドル、つまり当時の為替レートにすると、日本円で10万円くらいで
ヒトの遺伝子を解析できるようにしようというプロジェクトです。
アメリカの国家がだす多額の研究資金を目指して、
多くの企業が新しい遺伝子解析装置の開発に参入してきました。
こうなると、資金力と人手のある企業が有利になります。
私には資金力も人手もありません。
お金も人手もなくても競争に勝つ方法は?
ヒトより早く重要性を見極めて新しい技術開発をスタートすることです。
22.
このあたりの話は以前、NHKの「21世紀ビジネス塾」という番組の取材でしたことがあります。
「この人に聞く!脱・二番手主義」のすすめ」という番組です。
興味のある方は、YouTubeで見れますので、
先生に見せてもらって、QRコードでアクセスするか、
URLを教えてもらって、見てみてください。
23.
資金や人手のない私がいつもこころがけていたことがあります。
それはいろんな角度から情報を収集して、今後どんな未来になっていくだろうか、どんな技術が必要になってくるだろうか、と、未来を読むこと。
そうすることで、みんなが注目する前に、ライバルがいない状態で、物事を準備することができます。
これがブルーオーシャンといわれる状態です。
釣りを想像してみてください。
誰も知らない釣り場であれば、たくさんの魚がつれるチャンスがあります。
でも、「あの釣り場は釣れるらしいよ」とうわさが広がり、どんどん人が集まって来た頃には、
ライバルと魚の奪い合いになって、すでに魚はほとんど釣れない状態になってしまっています。
この状態がレッドオーシャンと呼ばれる状態です。
私が皆さんと同じ中学生の時に、レッドオーシャンである短距離走ではなく、
やるひとがほとんどいない、ブルーオーシャンの400mの中距離走に目をつけて
集中して取り組んで成果を挙げられたのも、同じ理論です。
私は常にブルーオーシャンに目を向けていました。
そうすることで、多くの人が着目する前に、いち早く準備をすることができ
多くの人が気付き始めたときには、すばやく製品化して世の中に出していくことができるので
優位な状態に立てるようになります。
24.
さて、次は何が来るかなと考えました。
ヒトの遺伝子は解析できましたが、その働きに関してはまだよくわかっていません。
同じ人間であればすべての細胞が同じ遺伝子を持っています。
なのに、ある細胞は手になり、ある細胞は足になり、また、ある細胞は肝臓になったり、骨になったりします。
不思議だと思いませんか?
これを、細胞の分化と呼びます。
同じ遺伝子を持っていても、体の部位によって、どの遺伝子が働いているのかが違うのです。
●
病気の原因を突き詰めると細胞の異常に行き着きます。
ガン細胞も、普通の細胞と同じ遺伝子を持っています。
なのに、狂った細胞になって、致命的な病気になってしまうのです。
●
逆に言うと、ひとつひとつの細胞がどんな動きをするのか、それにはどんな遺伝子が関わっているのかを知る事で
病気を理解し、治療法をみつけていくことができるのです。
25.
私は一つの細胞を分析する「一細胞解析」に目を付けました。
これまでの技術では、沢山の細胞のあつまりを丸ごと取ってきて調べていたので
一個の異常な細胞があっても、平均化されて違いを見つけることができませんでした。
でも、細胞を一個ずつ、それぞれ調べることができれば、
異常な細胞と正常な細胞、
働いている遺伝子にどんな違いがあるのかを見つけることができます。
これを見つけられれば、病気がどうして起こるのかを理解し、
治療法をみつけていくことができます。
そこで私は、ひとつの細胞をすばやく分析できるような装置を作れば
きっと医療の発展に役に立つだろうと考えました。
26.
そして2006年、私は文部科学省に、「今後、一細胞解析の分野が重要になります。だから研究費をください」と訴えて
国の特定領域研究という研究費をもらって、大学の研究仲間と技術開発をスタートしました。
また、多くの人に一細胞解析の重要性を知ってもらおうと、国際会議を毎年開催しました。
ところが、スタート当初、生命科学分野のみなさんの反応は
7-8割が1細胞解析について否定的でした。
「そんなことやったって、意味ないよ。今出ているデータで十分」
「細胞はたくさんあるのに一つだけ解析して何の意味があるんだ」
そこで私が
「一つずつを沢山解析するんです」 と言うと
「そんなの大変すぎる!ただでさえデータ量が多いのに、
ひとつずつ、たくさん解析するなんて、とてもやってられないよ」
と言います。
こんなに否定的な反応ばかりだと、普通は嫌になってやめてしまうかもしれません。
私も方向性を間違えたくないので、いろいろな人に話を聞きました。
しかし、様々な情報を集めた結果、一細胞分析が必ず重要になってくることを確信した私は、研究をつづけました。
そして2009年、1細胞解析技術の一部が完成しました。
解析はできるようになっても、たくさんの細胞の中から、一つの細胞だけを取ってこなくてはなりません。
そこで2010年、たくさんの細胞からできている組織の中から一つの細胞あるいは微小切片を取ってくる、採取装置の開発をスタートしました。
27.
一方、横目で様子を伺っていたアメリカの国立衛生研究所が、
2011年に「1細胞解析プログラム」を立ち上げて、沢山のお金をつぎこんでスタートさせました。
全米数か所に一細胞解析センターを設置して
関連した技術の開発をおしすすめはじめたのです。
いろいろな技術が出てきました。
すると、これまで一細胞解析に否定的だった人たちも
「一細胞解析をしないと、病気の仕組みはわからないよね」
とすっかり言う事が変わってしまいました。
今や、一細胞解析が生命科学を飛躍的に発展させるだろうと多くの人が考え始めています。
28.
一方、採取装置の開発から5年が経った2015年、
ようやく組織の中から微小切片を取ってくる装置が完成しました。
70歳になった私は、日立を退職いたしました。
開発してきた装置は、これからとても重要な役割を果たすに違いないと考えていましたから
ぜひ製品化をして国内の研究開発を活性化したい、と思いました。
ところが、どの会社も
「いやぁ、本当に買ってくれるお客さんが現れるのか、どのくらい売れるのかもわからないからねぇ」
といって製品化には後ろ向きでした。
皆、真新しい事は、うまくいくかわからないから、やろうとしないんです。
将来きっと役立つのに、作ってくれる会社が見つからない、
資金を得ようにも、こういった新しい事には、日本では、お金を出してもらえません。
29.
しょうがない
2017年、ついに私は、自分で会社を興すことにしました。
資金なし、人手なし、72歳、一人での起業でした。
それでもチャレンジするのに遅すぎることはありません。
常に開拓者であれ、そんな思いを込めて、社名には、フロンティアバイオシステムズと名付けました。
資金も人手もありませんから、何もかも自分でやらなくてはなりません。
この装置の重要な部品の一つに、採取針があるんですが、 何処も作ってくれません。
そこで自分で作る事にしました。
内径100ミクロンのストロー状の針です。
朝から夜遅くまで製作に挑戦しましたが、なかなかうまくいきません。
・ 一週間たち、一か月たち、二か月たちましたがうまくいきません。
三か月たちました。 ようやくうまくいきました。
30.
装置を自動化するには機械をプログラムで動かす必要があります。
これは専門家でないと無理だ、と言われていました。
しかし、人に頼むお金はありません。
そんな時、自動彫刻機というものをウェブで見つけました。面白そうだと購入してみると
精度は悪いですが、自分が必要としている機能があります。
調べてみると素人でも使える制御コンピューターがあることが分かりました。
これを購入し、自分でプログラミングを行い装置を完成させました。
ここで大学時代にプログラミングをした経験や、
一見何の関係もなさそうな、趣味の彫刻の経験なんかが役に立ちました。
最近ではChatGPTなどAIが助けてくれるので制御プログラム作成なども楽になってきました。
やる気になれば何でもできる世の中になってきました。。
組織の中から微小切片を取ってくる、
世界初の打ち抜き採取装置の実用化に成功したのです。
工夫に工夫を重ねましたから、小型で安価な装置を製品化することができました。
これは現在、東京大学をはじめ10以上の国内外の大学の研究で使われています。
何か新しいことをやろうとすれば、いつも困難が立ちはだかります。
でも、やる気になって努力するか
それともできない理由を見つけて逃げていくかで
人生に大きな差が出てきます。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.
これまでの経験から学んだことを並べました。
けりをつけること。
けりをつけないでいろいろなことをしていると、10年くらいたってから振り返ってみると何も残っていないことに気がつきます。ひとつずつ「自分はこれをしたんだ」という成果をまとめましょう。
一つのことに集中する事。
あれこれ手を出していると、力が分散してしまいます。どれもどっちつかずになってしまいます。あれこれやらずに一つに集中しましょう。
すばやく行動に移す事。
世界は広いので、同じようなことを考える人はいます。
相手よりもすばやく行動に移すことで、大きなチャンスをつかむことができます。
誰かのマネをするのではなく、自分の頭で考えて行動すること。
そうすることで、誰も経験した事のないようなことが起きても、落ち着いて対応することができます。
将来の予測をすること。
将来世の中がどう発展していくのかを、いろんな情報にアンテナを張って、情報収集をして、自分で考えるくせをつけると、未来が見えてきます。
ゴールを明確にする
人生でも研究でも、自分が今何を目指していてどこに向かっているのかを
はっきり認識することが重要です。
そうすることで、必ず行きたい先にたどり着くことができます。
チャンスを生かす
全ての人にチャンスはあります。
でも、たいてい、チャンスは困難の中に隠れていたりします。
何か壁にぶつかったら、それはもしかしたらチャンスかもしれません。
チャンスかどうか見極め、チャンスを生かすために努力することで
チャンスをつかむことができます。
32.
チャンスをつかむための能力開発
(スライドをご覧ください)
33.
人生山あれば谷ありです。うまくいったときには有頂天にならず、次の手を打つ必要があります。
世の中の技術進歩は早いですから、何時までも喜んでいるとすぐに追い越されてしまいます。
世界は広いですから自分と同じかそれ以上の人はいくらでもいます。その中でよい研究や技術開発をしようとすると思いついたことは迅速に実行する。
なるべくまねをしないで自分のアイディアで勝負するのが良いと思います。
34.
人生には苦しいこともありますが、苦しい苦しいと口にするとますます苦しくなります。
健康な人を部屋に閉じ込めてお前は病気だと毎日いい、自分でも言うように仕向ければおそらく病気になります。
自分の言葉が自分の精神を作ります。元気なポジティブな言葉を口にするように心がけましょう。
35.
皆さんには無限の可能性があります。自分の努力次第でいろいろな明日が開けてきます。
大きな夢を持ち、まず行動しましょう
信念を持って行動を続ける限り挫折はありません。
今は不可能に思えることも、いつかは実現します。
みなさんも、このことを忘れずに、これから頑張ってください。
| スライド11(子ども時代から) | スライド19 (遺伝子解析装置の開発) | スライド25. (一細胞分析) | 英文ページ |
最終更新日 : 2025. 8.18 連絡先: 中川 徹 nakagawa@ogu.ac.jp